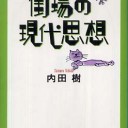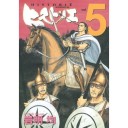内田樹「街場の現代思想」(08年。文春文庫)
2010年10月3日 読書
今日はフレスコに買い物を行った以外、ほとんど部屋の中で過ごす。午後からは天気も悪くなってきたので、読みかけだったこの本を最後まで読み通した。
本書の大部分は第3章の「街場の常識」に割かれている。この章について内田さんはこのように説明する。
<本章では「若い方」からの素朴かつ根源的な問いに不肖内田がお答えし、「なるほど、そうだったのか」と案を叩いて得心していただこうという、「こども電話相談室」青年版的趣旨のものである」(P.78)>
こうした形式で15回にわたり、敬語、お金、給与、転職、結婚、離婚、大学といったことについて内田さんの見解が人生相談形式で述べられている。
いずれの項もなかなか勉強になることは多いが、「いま現在の私」の心境からして以下のような部分が気になった。それは1回目の「敬語について」である。
敬語を使うのが面倒で邪魔臭い、という意見に対して内田さんは、敬語は「生存のための道具」だから「じゃまくさい」もので「重苦しい」ものであると結論づける(P.86)。敬語が「生存のため」とはかなり大げさな表現に感じるかもしれないが、理由は以下の通りだ。
<若い人にとって「生きる」ということは、要するに「自分より力のある人間」(それは必ずしも「自分より賢明な人間」や「自分より善良な人間」ではない。ほとんどの場合、そうではない)に「こづき回される」という経験だ。命令され、訓導され、教育され、査定され、処罰される」>(P.83)
この感覚は若い人ならば特にわかってもらえるだろう。しかしこうした「自分より力のある人間」とは直接闘ってはいけないのだ。
<「敬する」というのは、別に「自分より力のあるもの」に「何かよいもの」を贈ることではない。自分が傷つかないために「身をよじらせて」攻撃を避けることだ。そのためには、自分より力のある相手とは決して、直接向き合わないことが必要だ。
してはいけないことは、そういう相手に「素」で立ち向かうことである。自分の「本音」や「素顔」をさらすことは自己防衛上最低の選択である。>(P.83-84)
私の下の世代にも、上司に「素」で立ち向かったり、「本音」や「素顔」をさらすことを是とするかのような血気盛んな人を見かけるときがある。組織の中においても自分の信条を貫くのが格好いい、というような無責任な流説をときおり見かけることはあるけれど(私もそうした考えにハマっていた時期はある)、しかし若い人にはもっと大事なことがある。
<自分を守ることだ。
君たちを傷つけ、損なう可能性のある「自分より力のあるもの」からわが身を守ることだ>(P.83)
人生がまだまだ残っている若者の現実的な課題は、出世や昇進をする前に自分が潰されないこと、まずはこれが第一だ。内田さんの論理はもう少し難しいものになっているけれど、「敬語を使って話す」という行為はそうした道具であると説明してくれている。
さきほど私は、「いま現在の私」の心境でこの文章が気になった、と書いた。その理由はやはり、これから職場など様々な環境の変化に慣れなければいけない今の自分が生き抜くためには、上のようなことが喫緊の課題だからであろう。
本書の大部分は第3章の「街場の常識」に割かれている。この章について内田さんはこのように説明する。
<本章では「若い方」からの素朴かつ根源的な問いに不肖内田がお答えし、「なるほど、そうだったのか」と案を叩いて得心していただこうという、「こども電話相談室」青年版的趣旨のものである」(P.78)>
こうした形式で15回にわたり、敬語、お金、給与、転職、結婚、離婚、大学といったことについて内田さんの見解が人生相談形式で述べられている。
いずれの項もなかなか勉強になることは多いが、「いま現在の私」の心境からして以下のような部分が気になった。それは1回目の「敬語について」である。
敬語を使うのが面倒で邪魔臭い、という意見に対して内田さんは、敬語は「生存のための道具」だから「じゃまくさい」もので「重苦しい」ものであると結論づける(P.86)。敬語が「生存のため」とはかなり大げさな表現に感じるかもしれないが、理由は以下の通りだ。
<若い人にとって「生きる」ということは、要するに「自分より力のある人間」(それは必ずしも「自分より賢明な人間」や「自分より善良な人間」ではない。ほとんどの場合、そうではない)に「こづき回される」という経験だ。命令され、訓導され、教育され、査定され、処罰される」>(P.83)
この感覚は若い人ならば特にわかってもらえるだろう。しかしこうした「自分より力のある人間」とは直接闘ってはいけないのだ。
<「敬する」というのは、別に「自分より力のあるもの」に「何かよいもの」を贈ることではない。自分が傷つかないために「身をよじらせて」攻撃を避けることだ。そのためには、自分より力のある相手とは決して、直接向き合わないことが必要だ。
してはいけないことは、そういう相手に「素」で立ち向かうことである。自分の「本音」や「素顔」をさらすことは自己防衛上最低の選択である。>(P.83-84)
私の下の世代にも、上司に「素」で立ち向かったり、「本音」や「素顔」をさらすことを是とするかのような血気盛んな人を見かけるときがある。組織の中においても自分の信条を貫くのが格好いい、というような無責任な流説をときおり見かけることはあるけれど(私もそうした考えにハマっていた時期はある)、しかし若い人にはもっと大事なことがある。
<自分を守ることだ。
君たちを傷つけ、損なう可能性のある「自分より力のあるもの」からわが身を守ることだ>(P.83)
人生がまだまだ残っている若者の現実的な課題は、出世や昇進をする前に自分が潰されないこと、まずはこれが第一だ。内田さんの論理はもう少し難しいものになっているけれど、「敬語を使って話す」という行為はそうした道具であると説明してくれている。
さきほど私は、「いま現在の私」の心境でこの文章が気になった、と書いた。その理由はやはり、これから職場など様々な環境の変化に慣れなければいけない今の自分が生き抜くためには、上のようなことが喫緊の課題だからであろう。
エウメネスの言葉
2010年10月2日 とどめておきたこと、特記事項
2010年9月30日から10月1日にかけての2日間は、私の人生で最も大きな分岐点の一つとなった。30日は個人的にショッキングな出来事に出会い、その晩は夜明け近くまで眠れず過ごした。しかしその翌日は人事異動の関係で9年ぶりに職場が変わるということもあって、否応無く新しい環境に放り込まれて働くこととなる。そんなこんなが入り交じって、仕事が終わる頃にはいまだかつてないほど精神がボロボロになってしまった。しかしその夜は周囲の友人の叱咤激励のおかげもあってなんとか気持ちも上向きになった。週明けには仕事も問題なくできる状態まで回復していることだろう。
ただ、今回自分が受けたダメージはおそらく死ぬまで自分につきまとうに違いない。
「寄生獣」で知られる岩明均の作品「ヒストリエ」は、アレクサンドロス大王(アレクサンドロス3世)の書記官だったエウメネスを主人公にしたマンガだ。紀元前4世紀ごろのギリシャ周辺を舞台にした非常にスケールの大きな歴史作品で、あまりマンガを知らない私にとって数少ない愛読書の一つとなっている。現在も「月刊アフタヌーン」で連載中で、単行本は6巻まで出ている。
そのヒストリエの5巻でエウメネスは非常に印象的なセリフを言っている。
エウメネスは故郷カルディアを追われた身であったが、紆余曲折を経て数年後に帰ってきた。その時、かつて父親を殺したゲラダスと再会してしまう。エウメネスに復讐されるのを恐れたゲラダスはエウメネスに斬りかかるも返り討ちに会う。
その翌朝、同じく数年ぶりに再会した兄・ヒエロニュモスに父親の仇討ちを果たしたことを讃えられる。ヒエロニュモスは、それに比べて自分は父親を殺した首謀者ヘカタイオスに面倒を見てもらっているような立場だと言って、
「だ、だってさァ、エウメネス!こ この町でヘカタイオスに逆らったら生きていけないんだよ?!ぼくなんかとても・・・」(P.93)
と卑下する。
そんな兄に対してエウメネスは微笑みながら、それでいいんだ、と言って遠い目をしながらこう続ける。
「人はそれぞれ・・・スッキリしないものをいくつか抱えたまま生きてる・・・それが普通なんだと思う。
心に傷を負ったままでも楽しく暮らす事はできるさ・・・」(P.94)
生きている限り、辛い経験や悲しい出来事に遭遇することは避けられない。そして「それが普通」なのだろう。
それにしても、18歳ないし19歳(生年月日が不明だから)にしてこんなセリフが口から出てくるエウメネスはつくづく波瀾万丈な生き方を送ったのだなと再認識する。
ただ、今回自分が受けたダメージはおそらく死ぬまで自分につきまとうに違いない。
「寄生獣」で知られる岩明均の作品「ヒストリエ」は、アレクサンドロス大王(アレクサンドロス3世)の書記官だったエウメネスを主人公にしたマンガだ。紀元前4世紀ごろのギリシャ周辺を舞台にした非常にスケールの大きな歴史作品で、あまりマンガを知らない私にとって数少ない愛読書の一つとなっている。現在も「月刊アフタヌーン」で連載中で、単行本は6巻まで出ている。
そのヒストリエの5巻でエウメネスは非常に印象的なセリフを言っている。
エウメネスは故郷カルディアを追われた身であったが、紆余曲折を経て数年後に帰ってきた。その時、かつて父親を殺したゲラダスと再会してしまう。エウメネスに復讐されるのを恐れたゲラダスはエウメネスに斬りかかるも返り討ちに会う。
その翌朝、同じく数年ぶりに再会した兄・ヒエロニュモスに父親の仇討ちを果たしたことを讃えられる。ヒエロニュモスは、それに比べて自分は父親を殺した首謀者ヘカタイオスに面倒を見てもらっているような立場だと言って、
「だ、だってさァ、エウメネス!こ この町でヘカタイオスに逆らったら生きていけないんだよ?!ぼくなんかとても・・・」(P.93)
と卑下する。
そんな兄に対してエウメネスは微笑みながら、それでいいんだ、と言って遠い目をしながらこう続ける。
「人はそれぞれ・・・スッキリしないものをいくつか抱えたまま生きてる・・・それが普通なんだと思う。
心に傷を負ったままでも楽しく暮らす事はできるさ・・・」(P.94)
生きている限り、辛い経験や悲しい出来事に遭遇することは避けられない。そして「それが普通」なのだろう。
それにしても、18歳ないし19歳(生年月日が不明だから)にしてこんなセリフが口から出てくるエウメネスはつくづく波瀾万丈な生き方を送ったのだなと再認識する。
雨の日には履けない靴
2010年9月27日いまから1ヶ月前に新京極で仕事用の靴を買いに行った。何か適当なものはないかと店で探していたら、通気性が非常に良いと書かれた商品が目に止まる。これが自分には良いかなとその靴を手に取ってみる。軽いしなかなかいい感じかなと思ったけれど、靴の底を見て気になる部分があった。やたらボコボコと穴が開いているからだ。
店の人に、
「これって雨の時は水が入るんじゃないんですか?」
と訊ねてみたら、
「そうですねえ。でも、水が全く入らないという靴もありませんから・・・」
という感じの答えが返ってくる。確かにそうだな、とその時は納得して買うことにした。それから先はご存知のように猛暑続きだったので、通気性の良い靴は非常に快適だった。いい買い物をしたと思った。
しかし、今日のような大雨に遭遇した場合はやはり弱点を露呈する。会社から出てみれば道は水たまりだらけだ。果たしてこの靴で大丈夫か?と思いながらおそるおそる歩いてみると、やはり水がドボドボと足下へ侵入してくる。これは明らかに、通常の靴より酷い濡れ方だ。穴から水が入ってくるのは自然の道理だから仕方ないとはいえ、天気が悪い日や雲行きが怪しい日に履くには適さない靴である。
店の人に、
「これって雨の時は水が入るんじゃないんですか?」
と訊ねてみたら、
「そうですねえ。でも、水が全く入らないという靴もありませんから・・・」
という感じの答えが返ってくる。確かにそうだな、とその時は納得して買うことにした。それから先はご存知のように猛暑続きだったので、通気性の良い靴は非常に快適だった。いい買い物をしたと思った。
しかし、今日のような大雨に遭遇した場合はやはり弱点を露呈する。会社から出てみれば道は水たまりだらけだ。果たしてこの靴で大丈夫か?と思いながらおそるおそる歩いてみると、やはり水がドボドボと足下へ侵入してくる。これは明らかに、通常の靴より酷い濡れ方だ。穴から水が入ってくるのは自然の道理だから仕方ないとはいえ、天気が悪い日や雲行きが怪しい日に履くには適さない靴である。
時計が午後5時を指したらすぐ会社を出て地下鉄に乗る。東西線に乗り換え、京阪浜大津駅で再び乗り換えて「石場」駅で降りる。そこから3分ほど歩いたところにびわ湖ホールが立っている。名前の通り、すぐ隣にびわ湖があるなかなか風光明媚な会場だ。
今日は山下達郎を観るためにここまでやって来た。といっても、積極的にこの場所に来たわけではなかった。今回のツアーに大阪公演が組み込まれなかったので(これからも無いと思われる)、チケットが「ぴあ」で抽選販売が始まった時は神戸公演とこの滋賀公演を申し込む。しかし神戸公演が外れてしまいこちらが当選する。そんな流れがあった。
余談だが、いまから3年前の2007年にここで中島美嘉を観る予定だった。実際にチケットも取っていたけれど、急にロンドン(!)に行くことにしてしまったので取りやめとなった。そういうわけで、今日は私にとって初めてのびわ湖ホールである。
ホールについたのは午後5時50分くらいにで、まだ開場はしていなかった。別に遅れて入っても構わないと思っていたので入場列には加わらなかったけれど、列はどんどん伸びていて少し焦ってくる。案の定、入場したのが6時15分くらいで、さらにグッズ売り場でも10分近く待ったため、パンフレットを買って自分の席に着く頃には開演時間の3分前くらいというギリギリの状況だった。
席について驚いたのは、1848席(車イス4席を含む)という大ホールが実にステージから近く感じることだ。私の席は「3階席」となっているけれど、他のホールの感覚からすれば1・5階席とでも表現したくなるような高さである。私の横にいたお客さんなど、
「すいません。ここは2階席ですか?」
と私に訊いてきたほどだ。しかしそう錯覚してもおかしくないような構造のホールであった。
開演は予定より5分遅れくらいで始まった。最初は絶対に”SPARKLE”がくると思ったけれど、いつものギターの音ではなかった。なんと1曲目はKinki Kidsに提供した”HAPPY HAPPY GREETING”だった。今回のツアーについて全く知識を入れてなかったけれど、今年で山下はシュガー・ベイブ時代から数えてデビュー35周年になるという。よってツアーも35本設定されている(追加公演が出たため、厳密には35本でないけれど)。そんな意味合いもあっての”HAPPY HAPPY GREETING”らしい。そして2曲目が”SPARKLE”であった。
山下のライブを観るのはこれで5回目になるけれど、大枠の流れとのようなものは出来上がっている。”SPARKLE”から始まり、途中でアカペラがあり”クリスマス・イブ”があり、後半は”LET’S DANCE BABY”に”RIDE ON TIME”、そしてアンコールの最後は再びアカペラの”YOUR EYES”で締めるという具合だ。
ただ今回はデビュー35周年ということもあってか、昔のことが色々と山下の頭に中によぎったようで、シュガー・ベイブ時代の”今日のなんだか”や”WINDY LADY”(録音されていないがライブでは演奏されていた)などを披露してくれた。
個人的に最も嬉しかったのは、ファンクラブで人気投票をしたらこの曲が1位になった、と言って”潮騒”が聴けたことだろう。事情があって長いあいだライブに組み込まれなかったとも触れていたが、私も聴きたいとずっと願っていた曲である。
山下も今日は機嫌良く演奏できたようで、京都会館を「史上最悪のホール」(音響うんぬんとかよりも、ステージのセットが入らないからという理由で)と比較しながら、びわ湖ホールが良い会場なのでまたやりたいと言っていた。そういえば、滋賀でライブをするのは今回が初めてだったらしい。しかし先の発言からすれば、京都公演というのはおそらく実現することもないだろう。
”YOUR EYES”が終わった時に、私の携帯は「21:52」の数字を示していた。実に3時間半近くである。相変わらずタフだなと思ったものの、還暦までは毎年ツアーをしたいとステージで宣言していたのは頼もしい。一方MCで、忌野清志郎や桑田圭佑のような事態が他人事と思えない、とも言っていたのはなかなか重たいものを感じる。
生死に関わるというような次元とは全く違うけれど、私も来月からいろいろと周囲の環境が変化するため、平日の合間を縫ってライブに行くような真似はあまりできなくなる見込みだ。そんなことがずっと頭の中を去来しながら今日の山下のステージを観ていて、不安にも似たなんともいえない思いに駆られてしまったのである。
石場駅から再び電車を乗り継いで帰ったのは11時40分ごろだった。最後に演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)HAPPY HAPPY GREETING
(2)SPARKLE
(3)DAYDREAM
(4)DONUT SONG
(5)僕らの夏の夢
(6)WINDY LADY
(7)砂の女
(8)SOLID SLIDER
(9)潮騒
(10)MOST OF ALL
(11)I ONLY HAVE EYES FOR YOU
(12)クリスマス・イブ
(13)希望という名の光
(14)さよなら夏の日
(15)今日はなんだか
(16)LET’S DANCE BABY
(17)アトムの子
(18)LOVELAND,ISLAND
(アンコール)
(19)街物語
(20)RIDE ON TIME
(21)いつか
(22)ダウンタウン
(23)YOUR EYES
今日は山下達郎を観るためにここまでやって来た。といっても、積極的にこの場所に来たわけではなかった。今回のツアーに大阪公演が組み込まれなかったので(これからも無いと思われる)、チケットが「ぴあ」で抽選販売が始まった時は神戸公演とこの滋賀公演を申し込む。しかし神戸公演が外れてしまいこちらが当選する。そんな流れがあった。
余談だが、いまから3年前の2007年にここで中島美嘉を観る予定だった。実際にチケットも取っていたけれど、急にロンドン(!)に行くことにしてしまったので取りやめとなった。そういうわけで、今日は私にとって初めてのびわ湖ホールである。
ホールについたのは午後5時50分くらいにで、まだ開場はしていなかった。別に遅れて入っても構わないと思っていたので入場列には加わらなかったけれど、列はどんどん伸びていて少し焦ってくる。案の定、入場したのが6時15分くらいで、さらにグッズ売り場でも10分近く待ったため、パンフレットを買って自分の席に着く頃には開演時間の3分前くらいというギリギリの状況だった。
席について驚いたのは、1848席(車イス4席を含む)という大ホールが実にステージから近く感じることだ。私の席は「3階席」となっているけれど、他のホールの感覚からすれば1・5階席とでも表現したくなるような高さである。私の横にいたお客さんなど、
「すいません。ここは2階席ですか?」
と私に訊いてきたほどだ。しかしそう錯覚してもおかしくないような構造のホールであった。
開演は予定より5分遅れくらいで始まった。最初は絶対に”SPARKLE”がくると思ったけれど、いつものギターの音ではなかった。なんと1曲目はKinki Kidsに提供した”HAPPY HAPPY GREETING”だった。今回のツアーについて全く知識を入れてなかったけれど、今年で山下はシュガー・ベイブ時代から数えてデビュー35周年になるという。よってツアーも35本設定されている(追加公演が出たため、厳密には35本でないけれど)。そんな意味合いもあっての”HAPPY HAPPY GREETING”らしい。そして2曲目が”SPARKLE”であった。
山下のライブを観るのはこれで5回目になるけれど、大枠の流れとのようなものは出来上がっている。”SPARKLE”から始まり、途中でアカペラがあり”クリスマス・イブ”があり、後半は”LET’S DANCE BABY”に”RIDE ON TIME”、そしてアンコールの最後は再びアカペラの”YOUR EYES”で締めるという具合だ。
ただ今回はデビュー35周年ということもあってか、昔のことが色々と山下の頭に中によぎったようで、シュガー・ベイブ時代の”今日のなんだか”や”WINDY LADY”(録音されていないがライブでは演奏されていた)などを披露してくれた。
個人的に最も嬉しかったのは、ファンクラブで人気投票をしたらこの曲が1位になった、と言って”潮騒”が聴けたことだろう。事情があって長いあいだライブに組み込まれなかったとも触れていたが、私も聴きたいとずっと願っていた曲である。
山下も今日は機嫌良く演奏できたようで、京都会館を「史上最悪のホール」(音響うんぬんとかよりも、ステージのセットが入らないからという理由で)と比較しながら、びわ湖ホールが良い会場なのでまたやりたいと言っていた。そういえば、滋賀でライブをするのは今回が初めてだったらしい。しかし先の発言からすれば、京都公演というのはおそらく実現することもないだろう。
”YOUR EYES”が終わった時に、私の携帯は「21:52」の数字を示していた。実に3時間半近くである。相変わらずタフだなと思ったものの、還暦までは毎年ツアーをしたいとステージで宣言していたのは頼もしい。一方MCで、忌野清志郎や桑田圭佑のような事態が他人事と思えない、とも言っていたのはなかなか重たいものを感じる。
生死に関わるというような次元とは全く違うけれど、私も来月からいろいろと周囲の環境が変化するため、平日の合間を縫ってライブに行くような真似はあまりできなくなる見込みだ。そんなことがずっと頭の中を去来しながら今日の山下のステージを観ていて、不安にも似たなんともいえない思いに駆られてしまったのである。
石場駅から再び電車を乗り継いで帰ったのは11時40分ごろだった。最後に演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)HAPPY HAPPY GREETING
(2)SPARKLE
(3)DAYDREAM
(4)DONUT SONG
(5)僕らの夏の夢
(6)WINDY LADY
(7)砂の女
(8)SOLID SLIDER
(9)潮騒
(10)MOST OF ALL
(11)I ONLY HAVE EYES FOR YOU
(12)クリスマス・イブ
(13)希望という名の光
(14)さよなら夏の日
(15)今日はなんだか
(16)LET’S DANCE BABY
(17)アトムの子
(18)LOVELAND,ISLAND
(アンコール)
(19)街物語
(20)RIDE ON TIME
(21)いつか
(22)ダウンタウン
(23)YOUR EYES
そういえば去年、イースタン・ユースの大阪公演は中止になってしまったことを思い出した。しかし吉野寿が心筋梗塞に襲われるという緊急事態だったから仕方ない。昨年の手帳をめくってみたら10月9日の項目に、
「心斎橋クラブクアトロ(easten youth)」
と書かれていて、そこに黒いボールペンで斜線が2本引かれていた。
それから今年の6月、ogre you assholeというバンドとのジョイントという形で大阪に来たけれど、仕事の都合で会場入りが遅れたため持ち時間の半分以下もライブを観ることができなかった。そんなこともあって、彼らに対しての思いはなんとなく宙ぶらりんな状態になっていたような気もする。
今回も特に何か特別な期待をしてライブに臨んだわけではなかった。考えてみれば、彼らのライブを初めて観たのが02年7月12日、ミナミアメリカ村のBIG CATにおいてであった。最初のライブは実に鮮烈な体験だったが、それから何度も会場に足を運んだかは数知れない。すっかり私の目や耳も落ち着いてしまった気もする。なんだか愚痴めいたように感じるかもしれないが、こんなことを書いたのには伏線がある。
6月のライブは20分ほど遅刻したものの、今日は仕事も昼で切り上げて開場5分前にはクアトロに到着していた。お客の入りはいつも気になっているけれど、200から300人の間くらいだろうか。前の大阪公演とそれほど変わらない印象だ。開演までは新書を読んで時間をつぶした。しかしいつも思うのだが、このキャパで1時間も待ち時間を設ける必要があるのだろうか。ドリンクなどを注文させようとかいう考えなのか、その辺がどうもよくわからない。
ライブはほぼ予定通りの時間に始まった。1曲目は、最近はアンコールなど終盤で演奏することが多い”夜明けの歌”だった。私がいままで観た中でこの曲が冒頭という経験が無いので、今夜はけっこう期待できる内容かも、という予感がした。2曲目は最新作「歩幅と太陽」(09年)から”いつだってそれは簡単なことじゃない”だったが、このとき辺りから、
「今日の彼らの勢いは尋常じゃないのでは」
と感じる。そしてその思いはライブが進むほどに確信へと変わっていった。
ここ数年の楽曲についていえば、この言い方は適当かどうかわからないが、アルバムよりライブの方が素晴らしい。こうした姿をCDにも納められたら最高なのだが、と惜しい気持ちになってしまうほどだ。実際、今夜は昔の曲と最新作との間に落差らしきものは全く感じられなかった。いやそれどころか、今日はいままで観た中で一番良いでは?と思えるほどの出来である。
これは正直いって予想外の光景だった。彼らが札幌市で結成されたのが1988年、私がまだ小学4年生の頃である。それから22年も経っているわけだ。多くのバンドの事例を考えてみると、耐用年数をはるかに超えている活動期間であろう。
ニール・ヤング&ザ・クレイジーホースの78年のライブを納めた「ラスト・ネヴァー・スリープス」という映像作品の傑作がある。「Rust Never Sleeps」とは「錆(さび)は絶えず進行する」という意味で、全てのバンドは錆びる、と作品中にもセリフが出てくる。確かにミュージシャンやバンドに衰えというのは付きものに違いない。しかしこの日のイースタン・ユースに関していえばそのようなものが全く見当たらなかった。これはニール・ヤングにもいえることだが、音楽と年齢という二つの要素に関係はないのだろうか。そんなことを思ってしまった。
この日の彼らに感激したのは私だけではなかったようで、アンコール2曲目の”一切合切太陽みたいに輝く”が終わりバンドが去って会場が明るくなって音楽が流れても、ほとんどのお客は帰らない。3分ほど拍手を続けているとバンドが再登場し”青すぎる空”を披露する。終わったのが9時20分、1時間50分というのは彼らにしては長めの時間であった。
ライブに行く本数を削っていこうかなあと思っていた今日このごろだったが、こうしたものを見せられると、削るわけにはいくまいと思い直してしまう。最後にこの日の曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)夜明けの歌
(2)いつだってそれは簡単な事じゃない
(3)世界は割れ響く耳鳴りのようだ
(4)踵鳴る
(5)男子畢生危機一髪
(6)未ダ未ダヨ
(7)地下鉄の喧騒
(8)扉
(9)いずこへ
(10)野良犬、走る
(11)まともな世界
(12)街はふるさと
(13)沸点36℃
(14)荒野に針路を取れ
<アンコール1>
(15)雨曝しなら濡れるがいいさ
(16)一切合切太陽みたいに輝く
<アンコール2>
(17)青すぎる空
「心斎橋クラブクアトロ(easten youth)」
と書かれていて、そこに黒いボールペンで斜線が2本引かれていた。
それから今年の6月、ogre you assholeというバンドとのジョイントという形で大阪に来たけれど、仕事の都合で会場入りが遅れたため持ち時間の半分以下もライブを観ることができなかった。そんなこともあって、彼らに対しての思いはなんとなく宙ぶらりんな状態になっていたような気もする。
今回も特に何か特別な期待をしてライブに臨んだわけではなかった。考えてみれば、彼らのライブを初めて観たのが02年7月12日、ミナミアメリカ村のBIG CATにおいてであった。最初のライブは実に鮮烈な体験だったが、それから何度も会場に足を運んだかは数知れない。すっかり私の目や耳も落ち着いてしまった気もする。なんだか愚痴めいたように感じるかもしれないが、こんなことを書いたのには伏線がある。
6月のライブは20分ほど遅刻したものの、今日は仕事も昼で切り上げて開場5分前にはクアトロに到着していた。お客の入りはいつも気になっているけれど、200から300人の間くらいだろうか。前の大阪公演とそれほど変わらない印象だ。開演までは新書を読んで時間をつぶした。しかしいつも思うのだが、このキャパで1時間も待ち時間を設ける必要があるのだろうか。ドリンクなどを注文させようとかいう考えなのか、その辺がどうもよくわからない。
ライブはほぼ予定通りの時間に始まった。1曲目は、最近はアンコールなど終盤で演奏することが多い”夜明けの歌”だった。私がいままで観た中でこの曲が冒頭という経験が無いので、今夜はけっこう期待できる内容かも、という予感がした。2曲目は最新作「歩幅と太陽」(09年)から”いつだってそれは簡単なことじゃない”だったが、このとき辺りから、
「今日の彼らの勢いは尋常じゃないのでは」
と感じる。そしてその思いはライブが進むほどに確信へと変わっていった。
ここ数年の楽曲についていえば、この言い方は適当かどうかわからないが、アルバムよりライブの方が素晴らしい。こうした姿をCDにも納められたら最高なのだが、と惜しい気持ちになってしまうほどだ。実際、今夜は昔の曲と最新作との間に落差らしきものは全く感じられなかった。いやそれどころか、今日はいままで観た中で一番良いでは?と思えるほどの出来である。
これは正直いって予想外の光景だった。彼らが札幌市で結成されたのが1988年、私がまだ小学4年生の頃である。それから22年も経っているわけだ。多くのバンドの事例を考えてみると、耐用年数をはるかに超えている活動期間であろう。
ニール・ヤング&ザ・クレイジーホースの78年のライブを納めた「ラスト・ネヴァー・スリープス」という映像作品の傑作がある。「Rust Never Sleeps」とは「錆(さび)は絶えず進行する」という意味で、全てのバンドは錆びる、と作品中にもセリフが出てくる。確かにミュージシャンやバンドに衰えというのは付きものに違いない。しかしこの日のイースタン・ユースに関していえばそのようなものが全く見当たらなかった。これはニール・ヤングにもいえることだが、音楽と年齢という二つの要素に関係はないのだろうか。そんなことを思ってしまった。
この日の彼らに感激したのは私だけではなかったようで、アンコール2曲目の”一切合切太陽みたいに輝く”が終わりバンドが去って会場が明るくなって音楽が流れても、ほとんどのお客は帰らない。3分ほど拍手を続けているとバンドが再登場し”青すぎる空”を披露する。終わったのが9時20分、1時間50分というのは彼らにしては長めの時間であった。
ライブに行く本数を削っていこうかなあと思っていた今日このごろだったが、こうしたものを見せられると、削るわけにはいくまいと思い直してしまう。最後にこの日の曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)夜明けの歌
(2)いつだってそれは簡単な事じゃない
(3)世界は割れ響く耳鳴りのようだ
(4)踵鳴る
(5)男子畢生危機一髪
(6)未ダ未ダヨ
(7)地下鉄の喧騒
(8)扉
(9)いずこへ
(10)野良犬、走る
(11)まともな世界
(12)街はふるさと
(13)沸点36℃
(14)荒野に針路を取れ
<アンコール1>
(15)雨曝しなら濡れるがいいさ
(16)一切合切太陽みたいに輝く
<アンコール2>
(17)青すぎる空
副業をしている芸能人は数多いが、成功例はそれほど多くはないだろう。かつて「タレントショップ」なるものが流行した時代もあったが、現在はその面影もない。しかし島田紳助も25歳からビジネスを始めたが、それから25年以上にわたり様々な商売をするも「一度も負けたことがない」(本書P.16)という。本書はそんな島田がビジネスについての持論を書いたものである。
2004年の暴力事件のみならず傍若無人なイメージがつきまとって大嫌いな人ではあるものの、本書の内容には本当に唸らされた。ともかく商売に対する分析があまりも鋭いからだ。
例えば島田は、成功する店は「特殊な店、常識はずれの店」(P.23)であると書いている。しかしその後の文章で、ただ常識はずれのことをしても失敗する、と付け加える。
<ビジネスとして成立させるためには、どんなに常識はずれであっても、合理的でなければならない。常識はずれというのは、世間や業界の常識に反しているということを意味しているだけであって、理にかなっていないという意味ではない。
(中略)
常識はずれのビジネスをやろうとするなら、まず第一に、モノゴトを徹底的に合理的に考えなければいけない。>(P.24-26)
単に変わったことをするだけでは成功しない。いままで世間や常識が気づいていないもので、しかも合理的で優れたアイデアを出して始めて成功を手にできるというわけだ。
こうした観察眼は彼が漫才を目指していた頃、売れている先輩芸人の漫才を徹底的に分析することによって磨かれたものだが、それを見事にビジネスへも応用している。
<これはどんな商売でも一緒だと思うのだけれど、結局のところ、人に何か買ってもらうということは、人の心を動かすということだ。
そして僕は、この「人の心を動かす」ということが大好きなのだ。誰かが喜んだり笑ったりする顔を思い描けば、アイデアはいくらでも湧いてくる。
「こういうモノを作ったら売れるんとちゃうか」
「こういう店はやったら流行(はや)るやろ」
>(P.9)
このなかなかカッコいいセリフの中に、ビジネスで成功するためには必ず押さえなければならない要素がたくさん含まれていると思う。
さきほど私は島田に対して「傍若無人なイメージ」と書いていて、現在もそれは変わらないけれど、本書を読むと実に人情の機微に通じている面もある人だと理解できた。
<1つだけ言えるのは、根本のところで、みんなが幸せになれなきゃ意味がないということを、経営者がいつも真っ先に考えているかどうかだ。どうすればみんなが幸せになれるのかは、業種やその店の性格によって、違う部分もあるだろう。けれどその根本の目標が揺るがない限り、きっと上手くいく。>(P.35)
<その会社で働くことが、社員それぞれの幸福につながるようにするのが、経営者の役割なのだ。なぜなら、そうなれば社員は本気で働いてくれるからだ。みんなが本気で働けば会社の業績は必ず伸びる。業績を伸ばすのが経営者の重要な役目であれば、社員の幸せを考えることも、経営者の役割ということになる。自分の役割をちゃんと知っている経営者の下で働きたいというのは、当たり前のことだ。>(P.38)
いま私は線を引きながらこの本を読んでいるが、このままいけば線だらけになりそうだ。ビジネスを始めようとしている人以外にも参考になるアイデアが本書にはたくさん詰まっている。
2004年の暴力事件のみならず傍若無人なイメージがつきまとって大嫌いな人ではあるものの、本書の内容には本当に唸らされた。ともかく商売に対する分析があまりも鋭いからだ。
例えば島田は、成功する店は「特殊な店、常識はずれの店」(P.23)であると書いている。しかしその後の文章で、ただ常識はずれのことをしても失敗する、と付け加える。
<ビジネスとして成立させるためには、どんなに常識はずれであっても、合理的でなければならない。常識はずれというのは、世間や業界の常識に反しているということを意味しているだけであって、理にかなっていないという意味ではない。
(中略)
常識はずれのビジネスをやろうとするなら、まず第一に、モノゴトを徹底的に合理的に考えなければいけない。>(P.24-26)
単に変わったことをするだけでは成功しない。いままで世間や常識が気づいていないもので、しかも合理的で優れたアイデアを出して始めて成功を手にできるというわけだ。
こうした観察眼は彼が漫才を目指していた頃、売れている先輩芸人の漫才を徹底的に分析することによって磨かれたものだが、それを見事にビジネスへも応用している。
<これはどんな商売でも一緒だと思うのだけれど、結局のところ、人に何か買ってもらうということは、人の心を動かすということだ。
そして僕は、この「人の心を動かす」ということが大好きなのだ。誰かが喜んだり笑ったりする顔を思い描けば、アイデアはいくらでも湧いてくる。
「こういうモノを作ったら売れるんとちゃうか」
「こういう店はやったら流行(はや)るやろ」
>(P.9)
このなかなかカッコいいセリフの中に、ビジネスで成功するためには必ず押さえなければならない要素がたくさん含まれていると思う。
さきほど私は島田に対して「傍若無人なイメージ」と書いていて、現在もそれは変わらないけれど、本書を読むと実に人情の機微に通じている面もある人だと理解できた。
<1つだけ言えるのは、根本のところで、みんなが幸せになれなきゃ意味がないということを、経営者がいつも真っ先に考えているかどうかだ。どうすればみんなが幸せになれるのかは、業種やその店の性格によって、違う部分もあるだろう。けれどその根本の目標が揺るがない限り、きっと上手くいく。>(P.35)
<その会社で働くことが、社員それぞれの幸福につながるようにするのが、経営者の役割なのだ。なぜなら、そうなれば社員は本気で働いてくれるからだ。みんなが本気で働けば会社の業績は必ず伸びる。業績を伸ばすのが経営者の重要な役目であれば、社員の幸せを考えることも、経営者の役割ということになる。自分の役割をちゃんと知っている経営者の下で働きたいというのは、当たり前のことだ。>(P.38)
いま私は線を引きながらこの本を読んでいるが、このままいけば線だらけになりそうだ。ビジネスを始めようとしている人以外にも参考になるアイデアが本書にはたくさん詰まっている。
「デートの約束があった時、残業を命じられたらあなたはどうしますか」
という質問に記憶のある方もいるだろう。私もどこかで見たことがあるような気がする。これは財団法人社会経済生産性本部と社団法人日本経済青年協議会が共同で主催している『新入社員「働くことの意識」調査』の中の一文だ。この調査は1969(昭和44)年に始まり、新入社員の入社にあわせて毎年4月に実施されている。本書は40年近くにわたる調査の結果を俯瞰し、就職や仕事に対する若者の考え方がどのような変化をしていったかを分析している。
ひとことで40年といっても、その間に起こった変化はすさまじい。著者は「はじめに」でこのように要約する。
<この40年の間に日本の社会像は一変してしまった。調査が開始された1969年は高度成長期のまっただなか。経済成長率は年10%以上。「モーレツ社員」などという言葉が生まれ、いわば企業サラリーマンの黄金時代が出現しつつあった。その後、2度にわたるオイルショックをはさんで、バブル景気の時代、そしてその後の長い平成不況の時代。平成不況は、サラリーマンの意識を基本的に決定していた終身雇用制にとどめをさした。おのずと、新入社員の意識も変化をまぬがれない。>(P.12)
私の周囲にいる人たちを見ていても、世代によって意識がかなり異なっていることを実感する。下の世代は今の会社にとどまろうという意思は最初から持っていない。私の10〜20歳くらい上の世代は、もはや行く場所も無いから自分の退職までは会社が存続してほしい、と願い最後までへばりつこうとしている。さらに上の世代となれば、退職の日を指折り数えているという始末だ。このような人たちを見ながら、さて自分はどうしようか、と密かに悩みながら毎日を過ごしている。
私が高校を卒業する頃はバブルが崩壊し国内の景気が急激に冷え込み、企業の新卒採用も悪化の一途を辿っていく。いわゆる「日本的雇用慣行」とよばれるシステムが崩壊していく光景だった。おそらく平成生まれには実感できないであろう日本的雇用慣行とは何だろう。本書では平成10年版の厚生白書の定義が引用されている。
<「日本的雇用慣行」とは、企業が、新規学卒者を一括採用し、長期雇用を前提として、雇用者が若年の時は賃金を上回る貢献をしながら、企業内訓練による人的資本形成を行い、中高年期になって蓄積された人的資本への対価として貢献を上回る賃金を支払うことにより、企業固有の技術を持つ熟練労働者を長期に確保する仕組みである。>(P.17)
少しわかりにくい文章かもしれないが、日本的雇用慣行は大きな特徴が2つある。
・定期一律一括採用
・終身雇用
だ。こうしてキーワードを取り出してみると、なんとなく実感していただけるかと思う。中学・高校・大学を卒業したばかりの若者を社員として採用し、年功序列の賃金制度や退職金をうまく機能させながら長期にわたり人員を確保する。私の抱いていた企業像もこうしたものと一致する。しかしそれが平成に入ったあたりからガタガタと崩れてきた。バブルの恩恵も何も受けなかった私の世代は、こうした時代の流れに乗り遅れた、という被害者意識のようなものも抱いているのではないだろうか。
いや私個人についていえば、上の世代に対して苦々しい思いを持っていることは否定できない。何も仕事もしないで高い給料をもらって退職金まで持っていくのか、と。しかしながら、あまり詳しいことはここでは書かないけれど、時代によってここまで待遇が違うのかと露骨に見えてくる職場にいるのだから仕方ない。
それでもこの本を読み終わってからは、こうした被害者意識はずいぶん収まった気がする。なぜならば「日本的雇用慣行」は高度成長期だったからこそ実現した時代の産物であることが理解できたからだ。
<振り返って考えてみると、日本型雇用慣行は、当時の社会状況に照らしてみて、これ以外に選択肢はなかったのではないかと思えるほど合理的なものだった。すでに述べた事情以外にも、当時、多くの企業が共通して抱えていた経営課題はいかに良質の労働力を安定的に確保するかで、これに失敗すれば、人手不足倒産などというもののあったほどである。いうまでもなく、日本型雇用慣行はこの課題の解決にも大きく寄与している>(P.19)
リストラの号令をもとに徹底的な人員削減が進んだ時代を生きてきた人間からすれば「人手不足倒産」というのは到底理解できない話だけれど、事実はそうだったのである。
ちなみに日本的雇用慣行は長期にわたり人材を確保していく性質のものなので、経営規模を縮小することが非常に困難であることも本書は指摘している(P.20)。こうしたことを踏まえれば、いまの国内状況で終身雇用や年功序列などを期待するのは、構造的に無理、と結論づけるしかない。著者も「はじめに」でこのように述べる。
<新入社員といえば、とりもなおさず新卒学生のことであり、それが同期社員として一斉に職業歴を開始するシステムは「終身雇用制」と「定期一律一括採用」の時代の、つまりは、あの高度経済成長期の風景なのだ。なごり惜しい気はするが、よき時代の思い出の風景として記憶の中にとどめる時期が到来しつつあるようだ。>(P.9-10)
著者の分析は徹底的に冷静になっているのが非常に好感がもてる。日本の雇用状況の変化についていたずらに感情的になったり悲観的な調子になっていないのが本書の優れたところであろう。
この日記でよく日垣さんの文章を引用させてもらっていたけれど、その著書を紹介するのはおそらく初めてかと思う。ご存じない方もいるだろうし、本書に載っているプロフィールを紹介しよう。
<作家、ジャーナリスト。1958年長野県生まれ。東北大学法学部卒業。書店員、トラック配送員、TVレポーター、編集者など数々の職を経て、87年から執筆活動に入る。>
「情報の『目利き』になる!-メディア・リテラシーを高めるQ&A」(02年。ちくま新書)という本では、「3度の瀕死体験と失業3回」を経験していると書いている。このような経験をしているためか、日垣さんは一貫して国家や共同体といったものには過大な期待はしていないように思える。よって、いわゆる「格差社会」にまつわる議論に対しても以下のような立場をとる。
<格差がないことほど、恐ろしい支配現象はありません。格差は、あって当然です。
一国や大企業のリーダーと、何もしないプー太郎君が、同じ月収であるのは不自然なことでしょう。>(P.14)
<格差是正と言えば聞こえがいいが、「格差ゼロ」の行き着く先はキューバか北朝鮮である。>(P.100)
<ある一家が貧しいことと、社会の仕組みが間違っていることは元来、関係がない。
笑った方も、おられるかもしれぬ。しかし、冗談ではない。この発想は、個人の努力や創意を否定するものだ。のみならずこの発想は、今も「格差」論争の占めてさえいる。>(P.146)
<弱者救済は美徳であり必要なことだが、働けるのに働かないほうがラクをできるシステムは、国を不幸にする。>(P.151)
かなり手厳しい調子の文章が特徴の日垣さんではあるが、冷静に考えてみれば、まさにその通り、という指摘ばかりである。
ではこうした状況を打破するために日垣さんはどのような提言しているのか。本のカバーには、
「鬱と不況の現代に、個人のスキルと努力で打ち勝て!」
と書いている。個人の地道な行動によって現状を変えていこうというわけだ。
<全体が元気をなくしている時だからこそ、行動力のある個人は突出しやすい、という事実を胆に銘じましょう。そうして、新たな事業や雇用を作り出す個人(企業内の個人も含めて、です)が増えることこそ、不況脱出への近道だと知りましょう。>(P.15)
<目の前の不都合や理不尽は、「社会問題」として「人のせい」に棚上げするのではなく、我が身に降りかかった「今すぐ取り払うべき」問題として一つずつ解決していこうではありませんか。>(P.16)
こうした視点の日垣さんがする提言にはハッとさせられることがあまりに多い。
<日本では格差が開いているというよりも、下層の厚みがぐんぐん増している、というのが憂うべき実態なのです。そこを勘違いしてはなりません。>(P.14)
<問題点は、バブル経済とは無関係に86年以降一貫して「廃業率」が「開業率」を上回っている事実だ。つまり、日本の資本主義は死滅に向かっている。(中略)中国やロシアやインドやブラジルや韓国や台湾は言うに及ばず、先進諸国でも「廃業率が開業率を上回っている」のは日本だけだ。>(P.107)
この国で本当に深刻なことは、このような問題が全く顧みられずに刻一刻と時間だけが過ぎていっていることではないだろうか。
これらの指摘も間違いなく貴重だが、私がこの本を日記で取り上げたかった本当の動機はもっと別のところにある。それは本書の最後に「激変時代に読みたい十〇冊の新書」が紹介されていることだ。以下がそれである。
・長嶋修「住宅購入学入門 いま何を買わないか」(講談社+α新書)
・岩間夏樹「新卒ゼロ社会」(角川oneテーマ21)
・香山リカ「老後がこわい」(講談社現代新書)
・橘玲「マネーロンダリング入門」(幻冬舎新書)
・渡辺千賀「ヒューマン2.0」(朝日新書)
・矢部正秋「プロ弁護士の思考術」(PHP新書)
・岩瀬彰『「月給百円」サラリーマン」(講談社現代新書)
・大前研一「ビジネス力の磨き方」(PHPビジネス新書)
・島田紳助「ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する」(幻冬舎新書)
・小松秀樹「医療の限界」(新潮新書)
・中山治『「格差突破力」をつける方法」(新書y 洋泉社)
手始めに私は(暴力沙汰の事件以来、大嫌いだった)島田紳助の本を読んでみたけれど、これから生きるためのヒントが満載で本当にビックリした。その勢いで古本屋やアマゾンで上の全ての本を買ってしまったほどである。これらを読んだ後は、何か行動しなくては!という気持ちになること請け合いだ。そして、これから私なりの感想も日記で記してみたいと思っている。
ところで、これらの本を集めてから気づいたことが1点ある。これらの新書は合わせて「11冊」だったのだ。私からすれば全く隙らしいものが見当たらない日垣さんのような人でもこうした間違いをするんだなあと知って、なんだかホッとした心境になっている。
<作家、ジャーナリスト。1958年長野県生まれ。東北大学法学部卒業。書店員、トラック配送員、TVレポーター、編集者など数々の職を経て、87年から執筆活動に入る。>
「情報の『目利き』になる!-メディア・リテラシーを高めるQ&A」(02年。ちくま新書)という本では、「3度の瀕死体験と失業3回」を経験していると書いている。このような経験をしているためか、日垣さんは一貫して国家や共同体といったものには過大な期待はしていないように思える。よって、いわゆる「格差社会」にまつわる議論に対しても以下のような立場をとる。
<格差がないことほど、恐ろしい支配現象はありません。格差は、あって当然です。
一国や大企業のリーダーと、何もしないプー太郎君が、同じ月収であるのは不自然なことでしょう。>(P.14)
<格差是正と言えば聞こえがいいが、「格差ゼロ」の行き着く先はキューバか北朝鮮である。>(P.100)
<ある一家が貧しいことと、社会の仕組みが間違っていることは元来、関係がない。
笑った方も、おられるかもしれぬ。しかし、冗談ではない。この発想は、個人の努力や創意を否定するものだ。のみならずこの発想は、今も「格差」論争の占めてさえいる。>(P.146)
<弱者救済は美徳であり必要なことだが、働けるのに働かないほうがラクをできるシステムは、国を不幸にする。>(P.151)
かなり手厳しい調子の文章が特徴の日垣さんではあるが、冷静に考えてみれば、まさにその通り、という指摘ばかりである。
ではこうした状況を打破するために日垣さんはどのような提言しているのか。本のカバーには、
「鬱と不況の現代に、個人のスキルと努力で打ち勝て!」
と書いている。個人の地道な行動によって現状を変えていこうというわけだ。
<全体が元気をなくしている時だからこそ、行動力のある個人は突出しやすい、という事実を胆に銘じましょう。そうして、新たな事業や雇用を作り出す個人(企業内の個人も含めて、です)が増えることこそ、不況脱出への近道だと知りましょう。>(P.15)
<目の前の不都合や理不尽は、「社会問題」として「人のせい」に棚上げするのではなく、我が身に降りかかった「今すぐ取り払うべき」問題として一つずつ解決していこうではありませんか。>(P.16)
こうした視点の日垣さんがする提言にはハッとさせられることがあまりに多い。
<日本では格差が開いているというよりも、下層の厚みがぐんぐん増している、というのが憂うべき実態なのです。そこを勘違いしてはなりません。>(P.14)
<問題点は、バブル経済とは無関係に86年以降一貫して「廃業率」が「開業率」を上回っている事実だ。つまり、日本の資本主義は死滅に向かっている。(中略)中国やロシアやインドやブラジルや韓国や台湾は言うに及ばず、先進諸国でも「廃業率が開業率を上回っている」のは日本だけだ。>(P.107)
この国で本当に深刻なことは、このような問題が全く顧みられずに刻一刻と時間だけが過ぎていっていることではないだろうか。
これらの指摘も間違いなく貴重だが、私がこの本を日記で取り上げたかった本当の動機はもっと別のところにある。それは本書の最後に「激変時代に読みたい十〇冊の新書」が紹介されていることだ。以下がそれである。
・長嶋修「住宅購入学入門 いま何を買わないか」(講談社+α新書)
・岩間夏樹「新卒ゼロ社会」(角川oneテーマ21)
・香山リカ「老後がこわい」(講談社現代新書)
・橘玲「マネーロンダリング入門」(幻冬舎新書)
・渡辺千賀「ヒューマン2.0」(朝日新書)
・矢部正秋「プロ弁護士の思考術」(PHP新書)
・岩瀬彰『「月給百円」サラリーマン」(講談社現代新書)
・大前研一「ビジネス力の磨き方」(PHPビジネス新書)
・島田紳助「ご飯を大盛りにするオバチャンの店は必ず繁盛する」(幻冬舎新書)
・小松秀樹「医療の限界」(新潮新書)
・中山治『「格差突破力」をつける方法」(新書y 洋泉社)
手始めに私は(暴力沙汰の事件以来、大嫌いだった)島田紳助の本を読んでみたけれど、これから生きるためのヒントが満載で本当にビックリした。その勢いで古本屋やアマゾンで上の全ての本を買ってしまったほどである。これらを読んだ後は、何か行動しなくては!という気持ちになること請け合いだ。そして、これから私なりの感想も日記で記してみたいと思っている。
ところで、これらの本を集めてから気づいたことが1点ある。これらの新書は合わせて「11冊」だったのだ。私からすれば全く隙らしいものが見当たらない日垣さんのような人でもこうした間違いをするんだなあと知って、なんだかホッとした心境になっている。
生まれて初めて聞いた「文系の方が高所得」説
2010年8月25日ネットでニュースを見ていたら、目を疑ってしまうような研究結果に出会った。それは京都大学や同志社大学がインターネットでおこなった調査で、100を超える国公私立大学を卒業した人たち(文系988人、理系644人の計1632人)の年収を調べるというものだった。
その結果、平均年収を文系・理系で比較すると、
文系:583万円
理系:681万円
と理系が約100万円も文系を上回っていたというのである。この研究チームの一人である西村和雄・京都大学特任教授は、
「文系の方が高収入という”通説”が覆された」(「毎日新聞」8月24日19時5分配信)
と述べている。しかしこれを見て
「そんな通説があったんですか?」
と冗談抜きに驚いてしまった。私の中では、理系の方が就職に有利で待遇も良い、というのが「通説」だったからだ。
基本的に、文系よりも理系の学生の方が企業から高く評価されているのは間違いない。その最も端的な例が大学院生に対する待遇の違いだろう。理系の採用については学部卒と大学院卒に分かれていて、当然のごとく大学院卒の方が待遇は良い。これに対して文系の院卒など大半は「既卒者」としか扱われないだろう。ここに、就職に役立つ学部に人気が出ている「実学志向」という世の流れが加わるから、ほとんど企業で役に立つと思われていない文学系の学部はどんどん立場が悪くなっていいる。
また西村教授は、
「理系は技術を身につけることで、より広い範囲の職業を選べることが理由の一つでは」(「読売新聞」8月24日20時49分配信)
とも言っているけれど、
「そんなことわざわざネットで調べなくてもわかるんじゃないんですか?」
とこの見解にも疑問を抱いてしまう。今から14年ほど昔の話になるが、私がアルバイトをしていた時に同じ大学で工学部の人間が一緒だった。そいつは何かあるたびに、
「理系は授業ばっかりで忙しい。いいよなあ、文系は」
と文学部の私に言ってきて気分が悪かったことを、今でも思い出す。また室蘭工業大学に在籍していた人間も「授業で忙しい」と電話口で嘆いていたこともあり、
「理系はけっこう授業が詰まっていてキツいんだな」
という「通説」が自分の中に今でも残っている。
とはいいながらも、新聞で大々的に報道されているからには今回の研究結果は学術的には「新発見」だったのだろう。しかし私としては、何がどうなって「文系の方が高所得」という説ができあがったのか。そもそもそんな話がささやかれた時代が存在していたのか。そちらの方を知りたい。
その結果、平均年収を文系・理系で比較すると、
文系:583万円
理系:681万円
と理系が約100万円も文系を上回っていたというのである。この研究チームの一人である西村和雄・京都大学特任教授は、
「文系の方が高収入という”通説”が覆された」(「毎日新聞」8月24日19時5分配信)
と述べている。しかしこれを見て
「そんな通説があったんですか?」
と冗談抜きに驚いてしまった。私の中では、理系の方が就職に有利で待遇も良い、というのが「通説」だったからだ。
基本的に、文系よりも理系の学生の方が企業から高く評価されているのは間違いない。その最も端的な例が大学院生に対する待遇の違いだろう。理系の採用については学部卒と大学院卒に分かれていて、当然のごとく大学院卒の方が待遇は良い。これに対して文系の院卒など大半は「既卒者」としか扱われないだろう。ここに、就職に役立つ学部に人気が出ている「実学志向」という世の流れが加わるから、ほとんど企業で役に立つと思われていない文学系の学部はどんどん立場が悪くなっていいる。
また西村教授は、
「理系は技術を身につけることで、より広い範囲の職業を選べることが理由の一つでは」(「読売新聞」8月24日20時49分配信)
とも言っているけれど、
「そんなことわざわざネットで調べなくてもわかるんじゃないんですか?」
とこの見解にも疑問を抱いてしまう。今から14年ほど昔の話になるが、私がアルバイトをしていた時に同じ大学で工学部の人間が一緒だった。そいつは何かあるたびに、
「理系は授業ばっかりで忙しい。いいよなあ、文系は」
と文学部の私に言ってきて気分が悪かったことを、今でも思い出す。また室蘭工業大学に在籍していた人間も「授業で忙しい」と電話口で嘆いていたこともあり、
「理系はけっこう授業が詰まっていてキツいんだな」
という「通説」が自分の中に今でも残っている。
とはいいながらも、新聞で大々的に報道されているからには今回の研究結果は学術的には「新発見」だったのだろう。しかし私としては、何がどうなって「文系の方が高所得」という説ができあがったのか。そもそもそんな話がささやかれた時代が存在していたのか。そちらの方を知りたい。
要らぬ心配をおかけしました
2010年8月20日今日の当初は仕事が入っていたけれど、いろいろあって行く必要がなくなった。他に用事もないので会社を1日休む。だが特に予定もないので、昼は一乗寺に最近できたラーメン店にでも行こうと思い立つ。
昼前に自転車へ乗ろうと部屋を出ようとした時、ちょうど1階に住んでいる大家さんに出会った。
私の顔を見たとたん大家さんが開口一番、
「あ?いたんか?」
と言ってきた。いたんか?とはどういうことだろう。その意味がつかめなかった。
「ずっと自転車が置いてあるから、熱中症で倒れてるんとちゃうかなあと思ってて・・・」
と大家さんは続けて言ったので、向こうが何を思っていたのかやっと気づいた。ここ数日の私は歩いて通勤をしていたので自転車をずっと置きっぱなしにしていたのである。それを見て大家さんが心配したわけだ。
大家さんには事情を説明し、体は大丈夫です、と言って自転車で一乗寺に向かった。大家さんには要らぬ心配をかけてしまった。変なことをするもんじゃないな、と思いながら。
昼前に自転車へ乗ろうと部屋を出ようとした時、ちょうど1階に住んでいる大家さんに出会った。
私の顔を見たとたん大家さんが開口一番、
「あ?いたんか?」
と言ってきた。いたんか?とはどういうことだろう。その意味がつかめなかった。
「ずっと自転車が置いてあるから、熱中症で倒れてるんとちゃうかなあと思ってて・・・」
と大家さんは続けて言ったので、向こうが何を思っていたのかやっと気づいた。ここ数日の私は歩いて通勤をしていたので自転車をずっと置きっぱなしにしていたのである。それを見て大家さんが心配したわけだ。
大家さんには事情を説明し、体は大丈夫です、と言って自転車で一乗寺に向かった。大家さんには要らぬ心配をかけてしまった。変なことをするもんじゃないな、と思いながら。
我が生涯最高のライブ(1992年8月18日、真駒内アイスアリーナ)
2010年8月18日 渡辺美里いまから18年前の今日は、私がこれまでの人生で最も衝撃的な経験をした日である。もはやはっきりと思い出せないことも多いけれど、日記ではいままでこの話をしたことがなかったのでこれを機会になんとか文章にしてみたい。
当時の私は高校1年生で、北海道は室蘭市にある公立高校に通っていた。そして8月18日は確か2学期が始まった日で(北海道の夏休み期間は短く、25日くらいしかない)、その学校の始まりはいつもテストが実施される。それが終わって校舎を出ると父親が車で待っていた。そのまま3時間ほど走り札幌方面に向かう。格好は学生服だったので車中で私服に着替えていた。そうして到着した先が、1万人ほど収容できる真駒内アイスアリーナであった。ここで私は生まれて初めて「ライブ」というものを観ることになる。そしてステージに立つのは、昨日まではCDやラジオの中の存在でしかなかった、渡辺美里である。
何度も同じことを書いてるような気もするけれど、当時「明治生命」のCMで動く彼女を観てファンになって以来、彼女のパフォーマンスや歌声を生で体験したいとずっと願い続けていた。それが実現したのが今から18年前のことだった。この年の彼女は「スタジアム伝説’92」というスタジアム級の会場を回るツアーをおこなっていた。
会場がどんな感じだったかというようなことは全く覚えていない。ただ強く記憶に残っていることが2つだけある。一つは、入場する時のチラシと一緒にツアーの日程と美里の写真が印刷された下敷きが入っていたことだ。下敷きを無料でもらった記憶はいままで100本以上観たライブでも経験が無い。当時は明治生命がスポンサーについていたりと景気も良かったのだろう。
もう一つの記憶は、会場へ向かう私の前に当時STV(札幌テレビ放送)のアナウンサーだった「船守さちこ」(現在はフリーアナウンサー、音楽評論家)さんがいたことである。その頃の私はラジオやテレビでSTVに親しんでいたので、そこのアナウンサーが眼前にいるというのもなかなか新鮮な経験であった。確か、友だちも一緒に来てるんですけど、とか言っていた気がする。マスコミ関係者として無料で観ていたのだろう。あとはグッズ売り場でデビュー曲”I’m free”を入手したことくらいだろうか。そんなことをしながら客席に向かう。
座席は2階スタンド席の右側だった。北海道での彼女の人気は他府県ほどではなかったので、入りは8割くらい。場内はスモークが炊かれていて、その向こうのステージには、ライブの告知CMにも出てきた大きな大きなメリー・ゴーランドがドンと中央に置かれている。この光景には本当に驚いた。ライブが始まる前から体中に鳥肌が立っていたことが忘れられない。こうした経験もいままでの人生で空前絶後のことである。そうした異様なテンションのまま、セルフカバー・アルバム「HELLO LOVERS」(92年)バージョンの”サマータイムブルース”のイントロが鳴り、花火がボンと音を立ててついにライブの始まりである。この日の主役はメリーゴーランドの上から登場した。
初めて生で聴く美里の歌声を聴いた第一印象は、
「CDよりずっとしゃがれた声だなあ!」
だった。歌もMCもかなりガラガラ声だ。しかしながら、スタジアム規模の会場でもいっぱいに響き渡る彼女の迫力は、CDやライブ・ビデオを遥かに超えて凄まじい。
曲順もおぼろげだが、冒頭ではパイナップルロマンス”、”大冒険”、”シャララ”あたりのアップ・テンポな曲が並んだ。そして中盤の”19才の秘かな欲望”で現在は観ることのできない、スタジアムの端まで生声を響かせるパフォーマンスを披露する。これにはさらにテンションが上がる。そして本編最後では最も聴きたかった”夏が来た!”が飛び出して感無量の状態に。1回目のアンコールで”泣いちゃいそうだよ”と”JUMP”、2回目のアンコールは新曲”メリーゴーランド”、最後に”恋したっていいじゃない”という流れで、最後の最後まで勢いが止まらぬまま駆け抜けるようにライブが幕を閉じた。
驚くことにこの日の選曲には代表曲である”My Revolution”も”10 years”も入っていない。西武球場での曲目にも入っていないところを見ると、ツアーを通しても披露されなかったと思われる。この2曲は当時も人気はあったが、この時の彼女は歌うのに飽きていたのだろうか。だがこれらの曲を封印するというだけでも、あの頃の彼女がどれほど自信を持っていたかがうかがわれる。
ところで私がこの日のライブを「生涯最高」と位置づけているのは、当時の彼女がアーティストとして全盛期だった、という彼女側の要因ばかりではない。客席でステージを観ていた私自身のテンションも異常なほどに高かったからだ。そして、それもまた二度と再現できるものではないものである。
そんなライブが終わった時にはすっかり私は彼女の信者になっていた。それに対してどう思うかは他人の自由だけれど、この日を超えるライブを(彼女自身のライブも含めて)現在まで観ることができなかったことを思えば、それも自分の運命だったというしかない。
それにしても、生まれて初めて観たライブが生涯最高のものになったという事実は、私の中でずっと心の拠り所になっているような気がしてならない。人生の節目節目でこんなことを思う時があるからだ。
これほど凄いものが観られるのだったらこんな世の中でもまだ生きている価値があるかもしれない、と。
最後に、参考資料としてネットで拾ったこの日の曲目を記す。ただし、残念ながら順不同である。
悲しいボーイフレンド
19才の秘かな欲望〜NEWS
Steppin’Now
Lovin’you
Boys Cried(あの時からかもしれない)
It’s Tough
恋したっていいじゃない
シャララ
やるじゃん女の子
跳べ模型ヒコーキ
パイナップルロマンス
サマータイムブルース
恋するパンクス
Boys kiss Girls
夏が来た!
大冒険
JUMP
泣いちゃいそうだよ
青空
メリーゴーランド
当時の私は高校1年生で、北海道は室蘭市にある公立高校に通っていた。そして8月18日は確か2学期が始まった日で(北海道の夏休み期間は短く、25日くらいしかない)、その学校の始まりはいつもテストが実施される。それが終わって校舎を出ると父親が車で待っていた。そのまま3時間ほど走り札幌方面に向かう。格好は学生服だったので車中で私服に着替えていた。そうして到着した先が、1万人ほど収容できる真駒内アイスアリーナであった。ここで私は生まれて初めて「ライブ」というものを観ることになる。そしてステージに立つのは、昨日まではCDやラジオの中の存在でしかなかった、渡辺美里である。
何度も同じことを書いてるような気もするけれど、当時「明治生命」のCMで動く彼女を観てファンになって以来、彼女のパフォーマンスや歌声を生で体験したいとずっと願い続けていた。それが実現したのが今から18年前のことだった。この年の彼女は「スタジアム伝説’92」というスタジアム級の会場を回るツアーをおこなっていた。
会場がどんな感じだったかというようなことは全く覚えていない。ただ強く記憶に残っていることが2つだけある。一つは、入場する時のチラシと一緒にツアーの日程と美里の写真が印刷された下敷きが入っていたことだ。下敷きを無料でもらった記憶はいままで100本以上観たライブでも経験が無い。当時は明治生命がスポンサーについていたりと景気も良かったのだろう。
もう一つの記憶は、会場へ向かう私の前に当時STV(札幌テレビ放送)のアナウンサーだった「船守さちこ」(現在はフリーアナウンサー、音楽評論家)さんがいたことである。その頃の私はラジオやテレビでSTVに親しんでいたので、そこのアナウンサーが眼前にいるというのもなかなか新鮮な経験であった。確か、友だちも一緒に来てるんですけど、とか言っていた気がする。マスコミ関係者として無料で観ていたのだろう。あとはグッズ売り場でデビュー曲”I’m free”を入手したことくらいだろうか。そんなことをしながら客席に向かう。
座席は2階スタンド席の右側だった。北海道での彼女の人気は他府県ほどではなかったので、入りは8割くらい。場内はスモークが炊かれていて、その向こうのステージには、ライブの告知CMにも出てきた大きな大きなメリー・ゴーランドがドンと中央に置かれている。この光景には本当に驚いた。ライブが始まる前から体中に鳥肌が立っていたことが忘れられない。こうした経験もいままでの人生で空前絶後のことである。そうした異様なテンションのまま、セルフカバー・アルバム「HELLO LOVERS」(92年)バージョンの”サマータイムブルース”のイントロが鳴り、花火がボンと音を立ててついにライブの始まりである。この日の主役はメリーゴーランドの上から登場した。
初めて生で聴く美里の歌声を聴いた第一印象は、
「CDよりずっとしゃがれた声だなあ!」
だった。歌もMCもかなりガラガラ声だ。しかしながら、スタジアム規模の会場でもいっぱいに響き渡る彼女の迫力は、CDやライブ・ビデオを遥かに超えて凄まじい。
曲順もおぼろげだが、冒頭ではパイナップルロマンス”、”大冒険”、”シャララ”あたりのアップ・テンポな曲が並んだ。そして中盤の”19才の秘かな欲望”で現在は観ることのできない、スタジアムの端まで生声を響かせるパフォーマンスを披露する。これにはさらにテンションが上がる。そして本編最後では最も聴きたかった”夏が来た!”が飛び出して感無量の状態に。1回目のアンコールで”泣いちゃいそうだよ”と”JUMP”、2回目のアンコールは新曲”メリーゴーランド”、最後に”恋したっていいじゃない”という流れで、最後の最後まで勢いが止まらぬまま駆け抜けるようにライブが幕を閉じた。
驚くことにこの日の選曲には代表曲である”My Revolution”も”10 years”も入っていない。西武球場での曲目にも入っていないところを見ると、ツアーを通しても披露されなかったと思われる。この2曲は当時も人気はあったが、この時の彼女は歌うのに飽きていたのだろうか。だがこれらの曲を封印するというだけでも、あの頃の彼女がどれほど自信を持っていたかがうかがわれる。
ところで私がこの日のライブを「生涯最高」と位置づけているのは、当時の彼女がアーティストとして全盛期だった、という彼女側の要因ばかりではない。客席でステージを観ていた私自身のテンションも異常なほどに高かったからだ。そして、それもまた二度と再現できるものではないものである。
そんなライブが終わった時にはすっかり私は彼女の信者になっていた。それに対してどう思うかは他人の自由だけれど、この日を超えるライブを(彼女自身のライブも含めて)現在まで観ることができなかったことを思えば、それも自分の運命だったというしかない。
それにしても、生まれて初めて観たライブが生涯最高のものになったという事実は、私の中でずっと心の拠り所になっているような気がしてならない。人生の節目節目でこんなことを思う時があるからだ。
これほど凄いものが観られるのだったらこんな世の中でもまだ生きている価値があるかもしれない、と。
最後に、参考資料としてネットで拾ったこの日の曲目を記す。ただし、残念ながら順不同である。
悲しいボーイフレンド
19才の秘かな欲望〜NEWS
Steppin’Now
Lovin’you
Boys Cried(あの時からかもしれない)
It’s Tough
恋したっていいじゃない
シャララ
やるじゃん女の子
跳べ模型ヒコーキ
パイナップルロマンス
サマータイムブルース
恋するパンクス
Boys kiss Girls
夏が来た!
大冒険
JUMP
泣いちゃいそうだよ
青空
メリーゴーランド
兵庫縦断
2010年8月17日
8月の後半に入ってから仕事に余裕が出てきたのは良いけれど、会議とか来客とかが断続的にあるため連休をとることがままならない。今日も休みをとったものの1日だけである。近場で何か良い催しがないかなと展覧会などを調べていたら、兵庫県立美術館で「水木しげる・妖怪図鑑」展が開催しているのでこれに行くことに決める。
せっかく神戸まで行くのだから展覧会の他にも用事をつくりたい。そこで以前から気になっていた「神戸ちぇりー亭」という、ネットの写真を見る限りはかなり量の多そうなラーメン店も寄ろうと思い立つ。
しかしながら、ラーメンを食べて展覧会に行くという計画を立てたものの、具体的に道順など調べてみると少し無理があることに気づく。ラーメン店は「神戸」という名前がついているけれど、実際の住所は三田市にあるからだ。南の海沿いの県立美術館に対して、北の山の中にある三田市である。1日でこの両方を回った人などあまりいないだろうが、どうせ行くのは自分一人なんだしと決行することにした。
行き方はこういう感じだ。まず朝の8時くらいにバスに乗って四条河原町に向かい阪急電車で梅田まで行く。そこからJRに乗り換えて、かの事故で有名になった「福知山線」で「三田」駅へ向かう。そこから神戸電鉄にまた乗り換えて「横山」駅へ着いたのが10時40分くらいだった。「神戸ちぇりー亭」はそこから歩いて5分くらいのところに建っている。開店は11時ですぐ入ったが、私が一番目のお客だった。画像がその目当てのラーメン「ど根性の醤油」(590円)で、トッピングで麺を100グラム増しの「麺男盛」(150円)、野菜増しの「野菜盛」(150円)、そして半熟卵の「とろ卵」(120円)を追加した。
写真を見る分にはもの凄い量に感じるかもしれないが、ドンブリの量はそんなに大きくなかった。そして実際すんなりと完食することができた。東京で食べた「ラーメン二郎」や京都の「ラーメン荘」はけっこう塩辛いけれど、ここのラーメンは割と甘めのスープになっているのが印象に残る。
食べ終わったら横山駅に戻り、今度はひたすら「新開地」に向かって南下していく。有馬温泉を通過し、終点の新開地から阪神電車に乗り換えてやっと次の目的地の三宮に到着だ。ここまで1時間ほどかかった。この時点でまだ12時半を少し回ったくらいである。
三宮駅からバスに乗って兵庫県立美術館へ行く。行列はできてなかったが、展示場の中はびっしりと人が入っていて、妖怪の絵を熱心に見ていた。なぜか私は小学生くらいの頃から小学館の「妖怪なんでも入門」などで水木しげるの妖怪に親しんでいた。だから展覧会で紹介されている妖怪の名前も半分以上は知っている。思い入れは結構深いはずなのだが、こうした絵を再び見て何か感慨にとらわれることもなかった。振り返ってみても水木さんのマンガというのもそれほど熱心に読んだこともない。おそらく、分別もついていない年齢の時にただ絵を見ていただけだったから、影響を受けるとかも何もなかったのだろう。
そんな感じだったので図録などグッズ類も何も買わず、バスで三宮駅まで戻り、阪急電車とバスで部屋に戻った。その時はまだ午後5時ころだったから、今日の行程はあまり無茶なものでなかったかもしれない。
せっかく神戸まで行くのだから展覧会の他にも用事をつくりたい。そこで以前から気になっていた「神戸ちぇりー亭」という、ネットの写真を見る限りはかなり量の多そうなラーメン店も寄ろうと思い立つ。
しかしながら、ラーメンを食べて展覧会に行くという計画を立てたものの、具体的に道順など調べてみると少し無理があることに気づく。ラーメン店は「神戸」という名前がついているけれど、実際の住所は三田市にあるからだ。南の海沿いの県立美術館に対して、北の山の中にある三田市である。1日でこの両方を回った人などあまりいないだろうが、どうせ行くのは自分一人なんだしと決行することにした。
行き方はこういう感じだ。まず朝の8時くらいにバスに乗って四条河原町に向かい阪急電車で梅田まで行く。そこからJRに乗り換えて、かの事故で有名になった「福知山線」で「三田」駅へ向かう。そこから神戸電鉄にまた乗り換えて「横山」駅へ着いたのが10時40分くらいだった。「神戸ちぇりー亭」はそこから歩いて5分くらいのところに建っている。開店は11時ですぐ入ったが、私が一番目のお客だった。画像がその目当てのラーメン「ど根性の醤油」(590円)で、トッピングで麺を100グラム増しの「麺男盛」(150円)、野菜増しの「野菜盛」(150円)、そして半熟卵の「とろ卵」(120円)を追加した。
写真を見る分にはもの凄い量に感じるかもしれないが、ドンブリの量はそんなに大きくなかった。そして実際すんなりと完食することができた。東京で食べた「ラーメン二郎」や京都の「ラーメン荘」はけっこう塩辛いけれど、ここのラーメンは割と甘めのスープになっているのが印象に残る。
食べ終わったら横山駅に戻り、今度はひたすら「新開地」に向かって南下していく。有馬温泉を通過し、終点の新開地から阪神電車に乗り換えてやっと次の目的地の三宮に到着だ。ここまで1時間ほどかかった。この時点でまだ12時半を少し回ったくらいである。
三宮駅からバスに乗って兵庫県立美術館へ行く。行列はできてなかったが、展示場の中はびっしりと人が入っていて、妖怪の絵を熱心に見ていた。なぜか私は小学生くらいの頃から小学館の「妖怪なんでも入門」などで水木しげるの妖怪に親しんでいた。だから展覧会で紹介されている妖怪の名前も半分以上は知っている。思い入れは結構深いはずなのだが、こうした絵を再び見て何か感慨にとらわれることもなかった。振り返ってみても水木さんのマンガというのもそれほど熱心に読んだこともない。おそらく、分別もついていない年齢の時にただ絵を見ていただけだったから、影響を受けるとかも何もなかったのだろう。
そんな感じだったので図録などグッズ類も何も買わず、バスで三宮駅まで戻り、阪急電車とバスで部屋に戻った。その時はまだ午後5時ころだったから、今日の行程はあまり無茶なものでなかったかもしれない。
洋楽倶楽部80’s
2010年8月11日今朝の新聞のテレビ欄にこんな名前の番組を見つける。NHKの公式サイトで番組の紹介が以下のように載っていた。
<洋楽倶楽部80’s・・・
それは、「アラフォー」世代やその前後の世代~80年代に青春時代をすごした皆さん・・・にお送りする洋楽番組です。
80年代は「洋楽」が幅広く認知された時代です・・・
「キング・オブ・ポップス」マイケル・ジャクソンに代表される、1981年MTV開局で巻き起こったミュージック・ビデオ黄金時代でした。
当時、a-ha、マドンナ、ヴァンヘイレン、ヨーロッパ、シカゴ、デュランデュラン、ワム、カルチャークラブなどなど、印象に残る洋楽ミュージック・ビデオが一世を風靡、それまであまり見れなかった、海外のロック・ポップス系アーチストの動く姿をテレビで楽しむことができるようになりました。
また、音楽を聴くメディアがレコードからCDに変わっていったのも80年代です。
そんな時代の今や懐かしい洋楽ミュージック・ビデオとともに、甘酸っぱい青春時代を振り返る。
寛ぎながら80’sを中心とした洋楽ミュージックビデオを楽しむ、洋楽がかかるロックバーのような番組です。
多感であった青春時代の初々しい感情を呼び戻し、今の自分を元気づけて、明日への活力としてください。
【ミュージック・ビデオ】・・・何が流れるかはお楽しみに!!>
80年代の音楽はラジオなどでなんとなく耳にしてはいたものの、その映像作品はほとんど観ていない気がする。これはいい機会と思い、部屋でこれを観ることにした。
この日紹介された映像は、
バグルス”Video Killed The Radio Star”(79年)
シンディー・ローパー”Girls Just Want To Have Fun”(83年)
プリンス&ザ・レヴォリューション”Purple Rain”(84年)
デュラン・デュラン”The Reflex”(84年)
エイジア”Heat Of The Moment”(82年)
ロバート・パーマー”Addicted To Love”(85年)
の6曲だった。いずれも名前はよく知っているけれど、まともに観たことも聴いたこともない人たちだ。
80年代の音楽は商業的にかなり成功をしたものの音楽的には不毛の時代、という見方が強い。そして私もだいたい同じような印象を抱いていた。ただ、ミュージック・ビデオというメディアが異様に発達していったのもこの10年間だ。この点は見過ごせない。
今回の番組で紹介された6曲の映像はいずれもかなり凝った作りになっている。ポピュラー音楽の映像を24時間流し続けるケーブル・テレビ局「MTV(Music Television)」が登場したのが81年のことだ。それ以前はライブの模様を収めたものをただ流すという感じのものが大半だったが、音楽映像それ自体が一つの芸術作品として認知されるようになった時代ともいえる。こういう機会にミュージック・ビデオを観て感じたが、やはり映像から受けるインパクトというものは強烈だ。だからこそこの時代にレコードやCDの売り上げも急激に増大していったのだろう。
しかしながら映像作品があまりに重要視されたおかげで、鳴らされている音楽自体の中身はなおざりにされて空洞化していったのかもしれない。善くも悪くも、80年代というのは70年代とも90年代とも違う特殊な時代である。この番組の案内役で「80’s洋楽とプログレッシブ・ロックをこよなく愛する44歳」(番組の公式サイトより)の高嶋政弘はリアルタイムでこの時代を観ていたわけで、実に嬉しそうにこれらの音楽について話していた。しかし、同時代を共有していない私のような人間にはこれらの音楽に対して強い興味とか愛着は湧くのはなかなか困難な気がする。
ところで今回観た映像作品はいずれも、現在の目からすれば「ゆったりした」印象を個人的には持った。「ゆったりした」というのは、スピード感というかせわしない印象を与えるものは一つもなかったということである。おそらくこの時代はまだCGなどの編集技術もそれほど進んでいないのが原因な気がするが、いかがだろうか。機会があれば同時代の他の映像作品をyou tubeなどで確認してみたい。
<洋楽倶楽部80’s・・・
それは、「アラフォー」世代やその前後の世代~80年代に青春時代をすごした皆さん・・・にお送りする洋楽番組です。
80年代は「洋楽」が幅広く認知された時代です・・・
「キング・オブ・ポップス」マイケル・ジャクソンに代表される、1981年MTV開局で巻き起こったミュージック・ビデオ黄金時代でした。
当時、a-ha、マドンナ、ヴァンヘイレン、ヨーロッパ、シカゴ、デュランデュラン、ワム、カルチャークラブなどなど、印象に残る洋楽ミュージック・ビデオが一世を風靡、それまであまり見れなかった、海外のロック・ポップス系アーチストの動く姿をテレビで楽しむことができるようになりました。
また、音楽を聴くメディアがレコードからCDに変わっていったのも80年代です。
そんな時代の今や懐かしい洋楽ミュージック・ビデオとともに、甘酸っぱい青春時代を振り返る。
寛ぎながら80’sを中心とした洋楽ミュージックビデオを楽しむ、洋楽がかかるロックバーのような番組です。
多感であった青春時代の初々しい感情を呼び戻し、今の自分を元気づけて、明日への活力としてください。
【ミュージック・ビデオ】・・・何が流れるかはお楽しみに!!>
80年代の音楽はラジオなどでなんとなく耳にしてはいたものの、その映像作品はほとんど観ていない気がする。これはいい機会と思い、部屋でこれを観ることにした。
この日紹介された映像は、
バグルス”Video Killed The Radio Star”(79年)
シンディー・ローパー”Girls Just Want To Have Fun”(83年)
プリンス&ザ・レヴォリューション”Purple Rain”(84年)
デュラン・デュラン”The Reflex”(84年)
エイジア”Heat Of The Moment”(82年)
ロバート・パーマー”Addicted To Love”(85年)
の6曲だった。いずれも名前はよく知っているけれど、まともに観たことも聴いたこともない人たちだ。
80年代の音楽は商業的にかなり成功をしたものの音楽的には不毛の時代、という見方が強い。そして私もだいたい同じような印象を抱いていた。ただ、ミュージック・ビデオというメディアが異様に発達していったのもこの10年間だ。この点は見過ごせない。
今回の番組で紹介された6曲の映像はいずれもかなり凝った作りになっている。ポピュラー音楽の映像を24時間流し続けるケーブル・テレビ局「MTV(Music Television)」が登場したのが81年のことだ。それ以前はライブの模様を収めたものをただ流すという感じのものが大半だったが、音楽映像それ自体が一つの芸術作品として認知されるようになった時代ともいえる。こういう機会にミュージック・ビデオを観て感じたが、やはり映像から受けるインパクトというものは強烈だ。だからこそこの時代にレコードやCDの売り上げも急激に増大していったのだろう。
しかしながら映像作品があまりに重要視されたおかげで、鳴らされている音楽自体の中身はなおざりにされて空洞化していったのかもしれない。善くも悪くも、80年代というのは70年代とも90年代とも違う特殊な時代である。この番組の案内役で「80’s洋楽とプログレッシブ・ロックをこよなく愛する44歳」(番組の公式サイトより)の高嶋政弘はリアルタイムでこの時代を観ていたわけで、実に嬉しそうにこれらの音楽について話していた。しかし、同時代を共有していない私のような人間にはこれらの音楽に対して強い興味とか愛着は湧くのはなかなか困難な気がする。
ところで今回観た映像作品はいずれも、現在の目からすれば「ゆったりした」印象を個人的には持った。「ゆったりした」というのは、スピード感というかせわしない印象を与えるものは一つもなかったということである。おそらくこの時代はまだCGなどの編集技術もそれほど進んでいないのが原因な気がするが、いかがだろうか。機会があれば同時代の他の映像作品をyou tubeなどで確認してみたい。
アーティストの「無期限活動休止」
2010年8月10日宇多田ヒカルが8月9日に自身のブログで、来年からアーティスト活動を休止すると発表した。
ブログでは「しばらくの間」とか「2年になるか、5年になるか、わからないけど」と書いており明確な期間は述べられていないから、ネットや新聞に載っているとおり「無期限の活動休止」という表現は間違っていないだろう。
私のマイミクがツイッターで、
「引退するわけじゃないんだから、活動休止しますってことをいちいち宣言する必要あるのか?」
と言っていたので、
「引退するかもしれませんよ(笑)。パチンコ店やコンビニも、改装しますとか当面休業します、とか言ってそのままのケースもありますから・・・。」
と思わず返信してしまった。
しかしながら、3年休みますとか5年間活動しませんとか期限を言っているわけではないから、私の指摘していることは可能性ゼロとは誰も断言できないだろう。それは宇多田ファンにとっては最悪な事態であるが。
実際のところ、解散してしまったバンドも突然に活動再開することも十分にある。例えばユニコーンが再結成すると思わなかったし、個人的なところではペイヴメントの今年の再来日などが記憶に新しい。それはアーティストの意思次第としかいえない。
ただ、ポピュラーミュージックが飽和状態な現在で何年も活動を休止することは実際のところ得策ではないだろう。他に聴く音楽がたくさんあるとすれば、その間に多くのファンはそっちに流れていってしまう。それでもミュージシャンの活動再開した時にまた迎えてくれるのが真のファンとか支持者なのだろう。
そういうことを考えると、いまだに大滝詠一(この人はたぶん「活動休止」とか「引退」とかは明言していないはず)の新作を25年以上待ち続けている「ナイアガラー」の皆さんは本当に凄い。
ブログでは「しばらくの間」とか「2年になるか、5年になるか、わからないけど」と書いており明確な期間は述べられていないから、ネットや新聞に載っているとおり「無期限の活動休止」という表現は間違っていないだろう。
私のマイミクがツイッターで、
「引退するわけじゃないんだから、活動休止しますってことをいちいち宣言する必要あるのか?」
と言っていたので、
「引退するかもしれませんよ(笑)。パチンコ店やコンビニも、改装しますとか当面休業します、とか言ってそのままのケースもありますから・・・。」
と思わず返信してしまった。
しかしながら、3年休みますとか5年間活動しませんとか期限を言っているわけではないから、私の指摘していることは可能性ゼロとは誰も断言できないだろう。それは宇多田ファンにとっては最悪な事態であるが。
実際のところ、解散してしまったバンドも突然に活動再開することも十分にある。例えばユニコーンが再結成すると思わなかったし、個人的なところではペイヴメントの今年の再来日などが記憶に新しい。それはアーティストの意思次第としかいえない。
ただ、ポピュラーミュージックが飽和状態な現在で何年も活動を休止することは実際のところ得策ではないだろう。他に聴く音楽がたくさんあるとすれば、その間に多くのファンはそっちに流れていってしまう。それでもミュージシャンの活動再開した時にまた迎えてくれるのが真のファンとか支持者なのだろう。
そういうことを考えると、いまだに大滝詠一(この人はたぶん「活動休止」とか「引退」とかは明言していないはず)の新作を25年以上待ち続けている「ナイアガラー」の皆さんは本当に凄い。
こういうミスはどう防ぐ?
2010年8月8日本日は仕事でなかなか手痛い失敗をした。現在、部屋で落ち込みながら日記を書いている。しかしいつまでそんな状態になっていても仕方ない。そこで次回は失敗しない方策を考えている。
だが、私の頭の中では解決方法が一向に見えてこない。本日の業務内容の流れを抽象的に表現するとこういう感じである。
(1)私がある作業Xをおこない、某団体Aに引き渡す。
(2)団体Aが作業Xを仕上げる。
(3)直前に団体Aと私が作業Xの最終点検をする。
(4)作業Xの本番
というのがこれまでの流れである。だが今日は最初に私の業務(1)でミスをしてしまい、さらに(3)の団体Aと私による直前確認を怠ったため失敗が引き起きてしまった。簡単にいえば、私のミスを先方が見つけることができなかったわけだ。
こういう作業の場合、失敗を回避するための方法は2つしかない。(3)の団体Aと私の相互点検を強化するか、(1)でそもそも私がミスをしないようにするか。それだけだ。
現実的には(3)の事前チェックを手厚くするのが安全だと考える人が多いに違いない。確かに一人で作業をするより他人の目があった方がミスをする確率は減る。しかし、もし先方の団体Aが全く機能せず点検も全くしてくれなくなったとしたら、どうだろう。相手に対して何も期待ができない。かといって、仕事で再び失敗をしたくもない。とすれば、自分のチェック機能を強化してミスを防ぐしか方法は残されていないことになる。
しかし、それは同時に自分の業務内容が増えることも意味する。以前は先方がしていた作業をひっかぶるのだから当然だ。自分で仕事を被れるなら被れや、という意見の方もいるだろう。だが私はこの9年ほどずっとそんな感じで業務を押しつけられて被り続けてきている。同じ仕事を何年も続けているうちに、相手がしている業務がどんどんこちらに移行されてしまうのだ。いままでは、それも運命だ使命だ、と自分に言い聞かせて我慢してきた部分もある。しかし、残念ながら人間の能力や集中力には限界というものがある。時々そんなことがボロっと出てきて今日のような失敗が出てきた。私の反省というか分析はそんなところだ。
誰かが私のことを完璧主義と言った記憶があるが、実際のところ自分の頭や能力など全く信用していない人間だ。だからこそ事前に色々と準備をして、失敗してもすぐなんとかなるような予防線をいくつも張っている。そして、それでもミスをしてしまう。基本的に、人間ひとりの力などたかがしれているからだ。
それでも、引き続き来年も同じ業務をおこなう可能性は高い。果たして次回はどうやってそれに臨むのか。そのはっきりした方針はまだ見えてこない。ただ、自分で何もかもひっかぶるのはもはや限界な気がしてくる。
個人の努力や工夫や注意だけでどうにかなるのだったら、そもそも失敗など起きるはずがないのだから。
だが、私の頭の中では解決方法が一向に見えてこない。本日の業務内容の流れを抽象的に表現するとこういう感じである。
(1)私がある作業Xをおこない、某団体Aに引き渡す。
(2)団体Aが作業Xを仕上げる。
(3)直前に団体Aと私が作業Xの最終点検をする。
(4)作業Xの本番
というのがこれまでの流れである。だが今日は最初に私の業務(1)でミスをしてしまい、さらに(3)の団体Aと私による直前確認を怠ったため失敗が引き起きてしまった。簡単にいえば、私のミスを先方が見つけることができなかったわけだ。
こういう作業の場合、失敗を回避するための方法は2つしかない。(3)の団体Aと私の相互点検を強化するか、(1)でそもそも私がミスをしないようにするか。それだけだ。
現実的には(3)の事前チェックを手厚くするのが安全だと考える人が多いに違いない。確かに一人で作業をするより他人の目があった方がミスをする確率は減る。しかし、もし先方の団体Aが全く機能せず点検も全くしてくれなくなったとしたら、どうだろう。相手に対して何も期待ができない。かといって、仕事で再び失敗をしたくもない。とすれば、自分のチェック機能を強化してミスを防ぐしか方法は残されていないことになる。
しかし、それは同時に自分の業務内容が増えることも意味する。以前は先方がしていた作業をひっかぶるのだから当然だ。自分で仕事を被れるなら被れや、という意見の方もいるだろう。だが私はこの9年ほどずっとそんな感じで業務を押しつけられて被り続けてきている。同じ仕事を何年も続けているうちに、相手がしている業務がどんどんこちらに移行されてしまうのだ。いままでは、それも運命だ使命だ、と自分に言い聞かせて我慢してきた部分もある。しかし、残念ながら人間の能力や集中力には限界というものがある。時々そんなことがボロっと出てきて今日のような失敗が出てきた。私の反省というか分析はそんなところだ。
誰かが私のことを完璧主義と言った記憶があるが、実際のところ自分の頭や能力など全く信用していない人間だ。だからこそ事前に色々と準備をして、失敗してもすぐなんとかなるような予防線をいくつも張っている。そして、それでもミスをしてしまう。基本的に、人間ひとりの力などたかがしれているからだ。
それでも、引き続き来年も同じ業務をおこなう可能性は高い。果たして次回はどうやってそれに臨むのか。そのはっきりした方針はまだ見えてこない。ただ、自分で何もかもひっかぶるのはもはや限界な気がしてくる。
個人の努力や工夫や注意だけでどうにかなるのだったら、そもそも失敗など起きるはずがないのだから。
昔の日記をたどってみたら
2010年8月1日以前からなんとなく、昔の日記の中身を確認する必要があるかなと考えていた。
「寺之内日記」と名付けてブログを書き始めたのは2002年の10月からである。それより前(2001年前後)にも書いてはいたものの、パソコンではなくセガのゲーム機「ドリームキャスト」にテレビをつないでネットをするというものだった。そのサイト自体が消滅してしまったため再び見ることはできない。確か「イサオ・ネット(isao.net)」とかいう名前だった。
ひとまず2002年10月の始まりから半年ほどザッと文章を読んでみた。その頃の日記と現在のものと決定的に違う点は、文字数がかなり少なめになっていることだ。内容はあくまで「日記」に徹していて自分の身辺について書いていたからだろう。何かについて長々と論ずるというのは少なかった。しかし以前の自分は毎日のように日記を更新していたのだからなかなか立派である。確か、「日記」とタイトルをつけているのだから毎日書かなければならない、と思い込んでいたような気がする。
そんな中で2004年の日記をふと見ていると「CDウォークマン」という単語を見つける。そういえばこの時期はまだiPodを持っておらず、CDウォークマンといくつかCDを持って外を出歩いたり旅行に行ったりしていた。ちなみCDウォークマンは振動に弱く、電車が激しく揺れたりすると「音飛び」が起きる。などといっても、今の子どもにはわからないかもしれないな。
2002年の自分と今の自分はたいして変わってないと思っていたけれど、持っているものも含めて現在とは色々と違う部分もたくさんあるのだろう。日記を振り返ってみるとそうしたものがたくさん出てくるに違いない。
しかし、文章についてはあまり今と大差がないような気もする。この辺りをどうするべきか。
「寺之内日記」と名付けてブログを書き始めたのは2002年の10月からである。それより前(2001年前後)にも書いてはいたものの、パソコンではなくセガのゲーム機「ドリームキャスト」にテレビをつないでネットをするというものだった。そのサイト自体が消滅してしまったため再び見ることはできない。確か「イサオ・ネット(isao.net)」とかいう名前だった。
ひとまず2002年10月の始まりから半年ほどザッと文章を読んでみた。その頃の日記と現在のものと決定的に違う点は、文字数がかなり少なめになっていることだ。内容はあくまで「日記」に徹していて自分の身辺について書いていたからだろう。何かについて長々と論ずるというのは少なかった。しかし以前の自分は毎日のように日記を更新していたのだからなかなか立派である。確か、「日記」とタイトルをつけているのだから毎日書かなければならない、と思い込んでいたような気がする。
そんな中で2004年の日記をふと見ていると「CDウォークマン」という単語を見つける。そういえばこの時期はまだiPodを持っておらず、CDウォークマンといくつかCDを持って外を出歩いたり旅行に行ったりしていた。ちなみCDウォークマンは振動に弱く、電車が激しく揺れたりすると「音飛び」が起きる。などといっても、今の子どもにはわからないかもしれないな。
2002年の自分と今の自分はたいして変わってないと思っていたけれど、持っているものも含めて現在とは色々と違う部分もたくさんあるのだろう。日記を振り返ってみるとそうしたものがたくさん出てくるに違いない。
しかし、文章についてはあまり今と大差がないような気もする。この辺りをどうするべきか。
桃屋「辛そうで辛くない少し辛いラー油」を食べてみた
2010年7月31日先日オークションで落札した「食べるラー油」こと桃屋「辛そうで辛くない少し辛いラー油」が届いたので郵便局へ引き取りに行った。さっそく味を試してみたいこともあり、久しぶりに部屋でご飯を炊いてみる。そのまま昼食も作ったが、こんなことをするのは数ヶ月ぶりのことな気がする。
ご飯ができあがったのでラー油のフタを開けて箸でかき混ぜてみると、なにやら砂のようなジャリジャリした感触がする。この具がビンの底まで目一杯はいっていた。
ラベルを見ると主な材料は、
・食用なたね油
・フライドガーリック
・食用ごま油
・唐辛子
・フライドオニオン
などととなっている。材料を見る限り固形物はフライドガーリックとフライドオニオンくらいしかないから、このたくさん入ってるものの正体はニンニクとタマネギということか。
またラベルには、
「スプーンでよく混ぜ、具体と共にお召し上がり下さい」
と但し書きが書いてあった。わざわざ「スプーンで」と書いてあるのは何か意味があるのだろうか。
ひとまずご飯に乗せて食べてみるけれど、予測したほど濃い味付けがされていない。他の場所でも「食べるラー油」は食べたことがあるが、それも同じような感じだった。ご飯と共に食べるなら、同じ桃屋でも「ごはんですよ」や「搾菜」や「穂先メンマ やわらぎ」などの方が良いと思う。それらに比べたらこの「辛そうで辛くない少し辛いラー油」は「調味料」という感じがする。私が食べた率直な感想はそんなところだ。これを買った人の多くはご飯に乗せて食べているのだろうか。
ご飯ができあがったのでラー油のフタを開けて箸でかき混ぜてみると、なにやら砂のようなジャリジャリした感触がする。この具がビンの底まで目一杯はいっていた。
ラベルを見ると主な材料は、
・食用なたね油
・フライドガーリック
・食用ごま油
・唐辛子
・フライドオニオン
などととなっている。材料を見る限り固形物はフライドガーリックとフライドオニオンくらいしかないから、このたくさん入ってるものの正体はニンニクとタマネギということか。
またラベルには、
「スプーンでよく混ぜ、具体と共にお召し上がり下さい」
と但し書きが書いてあった。わざわざ「スプーンで」と書いてあるのは何か意味があるのだろうか。
ひとまずご飯に乗せて食べてみるけれど、予測したほど濃い味付けがされていない。他の場所でも「食べるラー油」は食べたことがあるが、それも同じような感じだった。ご飯と共に食べるなら、同じ桃屋でも「ごはんですよ」や「搾菜」や「穂先メンマ やわらぎ」などの方が良いと思う。それらに比べたらこの「辛そうで辛くない少し辛いラー油」は「調味料」という感じがする。私が食べた率直な感想はそんなところだ。これを買った人の多くはご飯に乗せて食べているのだろうか。
二毛作や三毛作の飲食店経営
2010年7月29日YAHOOのトップを見ていると、
「二毛作、三毛作飲食店が急増」
という見出しが目につく。この記事は「週刊文春」2010年8月5日号のものであった。一般に「二毛作」といえば、同じ耕地で一年に二回、別々な作物を栽培することを指すが、ここでの話は飲食店のことだ。たとえば昼はラーメン店だが夜は居酒屋を経営する、といった営業形態のことである。そして東京や大阪でこのような店が増加しているらしい。
大阪の京橋にある「立ち呑み畑ECODEN」にいたっては、朝がモーニング喫茶、昼はクレープ、そして夜は立ち飲みの「三毛作」をしているという。そういえばここ京都でも、一乗寺にある老舗のラーメン店「天天有」がいままで夜のみの営業だったのを、この5月から昼間の営業も開始し「ひるまや」という屋号で夜とは全く違うタイプのラーメンを提供するようになった事例もある。
しかしながら、果たして二毛作だの三毛作だのといった経営手法はそれほど優れたものなのだろうか。昼と夜で全く違う営業をするとしたら、仕込み・オペレーション・片付けなどの作業がいずれも変わってくる。それは作業量の増加にほかならない。
「設備費や食材、人材コストの削減が可能」(西葛西で三毛作の飲食店を営業している店の経営母体である「APカンパニー」広報担当・岡田英樹氏の発言)などと記事では書いてあるが、この西葛西の事例は同じ店舗の中で外食・中食・小売りの3つをおこなっているという形態である。このような真似は人手の足りない飲食店では到底できない。
パッと考えれば二毛作や三毛作はメリットよりデメリットの方が目立つ。それでもあえて利点があるとすれば、居酒屋やラーメン屋など1つの業種で勝負するよりも複数の業種になればその分だけ当たる確率が増えることくらいか。これはこれで一つの重要な要素かもしれないが、むやみやたらに業種を増やすのが賢い選択でもないだろう。
この記事の最後で、フードビジネスニュースサイト「フードスタジアム」の佐藤こうぞう編集長の分析が載っているが、
「飲食店が不況で厳しいなか、うちは何屋ですという打ち出し方が限界にきている。」
というのも意味がよくわからない。どんな業種にせよセールスポイントのわからないような店が成功するわけがない。やはり二毛作・三毛作は「数打ちゃ当たる」の実践なのだろう。
そもそもこの週刊文春で取り上げられている店の中で、例えば昼も夜も繁盛しているような事例があるのだろうか。この記事を読んでその辺がもっとも疑問に残った。
「二毛作、三毛作飲食店が急増」
という見出しが目につく。この記事は「週刊文春」2010年8月5日号のものであった。一般に「二毛作」といえば、同じ耕地で一年に二回、別々な作物を栽培することを指すが、ここでの話は飲食店のことだ。たとえば昼はラーメン店だが夜は居酒屋を経営する、といった営業形態のことである。そして東京や大阪でこのような店が増加しているらしい。
大阪の京橋にある「立ち呑み畑ECODEN」にいたっては、朝がモーニング喫茶、昼はクレープ、そして夜は立ち飲みの「三毛作」をしているという。そういえばここ京都でも、一乗寺にある老舗のラーメン店「天天有」がいままで夜のみの営業だったのを、この5月から昼間の営業も開始し「ひるまや」という屋号で夜とは全く違うタイプのラーメンを提供するようになった事例もある。
しかしながら、果たして二毛作だの三毛作だのといった経営手法はそれほど優れたものなのだろうか。昼と夜で全く違う営業をするとしたら、仕込み・オペレーション・片付けなどの作業がいずれも変わってくる。それは作業量の増加にほかならない。
「設備費や食材、人材コストの削減が可能」(西葛西で三毛作の飲食店を営業している店の経営母体である「APカンパニー」広報担当・岡田英樹氏の発言)などと記事では書いてあるが、この西葛西の事例は同じ店舗の中で外食・中食・小売りの3つをおこなっているという形態である。このような真似は人手の足りない飲食店では到底できない。
パッと考えれば二毛作や三毛作はメリットよりデメリットの方が目立つ。それでもあえて利点があるとすれば、居酒屋やラーメン屋など1つの業種で勝負するよりも複数の業種になればその分だけ当たる確率が増えることくらいか。これはこれで一つの重要な要素かもしれないが、むやみやたらに業種を増やすのが賢い選択でもないだろう。
この記事の最後で、フードビジネスニュースサイト「フードスタジアム」の佐藤こうぞう編集長の分析が載っているが、
「飲食店が不況で厳しいなか、うちは何屋ですという打ち出し方が限界にきている。」
というのも意味がよくわからない。どんな業種にせよセールスポイントのわからないような店が成功するわけがない。やはり二毛作・三毛作は「数打ちゃ当たる」の実践なのだろう。
そもそもこの週刊文春で取り上げられている店の中で、例えば昼も夜も繁盛しているような事例があるのだろうか。この記事を読んでその辺がもっとも疑問に残った。
早起きは三文の得、とは言うものの
2010年7月28日今日の午前中は休みをもらった。午後出勤の場合は2時までに出社すれば構わないのだけれど、こんな日に限ってなぜか午前5時に目が覚めてしまう。そんな時は二度寝してしまうものであるが、今日は珍しくスッキリと起きてしまったようで再び眠れそうにない。
しかたないので、とりあえずパソコンを立ち上げてテレビの電源を入れる。6チャンネルでは「おはようコールABC」(朝日放送)がすでに始まっていて、辻元清美議員の社民党離党表明や沢尻エリカのセミヌードが紹介されていた。続く6時45分からの「おはよう朝日です」でも同じ内容のニュースが紹介され、8時の「スーパーモーニング」に至っては辻元清美本人が生でスタジオに出演していた。仕方ない話だけれど、朝のニュースは立て続けに同じ話題が出てくる。
テレビばかり見ていても仕方ないので、6時半くらいに朝食を済ませ、あとはニンテンドウDSで「英語漬け」や「美文字トレーニング」をして、それから新聞の朝刊を読んでいた。そんなことをしていても、時計はまだ8時半くらいだった。まだまだ時間がある。
いつものパターンだったらこれほど時間に余裕が出るのはありえない。目覚まし時計をセットしている時間はたいてい7時だけれど、いったん起きて目覚ましを止めてパソコンとテレビをつけると、また寝てしまうのが常だ。そして再び起きるのが8時か8時半くらいで、そこから急いで食事と身支度を済ませて9時ごろに部屋を出る。私の朝はだいたいこんな感じだ。
早起きをすればずいぶん時間が作れるものだ。もしその気があれば部屋を出る前に新書1冊くらい読めるだろう。一瞬そんなことを考えたが、一方で現在の自分では無理だろうなという思いもある。私は昔から朝が弱く、大学時代は朝の授業をたびたび寝坊していた。当時の血圧にしても上が100を切るくらいの低さだった。それでも勤めてからは毎日朝7時に目を覚ますような習慣を続けていくうちに、血圧も人並みくらいの水準に変化する。ただ血圧が高くなったからといって朝が強くなったというわけでもなく、朝の目覚めは相変わらず心地よくはない。
よく考えれば、最近は妙に朝早くにパッと目が覚めてしまう場面がたびたびあった。老化現象なのかはともかく、いつかスッキリと朝を迎えられるような日が私にも訪れるかもしれない。
しかたないので、とりあえずパソコンを立ち上げてテレビの電源を入れる。6チャンネルでは「おはようコールABC」(朝日放送)がすでに始まっていて、辻元清美議員の社民党離党表明や沢尻エリカのセミヌードが紹介されていた。続く6時45分からの「おはよう朝日です」でも同じ内容のニュースが紹介され、8時の「スーパーモーニング」に至っては辻元清美本人が生でスタジオに出演していた。仕方ない話だけれど、朝のニュースは立て続けに同じ話題が出てくる。
テレビばかり見ていても仕方ないので、6時半くらいに朝食を済ませ、あとはニンテンドウDSで「英語漬け」や「美文字トレーニング」をして、それから新聞の朝刊を読んでいた。そんなことをしていても、時計はまだ8時半くらいだった。まだまだ時間がある。
いつものパターンだったらこれほど時間に余裕が出るのはありえない。目覚まし時計をセットしている時間はたいてい7時だけれど、いったん起きて目覚ましを止めてパソコンとテレビをつけると、また寝てしまうのが常だ。そして再び起きるのが8時か8時半くらいで、そこから急いで食事と身支度を済ませて9時ごろに部屋を出る。私の朝はだいたいこんな感じだ。
早起きをすればずいぶん時間が作れるものだ。もしその気があれば部屋を出る前に新書1冊くらい読めるだろう。一瞬そんなことを考えたが、一方で現在の自分では無理だろうなという思いもある。私は昔から朝が弱く、大学時代は朝の授業をたびたび寝坊していた。当時の血圧にしても上が100を切るくらいの低さだった。それでも勤めてからは毎日朝7時に目を覚ますような習慣を続けていくうちに、血圧も人並みくらいの水準に変化する。ただ血圧が高くなったからといって朝が強くなったというわけでもなく、朝の目覚めは相変わらず心地よくはない。
よく考えれば、最近は妙に朝早くにパッと目が覚めてしまう場面がたびたびあった。老化現象なのかはともかく、いつかスッキリと朝を迎えられるような日が私にも訪れるかもしれない。
思わず入札、そして落札
2010年7月27日
いわゆる「食べるラー油」の人気はいまだに収まっていない。便乗商品がたくさん出回っているものの、ブームの火付け役となった桃屋の「辛そうで辛くない少し辛いラー油」は品薄状態であり、ショッピングサイトを覗いても全く見つからない。エスビー食品から出ている「ぶっかけ!おかずラー油」も同様だ。無論、スーパーやコンビニなどを回っても見当たらない。だが入手困難だと欲しくなってしまうのが人情である。
そういう状況の中で商品が確実に出回っているのがオークションサイトだ。YAHOO!オークションを調べたらやはりかなりの数が出てくるし、ご丁寧に桃屋とエスビーを1個ずつ付けた「食べ比べ2個セット」まで置いてある。
見ていると余計にほしくなったので、その中の一つを何気なく入札してみた。入札金額は1000円に設定する。1時間半ほどして時間切れとなったので、確認してみると540円で落札することができた。実際の価格は400円(税込)だから、個人的にはまあまあ手ごろな値に落ち着いたかなという感じだ。
しかしながらここに送料が500円かかり、さらに「Yahoo!かんたん決済」というシステムを通じて入金する際に「決済手数料」とやらが198円派生するため、合計1198円を費やすことになる。結局は定価の3倍ほどの値段で購入したことになる。これを高いと思う人も多いかもしれないが、もう買ってしまったのだから仕方ない。すみやかに先方へ入金を済ませて現物の到着を待ちたい。
そういう状況の中で商品が確実に出回っているのがオークションサイトだ。YAHOO!オークションを調べたらやはりかなりの数が出てくるし、ご丁寧に桃屋とエスビーを1個ずつ付けた「食べ比べ2個セット」まで置いてある。
見ていると余計にほしくなったので、その中の一つを何気なく入札してみた。入札金額は1000円に設定する。1時間半ほどして時間切れとなったので、確認してみると540円で落札することができた。実際の価格は400円(税込)だから、個人的にはまあまあ手ごろな値に落ち着いたかなという感じだ。
しかしながらここに送料が500円かかり、さらに「Yahoo!かんたん決済」というシステムを通じて入金する際に「決済手数料」とやらが198円派生するため、合計1198円を費やすことになる。結局は定価の3倍ほどの値段で購入したことになる。これを高いと思う人も多いかもしれないが、もう買ってしまったのだから仕方ない。すみやかに先方へ入金を済ませて現物の到着を待ちたい。