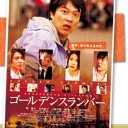「日本経済新聞 電子版」の行方は
2010年3月22日日本経済新聞がいよいよ明日から有料ニュースサイト「日本経済新聞 電子版」を開始する。これまではニュースを「NIKKEI.NET」で無料配信したものを、これからは有料購読者しか読めなくするわけだ。これまでのマス・メディアの流れを考えるとかなりの英断といえる。
この日経の姿勢に対し、「NIKKEI.NET」3月8日11時54分配信の、「『フリー』に挑む日経電子版の勇気ある社会実験」というコラムが掲載された。書いたのは慶応義塾大学大学院教授の岸博幸さんという人だ。岸さんは日経電子版を、「マスメディアが無料モデル(広告モデル)のネット事業でなかなか収益を上げられないなか、最適なビジネスモデルを探求しようとする重要な実験的取り組み」と位置づける。
岸さんはまず、「マスメディアがネット上で広告モデルを続けていても、絶対に儲からない」と指摘する。
ネット広告は大きく分けて、
・検索連動広告
・ディスプレー広告(バナー、動画など)
・その他(携帯広告など)
の3種類になるが、高い収益を上げているのはグーグルに代表される検索連動広告である。その一方、「ディスプレー広告の単価は世界中で下がり続けている」。無料サイトを作って広告で収益を上げるという方法はもはや頭打ちの状態というわけだ。だからマスメディアは新たな収益モデルを探さなければならないし、日経電子版はその一つとして岸さんは高い評価をしている。
しかしながら一方、日経電子版が成功するためには解決しなければならない課題も挙げている。
「無料に慣れ、デフレ下で生き抜く術を身に付けたユーザーは本当にシビアだからだ。『NHKオンデマンド』の失敗からも明らかなように、他の方法で無料で見られるものにお金を払う人は少ない。(中略)特にニュースは大変である。他のマスメディアが提供するコンテンツとの差別化が困難だからである。自社の紙の新聞と差別化し、かつ他のメディアとも十分に違いのあるコンテンツを提供しなければ、ユーザーは納得しないだろう」
多くの人も感じることだろうが、これまではタダで見ていたものに果たして金を払うかどうかという話だ。日経電子版はネット購読のみの「電子版月ぎめプラン」で料金が月額4000円かかる。これを受け入れられる人がそれほどいるかどうか。これは切実な問題だ。
これに対して岸さんは一つの方向性を示している。
「いろいろなコンテンツの世界に接してつくづく感じるのだが、どんなコンテンツでもユーザーは1対9に分かれる。前者はヘビーユーザーで、そのコンテンツが大好きあるいは不可欠だからいくらでもお金を払う。後者はライトユーザーで、そのコンテンツは好きだがお金を払う気はなく、無料で楽しめればそれでオーケーという層である。」
これは、こないだ私が買ったクリス・アンダーソン「フリー <無料>からお金を生み出す新戦略」(NHK出版、09年)に載っていた「フリーミアム(Freemium)」の考えに通じる。フリーミアムとはウェブの世界では一般的なビジネス・モデルである。例えばある会社の無料ソフトを利用した人の一部が、それを気に入ってもっと機能の豊富な有料ソフトを買うようになるというのがそれだ。
このビジネス・モデルの特徴的なことは、利用者全体のうちで有料ユーザーの占める割合が5%ほどしかいないという点だ。デジタルの世界ではサービスを提供するためのコストが限りなく低いので、有料ユーザーが20人に1人しかいなくても十分にやっていけるのである。
こうしたことを念頭におくと、日経電子版が生き抜くための方法はおぼろげながら見えてくるだろう。まず大量の無料ユーザーを囲い込み、そこから例えば5%の有料ユーザーを獲得して採算ラインにもっていく。これしかない。
さきほど指摘した「他のマスメディアが提供するコンテンツとの差別化」というのも、日経にはそれほど困難なこととは思えない。例えば勝間和代(経済評論家)さんはその著書「無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法」(07年、ディスカバー)で、
「ビジネスマンはなぜ日経新聞を読むのか?それは、記事の良し悪しはともかく、『みんなが読んでいるから』です。だからもちろん、あなたも読まなければなりません」(P.180)
と述べている。こうした人も世の中に結構いるような気がするからだ。
ちなみに日経電子版は無料登録ユーザーでも特ダネ記事を20本読むことができる。これを目当てに登録する人は多いだろうが、果たしてそこから有料ユーザーがどれくらい出てきてくれるか。その辺りを含めて、今後の日経の動きに注目してみたい。
この日経の姿勢に対し、「NIKKEI.NET」3月8日11時54分配信の、「『フリー』に挑む日経電子版の勇気ある社会実験」というコラムが掲載された。書いたのは慶応義塾大学大学院教授の岸博幸さんという人だ。岸さんは日経電子版を、「マスメディアが無料モデル(広告モデル)のネット事業でなかなか収益を上げられないなか、最適なビジネスモデルを探求しようとする重要な実験的取り組み」と位置づける。
岸さんはまず、「マスメディアがネット上で広告モデルを続けていても、絶対に儲からない」と指摘する。
ネット広告は大きく分けて、
・検索連動広告
・ディスプレー広告(バナー、動画など)
・その他(携帯広告など)
の3種類になるが、高い収益を上げているのはグーグルに代表される検索連動広告である。その一方、「ディスプレー広告の単価は世界中で下がり続けている」。無料サイトを作って広告で収益を上げるという方法はもはや頭打ちの状態というわけだ。だからマスメディアは新たな収益モデルを探さなければならないし、日経電子版はその一つとして岸さんは高い評価をしている。
しかしながら一方、日経電子版が成功するためには解決しなければならない課題も挙げている。
「無料に慣れ、デフレ下で生き抜く術を身に付けたユーザーは本当にシビアだからだ。『NHKオンデマンド』の失敗からも明らかなように、他の方法で無料で見られるものにお金を払う人は少ない。(中略)特にニュースは大変である。他のマスメディアが提供するコンテンツとの差別化が困難だからである。自社の紙の新聞と差別化し、かつ他のメディアとも十分に違いのあるコンテンツを提供しなければ、ユーザーは納得しないだろう」
多くの人も感じることだろうが、これまではタダで見ていたものに果たして金を払うかどうかという話だ。日経電子版はネット購読のみの「電子版月ぎめプラン」で料金が月額4000円かかる。これを受け入れられる人がそれほどいるかどうか。これは切実な問題だ。
これに対して岸さんは一つの方向性を示している。
「いろいろなコンテンツの世界に接してつくづく感じるのだが、どんなコンテンツでもユーザーは1対9に分かれる。前者はヘビーユーザーで、そのコンテンツが大好きあるいは不可欠だからいくらでもお金を払う。後者はライトユーザーで、そのコンテンツは好きだがお金を払う気はなく、無料で楽しめればそれでオーケーという層である。」
これは、こないだ私が買ったクリス・アンダーソン「フリー <無料>からお金を生み出す新戦略」(NHK出版、09年)に載っていた「フリーミアム(Freemium)」の考えに通じる。フリーミアムとはウェブの世界では一般的なビジネス・モデルである。例えばある会社の無料ソフトを利用した人の一部が、それを気に入ってもっと機能の豊富な有料ソフトを買うようになるというのがそれだ。
このビジネス・モデルの特徴的なことは、利用者全体のうちで有料ユーザーの占める割合が5%ほどしかいないという点だ。デジタルの世界ではサービスを提供するためのコストが限りなく低いので、有料ユーザーが20人に1人しかいなくても十分にやっていけるのである。
こうしたことを念頭におくと、日経電子版が生き抜くための方法はおぼろげながら見えてくるだろう。まず大量の無料ユーザーを囲い込み、そこから例えば5%の有料ユーザーを獲得して採算ラインにもっていく。これしかない。
さきほど指摘した「他のマスメディアが提供するコンテンツとの差別化」というのも、日経にはそれほど困難なこととは思えない。例えば勝間和代(経済評論家)さんはその著書「無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法」(07年、ディスカバー)で、
「ビジネスマンはなぜ日経新聞を読むのか?それは、記事の良し悪しはともかく、『みんなが読んでいるから』です。だからもちろん、あなたも読まなければなりません」(P.180)
と述べている。こうした人も世の中に結構いるような気がするからだ。
ちなみに日経電子版は無料登録ユーザーでも特ダネ記事を20本読むことができる。これを目当てに登録する人は多いだろうが、果たしてそこから有料ユーザーがどれくらい出てきてくれるか。その辺りを含めて、今後の日経の動きに注目してみたい。
音楽ギフトカードの消滅
2010年3月21日ファミリーマートと「ぴあ」が業務提携を解消するニュースに続き、またも気の滅入るような話が入ってきた。
3月21日7時56分配信の産経新聞によれば、全国約7千店の加盟CDショップや楽器店などでCDやDVDなどを購入できる「音楽ギフトカード」の発売が今月末の出荷分で終了するという。
発売元の「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」の広報担当者は、
「音楽業界を取り巻く環境は年々、厳しさを増しており、音楽ギフトカードの発行を継続していくことは困難との結論に達した」
と言っている。非常に抽象的な言い方だが実際の話は単純で、音楽配信の普及によってCDの売り上げが減ってきているためだ。それにより音楽ギフトカードを使う人も少なくなったわけである。
記事には日本レコード協会のデータも紹介されている。それによれば昨年(09年)の音楽配信の売上金額は約909億8200万円と、この10年で過去最高であった。しかしそれとは対照的に、CDなどオーディオの生産金額は約2496億3200万円と過去10年で最少となっている。
確かに数字を見ているだけでも、CDなどを取り巻く環境は厳しくなっているのは間違いない。しかしパソコンや携帯を通じて音楽を買う(またはタダで聴く)流れはもはや止められない。mp3プレーヤーを使っている人から見れば、CDなど大きくて煩わしい存在にしか見えないだろう。
しかし音楽ギフトカードが消滅した先に待っているのは、まずCDを売る店舗が無くなっていき、それからCDそのものが消えていくという流れである。実際アメリカではそのようになっているし、遠くない将来にこの国でも起きるに違いない。
ネットをつなげば音楽や映像が溢れており、それを無料で享受できて当たり前と思う人も増えている。こうした流れを歓迎できない私のような人間にとっては、今回のニュースはあまり気持ちの良いものではなかった。
3月21日7時56分配信の産経新聞によれば、全国約7千店の加盟CDショップや楽器店などでCDやDVDなどを購入できる「音楽ギフトカード」の発売が今月末の出荷分で終了するという。
発売元の「ジャパン・ミュージック・ギフトカード」の広報担当者は、
「音楽業界を取り巻く環境は年々、厳しさを増しており、音楽ギフトカードの発行を継続していくことは困難との結論に達した」
と言っている。非常に抽象的な言い方だが実際の話は単純で、音楽配信の普及によってCDの売り上げが減ってきているためだ。それにより音楽ギフトカードを使う人も少なくなったわけである。
記事には日本レコード協会のデータも紹介されている。それによれば昨年(09年)の音楽配信の売上金額は約909億8200万円と、この10年で過去最高であった。しかしそれとは対照的に、CDなどオーディオの生産金額は約2496億3200万円と過去10年で最少となっている。
確かに数字を見ているだけでも、CDなどを取り巻く環境は厳しくなっているのは間違いない。しかしパソコンや携帯を通じて音楽を買う(またはタダで聴く)流れはもはや止められない。mp3プレーヤーを使っている人から見れば、CDなど大きくて煩わしい存在にしか見えないだろう。
しかし音楽ギフトカードが消滅した先に待っているのは、まずCDを売る店舗が無くなっていき、それからCDそのものが消えていくという流れである。実際アメリカではそのようになっているし、遠くない将来にこの国でも起きるに違いない。
ネットをつなげば音楽や映像が溢れており、それを無料で享受できて当たり前と思う人も増えている。こうした流れを歓迎できない私のような人間にとっては、今回のニュースはあまり気持ちの良いものではなかった。
ファミリーマートと「ぴあ」の業務提携が解消
2010年3月19日コンビニのファミリーマートとチケット販売のエンタテインメントプラス(「イープラス」の会社)が資本提携すると19日に発表された。産経新聞の記事によれば、この不況でも堅調なオンラインチケットサービス事業分野の強化をファミマは目指しているという。だがそれに伴い、これまで提携してきた「ぴあ」との関係が5月末をもって解消される。
ライブのチケットのほとんどをチケットぴあで買っている私としては、このニュースに少なからず衝撃を受けた。ここ数年のチケットはもちろんネットを通して買っている。そしてチケットの引き取り方法は2種類ある。一つは郵送、もう一つはファミマにある端末「Famiポート」から発券する方法だ。郵送はもちろん代金がかかる。よって発券はいつもファミマでおこなっていた。
それが6月以降、どうなってしまうのだろうか。まだパソコンがそれほど普及してなかった頃は、電話でチケットを予約して「ぴあ」のマークの貼ってあるプレイガイドで発券してもらうのが常だった。私はいつもKBS京都の建物の中にあるプレイガイドで引き取りをしていたものである。最近はライブ直前にそこらのファミマで発券すれば事足りていたが、もうそれもできなくなる。これは面倒な話であり、これまで全国に持っていたチケット端末が無くなってしまう「ぴあ」はもっと大きな痛手である。
週明けは「ぴあ」の株価もガクッと下がるだろう。あーあ。
ライブのチケットのほとんどをチケットぴあで買っている私としては、このニュースに少なからず衝撃を受けた。ここ数年のチケットはもちろんネットを通して買っている。そしてチケットの引き取り方法は2種類ある。一つは郵送、もう一つはファミマにある端末「Famiポート」から発券する方法だ。郵送はもちろん代金がかかる。よって発券はいつもファミマでおこなっていた。
それが6月以降、どうなってしまうのだろうか。まだパソコンがそれほど普及してなかった頃は、電話でチケットを予約して「ぴあ」のマークの貼ってあるプレイガイドで発券してもらうのが常だった。私はいつもKBS京都の建物の中にあるプレイガイドで引き取りをしていたものである。最近はライブ直前にそこらのファミマで発券すれば事足りていたが、もうそれもできなくなる。これは面倒な話であり、これまで全国に持っていたチケット端末が無くなってしまう「ぴあ」はもっと大きな痛手である。
週明けは「ぴあ」の株価もガクッと下がるだろう。あーあ。
ピンク・フロイドのアーティスト美学に天晴れ!
2010年3月18日1週間ほど前の話題で申し訳ないが、どうしても書きたい話なので遅ればせながら述べさせてもらう。
3月12日21時14分配信の「BARKS」の記事によれば、自分たちの曲をオンラインで個別販売していたEMIをピンク・フロイドが訴え勝訴したという。
MPプレーヤーで音楽を聴くのが当然と感じている若い人たちは、曲を個別に売られて訴えるなんてこいつら何を考えてるんだ?と思う方ももしかしたらいるかもしれない。
しかしレコードやCDで育った人にとっては、この判決は至極当然と受け止められるし、このような態度を取ったピンク・フロイドのメンバーに対して私は敬意すら抱いてしまう。これは、パクったパクられたとか、曲を無断でネットに流されたとかいったようなケチ臭い話とはレベルが違う。
ピンク・フロイドはシングル・カットというものには消極的なアーティストだ。それは「アルバム」という総体を一つの作品として考えていたからである。「原子心母(70年)」も「おせっかい」(71年)も「狂気」(73年)もそのようなアーティストの信念が込められたものであり、また聴き手もこうした人たちの姿勢を理解していたからこそ、これらの作品を「コンセプト・アルバム」と称したのだと思う。
それでも最近の人たちには理解できない話かもしれないが、「アルバムの芸術性を保護する」という契約をEMIが違反したという判決の指摘はまさにその通りといえる。
それにしても、かつては「CCCD」のような欠陥商品を推進しようとして失敗したEMIは、またしてもアーティストや音楽ファンの意向を無視するような態度を相変わらず続けているようだ。
3月12日21時14分配信の「BARKS」の記事によれば、自分たちの曲をオンラインで個別販売していたEMIをピンク・フロイドが訴え勝訴したという。
MPプレーヤーで音楽を聴くのが当然と感じている若い人たちは、曲を個別に売られて訴えるなんてこいつら何を考えてるんだ?と思う方ももしかしたらいるかもしれない。
しかしレコードやCDで育った人にとっては、この判決は至極当然と受け止められるし、このような態度を取ったピンク・フロイドのメンバーに対して私は敬意すら抱いてしまう。これは、パクったパクられたとか、曲を無断でネットに流されたとかいったようなケチ臭い話とはレベルが違う。
ピンク・フロイドはシングル・カットというものには消極的なアーティストだ。それは「アルバム」という総体を一つの作品として考えていたからである。「原子心母(70年)」も「おせっかい」(71年)も「狂気」(73年)もそのようなアーティストの信念が込められたものであり、また聴き手もこうした人たちの姿勢を理解していたからこそ、これらの作品を「コンセプト・アルバム」と称したのだと思う。
それでも最近の人たちには理解できない話かもしれないが、「アルバムの芸術性を保護する」という契約をEMIが違反したという判決の指摘はまさにその通りといえる。
それにしても、かつては「CCCD」のような欠陥商品を推進しようとして失敗したEMIは、またしてもアーティストや音楽ファンの意向を無視するような態度を相変わらず続けているようだ。
ボブ・ディラン大阪公演(10年3月11日、Zepp Osaka)
2010年3月11日 ライブ・レポートボブ・ディランの9年ぶりの来日公演を観るため久しぶりにZepp Osakaを訪れた。コスモスクエア駅を出ると、以前よりもまたマンションやビルの数が増えている。初めて訪れたのは10年前のBONNE PINKのライブの時だったが、当時は空地ばかりだった。大阪南港周辺の開発はどんどん進んでいるようである。
今日は整理番号の入場だったにもかかわらず開場時間ギリギリの到着だった。年配の人が目立つかと予測したけれど、待っているお客をパッと見た限りではバラバラの年齢層という感じである。しかしながら、入口に注意書きの大きな紙が張ってあったり、場内で長い長いアナウンスの注意がされたり、いつもならば入る時にドリンク代500円を徴収されるのが今回は無かったりと、色々な面で配慮をしているのは明らかだった。ディランがライブをしなければ生涯Zeppに来ることがなかったであろう人たちへの対応に主催者側もいろいろと苦慮したことが忍ばれる。
私の整理番号は355番と割と若い番号だったので、前から4列目くらいの中央の位置を確保することができた。あとは開演を待つばかりである。9年前の大阪公演では時間になったらブツンと客電が落ちて、再び明かりがついた時にはバンドが全て現れているという感じだった。今回もそれを期待していたけれど、今回はどうしたことか、開演時間の7時を10分ほど過ぎてもバンドは一向に登場しない。観客も明らかに動揺している。当の私もかなり不安が大きくなっていく。ミュージシャンが出てくるかどうかここまで心配になったのは、サマーソニックのモリッシー以来だ。ディランも今年で69歳であり昔のようにはなかなかいかなくなっているということなのだろうか。そして7時20分、場内が暗くなりようやくバンドとディランが現れる。
事前にネットで情報を得ていたが、最近のディランはギターではなくキーボードを弾きながら歌うという。座って演奏するのかと思ったら、立ってキーボードにも寄りかかるような格好で歌っていた。しかしながら実際にその姿を観ると、9年前のイメージも残っていたためか、現在のディランに違和感を抱いたことは否定できない。また曲によってはスタンドマイクの前でポーズをとったりハンドマイクで歌ったりという場面もあり、その違和感にさらなる拍車がかかった。この9年の間、ディランの心境に一体何が起きたのだろう。
とは言いながらも、やはり演奏が進んでいくにつれてそんなことはどうでも良くなっていった。以前ほど鬼気迫る雰囲気はなかった気もするが、チャーリー・セクストンを筆頭にバンドの音は実に素晴らしい。ドライブの効いた演奏は”追憶のハイウェイ61”あたりでピークを迎える。アンコールの最後はジミ・ヘンドリックスやニール・ヤングのカバーでも知られる”見張り塔からずっと”なのも良かった。それが終わってもお客は帰らず拍手を送り続けるも、2回目のアンコールは訪れず無念にも客電がついてしまった。いま振り返れば、バンドの音が以前と違うように感じた原因はディランが高齢になったとかではなくて、彼自身の弾くオルガンのようなキーボードが入ったからではないかと今では思う。
1万3000人が参加しているディランのmixiコミュニティの冒頭には、
「彼のテクや演奏をコピーしてもまったく意味は無い。 彼の出す全体的な雰囲気は誰にも真似ができないから。」
と書かれている。それは私が前回の来日公演で感じたことを見事に表している。9年前も現在も彼の曲はほとんど頭に入っていないけれど、パフォーマーとしてなんともいえない魅力に惹かれて今回もライブに行ったわけだ。そして、今回の彼に対しても同じ感想をもった次第である。
とは言いながら、部屋に戻ってからネットで演奏曲目を調べて思わず苦笑してしまった。会場に行く前は、前回の来日公演の予習のために買った「ボブ・ディラン・ライヴ!1961-2000~39イヤーズ・オブ・グレート・コンサート・パフォーマンス」(01年)を聴いていた。このアルバムに入っている曲もかなり含まれていた(”To Ramona”、”I Don’t Believe You”、”Cold Irons Bound”、”Things Have Changed”)にもかかわらず、全く気づかなかったからである。
「この曲、演奏されてたっけ?」
としばし呆然となった。彼の曲がまったく頭に入っていないとは言いながらも、それでもここまで全く気づかなかったのは情けないというしかない。
それはともかく、演奏曲目を見てみると、この15年あたりに作った作品の比率も低くないことに気づく。
「タイム・アウト・オブ・マインド」(97年)から2曲
「ラヴ・アンド・セフト」(01年)から1曲
「モダン・タイムズ」(06年)から3曲
「トゥゲザー・スルー・ライフ」(09年)から1曲
という感じである。”Things Have Changed”も近年の曲だから、ここ15年の曲目が半分くらいを占めることになる。この辺りは、自分がまだ現役のミュージシャンであることを主張しているようで頼もしい気がする。
最後に一つだけ記したい話がある。今回、ディランがギターを手に取ったのはわずか2曲だけだった。フォーク・シンガーというイメージが今でも強い人だから、そう思って会場に臨んだ人は面食らったに違いない。実際、ライブが終わった後で若い人が、ディランが全然ギターを持たなかった、みたいなことを耳にした。
それを聞いた私は、9年前はそうじゃなかったんだけどねえ、とほくそ笑んでいたのであった。
最後に演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)Watching The River Flow
(2)Girl Of The North Country
(3)Things Have Changed
(4)To Ramona
(5)High Water (For Charley Patton)
(6)Spirit On The Water
(7)The Levee’s Gonna Break
(8)I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
(9)Cold Irons Bound
(10)A Hard Rain’s A-Gonna Fall
(11)Highway 61 Revisited
(12)Can’t Wait
(13)Thunder On The Mountain
(14)Ballad Of A Thin Man
<アンコール>
(15)Like A Rolling Stone
(16)Jolene
(17)All Along The Watchtower
今日は整理番号の入場だったにもかかわらず開場時間ギリギリの到着だった。年配の人が目立つかと予測したけれど、待っているお客をパッと見た限りではバラバラの年齢層という感じである。しかしながら、入口に注意書きの大きな紙が張ってあったり、場内で長い長いアナウンスの注意がされたり、いつもならば入る時にドリンク代500円を徴収されるのが今回は無かったりと、色々な面で配慮をしているのは明らかだった。ディランがライブをしなければ生涯Zeppに来ることがなかったであろう人たちへの対応に主催者側もいろいろと苦慮したことが忍ばれる。
私の整理番号は355番と割と若い番号だったので、前から4列目くらいの中央の位置を確保することができた。あとは開演を待つばかりである。9年前の大阪公演では時間になったらブツンと客電が落ちて、再び明かりがついた時にはバンドが全て現れているという感じだった。今回もそれを期待していたけれど、今回はどうしたことか、開演時間の7時を10分ほど過ぎてもバンドは一向に登場しない。観客も明らかに動揺している。当の私もかなり不安が大きくなっていく。ミュージシャンが出てくるかどうかここまで心配になったのは、サマーソニックのモリッシー以来だ。ディランも今年で69歳であり昔のようにはなかなかいかなくなっているということなのだろうか。そして7時20分、場内が暗くなりようやくバンドとディランが現れる。
事前にネットで情報を得ていたが、最近のディランはギターではなくキーボードを弾きながら歌うという。座って演奏するのかと思ったら、立ってキーボードにも寄りかかるような格好で歌っていた。しかしながら実際にその姿を観ると、9年前のイメージも残っていたためか、現在のディランに違和感を抱いたことは否定できない。また曲によってはスタンドマイクの前でポーズをとったりハンドマイクで歌ったりという場面もあり、その違和感にさらなる拍車がかかった。この9年の間、ディランの心境に一体何が起きたのだろう。
とは言いながらも、やはり演奏が進んでいくにつれてそんなことはどうでも良くなっていった。以前ほど鬼気迫る雰囲気はなかった気もするが、チャーリー・セクストンを筆頭にバンドの音は実に素晴らしい。ドライブの効いた演奏は”追憶のハイウェイ61”あたりでピークを迎える。アンコールの最後はジミ・ヘンドリックスやニール・ヤングのカバーでも知られる”見張り塔からずっと”なのも良かった。それが終わってもお客は帰らず拍手を送り続けるも、2回目のアンコールは訪れず無念にも客電がついてしまった。いま振り返れば、バンドの音が以前と違うように感じた原因はディランが高齢になったとかではなくて、彼自身の弾くオルガンのようなキーボードが入ったからではないかと今では思う。
1万3000人が参加しているディランのmixiコミュニティの冒頭には、
「彼のテクや演奏をコピーしてもまったく意味は無い。 彼の出す全体的な雰囲気は誰にも真似ができないから。」
と書かれている。それは私が前回の来日公演で感じたことを見事に表している。9年前も現在も彼の曲はほとんど頭に入っていないけれど、パフォーマーとしてなんともいえない魅力に惹かれて今回もライブに行ったわけだ。そして、今回の彼に対しても同じ感想をもった次第である。
とは言いながら、部屋に戻ってからネットで演奏曲目を調べて思わず苦笑してしまった。会場に行く前は、前回の来日公演の予習のために買った「ボブ・ディラン・ライヴ!1961-2000~39イヤーズ・オブ・グレート・コンサート・パフォーマンス」(01年)を聴いていた。このアルバムに入っている曲もかなり含まれていた(”To Ramona”、”I Don’t Believe You”、”Cold Irons Bound”、”Things Have Changed”)にもかかわらず、全く気づかなかったからである。
「この曲、演奏されてたっけ?」
としばし呆然となった。彼の曲がまったく頭に入っていないとは言いながらも、それでもここまで全く気づかなかったのは情けないというしかない。
それはともかく、演奏曲目を見てみると、この15年あたりに作った作品の比率も低くないことに気づく。
「タイム・アウト・オブ・マインド」(97年)から2曲
「ラヴ・アンド・セフト」(01年)から1曲
「モダン・タイムズ」(06年)から3曲
「トゥゲザー・スルー・ライフ」(09年)から1曲
という感じである。”Things Have Changed”も近年の曲だから、ここ15年の曲目が半分くらいを占めることになる。この辺りは、自分がまだ現役のミュージシャンであることを主張しているようで頼もしい気がする。
最後に一つだけ記したい話がある。今回、ディランがギターを手に取ったのはわずか2曲だけだった。フォーク・シンガーというイメージが今でも強い人だから、そう思って会場に臨んだ人は面食らったに違いない。実際、ライブが終わった後で若い人が、ディランが全然ギターを持たなかった、みたいなことを耳にした。
それを聞いた私は、9年前はそうじゃなかったんだけどねえ、とほくそ笑んでいたのであった。
最後に演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(1)Watching The River Flow
(2)Girl Of The North Country
(3)Things Have Changed
(4)To Ramona
(5)High Water (For Charley Patton)
(6)Spirit On The Water
(7)The Levee’s Gonna Break
(8)I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
(9)Cold Irons Bound
(10)A Hard Rain’s A-Gonna Fall
(11)Highway 61 Revisited
(12)Can’t Wait
(13)Thunder On The Mountain
(14)Ballad Of A Thin Man
<アンコール>
(15)Like A Rolling Stone
(16)Jolene
(17)All Along The Watchtower
ジャクソン・ブラウンのライブを観る時は、けっこう色々な期待をして会場に臨むのが常だった。好きな曲がたくさんあるし、日によって内容もけっこう変えてくる。そして何より、ライブの内容が破格に素晴らしい。
かつて山下達郎が自身のラジオ番組の中でジャクソンの特集をした時、彼のライブには海外のアーティストに見られる「手抜き」のようなものが感じられない、というようなことを言っていたのを今でも覚えている。私にはミュージシャンの手抜き云々を指摘できる目や耳は無いけれど、ジャクソンのライブが素晴らしすぎることだけは確信をしている。
それほどまでに好きなジャクソンだが、今回はいつもほど熱心になれていない自分がいた。その理由は明らかで、シェリル・クロウとのジョイント・ライブという形式をとっているからだ。どう頑張っても、いつもの半分くらいの時間しか彼のライブを観ることができない。それが本当に辛い。またネットの情報によれば、ジャクソンが一番手だそうだ。それでもジャクソンが観たい私は1万3000円のチケット(これもジョイント・ライブの弊害だ)を買って大阪国際会議場へ向かう。
午前中は仕事をして、いったん部屋に戻って着替えて少し休憩してから京阪電車で中之島まで向かう。途中の京橋駅の中でエビ入りのたこ焼きというのを食べてしまったりしたので、自分の席に着いたのは6時58分ほどになってしまった。座って間もなく7時2分には客電が落ちて、事前情報通りまずジャクソンの登場である。
初めの2曲は最新アルバム「時の征者」(08年)から立て続けに演奏されたものの、ジョイント・ライブで曲数が少ないこともあってか、以降はファンの喜ぶような曲の連続だった。
ところで、ジャクソン・ブラウンは非常に愛されている、というか愛され過ぎているミュージシャンである。よって、イタい取り巻きもたくさん会場に来る。リクエストにも柔軟に応じる部分もあるので、
「ロージー!ロージー!」
と客席から大きな声で求められる。それに負けるように、予定にはなかったであろう”ロージー”を歌ってくれた。あの時のジャクソンは明らかに、苦笑に近い笑顔を浮かべていた。
しかしそういうイタい人たちの気持ちもわからなくはないかな、と思ってしまうほど今夜のジャクソンのライブは素晴らしかった。いままで4回ほど観た彼のステージはどれも破格の出来であったけれど、今夜は短時間で凝縮したような感じが特に良かった。個人的には”サムバディズ・ベイビー”をバンド演奏で初めて聴けたのが収穫だったか。ともかく、フル・ステージで観たい、と演奏時間の短さを呪うばかりだった。それが今回のジャクソンに対する私から言える精一杯の賛辞である。
いつもの半分ほどの時間とはいえ、本編最後を飾る曲はやはり”孤独なランナー”だった。そしていつもならばお客が総立ちになるけれど、今日は全体の半分くらいしか立ち上がらない。シェリル・クロウのファンの方が多かったか、と一瞬は思った。しかし徐々に10人20人と立ち上がり、後半はほとんどの人が立ち上がって拍手を贈るようになる。これはさすがに感動的な光景であった。
演奏が終わって会場が最高潮になっているところに、いきなりシェリル・クロウと彼女のバンドが現れて会場がどよめく。ものすごく華奢な人だなと思っているうちに、そのまま”テイク・イット・イージー”へなだれ込み、客席はさらなる盛り上がりを見せてしまった。ここまでで1時間20分ほどだっだけれど、もう何も言うことがない内容である。
だが、一つだけ不思議な点があった。いつもライブで必ず演奏される”プリテンダー
”(The Prretender)がついに出てこなかったのだ。もしかして”ロージー”を演奏した関係で無くなったとか。抜けることがまずあり得ない曲なので、最後までそれが疑問である。
そこから舞台替えで25分ほど費やした。ドラムセットから後の照明までいろいろ変えていたけれど、もう携帯の時計は8時45分を示している。これでは終演は10時を大きく回るかなと思っていると、照明が落ちて舞台袖にスポット・ライトが当たる。さきほど少しだけ出て来たシェリル・クロウがギターを弾きながら登場した。楽器を演奏しながら舞台に向かうミュージシャンは初めて見たような気がする。
私はシェリルについて1曲も知らないほどの人間なので、果たしてライブを楽しむことができるか不安だった。そして実際のところ、心から楽しむという境地には最後まで至らなかったといえる。マイケル・ジャクソンやエリック・クラプトンの作品に参加するなどのキャリアを経て30過ぎてからデビューしたこの遅咲きのミュージシャンのパフォーマンスは堂に入ったものと感じたものの、いまひとつ魅力はわからなかった。ライブを観て思ったのは、アメリカン・ロックの王道のような曲よりも、カントリー調もしくはヒップ・ホップっぽい空気のある曲の時が彼女の本領を発揮していたように個人的には感じたけれど、たぶん彼女のファンにとっては全くそんなことはないだろう。
決定的だったのは、途中でジャクソンが加わって共演をした時である。この時、オッ!と感じる曲が出てきた。
「一体何だ?この自分の琴線に触れる曲は・・・」
と最初は驚いたけれど、すぐその理由に気づくことになった。その曲はニック・ロウがブリンズリー・シュウォーツ時代に作った名曲”PEACE LOVE & UNDERSTANDING”のカバーだったのである。そして、私はニックの大ファンである。
これにはつくづく考えさせられた。簡単には表現できないものの、自分の中に音楽の趣味嗜好というのは確かに存在しているということを痛感してしまったのである。そして、シェリル・クロウという人についても、自分には縁にないアーティストだったと今更ながらに気づくこととなる。そうでなかったら、1枚くらい彼女のアルバムを持っていたことだろう。
そんな複雑な思いに駆られながら、アンコールでシェリルのみが2曲演奏して、10時20分ごろに全てのライブが終了した。ジャクソンはついに出てくることはなかった。
「なんでジャクソンが出てこないんや。早く帰れば良かった」
と私の後ろの客が怒りに近い声をあげていた。私もジャクソンの再々登場を期待していた一人ではある。しかしながら、この15年くらいの両者の活躍を比較すれば、この扱いも致し方ない気はする。ただ、ジョイント・ライブというのは絶対に中途半端になることが避けられない、ということだけはこの場に記しておきたい。
最後にこの日の演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(ジャクソン・ブラウン)
(1)Time The Conqueror
(2)Off Of Wonderland
(3)Rock Me On The Water
(4)Fountain Of Sorrow
(5)These days
(6)Somebody’s Baby
(7)Rosie
(8)Late For The Sky
(9)Lives In The balance
(11)Doctor My Eyes /About My Imagination
(12)Giving That Heaven Away
(13)Running On Empty
(14)Take It Easy (with Sheryl Crow & her band)
(シェリル・クロウ)
(1)HAPPY
(2)CAN’T CRY
(3)LOVE IS FREE
(4)MISTAKE
(5)IT’S ONLY LOVE
(6)STRONG ENOUGH
(7)DETOURS
(8)LOVE HURTS with Jackson Browne
(9)PEACE LOVE & UNDERSTANDING with Jackson Browne
(10)REAL GONE
(11)NEIGHBORHOOD
(12)GOOD IS GOOD
(13)ALL I WANNA DO
(14)SOAK
(15)OUT OF OUR HEADS
<アンコール>
(16)CHANGE
(17)WINDING ROAD
かつて山下達郎が自身のラジオ番組の中でジャクソンの特集をした時、彼のライブには海外のアーティストに見られる「手抜き」のようなものが感じられない、というようなことを言っていたのを今でも覚えている。私にはミュージシャンの手抜き云々を指摘できる目や耳は無いけれど、ジャクソンのライブが素晴らしすぎることだけは確信をしている。
それほどまでに好きなジャクソンだが、今回はいつもほど熱心になれていない自分がいた。その理由は明らかで、シェリル・クロウとのジョイント・ライブという形式をとっているからだ。どう頑張っても、いつもの半分くらいの時間しか彼のライブを観ることができない。それが本当に辛い。またネットの情報によれば、ジャクソンが一番手だそうだ。それでもジャクソンが観たい私は1万3000円のチケット(これもジョイント・ライブの弊害だ)を買って大阪国際会議場へ向かう。
午前中は仕事をして、いったん部屋に戻って着替えて少し休憩してから京阪電車で中之島まで向かう。途中の京橋駅の中でエビ入りのたこ焼きというのを食べてしまったりしたので、自分の席に着いたのは6時58分ほどになってしまった。座って間もなく7時2分には客電が落ちて、事前情報通りまずジャクソンの登場である。
初めの2曲は最新アルバム「時の征者」(08年)から立て続けに演奏されたものの、ジョイント・ライブで曲数が少ないこともあってか、以降はファンの喜ぶような曲の連続だった。
ところで、ジャクソン・ブラウンは非常に愛されている、というか愛され過ぎているミュージシャンである。よって、イタい取り巻きもたくさん会場に来る。リクエストにも柔軟に応じる部分もあるので、
「ロージー!ロージー!」
と客席から大きな声で求められる。それに負けるように、予定にはなかったであろう”ロージー”を歌ってくれた。あの時のジャクソンは明らかに、苦笑に近い笑顔を浮かべていた。
しかしそういうイタい人たちの気持ちもわからなくはないかな、と思ってしまうほど今夜のジャクソンのライブは素晴らしかった。いままで4回ほど観た彼のステージはどれも破格の出来であったけれど、今夜は短時間で凝縮したような感じが特に良かった。個人的には”サムバディズ・ベイビー”をバンド演奏で初めて聴けたのが収穫だったか。ともかく、フル・ステージで観たい、と演奏時間の短さを呪うばかりだった。それが今回のジャクソンに対する私から言える精一杯の賛辞である。
いつもの半分ほどの時間とはいえ、本編最後を飾る曲はやはり”孤独なランナー”だった。そしていつもならばお客が総立ちになるけれど、今日は全体の半分くらいしか立ち上がらない。シェリル・クロウのファンの方が多かったか、と一瞬は思った。しかし徐々に10人20人と立ち上がり、後半はほとんどの人が立ち上がって拍手を贈るようになる。これはさすがに感動的な光景であった。
演奏が終わって会場が最高潮になっているところに、いきなりシェリル・クロウと彼女のバンドが現れて会場がどよめく。ものすごく華奢な人だなと思っているうちに、そのまま”テイク・イット・イージー”へなだれ込み、客席はさらなる盛り上がりを見せてしまった。ここまでで1時間20分ほどだっだけれど、もう何も言うことがない内容である。
だが、一つだけ不思議な点があった。いつもライブで必ず演奏される”プリテンダー
”(The Prretender)がついに出てこなかったのだ。もしかして”ロージー”を演奏した関係で無くなったとか。抜けることがまずあり得ない曲なので、最後までそれが疑問である。
そこから舞台替えで25分ほど費やした。ドラムセットから後の照明までいろいろ変えていたけれど、もう携帯の時計は8時45分を示している。これでは終演は10時を大きく回るかなと思っていると、照明が落ちて舞台袖にスポット・ライトが当たる。さきほど少しだけ出て来たシェリル・クロウがギターを弾きながら登場した。楽器を演奏しながら舞台に向かうミュージシャンは初めて見たような気がする。
私はシェリルについて1曲も知らないほどの人間なので、果たしてライブを楽しむことができるか不安だった。そして実際のところ、心から楽しむという境地には最後まで至らなかったといえる。マイケル・ジャクソンやエリック・クラプトンの作品に参加するなどのキャリアを経て30過ぎてからデビューしたこの遅咲きのミュージシャンのパフォーマンスは堂に入ったものと感じたものの、いまひとつ魅力はわからなかった。ライブを観て思ったのは、アメリカン・ロックの王道のような曲よりも、カントリー調もしくはヒップ・ホップっぽい空気のある曲の時が彼女の本領を発揮していたように個人的には感じたけれど、たぶん彼女のファンにとっては全くそんなことはないだろう。
決定的だったのは、途中でジャクソンが加わって共演をした時である。この時、オッ!と感じる曲が出てきた。
「一体何だ?この自分の琴線に触れる曲は・・・」
と最初は驚いたけれど、すぐその理由に気づくことになった。その曲はニック・ロウがブリンズリー・シュウォーツ時代に作った名曲”PEACE LOVE & UNDERSTANDING”のカバーだったのである。そして、私はニックの大ファンである。
これにはつくづく考えさせられた。簡単には表現できないものの、自分の中に音楽の趣味嗜好というのは確かに存在しているということを痛感してしまったのである。そして、シェリル・クロウという人についても、自分には縁にないアーティストだったと今更ながらに気づくこととなる。そうでなかったら、1枚くらい彼女のアルバムを持っていたことだろう。
そんな複雑な思いに駆られながら、アンコールでシェリルのみが2曲演奏して、10時20分ごろに全てのライブが終了した。ジャクソンはついに出てくることはなかった。
「なんでジャクソンが出てこないんや。早く帰れば良かった」
と私の後ろの客が怒りに近い声をあげていた。私もジャクソンの再々登場を期待していた一人ではある。しかしながら、この15年くらいの両者の活躍を比較すれば、この扱いも致し方ない気はする。ただ、ジョイント・ライブというのは絶対に中途半端になることが避けられない、ということだけはこの場に記しておきたい。
最後にこの日の演奏曲目を記す。
【演奏曲目】
(ジャクソン・ブラウン)
(1)Time The Conqueror
(2)Off Of Wonderland
(3)Rock Me On The Water
(4)Fountain Of Sorrow
(5)These days
(6)Somebody’s Baby
(7)Rosie
(8)Late For The Sky
(9)Lives In The balance
(11)Doctor My Eyes /About My Imagination
(12)Giving That Heaven Away
(13)Running On Empty
(14)Take It Easy (with Sheryl Crow & her band)
(シェリル・クロウ)
(1)HAPPY
(2)CAN’T CRY
(3)LOVE IS FREE
(4)MISTAKE
(5)IT’S ONLY LOVE
(6)STRONG ENOUGH
(7)DETOURS
(8)LOVE HURTS with Jackson Browne
(9)PEACE LOVE & UNDERSTANDING with Jackson Browne
(10)REAL GONE
(11)NEIGHBORHOOD
(12)GOOD IS GOOD
(13)ALL I WANNA DO
(14)SOAK
(15)OUT OF OUR HEADS
<アンコール>
(16)CHANGE
(17)WINDING ROAD
キャロル・キング「喜びにつつまれて」(74年)
2010年3月4日 CD評など
(1)Nightingale ナイチンゲール
(2)Change in Mind, Change of Heart チェンジ・イン・マインド・チェンジ・オブ・ハート
(3)Jazzman ジャズマン
(4)You Go Your Way, I’ll Go Mine アイル・ゴー・マイン
(5)You’re Something New ユア・サムシング・ニュー
(6)We Are All in This Together 世界はひとつに
(7)Wrap Around Joy ラップ・アラウンド・ジョイ
(8)You Gentle Me ユー・ジェントル・ミー
(9)My Lovin’ Eyes マイ・ラヴィン・アイズ
(10)Sweet Adonis スウィート・アドニス
(11)Night This Side of Dying ア・ナイト・ジス・サイド・オブ・ダイング
(12)Best Is Yet to Come いつか良き日々が
(13)Oh No,Not My Baby ノット・マイ・ベイビー ※ボーナス・トラック
来月ジェイムス・テイラーと一緒にキャロル・キングが2年ぶりの来日をする。それが頭に入っていたためだろうか、先日ふと彼女の代表作「つづれおり」(71年)を取り出して繰り返し聴いていた。
そうしているうちに、
「そういえば、彼女のアルバムは2枚しか持っていなかったな」
ということに気づく。確かに部屋にあるのは「つづれおり」と、いまのところ最新のオリジナル・アルバムである「ラヴ・メイクス・ザ・ワールド」(01年)だけである。彼女の作品をもっと聴きたいと思うことがこれまでも何度かあった。しかし、実際に何か他の作品を買うというまでには至らなかった。
理由は簡単な話である。どの作品を買えば良いのか判断がつかなかったからだ。キャロル・キングの代表作といえば間違いなく「つづれおり」であり、ガイドブック等でもこれ以外の作品が出てくることはまずない。実際のところ世界中で2200万枚を売り上げているわけで、内容以外の面でも突出したものであることは否定できない。彼女のアルバムでまず手にするべきものは「つづれおり」で異論は無いだろう。しかし、「じゃあ2枚目に何を手にするの?」と訊かれたら返答に窮してしまう。そして、いままでの私はそのような場所にいたわけであった。
ともかく何か試してみようと思い、市内のCDショップを回って3枚のアルバムを買ってみた。いずれも彼女が07年に来日した記念に出た紙ジャケット仕様のものである。そのうちの一つがこの「喜びにつつまれて」(Wrap Around Joy)だった。「つづれおり」から3枚のアルバムを置いて発表された74年の作品で、この中に入っている”ジャズマン”という曲がヒットしている。といっても、買った時点でこの曲がどんな曲か知らなかったが。つまり、この作品についての予備知識はほとんど皆無であった。
しかしながら、このアルバムの内容には本当に唸らされた。1曲目の”ナイチンゲール”から最後の”いつか良き日々が”に至るまで、出てくる曲がどれもこれも素晴らしいのである。それこそ「つづれおり」とも遜色が無いとまで感じたほどだ。この2枚のアルバムはどちらが優れているかと訊かれたら、私のレベルでは「どちらも最高です」としか言えない。
せっかくの機会なので、キャロル・キングの魅力についての見解を述べてみたい。私は「つづれおり」を初めて買ったのは高校2年か3年の頃だと記憶している。当時もこのアルバムは素晴らしい楽曲ばかりのアルバムと思っていたし、また彼女がリトル・エヴァの”ロコ・モーション”などのヒット曲を多数輩出した作曲家としての実績や、「シンガー・ソングライター」の代名詞であるということも後にガイドブックなどで知ることとなる。そうしているうちに、優れた作曲能力と巧みな自己表現力を兼ね備えた人という彼女のイメージが出来上がっていった。ガイドブックやネットにおける評価もおおむねそんなものではないかと思う。
しかしながら、彼女の本当の魅力を実感したのは、やはり実際にライブで演奏する姿を観た時である。たどたどしい日本語のMCを交えながら歌い演奏する彼女のパフォーマンスは、楽曲と同様に実に優しく暖かかなものであった。キャロルの音楽の魅力は彼女自身の人柄からにじみ出てくるものだと、ライブ会場で確信した。
「シンガー・ソングライター」(自作自演歌手)という言葉には、ミュージシャン個人の表現を追求するという意味で、ともすれば独善的な印象もつきまとう(私の最も敬愛するヴァン・モリソンなどその典型だろうな)。しかしながら、キャロルに関していえばそのような部分は微塵も感じられない。むしろそうしたエゴイスティックな姿勢とは対極の位置にいる人である。多くの人に愛される楽曲やパフォーマンスを生み出すためにはどうすれば良いのか。ひたすらそのために努力し試行錯誤をしているうちに、彼女の音楽も人間性もあのような魅力的なものになっていったのではないだろうか。私はそんな仮説を立てている。
(2)Change in Mind, Change of Heart チェンジ・イン・マインド・チェンジ・オブ・ハート
(3)Jazzman ジャズマン
(4)You Go Your Way, I’ll Go Mine アイル・ゴー・マイン
(5)You’re Something New ユア・サムシング・ニュー
(6)We Are All in This Together 世界はひとつに
(7)Wrap Around Joy ラップ・アラウンド・ジョイ
(8)You Gentle Me ユー・ジェントル・ミー
(9)My Lovin’ Eyes マイ・ラヴィン・アイズ
(10)Sweet Adonis スウィート・アドニス
(11)Night This Side of Dying ア・ナイト・ジス・サイド・オブ・ダイング
(12)Best Is Yet to Come いつか良き日々が
(13)Oh No,Not My Baby ノット・マイ・ベイビー ※ボーナス・トラック
来月ジェイムス・テイラーと一緒にキャロル・キングが2年ぶりの来日をする。それが頭に入っていたためだろうか、先日ふと彼女の代表作「つづれおり」(71年)を取り出して繰り返し聴いていた。
そうしているうちに、
「そういえば、彼女のアルバムは2枚しか持っていなかったな」
ということに気づく。確かに部屋にあるのは「つづれおり」と、いまのところ最新のオリジナル・アルバムである「ラヴ・メイクス・ザ・ワールド」(01年)だけである。彼女の作品をもっと聴きたいと思うことがこれまでも何度かあった。しかし、実際に何か他の作品を買うというまでには至らなかった。
理由は簡単な話である。どの作品を買えば良いのか判断がつかなかったからだ。キャロル・キングの代表作といえば間違いなく「つづれおり」であり、ガイドブック等でもこれ以外の作品が出てくることはまずない。実際のところ世界中で2200万枚を売り上げているわけで、内容以外の面でも突出したものであることは否定できない。彼女のアルバムでまず手にするべきものは「つづれおり」で異論は無いだろう。しかし、「じゃあ2枚目に何を手にするの?」と訊かれたら返答に窮してしまう。そして、いままでの私はそのような場所にいたわけであった。
ともかく何か試してみようと思い、市内のCDショップを回って3枚のアルバムを買ってみた。いずれも彼女が07年に来日した記念に出た紙ジャケット仕様のものである。そのうちの一つがこの「喜びにつつまれて」(Wrap Around Joy)だった。「つづれおり」から3枚のアルバムを置いて発表された74年の作品で、この中に入っている”ジャズマン”という曲がヒットしている。といっても、買った時点でこの曲がどんな曲か知らなかったが。つまり、この作品についての予備知識はほとんど皆無であった。
しかしながら、このアルバムの内容には本当に唸らされた。1曲目の”ナイチンゲール”から最後の”いつか良き日々が”に至るまで、出てくる曲がどれもこれも素晴らしいのである。それこそ「つづれおり」とも遜色が無いとまで感じたほどだ。この2枚のアルバムはどちらが優れているかと訊かれたら、私のレベルでは「どちらも最高です」としか言えない。
せっかくの機会なので、キャロル・キングの魅力についての見解を述べてみたい。私は「つづれおり」を初めて買ったのは高校2年か3年の頃だと記憶している。当時もこのアルバムは素晴らしい楽曲ばかりのアルバムと思っていたし、また彼女がリトル・エヴァの”ロコ・モーション”などのヒット曲を多数輩出した作曲家としての実績や、「シンガー・ソングライター」の代名詞であるということも後にガイドブックなどで知ることとなる。そうしているうちに、優れた作曲能力と巧みな自己表現力を兼ね備えた人という彼女のイメージが出来上がっていった。ガイドブックやネットにおける評価もおおむねそんなものではないかと思う。
しかしながら、彼女の本当の魅力を実感したのは、やはり実際にライブで演奏する姿を観た時である。たどたどしい日本語のMCを交えながら歌い演奏する彼女のパフォーマンスは、楽曲と同様に実に優しく暖かかなものであった。キャロルの音楽の魅力は彼女自身の人柄からにじみ出てくるものだと、ライブ会場で確信した。
「シンガー・ソングライター」(自作自演歌手)という言葉には、ミュージシャン個人の表現を追求するという意味で、ともすれば独善的な印象もつきまとう(私の最も敬愛するヴァン・モリソンなどその典型だろうな)。しかしながら、キャロルに関していえばそのような部分は微塵も感じられない。むしろそうしたエゴイスティックな姿勢とは対極の位置にいる人である。多くの人に愛される楽曲やパフォーマンスを生み出すためにはどうすれば良いのか。ひたすらそのために努力し試行錯誤をしているうちに、彼女の音楽も人間性もあのような魅力的なものになっていったのではないだろうか。私はそんな仮説を立てている。
「LRT推進団体解散へ」
2010年2月24日昨日(2月23日)の昼間は会社近くのパン屋でサンドイッチを買い、iPodでキャロル・キングを聴きながら職場の片隅で新聞を読んでいた。
「コンビニ売上高、8カ月連続マイナス」
「スーパー14カ月連続で前年割れ」
など明るい話題が見当たらない。その中で、表題の記事が京都新聞1面に掲載されていた。
LRT(次世代路面電車)は、京都市内の今出川通で整備を検討されていた乗り物だ。といってもLRTについて知ってる人はほとんどいないだろう。ネットで検索したら、「LRT京都に走らせよう!」というページに説明が載っていたので引用する。
「LRT(Light Rail Transit)とは、次世代型路面電車と呼ばれ、環境にやさしくバリアフリーを考慮した新しい都市の交通網として注目されている交通システムです。欧州や米国などでは20世紀末から敷設されはじめ、現在、フランスのストラスブールなどの都市では、古都の落ち着いた佇まいの中を、最新のデザインのハイテク路面電車が走っています。世界的な観光都市である京都においても、LRTは交通渋滞緩和や環境問題の解消を図る都市計画を進めていく上で、欠かせない重要な交通システムとして活発な議論がなされています。京都民報では、古い伝統と新しい都市機能が美しく調和する都市・京都を目指し、LRTについて考えていきます。」
このLRTを実現させるため市民団体「京都・今川通りにLRT実現を推進する会」(新今電会)」が99年に結成され、シンポジウムや意見交換会などを活発におこなってきた。
しかし、07年1月に今出川通で交通実験をして以降は京都市の動きが鈍くなり、そこに財政状況の悪化も加わって実現のメドが立たなくなってきた。新今電会もこの4月の総会を持って正式に解散するという。
このニュースを読んで個人的には少し安堵した。わざわざLRTを今出川通に敷く理由がさっぱり理解できなかったからだ。
まず今出川通は十分な本数の市バスが走っている。移動手段としてLRTの出てくる幕はない。お客の取り合いになるのは目に見えている。そして、今出川通はものすごく道幅が狭い。特に京都御所と同志社大学の間など、電車を走らせでもしたら自動車が通ることが
できなくなるだろう。
加えて、これが一番強調したい点だが、昔の京都市はもともと「京都市電」という路面電車が無数に走っていた。それは「日本最初の電気鉄道」である。京都市電はそれほど歴史ある乗り物だったが、自動車の普及、また地下鉄や市バスの導入を希望する声が強まり、1978年9月をもって全面廃止された。その歴史を京都市民は忘れていない。市電をつぶした過去を忘れてまた路面電車を導入したがるというのは説明がつかないではないか。
それに先ほど述べた「財政状況の悪化」というのも尋常な数字ではない。京都市地下鉄は1日あたり約4000万円もの赤字を出している。累積赤字になると3千億円を超えるという。この現実を果たしてLRT整備を推し進めてきた人たちは頭にあったのだろうか。
不必要なインフラを抱えられるほどの財政的余裕は、この京都市には無いのである。
「コンビニ売上高、8カ月連続マイナス」
「スーパー14カ月連続で前年割れ」
など明るい話題が見当たらない。その中で、表題の記事が京都新聞1面に掲載されていた。
LRT(次世代路面電車)は、京都市内の今出川通で整備を検討されていた乗り物だ。といってもLRTについて知ってる人はほとんどいないだろう。ネットで検索したら、「LRT京都に走らせよう!」というページに説明が載っていたので引用する。
「LRT(Light Rail Transit)とは、次世代型路面電車と呼ばれ、環境にやさしくバリアフリーを考慮した新しい都市の交通網として注目されている交通システムです。欧州や米国などでは20世紀末から敷設されはじめ、現在、フランスのストラスブールなどの都市では、古都の落ち着いた佇まいの中を、最新のデザインのハイテク路面電車が走っています。世界的な観光都市である京都においても、LRTは交通渋滞緩和や環境問題の解消を図る都市計画を進めていく上で、欠かせない重要な交通システムとして活発な議論がなされています。京都民報では、古い伝統と新しい都市機能が美しく調和する都市・京都を目指し、LRTについて考えていきます。」
このLRTを実現させるため市民団体「京都・今川通りにLRT実現を推進する会」(新今電会)」が99年に結成され、シンポジウムや意見交換会などを活発におこなってきた。
しかし、07年1月に今出川通で交通実験をして以降は京都市の動きが鈍くなり、そこに財政状況の悪化も加わって実現のメドが立たなくなってきた。新今電会もこの4月の総会を持って正式に解散するという。
このニュースを読んで個人的には少し安堵した。わざわざLRTを今出川通に敷く理由がさっぱり理解できなかったからだ。
まず今出川通は十分な本数の市バスが走っている。移動手段としてLRTの出てくる幕はない。お客の取り合いになるのは目に見えている。そして、今出川通はものすごく道幅が狭い。特に京都御所と同志社大学の間など、電車を走らせでもしたら自動車が通ることが
できなくなるだろう。
加えて、これが一番強調したい点だが、昔の京都市はもともと「京都市電」という路面電車が無数に走っていた。それは「日本最初の電気鉄道」である。京都市電はそれほど歴史ある乗り物だったが、自動車の普及、また地下鉄や市バスの導入を希望する声が強まり、1978年9月をもって全面廃止された。その歴史を京都市民は忘れていない。市電をつぶした過去を忘れてまた路面電車を導入したがるというのは説明がつかないではないか。
それに先ほど述べた「財政状況の悪化」というのも尋常な数字ではない。京都市地下鉄は1日あたり約4000万円もの赤字を出している。累積赤字になると3千億円を超えるという。この現実を果たしてLRT整備を推し進めてきた人たちは頭にあったのだろうか。
不必要なインフラを抱えられるほどの財政的余裕は、この京都市には無いのである。
長崎県知事選の結果を見て
2010年2月22日2月21日、任期満了にともなう長崎県知事選挙が投開票日を迎えた。結果は自民・公明の支援する中村法道氏(前・長崎県副知事)が、民主党ほか与党が支持する候補者を大差で破り当選する。昨年夏の衆議院選挙では民主党の新人である福田衣里子氏が自民党の大物である久間章生氏を破った勢いもあり、昨秋までは「与党有利」との評価が強かった。それが一転の大逆風である。
この選挙結果を受けて与党も危機感をかなり強めているようだ。鳩山由紀夫総理大臣は選挙の翌朝、
「厳しかった。国政の影響があったことは否めない。政治とカネの問題の影響を受けたと言うべきだ。真摯に受け止める必要がある」
と記者団の質問に答えている。マスコミ各社も大半は、総理や小沢幹事長の「政治とカネ」問題が大敗の原因と分析しているようだ。
本当にそうかねえ?
間違いとまでは言えないまでも、答えとしては半分くらいしか合っていないように感じて仕方ないのだ。
もし有権者が「政治とカネ」がらみの問題を嫌がったのだとしたら、長年にわたってその代名詞だった自民党の支持する人に投票することはあり得ないのではないか。それは時計の逆回りにしかならない。
私はこの選挙に関してほとんど予備知識は皆無の立場であるものの、それゆえ事態をもっと単純に考える。ここ最近は民主党にとってイメージの悪くなるニュースばかり続き、無党派層をはじめとする有権者が嫌気をさした。それだけの話ではないだろうか。
そもそも「無党派層」だの「浮動票」だのといった言葉の響きからしてフラフラした感じがつきまとう。こうした人たちは政治に対してこだわりのようなものは希薄である。端的にいえば「流されやすい」。昔のことも執念深く覚えていないから、ある時は「郵政民営化」という雰囲気に流され、またある時は「政権交代」という言葉に踊らされる。それが悪いなどというつもりは全くないけれど、おそらくはそんな感じで投票したのだろう。さらに言えば、小選挙区制という仕組みがそれを助長させていることも無視できない。
ともかく、民主党もこのまま悪い印象を抱かせる話題ばかり提供するような状態では、今年の参議院選挙も大逆風なものとなる可能性も大いにありうる。
昨年の「政権交代」も、参議院選が終わった後は「歴史の1コマ」とか「去年の夏の風物詩」とかの一言で片付けられるかもしれない。それが世間というものなのだが。
この選挙結果を受けて与党も危機感をかなり強めているようだ。鳩山由紀夫総理大臣は選挙の翌朝、
「厳しかった。国政の影響があったことは否めない。政治とカネの問題の影響を受けたと言うべきだ。真摯に受け止める必要がある」
と記者団の質問に答えている。マスコミ各社も大半は、総理や小沢幹事長の「政治とカネ」問題が大敗の原因と分析しているようだ。
本当にそうかねえ?
間違いとまでは言えないまでも、答えとしては半分くらいしか合っていないように感じて仕方ないのだ。
もし有権者が「政治とカネ」がらみの問題を嫌がったのだとしたら、長年にわたってその代名詞だった自民党の支持する人に投票することはあり得ないのではないか。それは時計の逆回りにしかならない。
私はこの選挙に関してほとんど予備知識は皆無の立場であるものの、それゆえ事態をもっと単純に考える。ここ最近は民主党にとってイメージの悪くなるニュースばかり続き、無党派層をはじめとする有権者が嫌気をさした。それだけの話ではないだろうか。
そもそも「無党派層」だの「浮動票」だのといった言葉の響きからしてフラフラした感じがつきまとう。こうした人たちは政治に対してこだわりのようなものは希薄である。端的にいえば「流されやすい」。昔のことも執念深く覚えていないから、ある時は「郵政民営化」という雰囲気に流され、またある時は「政権交代」という言葉に踊らされる。それが悪いなどというつもりは全くないけれど、おそらくはそんな感じで投票したのだろう。さらに言えば、小選挙区制という仕組みがそれを助長させていることも無視できない。
ともかく、民主党もこのまま悪い印象を抱かせる話題ばかり提供するような状態では、今年の参議院選挙も大逆風なものとなる可能性も大いにありうる。
昨年の「政権交代」も、参議院選が終わった後は「歴史の1コマ」とか「去年の夏の風物詩」とかの一言で片付けられるかもしれない。それが世間というものなのだが。
世間の流れにあまり便乗したくないが・・・藤田まことの話
2010年2月20日2月17日、俳優の藤田まことが大動脈瘤破裂のため急逝した。享年76歳である。
いままでテレビドラマは数えるほどしか観てないため、「必殺仕事人」や「はぐれ刑事」などにも思い入れはなく、藤田自身についても「たくさん借金をこさえた人」というイメージしか抱いてなかった。訃報に接したときも、真っ先に思い浮かんだのは「借金は完済したのかなあ」という感じであった。実際のところ借金は本人が作ったものではなく完済もしたようだが。
藤田に対する私の印象はそんなものだったけれど、奇しくも亡くなる前日にして彼のイメージが少し変わるような出来事があった。
その日は午前を半休にし、部屋で家事などをしていた。部屋にいる時はたいていテレビをつけっぱなしにしている。特にテレビが好きなわけでもないので、画面はいつも6チャンネルのままだ。6チャンネル(朝日放送)の平日午前はいつも「はぐれ刑事」の再放送をしている。
実はこの再放送についても不思議に感じていた。映像はかなり粗いのである。ずいぶん昔のものを流していることは一目で明らかだった。こんな古い番組をわざわざ再放送している理由が、その時にはまだわからなかった。そしていつもなら中身もろくに観ていないのだけれど、不思議とその日だけは画面を注視していた。
その日の話はざっとこんな感じである。建設中の家で、そこの工事を請け負っていた工務店の主人が殺害されていた。殺人なのでもちろん現場を調査する。するとその家が手抜き工事の欠陥住宅であることが判明してしまったのである。
工事を頼んだ夫婦は当然ものすごく怒る。特に奥さんのほうは尋常ではない。発注先の担当者に詰め寄って涙ながらに訴える。子どもをディズニーランドにも連れて行かせずに、そうまでして頭金を作ったのに・・・と。
そうだよなあ、家の頭金を作るまではさぞかし大変だったろうなあ。その婦人に対して大いに共感してしまったのである。それは、例えば10代の時や社会に出る前の自分には全く実感できなかったものに違いない。
「はぐれ刑事」シリーズでは、こうした何気ない市井の人たちの悲哀をずっと描いてきて、また藤田が演じる安浦刑事もこうした人たちに大上段に構えるわけでなくごく自然な感じで接する。そのスタンスが多くの人の支持を得たのだろう。「はぐれ刑事」は18シリーズ、全440回(400話とスペシャル4回)もの長きにわたって続く人気番組となった。
藤田が亡くなった翌朝の「おはよう朝日です」(朝日放送)で井上公造(芸能ジャーナリスト)は、藤田まことの再放送はものすごい視聴率を出す、と言っていた。司会の宮根誠二も裏で藤田まことが再放送をされるとたまらない気持ちになる、と応える。
大昔の「はぐれ刑事」シリーズをわざわざ再放送しているのは、人気があって数字が取れるという当たり前の理由からだったわけである。こうした事実が藤田の死によって初めて気づかされたことは個人的に残念でならない。
いままでテレビドラマは数えるほどしか観てないため、「必殺仕事人」や「はぐれ刑事」などにも思い入れはなく、藤田自身についても「たくさん借金をこさえた人」というイメージしか抱いてなかった。訃報に接したときも、真っ先に思い浮かんだのは「借金は完済したのかなあ」という感じであった。実際のところ借金は本人が作ったものではなく完済もしたようだが。
藤田に対する私の印象はそんなものだったけれど、奇しくも亡くなる前日にして彼のイメージが少し変わるような出来事があった。
その日は午前を半休にし、部屋で家事などをしていた。部屋にいる時はたいていテレビをつけっぱなしにしている。特にテレビが好きなわけでもないので、画面はいつも6チャンネルのままだ。6チャンネル(朝日放送)の平日午前はいつも「はぐれ刑事」の再放送をしている。
実はこの再放送についても不思議に感じていた。映像はかなり粗いのである。ずいぶん昔のものを流していることは一目で明らかだった。こんな古い番組をわざわざ再放送している理由が、その時にはまだわからなかった。そしていつもなら中身もろくに観ていないのだけれど、不思議とその日だけは画面を注視していた。
その日の話はざっとこんな感じである。建設中の家で、そこの工事を請け負っていた工務店の主人が殺害されていた。殺人なのでもちろん現場を調査する。するとその家が手抜き工事の欠陥住宅であることが判明してしまったのである。
工事を頼んだ夫婦は当然ものすごく怒る。特に奥さんのほうは尋常ではない。発注先の担当者に詰め寄って涙ながらに訴える。子どもをディズニーランドにも連れて行かせずに、そうまでして頭金を作ったのに・・・と。
そうだよなあ、家の頭金を作るまではさぞかし大変だったろうなあ。その婦人に対して大いに共感してしまったのである。それは、例えば10代の時や社会に出る前の自分には全く実感できなかったものに違いない。
「はぐれ刑事」シリーズでは、こうした何気ない市井の人たちの悲哀をずっと描いてきて、また藤田が演じる安浦刑事もこうした人たちに大上段に構えるわけでなくごく自然な感じで接する。そのスタンスが多くの人の支持を得たのだろう。「はぐれ刑事」は18シリーズ、全440回(400話とスペシャル4回)もの長きにわたって続く人気番組となった。
藤田が亡くなった翌朝の「おはよう朝日です」(朝日放送)で井上公造(芸能ジャーナリスト)は、藤田まことの再放送はものすごい視聴率を出す、と言っていた。司会の宮根誠二も裏で藤田まことが再放送をされるとたまらない気持ちになる、と応える。
大昔の「はぐれ刑事」シリーズをわざわざ再放送しているのは、人気があって数字が取れるという当たり前の理由からだったわけである。こうした事実が藤田の死によって初めて気づかされたことは個人的に残念でならない。
「ゴールデンスランバー」を観た・読んだ・聴いた
2010年2月13日
1月30日(土)の初日にTOHOシネマズ二条で映画「ゴールデンスランバー」を観に行った。お客の入りは7割くらいだろうか。悪いスタートでは無いと感じたが、ネットを観る限りはけっこうヒットしているようだ。
内容も非常に面白かった。2月1日(月)には原作の小説も買ってみる。500ページほどある中編だが半日ほどで読み通してしまった。自分がいつも本を読むペースを考えると異様なスピードだが、これは私が早く本が読めるようになったとかではなく、映画を観ていたため小説の筋がある程度頭に入っていたからだと思われる。
それを読んでる時にビートルズの「アビイ・ロード」(69年)を引っぱりだして、その中に収録されている”ゴールデン・スランバー”を聴いてみた。小説のタイトルはこの曲から引用されている。ただ原題は”GOLDEN SLUMBERS”と複数形だ。「スランバーズ」だと響きが悪いとかそういう理由なのだろうか。最近はそんな日々を過ごしていたけれど、それくらいこの映画は気に入ったわけである。
「ゴールデンスランバー」は元・宅配ドライバーである青柳雅春が、仙台で旧友の森田森吾と久しぶりに再会している途中で総理大臣の暗殺犯に仕立て上げられ、2日間にわたって警察から逃亡するという内容である。
森田は、自分の妻がパチンコで抱えた借金を帳消しにすると誘われ、ある仕事を引き受けたと告白する。その内容とは、青柳を誘導することだったのである。しかし、それが危険な仕事だと気づいた森田は、
「警戒して、疑え。じゃねえと、おまえ、オズワルドにされるぞ」(本書P.112)
と青柳は意味深な忠告を受ける。
オズワルドとは、アメリカ第35代大統領ジョン・F・ケネディの暗殺犯とされているリー・ハーヴェイ・オズワルドのことだ。そのオズワルドも逮捕された2日後、ダラス警察署の地下でテレビ中継している最中ジャック・ルビーに射殺された。逮捕直後のオズワルドは、自分ははめられた、などと記者団の前で主張していたという。そして、ケネディ暗殺事件はいまでも真相は明らかになっていない部分が多い。
そうこうしているうちに、外では大きな爆発音が起こり、制服姿の警察官2人が近づいてくる。森田は続ける。
「おまえは逃げるしかねえってことだ。いいか、青柳、逃げろよ。無様な姿を晒してもいいから、とにかく逃げて、生きろ。人間、生きててなんぼだ」(本書P.117)
森田にせかされるようにして青柳は逃げる。その青柳に対して警察は躊躇無く拳銃を発砲した。首相暗殺というのは確かに重大な罪ではある。しかしその容疑者をいきなり撃ってくるというのは異常な話だ。おそらくは、青柳を射殺し、それから彼を犯人であるかのようなストーリーを作り上げていくのだろう。青柳を追いつめているのは国家とか権力とか相当に大きなものらしい。果たして青柳は逃げ切ることができるのだろうか。
2時間13分とそこそこ長い映画の中で、青柳は最後の最後までとにかく逃げ回る。さまざまな人の手を借りながら、宅配便のトラックやポンコツの車を駆使したり、地下の雨水管の中に入り込んだりと、ひたすら逃げ続ける青柳の姿はスリリングであり終始飽きることなく観ることができた。
それから後で小説を読んでみて気づいたけれど、小説の大事なところを映画は実に見事に凝縮されている。印象的な部分については映画の中に全て収まったのではないだろうか。おそらくは原作者も満足な出来だったと想像する。
原作小説も「第5回本屋大賞」や「第21回山本周五郎賞」をもらうなど高い評価をされたけれど、個人的には「とにかく、まずは映画を!」と言いたいくらいに面白かった。
内容も非常に面白かった。2月1日(月)には原作の小説も買ってみる。500ページほどある中編だが半日ほどで読み通してしまった。自分がいつも本を読むペースを考えると異様なスピードだが、これは私が早く本が読めるようになったとかではなく、映画を観ていたため小説の筋がある程度頭に入っていたからだと思われる。
それを読んでる時にビートルズの「アビイ・ロード」(69年)を引っぱりだして、その中に収録されている”ゴールデン・スランバー”を聴いてみた。小説のタイトルはこの曲から引用されている。ただ原題は”GOLDEN SLUMBERS”と複数形だ。「スランバーズ」だと響きが悪いとかそういう理由なのだろうか。最近はそんな日々を過ごしていたけれど、それくらいこの映画は気に入ったわけである。
「ゴールデンスランバー」は元・宅配ドライバーである青柳雅春が、仙台で旧友の森田森吾と久しぶりに再会している途中で総理大臣の暗殺犯に仕立て上げられ、2日間にわたって警察から逃亡するという内容である。
森田は、自分の妻がパチンコで抱えた借金を帳消しにすると誘われ、ある仕事を引き受けたと告白する。その内容とは、青柳を誘導することだったのである。しかし、それが危険な仕事だと気づいた森田は、
「警戒して、疑え。じゃねえと、おまえ、オズワルドにされるぞ」(本書P.112)
と青柳は意味深な忠告を受ける。
オズワルドとは、アメリカ第35代大統領ジョン・F・ケネディの暗殺犯とされているリー・ハーヴェイ・オズワルドのことだ。そのオズワルドも逮捕された2日後、ダラス警察署の地下でテレビ中継している最中ジャック・ルビーに射殺された。逮捕直後のオズワルドは、自分ははめられた、などと記者団の前で主張していたという。そして、ケネディ暗殺事件はいまでも真相は明らかになっていない部分が多い。
そうこうしているうちに、外では大きな爆発音が起こり、制服姿の警察官2人が近づいてくる。森田は続ける。
「おまえは逃げるしかねえってことだ。いいか、青柳、逃げろよ。無様な姿を晒してもいいから、とにかく逃げて、生きろ。人間、生きててなんぼだ」(本書P.117)
森田にせかされるようにして青柳は逃げる。その青柳に対して警察は躊躇無く拳銃を発砲した。首相暗殺というのは確かに重大な罪ではある。しかしその容疑者をいきなり撃ってくるというのは異常な話だ。おそらくは、青柳を射殺し、それから彼を犯人であるかのようなストーリーを作り上げていくのだろう。青柳を追いつめているのは国家とか権力とか相当に大きなものらしい。果たして青柳は逃げ切ることができるのだろうか。
2時間13分とそこそこ長い映画の中で、青柳は最後の最後までとにかく逃げ回る。さまざまな人の手を借りながら、宅配便のトラックやポンコツの車を駆使したり、地下の雨水管の中に入り込んだりと、ひたすら逃げ続ける青柳の姿はスリリングであり終始飽きることなく観ることができた。
それから後で小説を読んでみて気づいたけれど、小説の大事なところを映画は実に見事に凝縮されている。印象的な部分については映画の中に全て収まったのではないだろうか。おそらくは原作者も満足な出来だったと想像する。
原作小説も「第5回本屋大賞」や「第21回山本周五郎賞」をもらうなど高い評価をされたけれど、個人的には「とにかく、まずは映画を!」と言いたいくらいに面白かった。
やっぱり、焼きが回ってます。
2010年2月11日昨夜は仕事の関係で酒を飲む機会があった。今年の初めから減量に努めているため、昼はサンドイッチくらいにして宴席に臨んだ。事前に会議があり、それが終わって食事になったのは午後7時30分である。その合間もあまり食べることはなく、酒ばかり飲んだり飲まされたりしていた。
食事制限のことが常に頭の中にあったとはいえ。飲んでばかりいたのはまずかった。いま振り返ればそう思う。
そして仕事が終わった後もまた飲む機会があり、そこでもワインやビールを飲んでいた。
結果、この2〜3年でも類を見ないほどガタガタに酔っぱらってしまった。会社の後輩に介抱されながらタクシーでなんとか部屋に戻った。
今朝起きると異常なほど頭が痛い。ここまで酷い二日酔いもちょっと覚えが無い。昨夜のこともほどんと記憶がなかった。こないだ定休日に「風花」へ行ったこと以上の失敗である。
ここまでの事態になったことにはいろいろな理由があるけど、要するにろくに食べないでひたすら飲んでいたのが最もまずかったのは間違いない。しかし、何か口に入れてないと済まない人間であるため、この習慣を直すのは容易なことではないと思う。
食事制限のことが常に頭の中にあったとはいえ。飲んでばかりいたのはまずかった。いま振り返ればそう思う。
そして仕事が終わった後もまた飲む機会があり、そこでもワインやビールを飲んでいた。
結果、この2〜3年でも類を見ないほどガタガタに酔っぱらってしまった。会社の後輩に介抱されながらタクシーでなんとか部屋に戻った。
今朝起きると異常なほど頭が痛い。ここまで酷い二日酔いもちょっと覚えが無い。昨夜のこともほどんと記憶がなかった。こないだ定休日に「風花」へ行ったこと以上の失敗である。
ここまでの事態になったことにはいろいろな理由があるけど、要するにろくに食べないでひたすら飲んでいたのが最もまずかったのは間違いない。しかし、何か口に入れてないと済まない人間であるため、この習慣を直すのは容易なことではないと思う。
いよいよ焼きが回ったか?
2010年2月9日
今日の昼は、仕事のついでに下京区のラーメン店「新宿めんや風花」に自転車で行った。
定休日だった。シャッターの閉まった店の前で呆然となる。
長年通っている店だ。しかも、今日が休みだったことは朝の時点では頭に残っていたはずである。それがスコーンと抜けてしまった。
どうしてこんなことになったのだろう。いよいよボケてきたのだろうか。それとも空腹だったからか。はたまた、この久しぶりの陽気のせいか。
気を取り直して自転車のペダルをこぎ、五条通の方にある「吟醸らーめん久保田」へ方向転換する。定休日などは把握してなかったが、幸いにして店は営業していた。しかも1時ごろの混雑時のはずなのに席は空いている。
座ってメニューを取ろうとすると、
「すいません。今日は限定メニューしかないんです」
と定員が言ってくる。壁を見れば、「二郎風豚骨醤油らーめん」と「吟醸らーめん『麻油』鶏白湯」の張り紙があった。ともに価格は800円である。二郎系は別に食べたくもないので「鶏白湯」を注文した。
頼んだ後でわかったのだが、久保田も通常は火曜日が定休日であった。それが何のきまぐれか今日に限って臨時営業をしていたのである。限定メニューしかなかったのはそのためだ。しかし臨時だったおかげでスッと入ることができたのだろう。それでもお客は後から後から入ってきた。
写真が「吟醸らーめん『麻油』鶏白湯」である。
定休日だった。シャッターの閉まった店の前で呆然となる。
長年通っている店だ。しかも、今日が休みだったことは朝の時点では頭に残っていたはずである。それがスコーンと抜けてしまった。
どうしてこんなことになったのだろう。いよいよボケてきたのだろうか。それとも空腹だったからか。はたまた、この久しぶりの陽気のせいか。
気を取り直して自転車のペダルをこぎ、五条通の方にある「吟醸らーめん久保田」へ方向転換する。定休日などは把握してなかったが、幸いにして店は営業していた。しかも1時ごろの混雑時のはずなのに席は空いている。
座ってメニューを取ろうとすると、
「すいません。今日は限定メニューしかないんです」
と定員が言ってくる。壁を見れば、「二郎風豚骨醤油らーめん」と「吟醸らーめん『麻油』鶏白湯」の張り紙があった。ともに価格は800円である。二郎系は別に食べたくもないので「鶏白湯」を注文した。
頼んだ後でわかったのだが、久保田も通常は火曜日が定休日であった。それが何のきまぐれか今日に限って臨時営業をしていたのである。限定メニューしかなかったのはそのためだ。しかし臨時だったおかげでスッと入ることができたのだろう。それでもお客は後から後から入ってきた。
写真が「吟醸らーめん『麻油』鶏白湯」である。
その後の経過
2010年2月8日朝の早くから病院に行き、リンパ節の具合を診てもらった。
そして喉を調べられた後、前回と同じく鼻の中に液体を注入されカメラを入れられた。2回目なのでもうすっかり平気である。人と話して気づいたが、先に入れられる液体は鼻の洗浄ではなく麻酔らしい。
喉はまだ少し腫れているという。しかし目立った症状もないので、また薬のみという結論に至った。
念のためもう一回来てくれた方がいいんだけど、と先生は言っていたが。
行きたくありません。
そして喉を調べられた後、前回と同じく鼻の中に液体を注入されカメラを入れられた。2回目なのでもうすっかり平気である。人と話して気づいたが、先に入れられる液体は鼻の洗浄ではなく麻酔らしい。
喉はまだ少し腫れているという。しかし目立った症状もないので、また薬のみという結論に至った。
念のためもう一回来てくれた方がいいんだけど、と先生は言っていたが。
行きたくありません。
【ディスク1】
(1)I’m Free
(2)GROWIN’ UP
(3) 死んでるみたいに生きたくない
(4) My Revolution
(5)Teenage Walk
(6) Long Night
(7)BELIEVE
(8) IT’S TOUGH
(9) 悲しいね
(10)恋したっていいじゃない
(11)センチメンタル カンガルー
(12)君の弱さ
(13)ムーンライト ダンス
(14)すき (Apricot Mix)
【ディスク2】
(1)虹をみたかい
(2)サマータイム ブルース
(3)恋するパンクス
(4)Power -明日の子供-
(5)卒業
(6)夏が来た!
(7)クリスマスまで待てない (雪だるま Version)
(8)My Revolution -第2章-
(9)泣いちゃいそうだよ
(10)メリーゴーランド
(11)いつか きっと
(12)BIG WAVE やってきた
(13)真夏のサンタクロース
【ディスク3】
(1)チェリーが3つ並ばない
(2)シンシアリー [Sincerely]
(3)世界で一番 遠い場所
(4)My Love Your Love ~たったひとりしかいない あなたへ~
(5)一緒だね
(6)夏の歌
(7)素顔
(8)太陽は知っている
(9)新しい日々
(10)もっと 遠くへ…
(11)荒ぶる胸のシンバル鳴らせ
(12)夏灼きたまご
(13)やさしく歌って -Killing me softly with his song-
【ディスク4】
(1)YOU ~新しい場所~
(2)12月の神様
(3)ドラえもんのうた
(4)小指
(5)十の秘密
(6)トマト
(7)おねがい太陽 ~夏のキセキ~
(8)青い鳥
(9)その手をつないで
(10)yes
(11)あしたの空
(12)始まりの詩、あなたへ
(13)Home Planet -地球こそ私の家 ※ボーナス・トラック
渡辺美里が「レコード・デビュー」したのは1985年5月2日のことである。デビュー曲がケニー・ロギンスの”I’m free”のカバーだったことを知っているのは熱心なファンくらいだろう。原曲は映画「フットルース」(84年)の挿入曲で、映画のサウンド・トラックにも収録されている。それにしてもMP3プレーヤー全盛の昨今からすれば、まだCDすら一般に流通してなかったレコードの時代は隔世の感がある。
今年は2010年で、彼女がデビューしてから25年を迎える。そんな節目ということもあり、これまでの全シングルを時系列に収めた4枚組アルバム「Song is Beautiful」がこのたび発売された。
振り返ってみれば、彼女がブランクらしきものもなく今まで25年間活動してきている。同世代のミュージシャンたちはレコード契約を打ち切られたり、また逮捕された人までいることを思えば、それはそれで一つの業績といえるかもしれない。いままで出した52枚のシングル曲はそれを物語っている。
これまでも何枚かベスト・アルバムを出しているけれど、全シングル収録という形のものは初めてのことだ。数はそれほどではないけれどアルバム未収録曲もあり(”君の弱さ”、”メリーゴーランド”、”12月の神様”、佐野元春とのデュエット曲”Home Planet-地球こそ私の家”、そして最近出たシングル3曲)、それらが復活したのは歓迎すべきことだろう。
しかしながら、それならばシングルのカップリング曲も全て収録する徹底ぶりを見せてほしかった。それでたとえ倍の値段になったとしても、買う人は買う。どうせ今の彼女のCDを買う人など限られているのだから、なるべく利益率が高いほうが良い。実際、私は最初JEUGIA三条本店に入ったがアルバムは置いてなく、その近くのジュンク堂のCDコーナーでこれを見つけた。JEUGIAに置いてあったのは買われてしまったのか、それとも最初から置いてなかったのかはわからない。いずれにせよこのCDの出荷枚数などたかがしれているのだ。もはやファンの増加は見込めず、またCDそのものが売れない現代においては、ファンの囲い込みのような方策が最も効果的だと思うのだが。(ちなみにいま公式サイトを確認したら、初回限定盤は完売していた)
愚痴が過ぎてしまったようだ。改めて内容について触れることにしたい。
今回特筆するのは、全曲を新たにロンドンでマスタリングし直したことだろう。試しに”夏が来た!”を以前の音源と比べて聴いてみたけれど、やはり今回のほうが音のメリハリとかクリアさは明らかに向上している。サウンドの古くささも薄まったように感じた。数えきれないほど聴いているはずの”サマータイム ブルース”など楽曲や彼女の声が妙に新鮮に感じてしまう場面もあった。そうだ。そもそも彼女の声が好きで私はファンになったんだ、などとそんなことまで思い出しながら。
また買って聴く前までは、シングル曲の集合なんて新鮮な発見はないだろう、と思っていた。しかしそれは少し違っていた。いちおう4枚のディスクをひと通り聴いたけれど、いまはもっぱらディスク2ばかり流している。ディスク2は私が最もこの人に熱心だった時期(91年後半から93年半ばごろ)と重なるからだ。”サマータイムブルース”、”卒業”、”夏が来た!”あたりの曲がやはり自分にとって最も求心力のあるものだと改めて気づかされる。
「なんだ、俺の根本は中学生の頃から同じということか」
そんなことを思った。そしてそれは死ぬまで変わらないような気がする。
私が初めて彼女のCD「lucky」を買ったのは91年の冬だった。まだ中学3年生の時である。それからでも18年の月日が流れたことになる。
「ずっとこの人を追いかけていこう」
と心に決めたのは初めて彼女のライブを観た高校1年の夏だっただろうか。さすがにそんな「信者」だった時期はあまり長く続かなかったけれど、結果として今も彼女の歌やライブと付き合い続けている。彼女と自分を比較することが不毛なのは百も承知だが、現在まで彼女も私も平坦な道のりを歩いていなかったと思う。そして、この間がどれほど実りのあった時期かといえば、それもお互いあまり自信がない。
たとえば今の10代や20代の人たちがこれらの曲を聴いて何か感じるものがあるのだろうか、と考えてしまう時もある。それに意識的な音楽ファンから見れば、渡辺美里を中心とする80年代のEPIC SONY周辺から出ていたミュージシャンといえば、音楽性に乏しい人たちと位置づけられていることが多い。その評価に対して特に異議を唱えるつもりもないけれど、人間や芸術というものはそんなに単純に割り切れるものではないだろう。いつも思うのだが、芸術は創っている送り手と、私のような受け手の双方があって成立する。
世間の評価など、もはやどうでもいい。渡辺美里と自分が歩んだ道は何だったのか。それはこれからも続く人生の中で、自分自身で見つけるしかないのだろう。ある時期からそう考えるようになった。そしてその道はまだ継続中である。
(1)I’m Free
(2)GROWIN’ UP
(3) 死んでるみたいに生きたくない
(4) My Revolution
(5)Teenage Walk
(6) Long Night
(7)BELIEVE
(8) IT’S TOUGH
(9) 悲しいね
(10)恋したっていいじゃない
(11)センチメンタル カンガルー
(12)君の弱さ
(13)ムーンライト ダンス
(14)すき (Apricot Mix)
【ディスク2】
(1)虹をみたかい
(2)サマータイム ブルース
(3)恋するパンクス
(4)Power -明日の子供-
(5)卒業
(6)夏が来た!
(7)クリスマスまで待てない (雪だるま Version)
(8)My Revolution -第2章-
(9)泣いちゃいそうだよ
(10)メリーゴーランド
(11)いつか きっと
(12)BIG WAVE やってきた
(13)真夏のサンタクロース
【ディスク3】
(1)チェリーが3つ並ばない
(2)シンシアリー [Sincerely]
(3)世界で一番 遠い場所
(4)My Love Your Love ~たったひとりしかいない あなたへ~
(5)一緒だね
(6)夏の歌
(7)素顔
(8)太陽は知っている
(9)新しい日々
(10)もっと 遠くへ…
(11)荒ぶる胸のシンバル鳴らせ
(12)夏灼きたまご
(13)やさしく歌って -Killing me softly with his song-
【ディスク4】
(1)YOU ~新しい場所~
(2)12月の神様
(3)ドラえもんのうた
(4)小指
(5)十の秘密
(6)トマト
(7)おねがい太陽 ~夏のキセキ~
(8)青い鳥
(9)その手をつないで
(10)yes
(11)あしたの空
(12)始まりの詩、あなたへ
(13)Home Planet -地球こそ私の家 ※ボーナス・トラック
渡辺美里が「レコード・デビュー」したのは1985年5月2日のことである。デビュー曲がケニー・ロギンスの”I’m free”のカバーだったことを知っているのは熱心なファンくらいだろう。原曲は映画「フットルース」(84年)の挿入曲で、映画のサウンド・トラックにも収録されている。それにしてもMP3プレーヤー全盛の昨今からすれば、まだCDすら一般に流通してなかったレコードの時代は隔世の感がある。
今年は2010年で、彼女がデビューしてから25年を迎える。そんな節目ということもあり、これまでの全シングルを時系列に収めた4枚組アルバム「Song is Beautiful」がこのたび発売された。
振り返ってみれば、彼女がブランクらしきものもなく今まで25年間活動してきている。同世代のミュージシャンたちはレコード契約を打ち切られたり、また逮捕された人までいることを思えば、それはそれで一つの業績といえるかもしれない。いままで出した52枚のシングル曲はそれを物語っている。
これまでも何枚かベスト・アルバムを出しているけれど、全シングル収録という形のものは初めてのことだ。数はそれほどではないけれどアルバム未収録曲もあり(”君の弱さ”、”メリーゴーランド”、”12月の神様”、佐野元春とのデュエット曲”Home Planet-地球こそ私の家”、そして最近出たシングル3曲)、それらが復活したのは歓迎すべきことだろう。
しかしながら、それならばシングルのカップリング曲も全て収録する徹底ぶりを見せてほしかった。それでたとえ倍の値段になったとしても、買う人は買う。どうせ今の彼女のCDを買う人など限られているのだから、なるべく利益率が高いほうが良い。実際、私は最初JEUGIA三条本店に入ったがアルバムは置いてなく、その近くのジュンク堂のCDコーナーでこれを見つけた。JEUGIAに置いてあったのは買われてしまったのか、それとも最初から置いてなかったのかはわからない。いずれにせよこのCDの出荷枚数などたかがしれているのだ。もはやファンの増加は見込めず、またCDそのものが売れない現代においては、ファンの囲い込みのような方策が最も効果的だと思うのだが。(ちなみにいま公式サイトを確認したら、初回限定盤は完売していた)
愚痴が過ぎてしまったようだ。改めて内容について触れることにしたい。
今回特筆するのは、全曲を新たにロンドンでマスタリングし直したことだろう。試しに”夏が来た!”を以前の音源と比べて聴いてみたけれど、やはり今回のほうが音のメリハリとかクリアさは明らかに向上している。サウンドの古くささも薄まったように感じた。数えきれないほど聴いているはずの”サマータイム ブルース”など楽曲や彼女の声が妙に新鮮に感じてしまう場面もあった。そうだ。そもそも彼女の声が好きで私はファンになったんだ、などとそんなことまで思い出しながら。
また買って聴く前までは、シングル曲の集合なんて新鮮な発見はないだろう、と思っていた。しかしそれは少し違っていた。いちおう4枚のディスクをひと通り聴いたけれど、いまはもっぱらディスク2ばかり流している。ディスク2は私が最もこの人に熱心だった時期(91年後半から93年半ばごろ)と重なるからだ。”サマータイムブルース”、”卒業”、”夏が来た!”あたりの曲がやはり自分にとって最も求心力のあるものだと改めて気づかされる。
「なんだ、俺の根本は中学生の頃から同じということか」
そんなことを思った。そしてそれは死ぬまで変わらないような気がする。
私が初めて彼女のCD「lucky」を買ったのは91年の冬だった。まだ中学3年生の時である。それからでも18年の月日が流れたことになる。
「ずっとこの人を追いかけていこう」
と心に決めたのは初めて彼女のライブを観た高校1年の夏だっただろうか。さすがにそんな「信者」だった時期はあまり長く続かなかったけれど、結果として今も彼女の歌やライブと付き合い続けている。彼女と自分を比較することが不毛なのは百も承知だが、現在まで彼女も私も平坦な道のりを歩いていなかったと思う。そして、この間がどれほど実りのあった時期かといえば、それもお互いあまり自信がない。
たとえば今の10代や20代の人たちがこれらの曲を聴いて何か感じるものがあるのだろうか、と考えてしまう時もある。それに意識的な音楽ファンから見れば、渡辺美里を中心とする80年代のEPIC SONY周辺から出ていたミュージシャンといえば、音楽性に乏しい人たちと位置づけられていることが多い。その評価に対して特に異議を唱えるつもりもないけれど、人間や芸術というものはそんなに単純に割り切れるものではないだろう。いつも思うのだが、芸術は創っている送り手と、私のような受け手の双方があって成立する。
世間の評価など、もはやどうでもいい。渡辺美里と自分が歩んだ道は何だったのか。それはこれからも続く人生の中で、自分自身で見つけるしかないのだろう。ある時期からそう考えるようになった。そしてその道はまだ継続中である。
壊されるなんて当たり前、だと思っていたあの頃
2010年2月6日北海道では2月5日の「さっぽろ雪まつり」に続き、6日は「旭川雪まつり」も始まった。この時期の一大イベントなのでたくさんの観光客が訪れるにちがいない。
しかし始まってまもないこの時期に嫌なニュースが飛び込んできた。祭りを盛り上げようと地元の商店街組合員および高校生が作った雪だるま約50個が壊されたというのだ。
このニュースを観て遠い昔の記憶がよみがえってきた。今日はそれについて書きたい。
私が生まれ育った北海道登別市は、旭川のような内陸ほど寒くはないものの、冬はそれなりに雪がつもる。子どもの頃は雪だるまやかまくらも作ってみたりした。しかし、一日かけて作ってみても、翌朝になればただの雪の残骸と化してしまう。誰かに壊されてしまうのだ。現場を確認したこともないけれど、近所にはガラの悪い中高生は何人かいた。彼らが夜中に、面白半分でおこなっていたのだろう。
しかしながら、そんな壊れた雪だるまやかまくらを見て悲しいとかいう気持ちは湧かなかった気がする。なぜなら、それらがすぐに壊されてしまうのは日常の光景だったからだ。昼間に作っても、その夜には壊される。そういうものだという認識はずっと思っていた。自分が作った以外にも、壊れた雪だるまの姿を見てきたからかもしれない。
ましてやこの現在に、しかもはるか遠くの旭川のニュースを見て何か感傷的になることもなかった。ただ犯人に対しては、他にすることがなかったのかねえ、とは言いたくなる。
しかし始まってまもないこの時期に嫌なニュースが飛び込んできた。祭りを盛り上げようと地元の商店街組合員および高校生が作った雪だるま約50個が壊されたというのだ。
このニュースを観て遠い昔の記憶がよみがえってきた。今日はそれについて書きたい。
私が生まれ育った北海道登別市は、旭川のような内陸ほど寒くはないものの、冬はそれなりに雪がつもる。子どもの頃は雪だるまやかまくらも作ってみたりした。しかし、一日かけて作ってみても、翌朝になればただの雪の残骸と化してしまう。誰かに壊されてしまうのだ。現場を確認したこともないけれど、近所にはガラの悪い中高生は何人かいた。彼らが夜中に、面白半分でおこなっていたのだろう。
しかしながら、そんな壊れた雪だるまやかまくらを見て悲しいとかいう気持ちは湧かなかった気がする。なぜなら、それらがすぐに壊されてしまうのは日常の光景だったからだ。昼間に作っても、その夜には壊される。そういうものだという認識はずっと思っていた。自分が作った以外にも、壊れた雪だるまの姿を見てきたからかもしれない。
ましてやこの現在に、しかもはるか遠くの旭川のニュースを見て何か感傷的になることもなかった。ただ犯人に対しては、他にすることがなかったのかねえ、とは言いたくなる。
鼻にカメラ、そして甲状腺エコー検査
2010年2月5日食事をしている時、左あごの下あたりに違和感があったことに気づいたのはいつからだろう。気になってその辺を触ってみると、なんだか固い。リンパ節が腫れているのだ。他に目立った症状は無いけれど腫れはしばらく続いているので、さきほど近所の病院に行ってみた。窓口に症状を伝えたら耳鼻科のほうに案内される。
実をいうと、リンパ節が腫れる症状は年末にもあり、その時も耳鼻科にかかった。診断してくれた先生も以前にお世話になった方である。まず口を開けて喉の奥を見られるも、先生の反応は「うーん」という感じで鈍い。そして、鼻に何やら薬を入れられた後(おそらく鼻を洗浄したのだろう)、鼻の穴にカメラを挿入した。インフルエンザの疑いがあったとき鼻に綿棒を入れられたことがあるが、その時ほど痛さや違和感はない。
「少し喉が腫れてますね。まだ時間がありますか?」
そう言われたので不安になったけれど、昼までなら大丈夫です、と答える。すると、エコーをしますから別棟の地下1階に行ってください、とのことだ。
「エコー」ってなんだ?しかも病院の地下の部屋とは。不安はますます高まっているが、もう仕方ない。病院に言われるまま進むと、「生理検査室」という部屋があった。しばらく待っていると、さきほどの耳鼻科の先生がやってくる。
「これは何をするんですか?」
とビクビクしながら質問したら、
「エコーしたことないの?」
と怪訝そうな返事をされる。部屋にはベッドとレーダーのような機械が置いてあった。上半身を裸にしてベッドに横になると、何やらヌルヌルしたものを首に押し当てられる。それ以外に痛みとか違和感は全くなかった。
エコーとは、さきほどネットで調べてみると、「エコー(超音波)検査」のことであった。超音波を当てて体の中の映像を出し、その様子を確認する検査である。私の場合は首のあたりを診断されるから「甲状腺エコー検査」になる。
「けっこう腫れてますねえ」
と先生に言われた。後で私も写真を見せてもらったら、膨らんだ丸いものがいくつか映っている。それが腫れているリンパ節だそうだ。
「他に目立った症状はないので、ひとまず薬で様子をみましょう。それで症状が変わらなければCTスキャンとかの必要も・・・」
CTまで出てくるか。なんだか話が大きくなってきたような気がする。
ひとまず4日分の薬を渡される。次の診断は8日(月)午前の予定だ。それまではおとなしくしておこうと思っている。
実をいうと、リンパ節が腫れる症状は年末にもあり、その時も耳鼻科にかかった。診断してくれた先生も以前にお世話になった方である。まず口を開けて喉の奥を見られるも、先生の反応は「うーん」という感じで鈍い。そして、鼻に何やら薬を入れられた後(おそらく鼻を洗浄したのだろう)、鼻の穴にカメラを挿入した。インフルエンザの疑いがあったとき鼻に綿棒を入れられたことがあるが、その時ほど痛さや違和感はない。
「少し喉が腫れてますね。まだ時間がありますか?」
そう言われたので不安になったけれど、昼までなら大丈夫です、と答える。すると、エコーをしますから別棟の地下1階に行ってください、とのことだ。
「エコー」ってなんだ?しかも病院の地下の部屋とは。不安はますます高まっているが、もう仕方ない。病院に言われるまま進むと、「生理検査室」という部屋があった。しばらく待っていると、さきほどの耳鼻科の先生がやってくる。
「これは何をするんですか?」
とビクビクしながら質問したら、
「エコーしたことないの?」
と怪訝そうな返事をされる。部屋にはベッドとレーダーのような機械が置いてあった。上半身を裸にしてベッドに横になると、何やらヌルヌルしたものを首に押し当てられる。それ以外に痛みとか違和感は全くなかった。
エコーとは、さきほどネットで調べてみると、「エコー(超音波)検査」のことであった。超音波を当てて体の中の映像を出し、その様子を確認する検査である。私の場合は首のあたりを診断されるから「甲状腺エコー検査」になる。
「けっこう腫れてますねえ」
と先生に言われた。後で私も写真を見せてもらったら、膨らんだ丸いものがいくつか映っている。それが腫れているリンパ節だそうだ。
「他に目立った症状はないので、ひとまず薬で様子をみましょう。それで症状が変わらなければCTスキャンとかの必要も・・・」
CTまで出てくるか。なんだか話が大きくなってきたような気がする。
ひとまず4日分の薬を渡される。次の診断は8日(月)午前の予定だ。それまではおとなしくしておこうと思っている。
マイケル・ジャクソン「THIS IS IT」を観てきた
2010年1月22日今さらの話かもしれないけれど、1月24日(日)までアンコール上映されているので、この日の夜にマイケル・ジャクソンの「THIS IS IT」をMOVIX京都で観てきた。時期がここまでギリギリになったのは、本当は観るつもりがなかったからである。きっかけは、周囲でやたら騒ぐ人が多かったためだ。
会社の後輩は、マイケルって悪いイメージがあったけどこれを観て変わりました、などと言っていた。彼が今も健在だったら、そのイメージが変わることもなかっただろう。
仕事でアルバイトをお願いしている女性にいたっては、
「ぜひ観てください!私は2回観ました!あれを観てダンスを始めようかと思った」
とまでの入れ込みぶりである。そこまで言うのならと、私のとても重たい腰が上がったわけだ。
しかしながら、レイトショーで観に行ったのはつくづく失敗だと感じる。昼間は町中をフラフラしたので上映の午後8時にはもう疲れて眠くなっていた。実際、1時間を過ぎるあたりでウトウトしてしまう。もともと思い入れなど全くない人の映画だったこともあるだろうが、最後までつき合うのは正直いって辛かった。
内容についてあれこれ言える立場ではないけれど、最も印象に残ったのは、
「観客のいないリハーサル風景というのは、こんなに寂しいもんなんだなあ」
ということである。これまで100本以上ライブを観ている身で音楽も人並み以上に好きではあるが、リハーサルの中で舞台監督やバック・ミュージシャンに指示を出すマイケルの姿は興味深かったものの、それ以上にこうした寂しさの方が強く感じてしまった。またこれが彼の最後の勇姿ということを考えると、そういう気持ちは余計に強くなってしまう。
アルバイトの女性は、
「やっぱり生きてないと。死んだら終わりなんだなあ、と観ていて思いました」
とも言っていた。それは同感である。
会社の後輩は、マイケルって悪いイメージがあったけどこれを観て変わりました、などと言っていた。彼が今も健在だったら、そのイメージが変わることもなかっただろう。
仕事でアルバイトをお願いしている女性にいたっては、
「ぜひ観てください!私は2回観ました!あれを観てダンスを始めようかと思った」
とまでの入れ込みぶりである。そこまで言うのならと、私のとても重たい腰が上がったわけだ。
しかしながら、レイトショーで観に行ったのはつくづく失敗だと感じる。昼間は町中をフラフラしたので上映の午後8時にはもう疲れて眠くなっていた。実際、1時間を過ぎるあたりでウトウトしてしまう。もともと思い入れなど全くない人の映画だったこともあるだろうが、最後までつき合うのは正直いって辛かった。
内容についてあれこれ言える立場ではないけれど、最も印象に残ったのは、
「観客のいないリハーサル風景というのは、こんなに寂しいもんなんだなあ」
ということである。これまで100本以上ライブを観ている身で音楽も人並み以上に好きではあるが、リハーサルの中で舞台監督やバック・ミュージシャンに指示を出すマイケルの姿は興味深かったものの、それ以上にこうした寂しさの方が強く感じてしまった。またこれが彼の最後の勇姿ということを考えると、そういう気持ちは余計に強くなってしまう。
アルバイトの女性は、
「やっぱり生きてないと。死んだら終わりなんだなあ、と観ていて思いました」
とも言っていた。それは同感である。
ボランティアは好きじゃない
2010年1月19日この1週間ほど仕事のおかげであまり落ち着くことができなかった。今日はようやく半休できたので、何か書いておきたい。
ただ、ここで書くことは誰かを批判するとかが目的ではなく、あくまで一般論でとどめることをお断りしておく。
私は仕事でさまざまなイベントと関わっている。スポーツや展覧会、シンポジウムなど内容は多彩だ。しかし、企業との取引などはそれほど多くないことに今さらながら気づく。
ではどういうところが多いかといえば、各種のスポーツ団体とか県人会とか、本業の仕事のかたわらでイベントを運営している人たちである。いずれも広い意味での「ボランティア」といって良いだろう。
私は、組織改編もあって会社自体が変わったこともあるものの、01年7月からそのような人たちと関わり続けている。だが、ここだけの話だけれど、そういう人たちで好意を抱いている人は皆無といっていい。イベントの運営というのはボランティアの人たちと共同運営の形になっている。専門的なことはボランティア、事務や雑用などは私らの仕事、おおざっぱに分けるとそんな感じで進んでいく。
しかしながら運営中に面倒な業務が生じた場合、連中は私たちにその処理を押し付けようとする。手間がかかることもあるし経費が派生する場合だってある。こちらもご多分に漏れず社内は苦しい台所事情もあるので、それは無理ですよ、などと答える場面もあった。
すると、
「あんたらは仕事だろ。こっちはボランティアでやってるんだ」
という決まり文句が飛び出すのだ。こんなセリフを繰り返し聞くうち、ボランティアというのはこんな思考回路の持ち主なんだなあと感じるようになった。奴らは「無償奉仕」を口実に逃げ道を作っているのだなあ、と。非営利で善意でやっているんだから多少のことは大目に見ろ、ということだ。そんな屁理屈は世間で通じるはずもないのだが。
もっと余計なことをいえば、金勘定もあまり考えない。世の中の経済状況がこれほど苦しい時でも経費削減などが頭に入っている人は多くないだろう。彼らはイベントが毎年変わらず続けていけるという確信があるらしい。その確信の根拠は何もないのだけれど。
そんな人たちとつき合ってから8年を過ぎてしまった。いよいよ限界になってきたような気がする今日このごろである。
ただ、ここで書くことは誰かを批判するとかが目的ではなく、あくまで一般論でとどめることをお断りしておく。
私は仕事でさまざまなイベントと関わっている。スポーツや展覧会、シンポジウムなど内容は多彩だ。しかし、企業との取引などはそれほど多くないことに今さらながら気づく。
ではどういうところが多いかといえば、各種のスポーツ団体とか県人会とか、本業の仕事のかたわらでイベントを運営している人たちである。いずれも広い意味での「ボランティア」といって良いだろう。
私は、組織改編もあって会社自体が変わったこともあるものの、01年7月からそのような人たちと関わり続けている。だが、ここだけの話だけれど、そういう人たちで好意を抱いている人は皆無といっていい。イベントの運営というのはボランティアの人たちと共同運営の形になっている。専門的なことはボランティア、事務や雑用などは私らの仕事、おおざっぱに分けるとそんな感じで進んでいく。
しかしながら運営中に面倒な業務が生じた場合、連中は私たちにその処理を押し付けようとする。手間がかかることもあるし経費が派生する場合だってある。こちらもご多分に漏れず社内は苦しい台所事情もあるので、それは無理ですよ、などと答える場面もあった。
すると、
「あんたらは仕事だろ。こっちはボランティアでやってるんだ」
という決まり文句が飛び出すのだ。こんなセリフを繰り返し聞くうち、ボランティアというのはこんな思考回路の持ち主なんだなあと感じるようになった。奴らは「無償奉仕」を口実に逃げ道を作っているのだなあ、と。非営利で善意でやっているんだから多少のことは大目に見ろ、ということだ。そんな屁理屈は世間で通じるはずもないのだが。
もっと余計なことをいえば、金勘定もあまり考えない。世の中の経済状況がこれほど苦しい時でも経費削減などが頭に入っている人は多くないだろう。彼らはイベントが毎年変わらず続けていけるという確信があるらしい。その確信の根拠は何もないのだけれど。
そんな人たちとつき合ってから8年を過ぎてしまった。いよいよ限界になってきたような気がする今日このごろである。
木が・・・
2010年1月14日
仕事の準備のため朝から西京極運動公園の中を歩き回っていた。ずっと作業があったため、昼も公園近くの喫茶店で済ませる。食べ終えて店を出ようとした時、私と同じく公園内で仕事をしていた設営業者の人が、
「渡部さん、木が倒れたよ。(仕事の)当日じゃなくて良かったねえ」
と言ってきた。
木が倒れた?どこの?
その時は、業者さんの言っていることがよくわからなかった。
しかし公園に入るとすぐ事情がわかった。写真のように、大きな木が根っこが倒れていたのである。折れているところを確認すると、木の中身が空洞になっていた。別に風などが原因ではなく、木の寿命がきたということだろう。
倒れた木の処理については、公園によく入っている造園業者がチェンソーでバラバラし、それをゴミ収集車のような車に放り込んでいた。
それにしても、倒れた場所は私が30分ほど前に歩いていた場所である。そして私が食事を取っている間にあんなことが起きたわけだ。非常に危なかったと思う。
「渡部さん、木が倒れたよ。(仕事の)当日じゃなくて良かったねえ」
と言ってきた。
木が倒れた?どこの?
その時は、業者さんの言っていることがよくわからなかった。
しかし公園に入るとすぐ事情がわかった。写真のように、大きな木が根っこが倒れていたのである。折れているところを確認すると、木の中身が空洞になっていた。別に風などが原因ではなく、木の寿命がきたということだろう。
倒れた木の処理については、公園によく入っている造園業者がチェンソーでバラバラし、それをゴミ収集車のような車に放り込んでいた。
それにしても、倒れた場所は私が30分ほど前に歩いていた場所である。そして私が食事を取っている間にあんなことが起きたわけだ。非常に危なかったと思う。