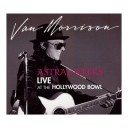私の部屋のパソコンは今もADSL回線だ。光ケーブル回線が国内でもかなり普及している現在ではあるけれど、ADSLの速度でたいして不都合を感じないのでそのまま使用している。
その回線が最近調子が悪い。インターネットに接続できなくなることが多くなっている。つまり、ネットをしている最中に回線が切断されてしまうのだ。それでもしばらくして再び接続すれば、ネットも元通り復旧する。不便だがいちおう使えるのでまあ大丈夫だと昨日まで思っていた。
そして今日も朝からネットがつながらない。しかし今回はちょっと事情が違うようだ。会社から戻った後で再接続しようとしても駄目だった。
ディスプレイには、
「PPPoEサーバが見つかりませんでした。」
というメッセージが表示されるばかりである。
ADSLモデムのマニュアルを開いてみると、どうやらこのメッセージは「物理的問題」が生じた時に出てくるらしい。
「物理的問題」の例を具体的に挙げれば、
・ケーブルがちゃんとつながってない。
・モデムが故障した。
・ケーブルが切れた。
といったようなことである。
しかし素人目で見た限りではモデムに異常はない。ケーブルもそうそう切れるものではない、と周囲の知人は言っていた。私もそう思う。
いずれにせよ、もはや自分では解決できない事態となっているのは間違いない。週明けにでもNTT西日本に相談してみよう。
その回線が最近調子が悪い。インターネットに接続できなくなることが多くなっている。つまり、ネットをしている最中に回線が切断されてしまうのだ。それでもしばらくして再び接続すれば、ネットも元通り復旧する。不便だがいちおう使えるのでまあ大丈夫だと昨日まで思っていた。
そして今日も朝からネットがつながらない。しかし今回はちょっと事情が違うようだ。会社から戻った後で再接続しようとしても駄目だった。
ディスプレイには、
「PPPoEサーバが見つかりませんでした。」
というメッセージが表示されるばかりである。
ADSLモデムのマニュアルを開いてみると、どうやらこのメッセージは「物理的問題」が生じた時に出てくるらしい。
「物理的問題」の例を具体的に挙げれば、
・ケーブルがちゃんとつながってない。
・モデムが故障した。
・ケーブルが切れた。
といったようなことである。
しかし素人目で見た限りではモデムに異常はない。ケーブルもそうそう切れるものではない、と周囲の知人は言っていた。私もそう思う。
いずれにせよ、もはや自分では解決できない事態となっているのは間違いない。週明けにでもNTT西日本に相談してみよう。
コンタクトレンズの具合、その後
2009年5月6日 日常 コメント (4)コンタクトレンズを切り替えて以来、目に違和感を生じる場面が多くなっている。そして、その原因は目の乾燥にあると、こないだまではそう思っていた。
今日も左目の調子が悪い。そこで、すぐに目薬を差してみた。しかし効果は一瞬のもので、また再び「ゴロゴロした感じ」が目を襲う。一度レンズを外してつけなおしても同じだ。
どうやら、乾燥が問題ではなかったようである。
そうなると、このレンズは自分に合わない、という結論を出さざるをえない。いくら素材が良くなったからといって万人に適するわけでもないだろう。コンタクトレンズの商品が載っているサイトを見ても、
「装着感には個人差があります」
と但し書きがついているくらいだから。
自分に都合の良いコンタクトに切り替えるのが一番良い。しかし、半年分のレンズを既にまとめ買いした後である。
それとも、コンタクトに目が合うようになるまで我慢して使用し続けるか。少なくとも、着ければ常に違和感が生じているわけでもないので、そうなる日が訪れる日を願ってしばらく待ってみることにする。当面はそれしか私には選択がない。
コンタクトレンズを替えてから
2009年5月5日 日常2002年の12月1日から現在までコンタクトレンズを着用している。生産中止になったという理由で最初のレンズを変更した以外は何年も同じ商品を使っていた。
しかし先月に眼科で検査をした際(コンタクトレンズを購入する際は診断を受けなければならない)、新しいレンズが出ているので替えてみませんか、と係の人に薦められる。素材がシリコンで空気の通りが良いですよ、というような説明だった。けっこう多くの人もこのレンズに切り替えているという。
別に今のレンズで何も問題なかったけれど、より快適に過ごせるならば、と思い言われるがまま買ってしまった。1箱あたりにすると300円ほど従来に比べて値段が上がった。その場でためしに着けた時点では、以前のレンズよりも柔らかいけれど良い感じかな、というのが印象である。
だが、しばらく使用していたら具合がどうも良くない。別に目が充血するとかいった深刻な症状が出てはいないものの、いわゆる「目がゴロゴロする」と言われるような違和感がよく起きる。ちなみに両目が同時に悪いということはなく、昨日は右目かと思ったら今日は左目がイマイチ、とそんな感じだった。
「空気が通りやすい、というのは、乾燥しやすい、という意味なのか?」
などと思うこともあった。
そして今日も左目の調子が悪い。あまりにも苦しいため近所のドラッグストアで目薬を買ってみる。目の乾燥が原因と思ったからだ。
買ってすぐに左目に目薬を入れてみる。冷たいと感じてからすぐに目の違和感は消え去った。
「やはり乾燥が原因だったか、これからしばらく目薬が手放せないな」
と一瞬だけ思った。しかし、左目に異常が起こっていることにすぐ気づく。どうも目が見えなくなっているのだ。
原因はすぐわかった。
左目のコンタクトレンズが目薬ではがれて落ちてしまったのである。
いったい私は何をしているのだろう。
しかし先月に眼科で検査をした際(コンタクトレンズを購入する際は診断を受けなければならない)、新しいレンズが出ているので替えてみませんか、と係の人に薦められる。素材がシリコンで空気の通りが良いですよ、というような説明だった。けっこう多くの人もこのレンズに切り替えているという。
別に今のレンズで何も問題なかったけれど、より快適に過ごせるならば、と思い言われるがまま買ってしまった。1箱あたりにすると300円ほど従来に比べて値段が上がった。その場でためしに着けた時点では、以前のレンズよりも柔らかいけれど良い感じかな、というのが印象である。
だが、しばらく使用していたら具合がどうも良くない。別に目が充血するとかいった深刻な症状が出てはいないものの、いわゆる「目がゴロゴロする」と言われるような違和感がよく起きる。ちなみに両目が同時に悪いということはなく、昨日は右目かと思ったら今日は左目がイマイチ、とそんな感じだった。
「空気が通りやすい、というのは、乾燥しやすい、という意味なのか?」
などと思うこともあった。
そして今日も左目の調子が悪い。あまりにも苦しいため近所のドラッグストアで目薬を買ってみる。目の乾燥が原因と思ったからだ。
買ってすぐに左目に目薬を入れてみる。冷たいと感じてからすぐに目の違和感は消え去った。
「やはり乾燥が原因だったか、これからしばらく目薬が手放せないな」
と一瞬だけ思った。しかし、左目に異常が起こっていることにすぐ気づく。どうも目が見えなくなっているのだ。
原因はすぐわかった。
左目のコンタクトレンズが目薬ではがれて落ちてしまったのである。
いったい私は何をしているのだろう。
映画「ルー・リード/ベルリン」を観る
2009年4月9日 CD評など
京都市下京区の商業施設「COCON烏丸」(京都市下京区)3階にある「京都シネマ」にて、ルー・リードのライブを収めた映画「ルー・リード/ベルリン」が上映されると知り、仕事を終えた後で観に行った。会場はこじんまりした劇場で1日1回のみの上映である。この日のお客は私を含めて6人しかいない。あとで知ったことだが、今年の1月には既にこのDVDが発売されている。熱心なファンはすでにそれを買っているのかもしれない。
映画「ルー・リード/ベルリン」は、ルーのソロとしては3枚目のアルバム「ベルリン」(73年)を全曲演奏したライブの模様を題材にしたものである。ルー・リードの紹介は不要だと思うので割愛するけれど、アルバムについては私なりに内容をまとめておきたい。デヴィッド・ボウイとミック・ロンソンがプロデューサーした前作「トランスフォーマー」(72年)の中から“ワイルドサイドを歩け(Walk On The WildSide)”がヒットし(これは現在まで彼の最大ヒット曲となっている)、調子が上向きだった彼が次に組んだプロデューサーは、同時期にアリス・クーパーの「スクールズ・アウト」(72年)をヒットさせたばかりのボブ・エズリンだった。彼の代表作には「コンセプト・アルバム」の傑作と言われるピンク・フロイドの「ザ・ウォール」(79年)もあり、そうした演劇性の高い音作りが得意なようだ。
「コンセプト・アルバム」という言葉の定義はあまりはっきりしないけれど、全体を通して一貫した雰囲気やテーマが流れている作品、といえば良いだろうか。ロックならばビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」(66年)、ビーチ・ボーイズの「ペット・サウンズ」(66年)、そして前述したピンク・フロイドをはじめとする「プログレッシブ・ロック」と称されたバンドの作品が主なものといえる。
「ベルリン」はスティーヴ・ウィンウッドやジャック・ブルースなど名うてのミュージシャンをバックに、まだ東西を分断していたベルリン(壁が崩壊したのは89年)を舞台にした10曲で構成されている。この説明だけでもなんだかコンセプト・アルバムのように思えてくるけれど、ルー自身はそれを否定している。しかしながら、バックに子どもの泣き声やバースデイ・ソングのコーラスなど効果音を随所に挿入するなど、かなり劇的というか視覚化しやすくなることを狙った音作りになっているのは間違いない。ちなみにアルバムを作った時点でルーはベルリンに足を踏み入れていなかったという。よって、この物語は純粋に彼の想像をつなぎあわせて作った作品ともいえる。
本作を最高傑作に挙げる人も多いらしい。しかしアレンジがちょっと過剰ぎみなのが個人的にはいつも気になってしまう。私が最も好きなのはほぼ一発で録音された「ブルーマスク」(82年)である。おそらくあまり派手なアレンジは性に合わないのだろう。そういうわけで、けっこう前からアルバムは所持をしていたものの、たいして聴かずに現在まで至っている。
商業的に失敗したせいか、長い間ライブでも「ベルリン」の曲を演奏することがなかった。しかしこのアルバムを「人生のサウンド・トラック」とまで称しているジュリアン・シュナベール監督の全面バックアップにより、発売から33年経った06年12月のニューヨークにて「ベルリン」を全曲演奏するライブが5夜にわたって実現する。ルー・リード、64歳の冬であった。
特別なライブだけあって、編成も通常では考えられない大所帯となっている。通常のロック・バンドに加え、ストリングス、ホーン・セクション、そして女の子が10人くらいコーラスで参加しているのが目を引く。音楽プロデューサーにはボブ・エズリン、そしてルーの現時点での最新作「ザ・レイヴン」(03年)を手がけたハル・ウィルナーの2人が担当した。彼らが一丸となって「ベルリン」の世界を見事に演出している。
映画は基本的にライブの模様が中心であるけれど、随所に他の映像を交差させた作りになっている。ライブ中にもバックに色々な映像が流れており、それらが複雑に入り混じるという具合だ。しかしそれが見づらくなるわけではなく、絶妙なバランスで映画が成立しているのはシュナーベル監督の手腕とか言いようがない。「ベルリン」に対する彼の愛情が伝わってくる。
余談になるが、英語のわからない人間にとって字幕スーパーの対訳はとてもありがたかった。映像と同時に歌詞をたどることにより、1曲の内容がこれまで以上にわかりやすく伝わってくる。思った以上に退廃的な内容でやたらと「ドラッグ」という言葉が出てくるが気になったけれど、アルバムの雰囲気はよくつかめたと思っている。
しかし何よりもライブ自体が素晴らしい。過去にルー・リードのライブは2回観ているけれど、それよりも良いとまで感じるほどだった。実際で会場に展開されたステージも破格の内容だったに違いない。
良かったばかりでまとまりのない感想になってしまったけれど、私の心境をズバリ表した文章が映画のパンフレットに書いてあった。これを最後に示したい。
「コンサート映画を観て、曲が終わったところで立ち上がって
拍手をせずにはいられない気持ちになったとしたら、それはたぶん最良の作品の証といえるだろう。
私はルー・リードのそれほどのファンではないが、本作を観たとき、まさにそんな感情に駆られた。
CHUD.com」
実際にライブを体験したような、充実した1時間25分だった。
映画「ルー・リード/ベルリン」は、ルーのソロとしては3枚目のアルバム「ベルリン」(73年)を全曲演奏したライブの模様を題材にしたものである。ルー・リードの紹介は不要だと思うので割愛するけれど、アルバムについては私なりに内容をまとめておきたい。デヴィッド・ボウイとミック・ロンソンがプロデューサーした前作「トランスフォーマー」(72年)の中から“ワイルドサイドを歩け(Walk On The WildSide)”がヒットし(これは現在まで彼の最大ヒット曲となっている)、調子が上向きだった彼が次に組んだプロデューサーは、同時期にアリス・クーパーの「スクールズ・アウト」(72年)をヒットさせたばかりのボブ・エズリンだった。彼の代表作には「コンセプト・アルバム」の傑作と言われるピンク・フロイドの「ザ・ウォール」(79年)もあり、そうした演劇性の高い音作りが得意なようだ。
「コンセプト・アルバム」という言葉の定義はあまりはっきりしないけれど、全体を通して一貫した雰囲気やテーマが流れている作品、といえば良いだろうか。ロックならばビートルズの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」(66年)、ビーチ・ボーイズの「ペット・サウンズ」(66年)、そして前述したピンク・フロイドをはじめとする「プログレッシブ・ロック」と称されたバンドの作品が主なものといえる。
「ベルリン」はスティーヴ・ウィンウッドやジャック・ブルースなど名うてのミュージシャンをバックに、まだ東西を分断していたベルリン(壁が崩壊したのは89年)を舞台にした10曲で構成されている。この説明だけでもなんだかコンセプト・アルバムのように思えてくるけれど、ルー自身はそれを否定している。しかしながら、バックに子どもの泣き声やバースデイ・ソングのコーラスなど効果音を随所に挿入するなど、かなり劇的というか視覚化しやすくなることを狙った音作りになっているのは間違いない。ちなみにアルバムを作った時点でルーはベルリンに足を踏み入れていなかったという。よって、この物語は純粋に彼の想像をつなぎあわせて作った作品ともいえる。
本作を最高傑作に挙げる人も多いらしい。しかしアレンジがちょっと過剰ぎみなのが個人的にはいつも気になってしまう。私が最も好きなのはほぼ一発で録音された「ブルーマスク」(82年)である。おそらくあまり派手なアレンジは性に合わないのだろう。そういうわけで、けっこう前からアルバムは所持をしていたものの、たいして聴かずに現在まで至っている。
商業的に失敗したせいか、長い間ライブでも「ベルリン」の曲を演奏することがなかった。しかしこのアルバムを「人生のサウンド・トラック」とまで称しているジュリアン・シュナベール監督の全面バックアップにより、発売から33年経った06年12月のニューヨークにて「ベルリン」を全曲演奏するライブが5夜にわたって実現する。ルー・リード、64歳の冬であった。
特別なライブだけあって、編成も通常では考えられない大所帯となっている。通常のロック・バンドに加え、ストリングス、ホーン・セクション、そして女の子が10人くらいコーラスで参加しているのが目を引く。音楽プロデューサーにはボブ・エズリン、そしてルーの現時点での最新作「ザ・レイヴン」(03年)を手がけたハル・ウィルナーの2人が担当した。彼らが一丸となって「ベルリン」の世界を見事に演出している。
映画は基本的にライブの模様が中心であるけれど、随所に他の映像を交差させた作りになっている。ライブ中にもバックに色々な映像が流れており、それらが複雑に入り混じるという具合だ。しかしそれが見づらくなるわけではなく、絶妙なバランスで映画が成立しているのはシュナーベル監督の手腕とか言いようがない。「ベルリン」に対する彼の愛情が伝わってくる。
余談になるが、英語のわからない人間にとって字幕スーパーの対訳はとてもありがたかった。映像と同時に歌詞をたどることにより、1曲の内容がこれまで以上にわかりやすく伝わってくる。思った以上に退廃的な内容でやたらと「ドラッグ」という言葉が出てくるが気になったけれど、アルバムの雰囲気はよくつかめたと思っている。
しかし何よりもライブ自体が素晴らしい。過去にルー・リードのライブは2回観ているけれど、それよりも良いとまで感じるほどだった。実際で会場に展開されたステージも破格の内容だったに違いない。
良かったばかりでまとまりのない感想になってしまったけれど、私の心境をズバリ表した文章が映画のパンフレットに書いてあった。これを最後に示したい。
「コンサート映画を観て、曲が終わったところで立ち上がって
拍手をせずにはいられない気持ちになったとしたら、それはたぶん最良の作品の証といえるだろう。
私はルー・リードのそれほどのファンではないが、本作を観たとき、まさにそんな感情に駆られた。
CHUD.com」
実際にライブを体験したような、充実した1時間25分だった。
そんなこと俺に訊くな
2009年4月5日 日常今日は朝の9時から午後2時ごろまで、三条京阪の駅前で仕事をしていた。
駅前だけあって人が多い。また桜の季節ということもあり、いつも以上に観光客があふれている。道のわからない人もいっぱいいるようで、何度か話しかけられた。
「南禅寺はどっち?」
「平野神社へ行くバスはどこ?」
「琵琶湖疎水から船に乗りたいんだけど」
などである。しかし一番困ったのは、
「この辺にトーストとコーヒーの美味しいところはありませんか?」
というものであった。知るか、そんなもん。
それよりも、ずっと仕事をしてバタバタしている人間にこうやって道を訊いてくるのはなぜだろう。こちらは何一つ答えられないというのに
駅前だけあって人が多い。また桜の季節ということもあり、いつも以上に観光客があふれている。道のわからない人もいっぱいいるようで、何度か話しかけられた。
「南禅寺はどっち?」
「平野神社へ行くバスはどこ?」
「琵琶湖疎水から船に乗りたいんだけど」
などである。しかし一番困ったのは、
「この辺にトーストとコーヒーの美味しいところはありませんか?」
というものであった。知るか、そんなもん。
それよりも、ずっと仕事をしてバタバタしている人間にこうやって道を訊いてくるのはなぜだろう。こちらは何一つ答えられないというのに
「100円マック」成功の裏に
2009年4月3日 お仕事いつ終わりがくるのかわからない不況だが、そんな状況でも利益を出している会社はある。日本マクドナルドもその一つだ。2008年12月期の連結決算は売上高・最終利益ともに過去最高だったという(09年2月4日、日本マクドナルドホールディングスの発表より)
4月3日12時22分配信の「プレジデント」の記事に、「なぜ『100円マック』でも儲かるのか:マック式ファイナンス論」というのがあった。マクドナルドはいまから15年前の1994年、これまで210円だったハンバーガーを100円という低価格に値下げする。これによって販売数は20倍にも増えたのである。
100円に値下げしても儲かる仕組みをハンバーガー1個の「固定費」と「変動費」の内訳からこの記事は分析している。固定費を簡単に言うと、売上の増減に関係なく発生する決まった額の費用のことである。マクドナルドに即して考えると社員人件費(社員の給料など)や店舗賃借料(店の家賃)が代表的なものである。これらは、たとえ売上が0円になろうとも、必ず出てくる費用だ。
一方、売上に比例するのが「変動費」で、原材料費(パンや肉などの代金)が筆頭にあげられる。ハンバーガーの生産量、また原材料の価格変動によってこのあたりの金額は変わっていく。
そしてハンバーガーは固定費の割合が多くを占める商品である。これまでの210円バーガー1個にあてまめると、
人件費が40.7円(19.4%)
店舗賃借料が21円(10%)
となる。ここに他の経費を引くと営業利益は12.9円しか残らない。比率にすればわずか「6.1%」だ。商品の価格から考えるとかなり効率の悪い商品といえる。
そこで原田泳幸CEO(最高経営責任者)は固定費の削減を試みる。売り上げが増大すれば、1個あたりの固定費が下がり、結果として利益が拡大する。原田CEOが100円マックに踏み切ったのはその点だった。
結果として、100円バーガーになってからは1個あたり、
人件費が2.3円(2.3%)
店舗賃借料が1.2円(1.2%)
と固定費は大幅に圧縮される。それにともない、1個あたりの営業利益も34.7円と跳ね上がる。利益率にすれば「34.7%」だからとんでもない話だ。今回の急躍進も納得できる話である。
しかしながら、このマクドナルドのビジネス手法は手放しで絶賛できるものなのだろうか。100円マックに切り替えて売上が20倍になったということは、とりもなおさず現場作業も20倍にキツくなったことを意味する。値段を下げても利益を出すためには、従来の何倍も商品を売らなければならない。薄利多売とはそういうことだ。
翻って、過去最高益を出すような状態になって社員の待遇も大幅に良くなったかといえば、おそらくそんなことはないだろう。固定費の削減に目をつけた経営者がやすやすと人件費を増やすような真似はしまい。
消費者も経営者も得をしているように見える100円マックであるが、そのしわ寄せをくらっている人たちも確実に存在しているということか。
4月3日12時22分配信の「プレジデント」の記事に、「なぜ『100円マック』でも儲かるのか:マック式ファイナンス論」というのがあった。マクドナルドはいまから15年前の1994年、これまで210円だったハンバーガーを100円という低価格に値下げする。これによって販売数は20倍にも増えたのである。
100円に値下げしても儲かる仕組みをハンバーガー1個の「固定費」と「変動費」の内訳からこの記事は分析している。固定費を簡単に言うと、売上の増減に関係なく発生する決まった額の費用のことである。マクドナルドに即して考えると社員人件費(社員の給料など)や店舗賃借料(店の家賃)が代表的なものである。これらは、たとえ売上が0円になろうとも、必ず出てくる費用だ。
一方、売上に比例するのが「変動費」で、原材料費(パンや肉などの代金)が筆頭にあげられる。ハンバーガーの生産量、また原材料の価格変動によってこのあたりの金額は変わっていく。
そしてハンバーガーは固定費の割合が多くを占める商品である。これまでの210円バーガー1個にあてまめると、
人件費が40.7円(19.4%)
店舗賃借料が21円(10%)
となる。ここに他の経費を引くと営業利益は12.9円しか残らない。比率にすればわずか「6.1%」だ。商品の価格から考えるとかなり効率の悪い商品といえる。
そこで原田泳幸CEO(最高経営責任者)は固定費の削減を試みる。売り上げが増大すれば、1個あたりの固定費が下がり、結果として利益が拡大する。原田CEOが100円マックに踏み切ったのはその点だった。
結果として、100円バーガーになってからは1個あたり、
人件費が2.3円(2.3%)
店舗賃借料が1.2円(1.2%)
と固定費は大幅に圧縮される。それにともない、1個あたりの営業利益も34.7円と跳ね上がる。利益率にすれば「34.7%」だからとんでもない話だ。今回の急躍進も納得できる話である。
しかしながら、このマクドナルドのビジネス手法は手放しで絶賛できるものなのだろうか。100円マックに切り替えて売上が20倍になったということは、とりもなおさず現場作業も20倍にキツくなったことを意味する。値段を下げても利益を出すためには、従来の何倍も商品を売らなければならない。薄利多売とはそういうことだ。
翻って、過去最高益を出すような状態になって社員の待遇も大幅に良くなったかといえば、おそらくそんなことはないだろう。固定費の削減に目をつけた経営者がやすやすと人件費を増やすような真似はしまい。
消費者も経営者も得をしているように見える100円マックであるが、そのしわ寄せをくらっている人たちも確実に存在しているということか。
別に待っていたわけではないけれど、渡辺美里の野外ライブの日程がようやく発表された。日時は8月22日(土)午後5時開演で、会場はおととし(07年7月29日)と同じく横浜だ。会場名は「横浜赤レンガパーク特設会場」となっている。
ちなみに前回の横浜は会場名が「横浜みなとみらい・新港埠頭」だった。おそらく会場規模が縮小されておこなわれるのだろう。確信があるわけでもないけれど、2年前より動員が見込めるとは思えないからだ。
チケットもファンクラブの先行予約で申し込んだ。内容について多くは期待しない。しかし以前の横浜ライブでは珍しく神懸かりともいえる素晴らしい場面があったり、“Tokyo Calling”、“夏のカーブ”、“一瞬の夏”など貴重な曲も聴けたという嬉しい瞬間も立ち会えたのを覚えている。
ともかく会場には行く。私にとってはそれだけだ。
ちなみに前回の横浜は会場名が「横浜みなとみらい・新港埠頭」だった。おそらく会場規模が縮小されておこなわれるのだろう。確信があるわけでもないけれど、2年前より動員が見込めるとは思えないからだ。
チケットもファンクラブの先行予約で申し込んだ。内容について多くは期待しない。しかし以前の横浜ライブでは珍しく神懸かりともいえる素晴らしい場面があったり、“Tokyo Calling”、“夏のカーブ”、“一瞬の夏”など貴重な曲も聴けたという嬉しい瞬間も立ち会えたのを覚えている。
ともかく会場には行く。私にとってはそれだけだ。
西原理恵子「いけちゃんとぼく」(06年、角川書店)
2009年3月29日 読書
この6月に映画化される西原理恵子の「いけちゃんとぼく」(角川書店。06年)の原作絵本を読みたい。そこでアマゾンのサイトででも買おうかと思った矢先、職場の人の机の上に置いてあった。これはちょうど良いと本を借り、仕事が一息ついたからその場で読んでみる。絵本という形式のためページ数も少なく、すぐに「2回」読み通すことができた。
いま「2回」とわざわざ強調したのには理由がある。本の帯にある宣伝文にこんなことが書いてあるからだ。
<この本には大きな仕掛けがある。
2度読み返してほしい。
号泣必至です
横里隆(「ダ・ヴィンチ」編集長)
(「ダ・ヴィンチ」06年10月号より)>
テレビ番組「ザ・ベストハウス123」(フジテレビ系列)では「絶対泣ける本BEST3」の第1位にもなった「いけちゃんとぼく」であるが、ともかく「泣ける」というのが魅力の一つらしい。先日のブログではネットの情報を再構成したり映画との関連で紹介したけれど、その時は私も未読な状態だった。しかし今回は読んだ感想を含めてこの作品について書いてみたい。
物語はヨシオという少年と、不思議な生き物「いけちゃん」との交流を描いた絵本だ。他に登場人物もいるけれど、ほとんどの内容は二人(1人と1匹という表現が正確か?)のやり取りだ。
冒頭にはこんな文章が載っている。
<いけちゃんは
ずっとまえから
そばにいる。
いけちゃんは
なんとなく そばにいる
それから ときどきなぞだ。
それで
ぼくといけちゃんは
なかよしだ
ずっと。>
「いけちゃん」はヨシオがものごころのつくずっと前から彼の近くにいるようだ。ではその「いけちゃん」とは一体何なのだ?と知らない人は疑問が出てくるだろう。しかし「いけちゃん」を具体的に説明するのは非常に難しい。表紙の画像を見れば、なんだかかわいらしいオバケのようにも見える。
「いけちゃん」は困ったことがあると小さくなり、嬉しいことがあると数が増える。いつもヨシオのそばにいて、彼が困ったときや落ち込んだときはなぐさめてくれる。だが、女の子と仲良くしていると真っ赤になって怒り出す。ともかくヨシオのことが気がかりだ。そうしてヨシオが成長していき、ある時点で「いけちゃん」が姿を消す日がやってくる・・・。
なぜ「いけちゃん」はヨシオの前に現れたのだろうか。その理由は「いけちゃん」の正体が明らかになる最後で一応はわかる。しかしこれこそが物語の肝心な部分であり、また絵本のあらすじを提示したところで伝わるものはあまりに乏しいので書かないことにする。
「泣ける!泣ける!」という触れ込みだったものの、私としては特に涙するような箇所はなかった。絵本を持っていた人は既婚者で子どももいる女性だがその人も泣かなかったそうだ。しかしそんな私でも、「いけちゃん」がなぜヨシオの前に姿をあらわしたかを知った瞬間にはなんともいえない心境になっていたことは否定できない。
そして、「いけちゃん」が何者かを知ってから絵本を再び読み返してみると、「いけちゃん」のセリフがまた違った思いで受け止められるようになっている。だから「2回読み返してほしい」のである。2回目で泣いたと言う感想を書いた人をネットで何人か見かけた。それはこの「仕掛け」によるものだろう、と泣いてもいない私は想像するよりほかにない。
それにしても、かつて「ちくろ幼稚園」(91-95年。小学館。全3巻)などでは子どもの嫌らしさや残酷さを描いてきた西原であるが、この作品における子どもを見つめる視線はずいぶん違っている。このような絵本を描けたのは、やはり作者自身が子どもを持つなど心境に大きな変化があったためだろう。初期の作品ばかりを知っている私はそのような感想を持った次第である。
いま「2回」とわざわざ強調したのには理由がある。本の帯にある宣伝文にこんなことが書いてあるからだ。
<この本には大きな仕掛けがある。
2度読み返してほしい。
号泣必至です
横里隆(「ダ・ヴィンチ」編集長)
(「ダ・ヴィンチ」06年10月号より)>
テレビ番組「ザ・ベストハウス123」(フジテレビ系列)では「絶対泣ける本BEST3」の第1位にもなった「いけちゃんとぼく」であるが、ともかく「泣ける」というのが魅力の一つらしい。先日のブログではネットの情報を再構成したり映画との関連で紹介したけれど、その時は私も未読な状態だった。しかし今回は読んだ感想を含めてこの作品について書いてみたい。
物語はヨシオという少年と、不思議な生き物「いけちゃん」との交流を描いた絵本だ。他に登場人物もいるけれど、ほとんどの内容は二人(1人と1匹という表現が正確か?)のやり取りだ。
冒頭にはこんな文章が載っている。
<いけちゃんは
ずっとまえから
そばにいる。
いけちゃんは
なんとなく そばにいる
それから ときどきなぞだ。
それで
ぼくといけちゃんは
なかよしだ
ずっと。>
「いけちゃん」はヨシオがものごころのつくずっと前から彼の近くにいるようだ。ではその「いけちゃん」とは一体何なのだ?と知らない人は疑問が出てくるだろう。しかし「いけちゃん」を具体的に説明するのは非常に難しい。表紙の画像を見れば、なんだかかわいらしいオバケのようにも見える。
「いけちゃん」は困ったことがあると小さくなり、嬉しいことがあると数が増える。いつもヨシオのそばにいて、彼が困ったときや落ち込んだときはなぐさめてくれる。だが、女の子と仲良くしていると真っ赤になって怒り出す。ともかくヨシオのことが気がかりだ。そうしてヨシオが成長していき、ある時点で「いけちゃん」が姿を消す日がやってくる・・・。
なぜ「いけちゃん」はヨシオの前に現れたのだろうか。その理由は「いけちゃん」の正体が明らかになる最後で一応はわかる。しかしこれこそが物語の肝心な部分であり、また絵本のあらすじを提示したところで伝わるものはあまりに乏しいので書かないことにする。
「泣ける!泣ける!」という触れ込みだったものの、私としては特に涙するような箇所はなかった。絵本を持っていた人は既婚者で子どももいる女性だがその人も泣かなかったそうだ。しかしそんな私でも、「いけちゃん」がなぜヨシオの前に姿をあらわしたかを知った瞬間にはなんともいえない心境になっていたことは否定できない。
そして、「いけちゃん」が何者かを知ってから絵本を再び読み返してみると、「いけちゃん」のセリフがまた違った思いで受け止められるようになっている。だから「2回読み返してほしい」のである。2回目で泣いたと言う感想を書いた人をネットで何人か見かけた。それはこの「仕掛け」によるものだろう、と泣いてもいない私は想像するよりほかにない。
それにしても、かつて「ちくろ幼稚園」(91-95年。小学館。全3巻)などでは子どもの嫌らしさや残酷さを描いてきた西原であるが、この作品における子どもを見つめる視線はずいぶん違っている。このような絵本を描けたのは、やはり作者自身が子どもを持つなど心境に大きな変化があったためだろう。初期の作品ばかりを知っている私はそのような感想を持った次第である。
FA制度は公務員に馴染むのか
2009年3月27日 地域情報京都市はこれまで管理職を対象にしてきた人事制度を全職員に拡大するなど「能力主義」を徹底するという。3月27日付の京都新聞に掲載されていた。それにともない年功重視の給与体系の見直し、希望の職場へ異動することのできるFA(フリー・エージェント)制度なども導入する。
京都市の人事課は
<組織内の「悪平等」を改め、職員がやりがいをもち働ける環境を整え、市民サービスを高めたい。>
と言っている。
このご時勢にまだ能力主義とは、つくづくお役所の動きは鈍いと思う。「悪平等」だの「やりがい」だのと言った惹句は、もう私たちはさんざん聞き飽きた言葉である。民間企業がさんざん試みて山のように積み重なった失敗例を知らないのだろうか。京都市民の一人として情けなくて仕方ない。
能力主義や成果主義などはいままでに色々とここで書いてきたので、それ以外に気になったことを今回は書きたい。
それは「FA制度」についてである。ネットで調べてみたら、「日本の人事部」(http://jinjibu.jp/)というサイトにぶちあたった。「社内FA制度」という言葉があり、
「社員が自らのキャリアやスキルを売り込み、希望する職種や職務を登録する」制度と説明がされていた。
また、
「社内公募制度や社内FA制度を導入することで、社員が職場や仕事の内容を選択できる環境が生まれ、社員のモチベーションを喚起する効果があると言われています。」
とも書いてある。能力主義や成果主義などとあわせて企業に広まった制度であることは間違いなさそうだ。
FA制度そのものの有効性や妥当性はここでは問わない。私が問題にしたいのは、公務員が自分の意志で職場や仕事の内容を選んでも良いのか、ということである。
やや硬い話になるけれど、日本国憲法の中で公務員についての規定をしている第15条の2項では、
<すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。>
と書かれている。
個人が自分の能力や特性を活かせる職場でバリバリ仕事をする、という姿そのものが美しいには違いない。しかし「全体の奉仕者」である公務員がそのような働き方をするというのは何となくそぐわない気がする。
内田樹(神戸女学院大学教授)さんが指摘するように、「労働」とは「国民の義務」であって断じて「権利」ではない。もともと「選り好み」などできない性質のものである。黙って働きなさいというのが内田さんの意見だが、公務員という立場だったらなおさらではないだろうか。私は別に公務員に対して悪意や不満はそれほど持っていないけれど、今回の能力重視うんぬんの件は京都市をおかしな方向に持っていくような気がしてならない。
京都市の人事課は
<組織内の「悪平等」を改め、職員がやりがいをもち働ける環境を整え、市民サービスを高めたい。>
と言っている。
このご時勢にまだ能力主義とは、つくづくお役所の動きは鈍いと思う。「悪平等」だの「やりがい」だのと言った惹句は、もう私たちはさんざん聞き飽きた言葉である。民間企業がさんざん試みて山のように積み重なった失敗例を知らないのだろうか。京都市民の一人として情けなくて仕方ない。
能力主義や成果主義などはいままでに色々とここで書いてきたので、それ以外に気になったことを今回は書きたい。
それは「FA制度」についてである。ネットで調べてみたら、「日本の人事部」(http://jinjibu.jp/)というサイトにぶちあたった。「社内FA制度」という言葉があり、
「社員が自らのキャリアやスキルを売り込み、希望する職種や職務を登録する」制度と説明がされていた。
また、
「社内公募制度や社内FA制度を導入することで、社員が職場や仕事の内容を選択できる環境が生まれ、社員のモチベーションを喚起する効果があると言われています。」
とも書いてある。能力主義や成果主義などとあわせて企業に広まった制度であることは間違いなさそうだ。
FA制度そのものの有効性や妥当性はここでは問わない。私が問題にしたいのは、公務員が自分の意志で職場や仕事の内容を選んでも良いのか、ということである。
やや硬い話になるけれど、日本国憲法の中で公務員についての規定をしている第15条の2項では、
<すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。>
と書かれている。
個人が自分の能力や特性を活かせる職場でバリバリ仕事をする、という姿そのものが美しいには違いない。しかし「全体の奉仕者」である公務員がそのような働き方をするというのは何となくそぐわない気がする。
内田樹(神戸女学院大学教授)さんが指摘するように、「労働」とは「国民の義務」であって断じて「権利」ではない。もともと「選り好み」などできない性質のものである。黙って働きなさいというのが内田さんの意見だが、公務員という立場だったらなおさらではないだろうか。私は別に公務員に対して悪意や不満はそれほど持っていないけれど、今回の能力重視うんぬんの件は京都市をおかしな方向に持っていくような気がしてならない。
パソコンと携帯のタイムラグ
2009年3月24日 日常WBC決勝が真っ最中の午後1時半ごろ、私は某ラーメン店にいた。店のご主人も奥さんも試合の結末を気にしていたが店にはテレビが置いてない。そこで私は携帯でニュース速報を追いかけることにした。
しかし、である。私の携帯機種はauだが、ニュースが見られる「EZニュースフラッシュ」に接続しても、韓国が同点に追いついた5回裏の時点から更新されていない。その時はもう午後1時50分くらいで、実際はもう9回に突入していただろう。
そこでパソコン向けのサイトが見られる「PCサイトビューアー」に切り替えて、Yahoo!のニュースで見る。そうしてやっと9回裏で再び同点になったことがわかった。そのYahoo!ニュースもアクセスが殺到していて、リアルタイムで結果を確認することはできなかったが。
しばらく時間がかかると思い、同点に追いつかれたことをお店に告げて外を出る。部屋に帰る頃には日本が勝利していた。
それにしても、携帯のニュースはなかなか更新されないということを気づかされた出来事である。
しかし、である。私の携帯機種はauだが、ニュースが見られる「EZニュースフラッシュ」に接続しても、韓国が同点に追いついた5回裏の時点から更新されていない。その時はもう午後1時50分くらいで、実際はもう9回に突入していただろう。
そこでパソコン向けのサイトが見られる「PCサイトビューアー」に切り替えて、Yahoo!のニュースで見る。そうしてやっと9回裏で再び同点になったことがわかった。そのYahoo!ニュースもアクセスが殺到していて、リアルタイムで結果を確認することはできなかったが。
しばらく時間がかかると思い、同点に追いつかれたことをお店に告げて外を出る。部屋に帰る頃には日本が勝利していた。
それにしても、携帯のニュースはなかなか更新されないということを気づかされた出来事である。
今日の午前6時50分、成田空港で起きた貨物航空機の事故は衝撃的な映像だった。真っ二つに裂け黒焦げになった機体は無惨だったし、乗員2人も亡くなってしまう。また成田空港における航空機の死亡事故は開港した1978年以来はじめてのことだという。かなり深刻な事故だとテレビを見た瞬間に感じる。
しかしながら、この日のマスコミはそれほどこの事件に大きな関心をもっていたように思えない。WBCのアメリカ戦、陣内智則と藤原紀香の離婚届提出の方が扱いが大きかった。
亡くなった2人の方への哀悼の声も聞こえない。たとえば3月23日13時6分配信の時事通信の記事はこうだ。
<米貨物航空会社フェデックスは23日正午ごろ、氏家正道北太平洋地区担当副社長が成田空港内で会見を開いたが、「状況の詳細をまだ把握できていない」と繰り返し、約10分で打ち切られた。謝罪の言葉を求められても、「現時点では調査中で申し上げられない。情報が入り次第、会見を開いてお知らせする」と話した。>
謝罪うんぬんよりも亡くなった方に哀悼の意を述べるのがまず最初ではないか。麻生総理ほか官邸からもそのような発言は聞こえてこない。
フェデックス社にしても、
「事故により従業員が巻き込まれ、悲しい日となった。」(3月23日18時3分配信の時事通信より)
と、その後の会見では述べているものの少し遅い気がする。なんだかどこもかしこも冷淡な対応だ。
嫌なことを言ってしまうけれど、亡くなった方に日本人が含まれていたらこの程度の扱いでは済まなかったのではないだろうか。
しかしながら、この日のマスコミはそれほどこの事件に大きな関心をもっていたように思えない。WBCのアメリカ戦、陣内智則と藤原紀香の離婚届提出の方が扱いが大きかった。
亡くなった2人の方への哀悼の声も聞こえない。たとえば3月23日13時6分配信の時事通信の記事はこうだ。
<米貨物航空会社フェデックスは23日正午ごろ、氏家正道北太平洋地区担当副社長が成田空港内で会見を開いたが、「状況の詳細をまだ把握できていない」と繰り返し、約10分で打ち切られた。謝罪の言葉を求められても、「現時点では調査中で申し上げられない。情報が入り次第、会見を開いてお知らせする」と話した。>
謝罪うんぬんよりも亡くなった方に哀悼の意を述べるのがまず最初ではないか。麻生総理ほか官邸からもそのような発言は聞こえてこない。
フェデックス社にしても、
「事故により従業員が巻き込まれ、悲しい日となった。」(3月23日18時3分配信の時事通信より)
と、その後の会見では述べているものの少し遅い気がする。なんだかどこもかしこも冷淡な対応だ。
嫌なことを言ってしまうけれど、亡くなった方に日本人が含まれていたらこの程度の扱いでは済まなかったのではないだろうか。
映画「いけちゃんとぼく」の主題歌に
2009年3月22日 渡辺美里
久しぶりに渡辺美里の公式サイトを覗いてみると、初夏に発売予定の新曲“あしたの空”が6月公開の映画「いけちゃんとぼく」の主題歌になるというニュースを見つけた。
実はここ最近、彼女の曲はけっこう映画主題歌に使われている。しかし、「ハンサムスーツ」(08年)は“My Revolution”(86年)、「悲しいボーイフレンド」(09年)は“悲しいボーイフレンド”(85年)と、取り上げられるのは大昔の曲ばかりであった。作品の質やセールスは80年代が最も良かったので仕方ない部分もあるかもしれない。一方、今回は新曲が起用されたのは大きな違いである。
それにしても、映画の原作が西原理恵子の絵本「いけちゃんとぼく」(06年。角川書店)だと知った時は、
「へえ。意外な組み合わせだな」
というのが率直な感想だった。
漫画全般についてほとんど知識はないけれど、浪人時代(95年)に読んだ「恨ミシュラン」(93-95年。朝日新聞社。全3巻。神足裕司との共著)をきっかけに彼女の作品を追いかけた時期はある。「まあじゃんほうろうき」(90-94年。竹書房。全4巻)、「ちくろ幼稚園」(91-95年。小学館。全3巻)、「ゆんぼくん」(90-97年。竹書房。全5巻)といった漫画から、「サイバラ式」(00年。角川書店)のようなエッセイ入りのものまでけっこう幅広くカバーしていた。絵はわりとかわいい雰囲気だけれど、そこに描かれている世界は社会の底辺といった感じの人ばかりで、かなり毒を含んだ作風だ。その組み合わせに惹かれていったのだと思う。そして、渡辺美里とは対極の位置にいる人ではないだろうか。それゆえ今回の組み合わせに驚いたのである。
ある時期から彼女の作品をあまり読まなくなった。それは第43回文藝春秋漫画賞を受賞した「ぼくんち」(96-98年。小学館。全3巻)が完結した98年あたりだったか。明確な理由はないけれど、多作な作家のため作品を追いかけるのに疲れたのだと今となっては思う。また、たまに立ち読みで本を手にしてみても彼女は絵のタッチがかなり荒れていて、読みづらく感じ敬遠していたこともあった。
最近の彼女についても「毎日かあさん」(毎日新聞で連載中)など家族とか子育てとか私には興味が湧かないテーマに比重が置かれているようで、彼女の作品に向かい合うには悪い条件が重なりすぎている。振り返ってみれば、10年くらい読んでいないことになるか。
前置きは長くなったが、肝心の「いけちゃんとぼく」である。しかし、いろいろネットで調べてみても中身がいまいち把握できない。
公式サイトで書いてある「STORY」にはこう書いてある。
映画の公式サイトはこちら。
http://www.ikeboku.jp/
<“いけちゃん”は不思議ないきもの。
いつの頃からかいつもヨシオのそばにいる。ヨシオにしか見えないし、色も形も変幻自在。
お父さんが死んだときも、いじめられたときも、いつも一緒にいてくれた。
だが、ヨシオが成長するにつれ、その姿はだんだん見えなくなっていき、とうとう最後の日にいけちゃんはヨシオにあることを打ち明ける。
それはあまりにも切ない告白だった・・・。>
漫画については、ここで中身の一部を確認することができる。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refISBN=9784048540537
http://www.kadokawa.co.jp/sp/200608-05/
3月11日におこなわれたマスコミ披露試写会で西原本人は、
「この映画は息子の落書きから生まれたいけちゃんと、
私が好きだった何人かの男の人の切ない思春期の話を覚えていて、
息子がちょうど傷つきやすい少年の時期を迎えた時に、
その話が蘇ってきたときに出来た話です。」
と説明している。
テレビ番組「ザ・ベストハウス123」(フジテレビ系列)では、「絶対に泣ける本 第1位」に選ばれたこともある。そんな断片的な情報をつなぎあわせると、なんとなく漫画の雰囲気はつかめてきたような気がする。
映画を観るかどうかは、まだ決めていない。ただ、原作は手に取ってみようかという気持ちに今はなっているところだ。
実はここ最近、彼女の曲はけっこう映画主題歌に使われている。しかし、「ハンサムスーツ」(08年)は“My Revolution”(86年)、「悲しいボーイフレンド」(09年)は“悲しいボーイフレンド”(85年)と、取り上げられるのは大昔の曲ばかりであった。作品の質やセールスは80年代が最も良かったので仕方ない部分もあるかもしれない。一方、今回は新曲が起用されたのは大きな違いである。
それにしても、映画の原作が西原理恵子の絵本「いけちゃんとぼく」(06年。角川書店)だと知った時は、
「へえ。意外な組み合わせだな」
というのが率直な感想だった。
漫画全般についてほとんど知識はないけれど、浪人時代(95年)に読んだ「恨ミシュラン」(93-95年。朝日新聞社。全3巻。神足裕司との共著)をきっかけに彼女の作品を追いかけた時期はある。「まあじゃんほうろうき」(90-94年。竹書房。全4巻)、「ちくろ幼稚園」(91-95年。小学館。全3巻)、「ゆんぼくん」(90-97年。竹書房。全5巻)といった漫画から、「サイバラ式」(00年。角川書店)のようなエッセイ入りのものまでけっこう幅広くカバーしていた。絵はわりとかわいい雰囲気だけれど、そこに描かれている世界は社会の底辺といった感じの人ばかりで、かなり毒を含んだ作風だ。その組み合わせに惹かれていったのだと思う。そして、渡辺美里とは対極の位置にいる人ではないだろうか。それゆえ今回の組み合わせに驚いたのである。
ある時期から彼女の作品をあまり読まなくなった。それは第43回文藝春秋漫画賞を受賞した「ぼくんち」(96-98年。小学館。全3巻)が完結した98年あたりだったか。明確な理由はないけれど、多作な作家のため作品を追いかけるのに疲れたのだと今となっては思う。また、たまに立ち読みで本を手にしてみても彼女は絵のタッチがかなり荒れていて、読みづらく感じ敬遠していたこともあった。
最近の彼女についても「毎日かあさん」(毎日新聞で連載中)など家族とか子育てとか私には興味が湧かないテーマに比重が置かれているようで、彼女の作品に向かい合うには悪い条件が重なりすぎている。振り返ってみれば、10年くらい読んでいないことになるか。
前置きは長くなったが、肝心の「いけちゃんとぼく」である。しかし、いろいろネットで調べてみても中身がいまいち把握できない。
公式サイトで書いてある「STORY」にはこう書いてある。
映画の公式サイトはこちら。
http://www.ikeboku.jp/
<“いけちゃん”は不思議ないきもの。
いつの頃からかいつもヨシオのそばにいる。ヨシオにしか見えないし、色も形も変幻自在。
お父さんが死んだときも、いじめられたときも、いつも一緒にいてくれた。
だが、ヨシオが成長するにつれ、その姿はだんだん見えなくなっていき、とうとう最後の日にいけちゃんはヨシオにあることを打ち明ける。
それはあまりにも切ない告白だった・・・。>
漫画については、ここで中身の一部を確認することができる。
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refISBN=9784048540537
http://www.kadokawa.co.jp/sp/200608-05/
3月11日におこなわれたマスコミ披露試写会で西原本人は、
「この映画は息子の落書きから生まれたいけちゃんと、
私が好きだった何人かの男の人の切ない思春期の話を覚えていて、
息子がちょうど傷つきやすい少年の時期を迎えた時に、
その話が蘇ってきたときに出来た話です。」
と説明している。
テレビ番組「ザ・ベストハウス123」(フジテレビ系列)では、「絶対に泣ける本 第1位」に選ばれたこともある。そんな断片的な情報をつなぎあわせると、なんとなく漫画の雰囲気はつかめてきたような気がする。
映画を観るかどうかは、まだ決めていない。ただ、原作は手に取ってみようかという気持ちに今はなっているところだ。
今年度の正社員採用がゼロという企業が45.9%にものぼる。企業調査をしている帝国データバンクが3月4日に発表した調査結果は、企業の半分近くが正社員を採らないというのだからかなり深刻な話である。
採用を増やすと回答した企業も11.2%はあった。しかし派遣社員を始めとする非正規雇用の削減がある程度進み、今度は正社員の解雇が始まっている。景気が回復しない限り、社会全体でこのような正社員の減少を食い止めることはできないだろう。
しかしながら、こうした社員削減の影響は将来的に企業に跳ね返ってくるのは間違いない。派遣社員や契約社員やアルバイトがいなくなり、さらに正社員がいなくなったら会社というのは存続するのだろうか。経営者だけでやっていけるのか。その時は日本から「会社」そのものが消えるのだろう。
極端な話をしたけれど、そういう日が訪れないともいえない気がしてくる今日このごろである。
採用を増やすと回答した企業も11.2%はあった。しかし派遣社員を始めとする非正規雇用の削減がある程度進み、今度は正社員の解雇が始まっている。景気が回復しない限り、社会全体でこのような正社員の減少を食い止めることはできないだろう。
しかしながら、こうした社員削減の影響は将来的に企業に跳ね返ってくるのは間違いない。派遣社員や契約社員やアルバイトがいなくなり、さらに正社員がいなくなったら会社というのは存続するのだろうか。経営者だけでやっていけるのか。その時は日本から「会社」そのものが消えるのだろう。
極端な話をしたけれど、そういう日が訪れないともいえない気がしてくる今日このごろである。
給料が増えないのなら、せめて
2009年3月4日 お仕事景気については深刻なニュースが絶えないため、賃金や労働について色々と考えることが多い。
そんな時、内田樹(神戸女学院大学教授)さんの著書「街場の教育論」(08年。ミシマ社)を読んでいると興味深い箇所を見つけた。内田さんは大学にアクレディテーション(accreditation、信用供与)を導入することに積極的だった時がある。
アクレディテーションを平たく説明すると、大学を「まともな大学」と証明する第三者評価である。規制緩和の影響で大学が乱立し、「まともでない大学」が増えてきたのと同時期に出てきた制度だ。アクレディテーションを受けたところは「まともな大学」であると認定されるわけだ。
内田さんは当初アクレディテーションについて、「大学の研究教育活動から財務内容まで、包括的に点検する機会があるのは、問題発見の上でたいへん有用ではないか」(同書、P.78)、と思っていた。しかし、「今にして思えば、まことに軽率だった」(同書、P.78)と振り返っている。それはなぜか。長い引用になるが、「評価」という行為がどれほど困難をともなう作業なのかを実にわかりやすく書いているのでぜひ読んでいただきたい。
<私はそのとき「評価にかかるコスト」をほとんどゼロ査定していたからです。
評価には簡単なものと、手間のかかるものがあります。「欠陥品」を選び出すのは簡単です。「欠陥がないもの」を選び出すのは簡単ではありません。というか、論理的には不可能なんです。
(中略)
アクレディテーションという作業がやろうとしているのはそのようなことです。
「この大学はまともではない」ということを証明するのは簡単です。何か「まともじゃない」証拠を一つ発見すればいい。専任教員がいないとか、成績評価がデタラメであるとか、使途不明金があるとか、校地が活断層の真上にあるとか、どれでも「まともでない」ことを立証するには十分です。
(中略)
でも、この世に存在するのは「まともでないことを示す指標」だけです。「まとも」であることを示す実定的な指標というものは存在しません。ですから、アクレディテーションは論理的には「まともでないことを示すすべての指標を否定する」という絶対に終わりの来ない作業を意味することになります。
考えてもみてください。私たちがふだん市民として自由に街を歩き回っていられるのは、私たちが「まともな市民である」ことを証明できているからではありません。「まともな市民ではない」ことの証拠が示されていないからです。「推定無罪」の原理に基づいて私たちは市民権を行使できているのです。
アクレディテーションは逆に「推定有罪」の原理を採用します。その上で、「潔白であることを挙証せよ」と言っている。この要請に応えることは、理論的にも、実践的にも、不可能です。無罪である証拠をどれだけ積み上げても、有罪の証拠が一つ出れば、すべてが覆される。だから、「推定有罪」の上で潔白を挙証する作業には、「これで終わり」ということがありません。挙証作業はエンドレスのものになります。>(同書、P.78-80)
このアクレディテーションをめぐる話は、企業の人事や給与をめぐる評価と通じるものがあるのではないだろうか。日本もある時期から能力主義だの成果主義だのといった言葉とともに評価活動が急速に導入された。職場を活性化させるため、または単なる賃金切り下げのためなど、企業には色々と目的はあっただろう。しかし、それによって我々は何を得たのだろう。
大半の労働者は賃金が下がってしまった。そして自身の評価についても明確な指針は与えられず会社に対する不信が高まる。また職場の同僚どうしでも、たかだが数千円の給料の差でいがみ合う・・・。どこかの企業では、成果主義を導入してから先輩が後輩に仕事を教えなくなったという。自分より仕事ができるようになったら立場が悪くなるからだという理由らしいが、そういう事態もあった。
もちろん、不利益をこうむるのは労働者ばかりではない。企業にとっては、「人件費の削減」だけを絞れば大きな成果はあったに違いない。しかしその一方で、職場の士気が下がり企業の生産性も大きく落ち込んだとしたらどうだろう。また、人事評価を担当する人たちは、いい加減なことをしている企業が大半だろうが、真面目に取り組めば取り組むほど徒労感は大きくなるばかりの作業だ。
内田さんもこう書いている。
<私は大学の自己評価委員長を四年やって、文科省や大学基準協会に出すための
「うちの大学はまっとうである」ということを挙証するための文書を山のように書きました。だから、この作業が「終わりなき地獄」であることを全身の筋肉のきしみと、澱(おり)のようにたまった疲れに基づいて確信することができます。>(同書、P.80)
私は成果主義・能力主義をほとんど否定しているけれど、「いまこそ年功序列や終身雇用の復活を!」などと時代錯誤な表明をするつもりも全くない(サラリーマンの立場からいえばそれが最高ではあるが)。企業の存続自体が危ういこの経済状況でベースアップなどと言っている労働組合など倒錯していると思っているくらいだ。無いものを無理やり出せとまでは言えない。
ただ、給料が上がらないならば、せめて能力主義とか成果給といった人事評価をめぐる制度を見直してもらいたいとは思っている。さきほど触れた通り、現在主流の賃金制度は労使ともに問題が大きすぎる。いっそのこと撤廃したら良いのではないか。そのくらいまで思っている。
では、代わりにどうすれば良いか。例えば「初任給の年収が400万円」と一律に決めてしまうのである。そして入社から退社までずっと金額は変わらない。ただし、昇進などの場合は賃金が上がる余地を残す。私のイメージはそういうものだ。
「賃金を一律にしたら社員のモチベーションが上がらなくなる!」と常套的な批判をする方もいるだろう。しかし、不明瞭な能力評価に振り回されたり、上がる見込みもない成果給に幻想を抱くよりはよっぽどマシである。労働者にとっても収入が明確になっていれば人生設計も立てやすいし、安心して働くことができる。少なくとも能力主義うんぬんを行使して会社全体が疲弊することに比べたらずっと良い。
ともかく経営者も労働者も、「金のみが仕事のモチベーションを高める要素」だと思っている人が多すぎる。鼻先に人参をぶら下げられた馬のような単純なシステムで動くほど人間は簡単なものではない。そういうことを見直せる人がもう出てきても良いのではないかと期待しているのだが、そんな気配は全くなさそうである。
そんな時、内田樹(神戸女学院大学教授)さんの著書「街場の教育論」(08年。ミシマ社)を読んでいると興味深い箇所を見つけた。内田さんは大学にアクレディテーション(accreditation、信用供与)を導入することに積極的だった時がある。
アクレディテーションを平たく説明すると、大学を「まともな大学」と証明する第三者評価である。規制緩和の影響で大学が乱立し、「まともでない大学」が増えてきたのと同時期に出てきた制度だ。アクレディテーションを受けたところは「まともな大学」であると認定されるわけだ。
内田さんは当初アクレディテーションについて、「大学の研究教育活動から財務内容まで、包括的に点検する機会があるのは、問題発見の上でたいへん有用ではないか」(同書、P.78)、と思っていた。しかし、「今にして思えば、まことに軽率だった」(同書、P.78)と振り返っている。それはなぜか。長い引用になるが、「評価」という行為がどれほど困難をともなう作業なのかを実にわかりやすく書いているのでぜひ読んでいただきたい。
<私はそのとき「評価にかかるコスト」をほとんどゼロ査定していたからです。
評価には簡単なものと、手間のかかるものがあります。「欠陥品」を選び出すのは簡単です。「欠陥がないもの」を選び出すのは簡単ではありません。というか、論理的には不可能なんです。
(中略)
アクレディテーションという作業がやろうとしているのはそのようなことです。
「この大学はまともではない」ということを証明するのは簡単です。何か「まともじゃない」証拠を一つ発見すればいい。専任教員がいないとか、成績評価がデタラメであるとか、使途不明金があるとか、校地が活断層の真上にあるとか、どれでも「まともでない」ことを立証するには十分です。
(中略)
でも、この世に存在するのは「まともでないことを示す指標」だけです。「まとも」であることを示す実定的な指標というものは存在しません。ですから、アクレディテーションは論理的には「まともでないことを示すすべての指標を否定する」という絶対に終わりの来ない作業を意味することになります。
考えてもみてください。私たちがふだん市民として自由に街を歩き回っていられるのは、私たちが「まともな市民である」ことを証明できているからではありません。「まともな市民ではない」ことの証拠が示されていないからです。「推定無罪」の原理に基づいて私たちは市民権を行使できているのです。
アクレディテーションは逆に「推定有罪」の原理を採用します。その上で、「潔白であることを挙証せよ」と言っている。この要請に応えることは、理論的にも、実践的にも、不可能です。無罪である証拠をどれだけ積み上げても、有罪の証拠が一つ出れば、すべてが覆される。だから、「推定有罪」の上で潔白を挙証する作業には、「これで終わり」ということがありません。挙証作業はエンドレスのものになります。>(同書、P.78-80)
このアクレディテーションをめぐる話は、企業の人事や給与をめぐる評価と通じるものがあるのではないだろうか。日本もある時期から能力主義だの成果主義だのといった言葉とともに評価活動が急速に導入された。職場を活性化させるため、または単なる賃金切り下げのためなど、企業には色々と目的はあっただろう。しかし、それによって我々は何を得たのだろう。
大半の労働者は賃金が下がってしまった。そして自身の評価についても明確な指針は与えられず会社に対する不信が高まる。また職場の同僚どうしでも、たかだが数千円の給料の差でいがみ合う・・・。どこかの企業では、成果主義を導入してから先輩が後輩に仕事を教えなくなったという。自分より仕事ができるようになったら立場が悪くなるからだという理由らしいが、そういう事態もあった。
もちろん、不利益をこうむるのは労働者ばかりではない。企業にとっては、「人件費の削減」だけを絞れば大きな成果はあったに違いない。しかしその一方で、職場の士気が下がり企業の生産性も大きく落ち込んだとしたらどうだろう。また、人事評価を担当する人たちは、いい加減なことをしている企業が大半だろうが、真面目に取り組めば取り組むほど徒労感は大きくなるばかりの作業だ。
内田さんもこう書いている。
<私は大学の自己評価委員長を四年やって、文科省や大学基準協会に出すための
「うちの大学はまっとうである」ということを挙証するための文書を山のように書きました。だから、この作業が「終わりなき地獄」であることを全身の筋肉のきしみと、澱(おり)のようにたまった疲れに基づいて確信することができます。>(同書、P.80)
私は成果主義・能力主義をほとんど否定しているけれど、「いまこそ年功序列や終身雇用の復活を!」などと時代錯誤な表明をするつもりも全くない(サラリーマンの立場からいえばそれが最高ではあるが)。企業の存続自体が危ういこの経済状況でベースアップなどと言っている労働組合など倒錯していると思っているくらいだ。無いものを無理やり出せとまでは言えない。
ただ、給料が上がらないならば、せめて能力主義とか成果給といった人事評価をめぐる制度を見直してもらいたいとは思っている。さきほど触れた通り、現在主流の賃金制度は労使ともに問題が大きすぎる。いっそのこと撤廃したら良いのではないか。そのくらいまで思っている。
では、代わりにどうすれば良いか。例えば「初任給の年収が400万円」と一律に決めてしまうのである。そして入社から退社までずっと金額は変わらない。ただし、昇進などの場合は賃金が上がる余地を残す。私のイメージはそういうものだ。
「賃金を一律にしたら社員のモチベーションが上がらなくなる!」と常套的な批判をする方もいるだろう。しかし、不明瞭な能力評価に振り回されたり、上がる見込みもない成果給に幻想を抱くよりはよっぽどマシである。労働者にとっても収入が明確になっていれば人生設計も立てやすいし、安心して働くことができる。少なくとも能力主義うんぬんを行使して会社全体が疲弊することに比べたらずっと良い。
ともかく経営者も労働者も、「金のみが仕事のモチベーションを高める要素」だと思っている人が多すぎる。鼻先に人参をぶら下げられた馬のような単純なシステムで動くほど人間は簡単なものではない。そういうことを見直せる人がもう出てきても良いのではないかと期待しているのだが、そんな気配は全くなさそうである。
高校生のほぼ全員が携帯を持つ現代で
2009年2月26日 日常文部科学省が昨年末に全国の小学6年、中学2年、高校2年の計約1万7000人を対象に携帯に関する調査をした。その結果によれば、携帯電話の所有率は小学生が24・7%、中学生が45・9%で、高校生になると95・9%とほぼ全員になってしまうという。15年ほど前に高校生だった自分にとってはなかなか衝撃的なニュースである。
子どもに携帯は不要だという考えもあり、私もそう思う一方、もし持っていなければイジメなどの対象になりやすくなるではと想像してしまう。ネットによる誹謗中傷も含めて現代の子どもたちは、私たちが中高生だった時代とは違った問題に直面しているのだろう。
現代は携帯を持たなければ生活が成り立たない部分が多くなってしまった。そして、今の子どもたちもそれに対して何も違和感を抱いてないのだろう。
そんなご時世に私といえば、日中の間(9時半から午後6時半ごろ)は携帯の電源を切る生活を始めた。仕事に必要なのではと思う方もいるだろう。しかしこの時間帯は会社にいるので、わざわざ携帯にかけてくる必要はない。職場に電話をすれば十分である。ただし、社外に出る時は電源を入れておく。
こんなことを始めた理由はいろいろあるけれど、ともかく携帯に振り回されているような思いが強くなってきたことが大きい。そもそも私は携帯を持ちたくて持った人間ではない。就職してからもしばらく所持していなかったけれど、周囲の圧力に屈して仕方なく持ったという人間だ。プライベートでもほとんど使用しないし、仕事でも返信くらいしかかけない。もっぱら受信専用である。携帯が便利に使っているのではない。携帯によって便利に使われているだけだ。
他に経済的な理由がある。着信履歴があったらやはり返信しなければならない。それが積み重なって利用料金が1万2千円くらいになる月もある。こうした対策もどこかで打たなくては。そういう思いもあった。
携帯の電源を切ってまだ間もないけれど、余計な神経が向かなくなるだけ快適に仕事をすることができる。
ジャーナリストの斎藤貴男は携帯電話が嫌いで、人間が扱える代物ではない、というようなことを言っていた。確かに、ところかまわず送られてくる電話やメールをコントロールすることは不可能である。それでも持たなければならない人間は、少しの間でも電源を切るなどして乗り切るしかないだろう。
本音を言えば、もう携帯など手放したいのだが。
子どもに携帯は不要だという考えもあり、私もそう思う一方、もし持っていなければイジメなどの対象になりやすくなるではと想像してしまう。ネットによる誹謗中傷も含めて現代の子どもたちは、私たちが中高生だった時代とは違った問題に直面しているのだろう。
現代は携帯を持たなければ生活が成り立たない部分が多くなってしまった。そして、今の子どもたちもそれに対して何も違和感を抱いてないのだろう。
そんなご時世に私といえば、日中の間(9時半から午後6時半ごろ)は携帯の電源を切る生活を始めた。仕事に必要なのではと思う方もいるだろう。しかしこの時間帯は会社にいるので、わざわざ携帯にかけてくる必要はない。職場に電話をすれば十分である。ただし、社外に出る時は電源を入れておく。
こんなことを始めた理由はいろいろあるけれど、ともかく携帯に振り回されているような思いが強くなってきたことが大きい。そもそも私は携帯を持ちたくて持った人間ではない。就職してからもしばらく所持していなかったけれど、周囲の圧力に屈して仕方なく持ったという人間だ。プライベートでもほとんど使用しないし、仕事でも返信くらいしかかけない。もっぱら受信専用である。携帯が便利に使っているのではない。携帯によって便利に使われているだけだ。
他に経済的な理由がある。着信履歴があったらやはり返信しなければならない。それが積み重なって利用料金が1万2千円くらいになる月もある。こうした対策もどこかで打たなくては。そういう思いもあった。
携帯の電源を切ってまだ間もないけれど、余計な神経が向かなくなるだけ快適に仕事をすることができる。
ジャーナリストの斎藤貴男は携帯電話が嫌いで、人間が扱える代物ではない、というようなことを言っていた。確かに、ところかまわず送られてくる電話やメールをコントロールすることは不可能である。それでも持たなければならない人間は、少しの間でも電源を切るなどして乗り切るしかないだろう。
本音を言えば、もう携帯など手放したいのだが。
我慢できない。買ってやる。
2009年2月24日 音楽
明日は待ちに待った給料日である。だからというわけでもないけれど、CDを1枚買うことに決めた。
買おうと思ったのは「Astral Weeks: Live at the Hollywood Bowl 」というアルバムである。ヴァン・モリソンのファンならば説明不要だけれど、昨年ハリウッドで開催された、アルバム「アストラル・ウイークス」(68年)の全曲を披露するライブの模様を収録したCDだ。
すぐ輸入盤を入手した方は2月11日にはmixiで感想を書いている。しかし私は、「国内盤が出るまで様子を見ようかな」などという思いが頭をよぎってしまった。しかしながら、ベスト・アルバムすらまともに国内盤が出ないミュージシャンのライブ・アルバムなど果たして国内盤はあるのだろうか。そうした不安が高まるばかりだった。
もうこれ以上は我慢できない。そういう気持ちに駆られ、さきほどアマゾンのサイトでクリックをしてしまった。価格は手数料を入れて2324円だ。しばらくしたら最寄りのローソンに届くだろう。
聴いたらまた感想を記したい。
買おうと思ったのは「Astral Weeks: Live at the Hollywood Bowl 」というアルバムである。ヴァン・モリソンのファンならば説明不要だけれど、昨年ハリウッドで開催された、アルバム「アストラル・ウイークス」(68年)の全曲を披露するライブの模様を収録したCDだ。
すぐ輸入盤を入手した方は2月11日にはmixiで感想を書いている。しかし私は、「国内盤が出るまで様子を見ようかな」などという思いが頭をよぎってしまった。しかしながら、ベスト・アルバムすらまともに国内盤が出ないミュージシャンのライブ・アルバムなど果たして国内盤はあるのだろうか。そうした不安が高まるばかりだった。
もうこれ以上は我慢できない。そういう気持ちに駆られ、さきほどアマゾンのサイトでクリックをしてしまった。価格は手数料を入れて2324円だ。しばらくしたら最寄りのローソンに届くだろう。
聴いたらまた感想を記したい。
逮捕でCD出荷停止。その理由は?
2009年2月23日 音楽鈴木茂が大麻所持で逮捕というニュースはネットでも大きく取り上げられていた。
いまだに元「はっぴいえんど」(活動していたのは1970年から72年末。いまから35年以上も前だ)という紹介をされているのは悲しいけれど、このバンドにも彼にもたいして思い入れがない私にとっては重大な事件でもない。最初はそう思っていた。
だがポニーキャニオン、キングレコード、日本クラウンの各社が、鈴木のアルバム以外に、はっぴいえんど、ティン・パン・アレーなど、彼が参加しているアルバムにまで出荷停止するという話を聞いたときには非常にショックを受ける。
そもそも、ミュージシャンが事件事故をおこしたからという理由で、その人の関わった作品の発売を止めることにどれほど意味があるのだろうか。レコード会社の説明も納得がいくものはない。「JCASTニュース」というところの記事によればこうだ(09年2月19日)
「社内で協議した結果で、ホームページで書かせていただいたことがすべてです。音楽の歴史的価値は重々分かっており、残念な思いはありますが、刑事事件になりましたので致し方ないと思っています」(ポニーキャニオン)
「過剰反応ということではなく、世間をお騒がせした状況を考慮したということです」(キングレコード)
「特別にお答えすることはありません」(日本クラウン)
鈴木本人のみならず、一緒に作品を作ったミュージシャン、およびそのファンが一方的に不利益を受けただけではないだろうか。
ところで警視庁のまとめによれば、昨年(08年)の1年間における大麻取締法違反容疑で検挙されたのは2778人だ。これは昨年より507人増で、統計開始(1956年)以来、過去最高の数字である。麻薬汚染は日本国内でも深刻な問題になっているのは間違いない。
しかしながら、ミュージシャンだからといって不必要に社会的制裁を加えられるのは行き過ぎだ。大麻所持の刑罰は5年以下の懲役、初犯ならば2年で執行猶予が一般的だという。刑事罰を受ければそれで十分ではないか。赤の他人がどうこう言う話ではない。
たぶん、レコード会社がミュージシャンに余計な罰を与えることに私は最も憤慨しているのだと思う。だが、ジャニス・ジョプリンやジミ・ヘンドリックスやジム・モリソン(ザ・ドアーズ)といったドラッグで亡くなったミュージシャンに対するレコード会社の扱いはどうだろう。まるで神か仏ではないか。こうした人たちの作品で商売をすることについて全く非難するつもりはない。しかし、今回のようなCDの出荷停止をする姿勢とは全く結びつかないというほかない。
いまだに元「はっぴいえんど」(活動していたのは1970年から72年末。いまから35年以上も前だ)という紹介をされているのは悲しいけれど、このバンドにも彼にもたいして思い入れがない私にとっては重大な事件でもない。最初はそう思っていた。
だがポニーキャニオン、キングレコード、日本クラウンの各社が、鈴木のアルバム以外に、はっぴいえんど、ティン・パン・アレーなど、彼が参加しているアルバムにまで出荷停止するという話を聞いたときには非常にショックを受ける。
そもそも、ミュージシャンが事件事故をおこしたからという理由で、その人の関わった作品の発売を止めることにどれほど意味があるのだろうか。レコード会社の説明も納得がいくものはない。「JCASTニュース」というところの記事によればこうだ(09年2月19日)
「社内で協議した結果で、ホームページで書かせていただいたことがすべてです。音楽の歴史的価値は重々分かっており、残念な思いはありますが、刑事事件になりましたので致し方ないと思っています」(ポニーキャニオン)
「過剰反応ということではなく、世間をお騒がせした状況を考慮したということです」(キングレコード)
「特別にお答えすることはありません」(日本クラウン)
鈴木本人のみならず、一緒に作品を作ったミュージシャン、およびそのファンが一方的に不利益を受けただけではないだろうか。
ところで警視庁のまとめによれば、昨年(08年)の1年間における大麻取締法違反容疑で検挙されたのは2778人だ。これは昨年より507人増で、統計開始(1956年)以来、過去最高の数字である。麻薬汚染は日本国内でも深刻な問題になっているのは間違いない。
しかしながら、ミュージシャンだからといって不必要に社会的制裁を加えられるのは行き過ぎだ。大麻所持の刑罰は5年以下の懲役、初犯ならば2年で執行猶予が一般的だという。刑事罰を受ければそれで十分ではないか。赤の他人がどうこう言う話ではない。
たぶん、レコード会社がミュージシャンに余計な罰を与えることに私は最も憤慨しているのだと思う。だが、ジャニス・ジョプリンやジミ・ヘンドリックスやジム・モリソン(ザ・ドアーズ)といったドラッグで亡くなったミュージシャンに対するレコード会社の扱いはどうだろう。まるで神か仏ではないか。こうした人たちの作品で商売をすることについて全く非難するつもりはない。しかし、今回のようなCDの出荷停止をする姿勢とは全く結びつかないというほかない。
あのフリクションが新作を
2009年2月18日 音楽今年はライブに行く回数を控えると公言しているけれど、CDの買う数もいつのころかグッと減っていた。もともと時代とか流行を追いかけるのが好きな人間ではないので仕方ないけれど、最近は敬愛するヴァン・モリソンのごとく大昔のブルースやソウルのような音楽ばかり聴く生活を送っている。
しかし「これは買わねば!」と思わせるCDが来月に出ることとなった。なんと、あのフリクション(Friction)が新作を発売するというのだ。前作「Zone Tripper」(95年)以来、実に14年ぶりのアルバムである。
中村達也(ドラムス)と2人だけという特殊な編成でレックがフリクションの活動を再開したのは2006年のことである。もうこれが最後だろうと勝手に思っていた私は渋谷クアトロまで駆けつけて彼らのライブを体験した。しかし予想に反して、ライジング・サンやフジ・ロックなどのフェスティバルにも出演するなど活動はどんどん積極的になる。そして、大阪の心斎橋クラブクアトロで2回目のライブを観る機会もできた。
その時のライブの感想を書く機会を逃していたけれど、ステージに立つレックと中村の姿が実に楽しそうだったのが個人的に印象深かった。CDで体験していた鬼気迫る緊張感やテンションばかりでなかったので、自分の中にあった彼らのイメージが良い意味で壊されることとなった。
イギー・ポップやローリング・ストーンズのカバーなども収録されている「DEEPERS」と名付けられた新作は、いままでには無かったフリクションの姿が捉えられているものと密かに期待している。
しかし「これは買わねば!」と思わせるCDが来月に出ることとなった。なんと、あのフリクション(Friction)が新作を発売するというのだ。前作「Zone Tripper」(95年)以来、実に14年ぶりのアルバムである。
中村達也(ドラムス)と2人だけという特殊な編成でレックがフリクションの活動を再開したのは2006年のことである。もうこれが最後だろうと勝手に思っていた私は渋谷クアトロまで駆けつけて彼らのライブを体験した。しかし予想に反して、ライジング・サンやフジ・ロックなどのフェスティバルにも出演するなど活動はどんどん積極的になる。そして、大阪の心斎橋クラブクアトロで2回目のライブを観る機会もできた。
その時のライブの感想を書く機会を逃していたけれど、ステージに立つレックと中村の姿が実に楽しそうだったのが個人的に印象深かった。CDで体験していた鬼気迫る緊張感やテンションばかりでなかったので、自分の中にあった彼らのイメージが良い意味で壊されることとなった。
イギー・ポップやローリング・ストーンズのカバーなども収録されている「DEEPERS」と名付けられた新作は、いままでには無かったフリクションの姿が捉えられているものと密かに期待している。
小さくとも確かな支援〜京都橘大学の事例から〜
2009年2月17日 就職・転職2月13日に京都橘大学が、2009年卒業予定で内定を取り消された大学生について、授業料を1年間免除して卒業延期を認める方針をとった。
公式サイトはこちら。
http://www.tachibana-u.ac.jp/
支援策についての文書はこちら。
http://www.tachibana-u.ac.jp/official/pdf/assistance-measures.pdf
支援を受けるためには、
・要卒単位を満たしていること。
・ 内定取消を受けた企業から本学就職進路課に「新規学校卒業者の採用内定取消通知書」が提出されてい ること、または就職ができなくなったことを証明する書類が提出されていること。
・「卒業留保願」(本学所定用紙)を提出していること。
の3点を満たしていることが条件となる。ただ、在籍料として1学期2万円は必要だ。
2月17日付の京都新聞朝刊によると、同大学では今年に入って男子学生1人が内定を取り消され、女子学生1人が就職時期の半年延期を言い渡されたという。
大学は、
「今回の措置では、内定取り消しだけでなく、就職時期の延期や内定辞退の強要を受けた学生にも柔軟に対応したい」
とも言っている。
私は大学院入試を失敗してそのまま大学を出てしまった経験があるけれど、新卒と既卒とでは就職活動に圧倒的な差が出てくる。日本の企業はまだ新卒採用が大半だ。また、大学を離れれば情報も乏しくなる。就職課もないし、パソコンのような設備も自前で工面しなければならない。ハローワークに行ったり雑誌を買って当たっていくなどの限られた方法しかなくなるのだ。
内定を取り消された人たちはまだまだ困難は続いていくことだろう。就職活動や生活にかかる経費もあるし、正直いって大学料を免除してもそれほど効果がないかもしれない。しかしながら、この困難で不透明な経済状況下において京都橘大学のような配慮を草の根で増やしていくことが打開策への着実な道につながっていくような気がする。
公式サイトはこちら。
http://www.tachibana-u.ac.jp/
支援策についての文書はこちら。
http://www.tachibana-u.ac.jp/official/pdf/assistance-measures.pdf
支援を受けるためには、
・要卒単位を満たしていること。
・ 内定取消を受けた企業から本学就職進路課に「新規学校卒業者の採用内定取消通知書」が提出されてい ること、または就職ができなくなったことを証明する書類が提出されていること。
・「卒業留保願」(本学所定用紙)を提出していること。
の3点を満たしていることが条件となる。ただ、在籍料として1学期2万円は必要だ。
2月17日付の京都新聞朝刊によると、同大学では今年に入って男子学生1人が内定を取り消され、女子学生1人が就職時期の半年延期を言い渡されたという。
大学は、
「今回の措置では、内定取り消しだけでなく、就職時期の延期や内定辞退の強要を受けた学生にも柔軟に対応したい」
とも言っている。
私は大学院入試を失敗してそのまま大学を出てしまった経験があるけれど、新卒と既卒とでは就職活動に圧倒的な差が出てくる。日本の企業はまだ新卒採用が大半だ。また、大学を離れれば情報も乏しくなる。就職課もないし、パソコンのような設備も自前で工面しなければならない。ハローワークに行ったり雑誌を買って当たっていくなどの限られた方法しかなくなるのだ。
内定を取り消された人たちはまだまだ困難は続いていくことだろう。就職活動や生活にかかる経費もあるし、正直いって大学料を免除してもそれほど効果がないかもしれない。しかしながら、この困難で不透明な経済状況下において京都橘大学のような配慮を草の根で増やしていくことが打開策への着実な道につながっていくような気がする。
ワークシェアリングの可能性
2009年2月2日 お仕事「百年に一度の不況」と言われるこの頃、営業赤字や人員削減に関するニュースが後を絶たない。そんな話はうんざりだと思っていた時に、Yahooのトップに載っていた産経新聞の記事が目に止まる(1月22日16時27分配信)
それは「アスク」という大阪の部品メーカーが、人員削減ではなくワークシェアリングによってこの不況を耐えようと決めた話だった。
従業員1人あたりの賃金や労働時間を減らすことにより、人件費を抑制しながら全体の雇用を維持するというのがワークシェアリングのおおまかな定義だ。労働者の雇用打ち切りが社会問題になっている昨今、日本国内でも導入の動きが出てきてもいる。
アスクにおけるワークシェアリングの具体的な方策は、
・休日を年間97日間から130日程度に増やし、残業をゼロにする。
・空いた時間にアルバイトを認める。
・1時間あたりの賃金を一律数パーセント上げる。
といったものだ。
しかし、社員の受け止め方は複雑だという。増えた休みで家族サービスや資格取得に使おうという肯定的な人もいれば、手取りが減るなら転職も考えているという人もいる。また、経営者にしても難しい決断だったろう。経済界でも、ワークシェアリングでは人員削減ほどには効果は期待できないのでは、という声もけっこうあるのだから。
それでも、私は労使双方にとってワークシェアリングはリストラよりずっと良いと思う。労働者にとっては「収入ゼロ」で行き場がなくなるという最悪の事態はまぬがれる。経営者にとっても人員整理にかかるコスト(これは心理的な負担なども含まれる)もずっと軽くて済むだろう(この辺のことを勘定に入れない人は多い)
それから、「空いた時間にアルバイトを認める。」というアスクの出した方針も一つの可能性があるのではないだろうか。この流動性の激しい世の中において、複数の仕事で収入を得るという方法はリスク管理にも成りうる。
会社にも社員にも顕著なメリットが無いように思えるが、この不況によって社会が「さらに悪くならない」ための手段としてワークシェアリングは検討に値するのではないだろうか。
それは「アスク」という大阪の部品メーカーが、人員削減ではなくワークシェアリングによってこの不況を耐えようと決めた話だった。
従業員1人あたりの賃金や労働時間を減らすことにより、人件費を抑制しながら全体の雇用を維持するというのがワークシェアリングのおおまかな定義だ。労働者の雇用打ち切りが社会問題になっている昨今、日本国内でも導入の動きが出てきてもいる。
アスクにおけるワークシェアリングの具体的な方策は、
・休日を年間97日間から130日程度に増やし、残業をゼロにする。
・空いた時間にアルバイトを認める。
・1時間あたりの賃金を一律数パーセント上げる。
といったものだ。
しかし、社員の受け止め方は複雑だという。増えた休みで家族サービスや資格取得に使おうという肯定的な人もいれば、手取りが減るなら転職も考えているという人もいる。また、経営者にしても難しい決断だったろう。経済界でも、ワークシェアリングでは人員削減ほどには効果は期待できないのでは、という声もけっこうあるのだから。
それでも、私は労使双方にとってワークシェアリングはリストラよりずっと良いと思う。労働者にとっては「収入ゼロ」で行き場がなくなるという最悪の事態はまぬがれる。経営者にとっても人員整理にかかるコスト(これは心理的な負担なども含まれる)もずっと軽くて済むだろう(この辺のことを勘定に入れない人は多い)
それから、「空いた時間にアルバイトを認める。」というアスクの出した方針も一つの可能性があるのではないだろうか。この流動性の激しい世の中において、複数の仕事で収入を得るという方法はリスク管理にも成りうる。
会社にも社員にも顕著なメリットが無いように思えるが、この不況によって社会が「さらに悪くならない」ための手段としてワークシェアリングは検討に値するのではないだろうか。