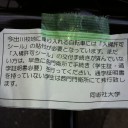本気で取り締まるつもりかよ、このクズ野郎(笑)
2011年6月6日
先日、同志社大学の構内に入る自転車は許可シールが必要なことを日記で書いた。しかし、自転車の数が多いためろくに取り締まられていないため、私は構うことなく自転車で大学に通っていた。
今日も朝から大学を訪れていた。そして昼過ぎに河原町三条の「丸亀製麺」に行こうと自転車に戻った時、画像の紙が自転車のサドルに張り付けられていた。どうやら大学当局は取り締まりに対して少し本気になってきたようだ。私の日記を誰かが見たとか?そんなことはないか。
どうして外部の自転車に対して神経質になったのだろう。そのはっきりした理由はしらないけれど、私の頭で考えつくことといえば放置自転車の対策あたりだろうか。しかし自転車を整理している係の人は3人くらいしかいないのに、こんな但し書きを自転車に張るクソみたいな作業をさせられているのは気の毒で仕方ない。
このまま自転車で通い続ければ自転車そのものをどこかに撤去させられるかもしれない。行く場所が見つかるまでは通うつもりだったので(笑)、なんだか面倒な話になってきた。
同志社大学今出川キャンパスに通っていて自転車を使用していない学生さん、シールを提供してくださいませんかねえ。多少のお礼はさせてもらいますよ(笑)
考えてみれば、大学に限らず京都市内は自転車を止めづらくなった気がしてならない。たとえば河原町御池の周辺では有料の駐輪場が多くなってきている。さきほど書いた丸亀製麺に行くときもその駐輪場(3時間以内は100円)に止めた。パッと食べて戻ったら、まだ無料時間の30分を超えてなかったのでタダで自転車を引き上げることができた。別に狙ったわけではないが、なんだか得をした気分である。
今日も朝から大学を訪れていた。そして昼過ぎに河原町三条の「丸亀製麺」に行こうと自転車に戻った時、画像の紙が自転車のサドルに張り付けられていた。どうやら大学当局は取り締まりに対して少し本気になってきたようだ。私の日記を誰かが見たとか?そんなことはないか。
どうして外部の自転車に対して神経質になったのだろう。そのはっきりした理由はしらないけれど、私の頭で考えつくことといえば放置自転車の対策あたりだろうか。しかし自転車を整理している係の人は3人くらいしかいないのに、こんな但し書きを自転車に張るクソみたいな作業をさせられているのは気の毒で仕方ない。
このまま自転車で通い続ければ自転車そのものをどこかに撤去させられるかもしれない。行く場所が見つかるまでは通うつもりだったので(笑)、なんだか面倒な話になってきた。
同志社大学今出川キャンパスに通っていて自転車を使用していない学生さん、シールを提供してくださいませんかねえ。多少のお礼はさせてもらいますよ(笑)
考えてみれば、大学に限らず京都市内は自転車を止めづらくなった気がしてならない。たとえば河原町御池の周辺では有料の駐輪場が多くなってきている。さきほど書いた丸亀製麺に行くときもその駐輪場(3時間以内は100円)に止めた。パッと食べて戻ったら、まだ無料時間の30分を超えてなかったのでタダで自転車を引き上げることができた。別に狙ったわけではないが、なんだか得をした気分である。
連合>米国>国民?
2011年6月5日国内政治において、多くの国民にとっては不可解な出来事が続いている。
一つは、浜岡原発の停止についてだ。浜岡についてはこれまで経済産業省も電力会社も「安全です!」と言い続けてきた発電所である。そんな浜岡に対して菅直人総理は突然に停止を要請し、なんと中部電力もそれを受け入れてしまったのだ。わけがわからない。
それについて内田樹さんは5月20日のブログで「脱原発の理路」という文章を書いており、こう説明している。
<政府と霞ヶ関と財界が根回し抜きで合意することがあるとしたら、その条件は一つしかない。アメリカ政府からの要請があったからである。>
引用元はこちら:http://blog.tatsuru.com/2011/05/20_0900.php
なるほど。アメリカからの圧力のおかげであって、別に国民の意思が顧みられたとかいうはないわけではないのだ。理由を聞けば実にわかりやすい話である。
そしてもう一つわけがわからないのは、菅内閣に対する不信任案決議に関わる一連の騒動だ。当初はマスコミの多くも不信任案が通るとさかんに言っていたのにあの結果である。
これについては渋谷陽一氏(「ロッキング・オン」代表取締役社長、音楽評論家)が6月3日のブログでこう要約してくれている。
<まず不信任案を自民公明が出そうしたのは、民主党を壊したいから。菅に反発する小沢グループ鳩山グループが反乱を起こしそうだという動きに乗って民主党を分裂させて、自分たちの勢力を伸ばしたかったのだ。次に小沢グループ鳩山グループが方針をいきなり変えたのは、民主党最大の支持基盤である連合が手打ちしろと言って来たから。
民主党が分裂して困るのは連合で、自分たちの力を失いたくなかったから。
何で菅が辞任を匂わしたかといえば、そうしないと不信任案が可決されて自分たちの力を失いそうだったから。>
引用元はこちら:http://ro69.jp/blog/shibuya/52147
なるほど。民主党の最大のスポンサーである連合の介入があったことでこのような急旋回が起きたわけだ。しかし、ここでも国民の声というのは全く反映されていない。
この2つの出来事を見ると、民主党がどこを見て動いているのかが実によくわかる。同盟国のアメリカ(向こうにとって日本は属国だろうが)、また支持母体である連合の顔色をうかがっているのだ。
しかし、こうしたことはいつまでも続くということもないだろう。時事通信社の5月20日における調査では民主党の支持率はわずか10.2%である。菅内閣の「不支持率」にいたっては59.5%に達している。もしもいま総選挙を実施したとしたら、その結果は惨憺たるものとなるのは容易に想像がつく。
たとえ連合がせっかくつかんだ政治力を奪われたくないからと今回の介入に至ったといっても、選挙で民主党が大敗して議席を減らしてしまえば必然的にその力も失ってしまう。そんなことを考えれば、今回の騒動もたんなる内閣の先送り以上のものはなかったのかもしれない。
現在の小選挙区制度のもとでは、かつての小泉政権も民主党もすさまじい結果を出した実績もあるが、その逆の結果も大いにあり得る。よって、議員の選出については国民の力が一番大きいには違いない。ただ、せっかく投票して結果を出してもその先の行動がともなっていないところが辛い。最近の政治を見ていると、誰を選んでも同じ、という虚無主義(ニヒリズム)が国内に蔓延しているような気がする。
もし次に選挙がおこなわれるとしたらどうなるだろう。おそらく全体的に投票率が大幅に下がり、それによって相対的に自民党が少し回復する、というようなつまらない結果が出てきそうだ。しかし、村井嘉浩・宮城県知事が、
<県議選もできないのに、(国政の)選挙の実施は不可能。選挙ができると思っている国会議員には、女川町や南三陸町、気仙沼市に足を運んでほしい>(2011年6月2日10時22分 読売新聞)
と嘆いたように、そんなことをしている余裕はこの国には無いはずである。
一つは、浜岡原発の停止についてだ。浜岡についてはこれまで経済産業省も電力会社も「安全です!」と言い続けてきた発電所である。そんな浜岡に対して菅直人総理は突然に停止を要請し、なんと中部電力もそれを受け入れてしまったのだ。わけがわからない。
それについて内田樹さんは5月20日のブログで「脱原発の理路」という文章を書いており、こう説明している。
<政府と霞ヶ関と財界が根回し抜きで合意することがあるとしたら、その条件は一つしかない。アメリカ政府からの要請があったからである。>
引用元はこちら:http://blog.tatsuru.com/2011/05/20_0900.php
なるほど。アメリカからの圧力のおかげであって、別に国民の意思が顧みられたとかいうはないわけではないのだ。理由を聞けば実にわかりやすい話である。
そしてもう一つわけがわからないのは、菅内閣に対する不信任案決議に関わる一連の騒動だ。当初はマスコミの多くも不信任案が通るとさかんに言っていたのにあの結果である。
これについては渋谷陽一氏(「ロッキング・オン」代表取締役社長、音楽評論家)が6月3日のブログでこう要約してくれている。
<まず不信任案を自民公明が出そうしたのは、民主党を壊したいから。菅に反発する小沢グループ鳩山グループが反乱を起こしそうだという動きに乗って民主党を分裂させて、自分たちの勢力を伸ばしたかったのだ。次に小沢グループ鳩山グループが方針をいきなり変えたのは、民主党最大の支持基盤である連合が手打ちしろと言って来たから。
民主党が分裂して困るのは連合で、自分たちの力を失いたくなかったから。
何で菅が辞任を匂わしたかといえば、そうしないと不信任案が可決されて自分たちの力を失いそうだったから。>
引用元はこちら:http://ro69.jp/blog/shibuya/52147
なるほど。民主党の最大のスポンサーである連合の介入があったことでこのような急旋回が起きたわけだ。しかし、ここでも国民の声というのは全く反映されていない。
この2つの出来事を見ると、民主党がどこを見て動いているのかが実によくわかる。同盟国のアメリカ(向こうにとって日本は属国だろうが)、また支持母体である連合の顔色をうかがっているのだ。
しかし、こうしたことはいつまでも続くということもないだろう。時事通信社の5月20日における調査では民主党の支持率はわずか10.2%である。菅内閣の「不支持率」にいたっては59.5%に達している。もしもいま総選挙を実施したとしたら、その結果は惨憺たるものとなるのは容易に想像がつく。
たとえ連合がせっかくつかんだ政治力を奪われたくないからと今回の介入に至ったといっても、選挙で民主党が大敗して議席を減らしてしまえば必然的にその力も失ってしまう。そんなことを考えれば、今回の騒動もたんなる内閣の先送り以上のものはなかったのかもしれない。
現在の小選挙区制度のもとでは、かつての小泉政権も民主党もすさまじい結果を出した実績もあるが、その逆の結果も大いにあり得る。よって、議員の選出については国民の力が一番大きいには違いない。ただ、せっかく投票して結果を出してもその先の行動がともなっていないところが辛い。最近の政治を見ていると、誰を選んでも同じ、という虚無主義(ニヒリズム)が国内に蔓延しているような気がする。
もし次に選挙がおこなわれるとしたらどうなるだろう。おそらく全体的に投票率が大幅に下がり、それによって相対的に自民党が少し回復する、というようなつまらない結果が出てきそうだ。しかし、村井嘉浩・宮城県知事が、
<県議選もできないのに、(国政の)選挙の実施は不可能。選挙ができると思っている国会議員には、女川町や南三陸町、気仙沼市に足を運んでほしい>(2011年6月2日10時22分 読売新聞)
と嘆いたように、そんなことをしている余裕はこの国には無いはずである。
リチャード・トンプソン「アムニージア」(88年)
2011年6月4日 音楽
(1)Turning Of The Tide
(2)Gypsy Love Songs
(3)Reckless Kind
(4)Jerusalem On The Jukebox
(5)I Still Dream
(6)Don’t Tempt Me
(7)Yankee, Go Home
(8)Can’t Win
(9)Waltzing’s For Dreamers
(10)Pharaoh
「ブリティッシュ・フォーク」とか「ブリティッシュ・トラッド」という音楽ジャンルについて多くの日本人はピンとこないに違いない。代表的なバンドといえばフェアポート・コンヴェンション(Fairport Convention)とペンタングル(Pentangle)が出てくるけれど、その名前すら聞いたこともない人がほとんどだろう。
先日この日記で、先月に来日したのを知らなかったと思ったら震災の影響で中止になっていた、とワーワー騒いでいたリチャード・トンプソン(Richard Thompson)がプロとして出発したのはそのフェアポート・コンヴェンションのギタリストとしてであった。そういうジャンルの人なのでこの国における知名度もかなり寂しいものがある。mixiのコミュニティの参加人数は300人にも達していないし、日本版ウィキペディアにいたっては彼の項目すら存在しないのだ。
私が彼の名前を知ったのは高校生の頃だった。当時(93年代前半)はまだ雑誌などで音楽についての情報を割と熱心に集めていた時期で、「ミュージック・マガジン」あたりで彼の名前を知ったのだと思う。ただ、具体的に彼の何について興味を持ったのかどうかははっきりと覚えていない。フェアポートなど英国のフォーク・ミュージックに関心を持ったのかもしれないし、このころ彼のプロデュースを手掛けていたのが90年代に活躍していたミッチェル•フルーム(シェリル・クロウやロン・セクスミス、Bonnie Pinkなどと仕事をしている)だったことも関係あったような気もする。それはともかく、英国にリチャード・トンプソンという何か凄いミュージシャンでありギタリストがいる、ということが自分の頭の中にいつの間にか刻まれていたのは間違いない。
ただ、高校まで私が住んでいた北海道登別市には、トンプソンやフェアポートのCDなど手に入らなかった(フェアポートは当時、国内盤は廃盤していたと思う)。しかし翌年(95年)に大学受験を失敗し浪人生活のため札幌に来たおかげでトンプソンを始め様々な作品が手軽に手に入るようになる。この「アムニージア」(Amnesia)もその時の1枚で、中古CDショップで880円か980円か、ともかく3桁の値段で置いてあったことをよく覚えている。こういうものを「掘り出し物」というのだろう。
93年に出た3枚組アルバム「ウォッチング・ザ・ダーク ザ・ヒストリー・オブ・リチャード・トンプスン」(これも札幌の古本屋で買った)は名前の通りトンプソンの69年~92年の軌跡をたどった作品であるが、その解説でグリール・マーカス(アメリカの音楽評論家)がトンプソンの音楽についてこのようなことを書いている。
<トンプスンの曲と演奏を時間の経過とたどってみても、発展、成熟、洗練といった感覚は殆どあるいは全くない>
そして「ヴァン・モリスンやニール・ヤングと並ぶ、たぶんトンプスンは数少ない真のポップの似た者同士」とも評していた。ニールやヴァンも大好きな私としては実に嬉しい讃え方である。ちなみにこの3人は私にとっての「3大ソング・ライター」でもある。それはともかく、確かにこの3枚組CDなどでトンプソンの歴史を追ってみても、フェアポート時代から最新作(2010年)まで彼の音楽には一貫したものが流れていることをなんとなく感じられる。
トンプソンが在籍していたフェアポート・コンヴェンションというバンドは、当初ボブ・ディランやレナード・コーエンといったアメリカのミュージシャンをカバーしていたけれど、69年に出した3枚目のアルバム「アンハーフブリッキング」(Unhalfbricking)において大きな転機を迎える。英国の伝承音楽(フォーク・ソング)だった「船乗りの生涯」(A Sailor’s Life)を取り上げたのが大きな評判を呼んだのだ。「フォーク・ロック」という音楽ジャンルはディランが産みの親の一人と言われている。私には未だにこの音楽の定義がさっぱりわからないけれど(そんなことをいったらフォークもロックも同じかな)、しかしフェアポートに関していえば、電子音楽で伝承音楽を演奏するという非常にわかりやすい意味での「フォーク・ロック」という音楽を作ったグループである。
そんなフェアポートにいたトンプソンの音楽は、基本的に英国のフォーク・ミュージックに根ざしたものだといって差し支えないと思う。彼を一つの音楽ジャンルに押し込むには無理な存在であることは重々承知している。たとえば94年に出たトンプソンのトリビュート•アルバム「ビート•ザ・リトリート〜ソングス・バイ・値チャード・トンプソン」に参加したミュージシャンはロス•ロボス、R.E.M、デヴィッド・バーン、ボニー•レイット、ブラインド•ボーイズ•オブ・アラバマ、ダイナソーJRなど実に多彩な顔ぶれとなっている。トンプソンの音楽を「オルタナティブ」と称していた人もいたけれど(本人もインタビューでそう言っていたような)、その一方で彼のどの作品の中にも英国フォークを感じる部分が消えたことはない。
88年に出たこの「アムニージア」は、パッと説明しただけではピンとこないトンプソンの音楽が実に伝わりやすい形に収まった傑作である。この次に出る「フィール・ソー•グッド」(91年)はグラミー書の候補になり商業的成功もおさめた作品であるし、その次の「ミラー•ブルー」(94年)も素晴らしいけれど、個人的にはやはりこのアルバムの方が愛着は強い。どうして自分がこのアルバムが一番好きなのか。その理由を色々と自分で考えてみたけれど、やはり”Waltzing’s For Dreamers”を始め、”Reckless Kind”や”I Still Dream”、など叙情的なメロディーのある楽曲が並んでいるからという気がする。この辺りを聴いてもらえれば、彼が作曲家としても優れているかを感じてもらえるだろう。
アルバムの随所にはアラブとか中近東を連想させるメロディーが飛び出してくる。そんな雑多な音楽性が「オルタナティブ」といわれる所以だが、音楽に詳しくない方でも聴いてもらえば、確かにそんな感じだなと思う音になっている。トンプソンの音楽がいかに幅広いジャンルからできているかもパッと伝わるかと思う。ちなみに彼ははイスラム教の信者で、スーフィズム(イスラム神秘主義)を信奉している。その辺の影響も音楽に出ているのではないだろうか。
ヴォーカルについては独特で音域も狭く、多くの人に好かれるようなものではないろう。私なりに表現すれば、熱にうかされているような、そんなフラフラした印象を受ける声である。もっと露骨にいえば、しょっちゅう聴きたくなるような性質ではない。彼が商業的にあまり成功していないのも、当然といえば当然な気がしてくる。当のトンプソン自身も歌うのはあまり好きではないようだが。
しかしながら繰り返し聴いているうちに、じわじわと伝わってくる凄みのある声ではある。例えば”Can’t Win”(この曲は「塔が崩れ落ち、バッタが大地を襲うだろう」などと、歌詞も不吉なフレーズが満載だ)で垣間見える不気味なほどの迫力に接しているうちに、このミュージシャンがどれほど底知れない才能の人なのか気づくだろう(本当のところ、ライブを観てもらえば一発でわかるのだが)
もしトンプソンの作品でおすすめは?と訊かれたら、このアルバムを真っ先に挙げたい。フランク•ザッパやヴァン・モリソンと同様、「駄作が無い人」と言われるトンプソンに対してあまり下手なことを言うのは躊躇してしまうが、少なくともこのアルバムが一番良いといっても反発は起きないと信じている(日本で数少ないリチャード・トンプソンのファンを邪険にするなんて事は無いですよね?)
日本盤はとっくの昔に廃盤となっているけれど(たぶん88年に出たきり再発はされていない)、現在はiTunesストアで音源を買うことができるようになっている。もし興味があればそこで手にいれてもらえればと願う。
(2)Gypsy Love Songs
(3)Reckless Kind
(4)Jerusalem On The Jukebox
(5)I Still Dream
(6)Don’t Tempt Me
(7)Yankee, Go Home
(8)Can’t Win
(9)Waltzing’s For Dreamers
(10)Pharaoh
「ブリティッシュ・フォーク」とか「ブリティッシュ・トラッド」という音楽ジャンルについて多くの日本人はピンとこないに違いない。代表的なバンドといえばフェアポート・コンヴェンション(Fairport Convention)とペンタングル(Pentangle)が出てくるけれど、その名前すら聞いたこともない人がほとんどだろう。
先日この日記で、先月に来日したのを知らなかったと思ったら震災の影響で中止になっていた、とワーワー騒いでいたリチャード・トンプソン(Richard Thompson)がプロとして出発したのはそのフェアポート・コンヴェンションのギタリストとしてであった。そういうジャンルの人なのでこの国における知名度もかなり寂しいものがある。mixiのコミュニティの参加人数は300人にも達していないし、日本版ウィキペディアにいたっては彼の項目すら存在しないのだ。
私が彼の名前を知ったのは高校生の頃だった。当時(93年代前半)はまだ雑誌などで音楽についての情報を割と熱心に集めていた時期で、「ミュージック・マガジン」あたりで彼の名前を知ったのだと思う。ただ、具体的に彼の何について興味を持ったのかどうかははっきりと覚えていない。フェアポートなど英国のフォーク・ミュージックに関心を持ったのかもしれないし、このころ彼のプロデュースを手掛けていたのが90年代に活躍していたミッチェル•フルーム(シェリル・クロウやロン・セクスミス、Bonnie Pinkなどと仕事をしている)だったことも関係あったような気もする。それはともかく、英国にリチャード・トンプソンという何か凄いミュージシャンでありギタリストがいる、ということが自分の頭の中にいつの間にか刻まれていたのは間違いない。
ただ、高校まで私が住んでいた北海道登別市には、トンプソンやフェアポートのCDなど手に入らなかった(フェアポートは当時、国内盤は廃盤していたと思う)。しかし翌年(95年)に大学受験を失敗し浪人生活のため札幌に来たおかげでトンプソンを始め様々な作品が手軽に手に入るようになる。この「アムニージア」(Amnesia)もその時の1枚で、中古CDショップで880円か980円か、ともかく3桁の値段で置いてあったことをよく覚えている。こういうものを「掘り出し物」というのだろう。
93年に出た3枚組アルバム「ウォッチング・ザ・ダーク ザ・ヒストリー・オブ・リチャード・トンプスン」(これも札幌の古本屋で買った)は名前の通りトンプソンの69年~92年の軌跡をたどった作品であるが、その解説でグリール・マーカス(アメリカの音楽評論家)がトンプソンの音楽についてこのようなことを書いている。
<トンプスンの曲と演奏を時間の経過とたどってみても、発展、成熟、洗練といった感覚は殆どあるいは全くない>
そして「ヴァン・モリスンやニール・ヤングと並ぶ、たぶんトンプスンは数少ない真のポップの似た者同士」とも評していた。ニールやヴァンも大好きな私としては実に嬉しい讃え方である。ちなみにこの3人は私にとっての「3大ソング・ライター」でもある。それはともかく、確かにこの3枚組CDなどでトンプソンの歴史を追ってみても、フェアポート時代から最新作(2010年)まで彼の音楽には一貫したものが流れていることをなんとなく感じられる。
トンプソンが在籍していたフェアポート・コンヴェンションというバンドは、当初ボブ・ディランやレナード・コーエンといったアメリカのミュージシャンをカバーしていたけれど、69年に出した3枚目のアルバム「アンハーフブリッキング」(Unhalfbricking)において大きな転機を迎える。英国の伝承音楽(フォーク・ソング)だった「船乗りの生涯」(A Sailor’s Life)を取り上げたのが大きな評判を呼んだのだ。「フォーク・ロック」という音楽ジャンルはディランが産みの親の一人と言われている。私には未だにこの音楽の定義がさっぱりわからないけれど(そんなことをいったらフォークもロックも同じかな)、しかしフェアポートに関していえば、電子音楽で伝承音楽を演奏するという非常にわかりやすい意味での「フォーク・ロック」という音楽を作ったグループである。
そんなフェアポートにいたトンプソンの音楽は、基本的に英国のフォーク・ミュージックに根ざしたものだといって差し支えないと思う。彼を一つの音楽ジャンルに押し込むには無理な存在であることは重々承知している。たとえば94年に出たトンプソンのトリビュート•アルバム「ビート•ザ・リトリート〜ソングス・バイ・値チャード・トンプソン」に参加したミュージシャンはロス•ロボス、R.E.M、デヴィッド・バーン、ボニー•レイット、ブラインド•ボーイズ•オブ・アラバマ、ダイナソーJRなど実に多彩な顔ぶれとなっている。トンプソンの音楽を「オルタナティブ」と称していた人もいたけれど(本人もインタビューでそう言っていたような)、その一方で彼のどの作品の中にも英国フォークを感じる部分が消えたことはない。
88年に出たこの「アムニージア」は、パッと説明しただけではピンとこないトンプソンの音楽が実に伝わりやすい形に収まった傑作である。この次に出る「フィール・ソー•グッド」(91年)はグラミー書の候補になり商業的成功もおさめた作品であるし、その次の「ミラー•ブルー」(94年)も素晴らしいけれど、個人的にはやはりこのアルバムの方が愛着は強い。どうして自分がこのアルバムが一番好きなのか。その理由を色々と自分で考えてみたけれど、やはり”Waltzing’s For Dreamers”を始め、”Reckless Kind”や”I Still Dream”、など叙情的なメロディーのある楽曲が並んでいるからという気がする。この辺りを聴いてもらえれば、彼が作曲家としても優れているかを感じてもらえるだろう。
アルバムの随所にはアラブとか中近東を連想させるメロディーが飛び出してくる。そんな雑多な音楽性が「オルタナティブ」といわれる所以だが、音楽に詳しくない方でも聴いてもらえば、確かにそんな感じだなと思う音になっている。トンプソンの音楽がいかに幅広いジャンルからできているかもパッと伝わるかと思う。ちなみに彼ははイスラム教の信者で、スーフィズム(イスラム神秘主義)を信奉している。その辺の影響も音楽に出ているのではないだろうか。
ヴォーカルについては独特で音域も狭く、多くの人に好かれるようなものではないろう。私なりに表現すれば、熱にうかされているような、そんなフラフラした印象を受ける声である。もっと露骨にいえば、しょっちゅう聴きたくなるような性質ではない。彼が商業的にあまり成功していないのも、当然といえば当然な気がしてくる。当のトンプソン自身も歌うのはあまり好きではないようだが。
しかしながら繰り返し聴いているうちに、じわじわと伝わってくる凄みのある声ではある。例えば”Can’t Win”(この曲は「塔が崩れ落ち、バッタが大地を襲うだろう」などと、歌詞も不吉なフレーズが満載だ)で垣間見える不気味なほどの迫力に接しているうちに、このミュージシャンがどれほど底知れない才能の人なのか気づくだろう(本当のところ、ライブを観てもらえば一発でわかるのだが)
もしトンプソンの作品でおすすめは?と訊かれたら、このアルバムを真っ先に挙げたい。フランク•ザッパやヴァン・モリソンと同様、「駄作が無い人」と言われるトンプソンに対してあまり下手なことを言うのは躊躇してしまうが、少なくともこのアルバムが一番良いといっても反発は起きないと信じている(日本で数少ないリチャード・トンプソンのファンを邪険にするなんて事は無いですよね?)
日本盤はとっくの昔に廃盤となっているけれど(たぶん88年に出たきり再発はされていない)、現在はiTunesストアで音源を買うことができるようになっている。もし興味があればそこで手にいれてもらえればと願う。
この数の自転車を管理するのは無理でしょう
2011年6月2日前の職場を辞めて、はや1ヶ月を過ぎた。資格の勉強とか就職活動とかぽつりぽつりとしているものの、バタバタと動いているわけではない。ほとんど何もしていないといえる。
ただ、大家さんが下に住んでいることもあり、昼間もずっと部屋にいるのもどうかなあと思うようになってきて、明るい時間はなるべく外に出るようにしている。こんなことは想定していなかったけれど、居場所が無いというのはなかなか辛い部分も出てくる。だからといって、辞める前に戻りたいなあ、などと思うことも一切ないけれど。
幸いなことに私は、同志社大学の図書館をOBも利用できるため、そこで勉強や読書をしている。自転車に乗って数分で行けるから非常に便利だ。
しかしながら、今年度から少し困ったことが起きている。大学が「自転車入構許可シール」というものを発行したのである。大学のサイトにもPDFで文書が載っていた。
http://www.doshisha.ac.jp/news_contents/attached/2011_bicycle.pdf
私はたまたま大学の壁に貼っていた文書を昨日見つけたのであるが、
「入構許可シールが貼付されていない自転車は今後随時撤去します」
という文を見た時はかなり面食らった。大学構内に入ってくる自転車の管理がなかなかうまくいかないための処置なのだろうと想像するが、大学は学生だけでなく一般の人もシンポジウムなどで訪れることは少なくないだろうし、このような処置は果たして合理的なのか疑問だ。
いや、自転車を止められなくなる心配などしなくてもいいかもしれない。構内の自転車をザッと見ただけでもシール無し車両はかなりの数にのぼっているからだ。自転車の整理や撤去をおこなっている係員の人はせいぜい2〜3人しか常駐していないのに、1000台以上はある自転車を仕分けすることなど物理的に不可能である。シールを配るまでは良かったが、その先に管理にまで大学の考えは及んでなかったようだ。
「今後随時撤去します」と書いてあるが、「今後」というのは永遠に訪れないような気がする。そして、明日も私は自転車で大学に行くだろう。
ただ、大家さんが下に住んでいることもあり、昼間もずっと部屋にいるのもどうかなあと思うようになってきて、明るい時間はなるべく外に出るようにしている。こんなことは想定していなかったけれど、居場所が無いというのはなかなか辛い部分も出てくる。だからといって、辞める前に戻りたいなあ、などと思うことも一切ないけれど。
幸いなことに私は、同志社大学の図書館をOBも利用できるため、そこで勉強や読書をしている。自転車に乗って数分で行けるから非常に便利だ。
しかしながら、今年度から少し困ったことが起きている。大学が「自転車入構許可シール」というものを発行したのである。大学のサイトにもPDFで文書が載っていた。
http://www.doshisha.ac.jp/news_contents/attached/2011_bicycle.pdf
私はたまたま大学の壁に貼っていた文書を昨日見つけたのであるが、
「入構許可シールが貼付されていない自転車は今後随時撤去します」
という文を見た時はかなり面食らった。大学構内に入ってくる自転車の管理がなかなかうまくいかないための処置なのだろうと想像するが、大学は学生だけでなく一般の人もシンポジウムなどで訪れることは少なくないだろうし、このような処置は果たして合理的なのか疑問だ。
いや、自転車を止められなくなる心配などしなくてもいいかもしれない。構内の自転車をザッと見ただけでもシール無し車両はかなりの数にのぼっているからだ。自転車の整理や撤去をおこなっている係員の人はせいぜい2〜3人しか常駐していないのに、1000台以上はある自転車を仕分けすることなど物理的に不可能である。シールを配るまでは良かったが、その先に管理にまで大学の考えは及んでなかったようだ。
「今後随時撤去します」と書いてあるが、「今後」というのは永遠に訪れないような気がする。そして、明日も私は自転車で大学に行くだろう。
日垣隆「電子書籍を日本一売ってみたけれど、やっぱり紙の本が好き。」(11年、講談社)
2011年5月31日 読書
今日をもって、部屋に宅配してもらっている新聞を終わりにした。これからまた新聞を購読することは、少なくとも紙の新聞という形では、もうないだろう。今年の4月まで新聞社の子会社で働いていた関係上とらざるをえなかったが、そういう「しがらみ」も無くなったことだし、スッパリと断ち切ったわけだ。
作家•ジャーナリストの日垣隆さんはこれまでの著書や有料メルマガなどで新聞の不毛さを指摘し続けてきた。そして、今年の4月28日(私が前の会社を出た最後の日)に発売された本書はその極めつけとなっている。これを読んでしまったら、もはや新聞の存在意義など吹っ飛んでしまうこと間違いない。本日は私にとっての「新聞購読最期の日」であるため、これを記念して本書を紹介してみたい。
新聞業界の先行きについて書かれた本で、歌川令三「新聞がなくなる日」(05年、草思社)というものがある。これも日垣さんの「すぐに稼げる文章術」(06年、幻冬舎文庫)で紹介されていたものだが、毎日新聞社に長年勤めていた人が新聞業界の過去•現在•未来について論じている。
この本の冒頭で日本の新聞がたどった歴史が触れられている。それによれば日本最古の「日刊新聞」は1830(明治3)年の「横浜毎日新聞」だという。「グーテンベルクの活版印刷術を用いた最古の日刊紙」(本書P.17)だ。ちなみに横浜が新聞誕生の地ということで「日本新聞博物館」が00年10月に設立されている。
我が国における新聞普及の速度はかなり速かった。江戸時代から民衆の識字率は高かったうえに、売り捌き店(新聞販売店)も全国に広がって行く。そして日本独自の新聞経営は20世紀初頭で早くも確立される。きっかけは1904年から05年に起きた日露戦争だった。当時の新聞は戦況を伝える唯一のメディアだったからである。日清戦争から日露戦争までの10年間で新聞の部数は10倍にふくれあがる。
肝心の新聞経営のことだが、当時ですでに以下のようなシステムができあがっている(以下はP.19-20より)。
•部数増のおかげて、個別配達網が確立した。
•月極め読者獲得のための販売合戦が激化した。拡張のためには付録や増ページなど何でもありの企業文化ができ上がった。1907年、時事新報は創刊25周年記念号でページ数が200を超える新聞を発行。この記録はいまだに破られていない。
•手動の平版印刷機の代わりに、輪転機が導入された。
•多色刷りのカラー印刷が始まった。
•広告集めが軌道に乗った(広告代理店「電通」の前身、「日本広告」が1901年に誕生)。
•新聞販売促進策として、美人コンクール、遠泳大会、四国八十八箇所の巡礼競争、全国テニス大会などの事業部門が開設された。
宅配新聞、新聞広告、輪転機にカラー印刷、文化事業など、現在も新聞社でおこなわれている業務の基礎は全てこの時代にできあがっているといえよう。特に新聞業界の安定的な経営の柱となった宅配新聞制度は重要だ。「まだラジオもなかった頃、すでに、世界一の戸別配達制度ができ上がっていた」(P,20)のである。著者はこうした新聞の経営法を「日露戦争式ビジネスモデル」または「20世紀モデル」と称している。
このビジネスモデルはなかなか強固で完成度の高いもので、1950年代にテレビという新たなメディアが登場したときも、その親会社となったり「◯◯新聞」の冠付きのニュースを流したりして、依然マスコミの王者に君臨していた。その間に新聞社で大きな技術革新といえば1980年にコンピューターによる新聞制作技術が開発され、鉛の活字の存在が消えたことだろうか。新聞制作にも「デジタル化」が押し寄せたわけだが、明治以来のビジネスモデルはそれ以外にほとんど変化することがなかった。新聞の経営モデルはそれくらい「凄かった」のである。あくまで過去形ではあるが。
しかしそれに翳りが見えたのは「インターネット元年」と言われた1996年であろう。かくいう私も「インターネット」なるものを触ったのもこの年であった。これを機会に新聞は、いやテレビをはじめ旧来のメディアは軒並み経営が右肩下がりとなっていく。著者が新聞を「20世紀モデル」と表現したのは実に見事というしかない。つまり、21世紀には通用しないものだからである。テレビもラジオもアナログからデジタルに移行しつつある中、新聞だけが取り残されている。かつては強みであった20世紀モデルのあちこちに綻びが出てきているからだ。では、ここからは日垣さんの指摘を紹介しよう。
<新聞業界は落ちるところまで落ちたかに見えるが、違う。さらに深い奈落の底がある。
かつてなら新聞をとらないと恥ずかしい思いをせざるをえない時代があった。けれども、今はそんなことはない。ネットで充分と考える賢明な人が圧倒的になった。
もともと宅配新聞は、自ら新聞を選ぶ頭脳さえ使わない、単なる「習慣だった」と本当のことを言ったのである。
(中略)
私も宅配新聞を読む習慣を経って久しい。新聞は知恵を研鑽する手段としてはもう役割を終えた。
晩酌と等価の習慣にすぎない。>(P.99-100)
宅配新聞は習慣であると喝破したのはさすがだが、私自身を例にすれば「習慣」のレベルにすら至らなかったといえる。毎日届けられる新聞も広げることは滅多にない。そのまま古紙回収に出すか、近所の居酒屋のキッチンに敷かれて活用されるかのどちらかだった。しかしそれでも仕事をするのにほとんど支障がなかった(新聞業界の片隅で働いていたのにもかかわらず!)。また、毎日読んでるからといって仕事ができるというわけでもない、という事実も付け加えておこう。
日垣さんは続ける。
<そもそも新聞は、必要なのだろうか。
いや、実はもう13年ほど前に私の結論は出ている。
必要など、ない。>(P.103)
文章はさらに続く、しかも徹底的に。
<新聞社の方々にお聞きしたい。
なぜ毎日毎日「同じ量のニュース」があるのか。逆に談合による一斉休刊日には、なぜ一行もないのですかねえ。
私も、よく取材されることがある。一昨日も、昨日も、依頼があった。ここのところ7年ほど、新聞社からの取材は原則断っている。
つまらないからだ。
記事もつまらないし、大切なことを、わかりやすく喋っても、新聞記者の多くは、摩訶不思議な教育機関でもあるのか、コメントをつまらなく縮める技に秀でている。
これは大変な技術かもしれない。すごい伝統だ。
間違って数日前、西日本新聞の取材を受けてしまった。テーマがおもしろそうだったからだ。けれども長大な記事を見て、やっぱりこうなるのかと思った。
見事に、つまらないものに化けていたからである。すべて電話かメールの取材だろう。直接合っていたら、ここまで阿呆な記事にはなりえない。なるのかな(笑)
雑誌で酷い取材者もいるけれど、新聞ほどではない。経験上、それは断言できる。>(P.103-104)
<雑誌だった、本だって、つまらないものが多いではないか、という反論もあろうかと思う。
ならば、買わなければいい。
そういうふうになっている。
新聞だけは、宅配制度と、再販制度による景品物量作戦で、かろうじて延命しているにすぎない。>(P.106)
<なぜ新聞各紙の中身が8割方も酷似したものになるかと言えば、昔から「黒板協定」だの「ぶら下がり」だのという各種談合を各社が繰り返してきたからだ。>(P.113)
<満州事変を機にポツダム宣言受諾まで新聞統制が行われ、いわゆる「1県1紙」となったわけだが、この独禁法違反としか思えぬ状況は、今でも維持されている。
重大な、そして恥ずべき既得権益だ。おおむね各県で一つだけの地方紙が独占を未だ継承しているため、地方紙のほうが全国紙より部数の減少が穏やかなのである。>(P.128)
<テレビの凋落が激しいと言われる。しかし、やはり同時にナマで見るという連帯感にかなうものはない。一方、デンマーク戦(引用者注:サッカーW杯南アフリカ大会のこと)翌日の新聞は、日経新聞電子版が5時35分に第一報をブチこめただけで、5時にiPhoneで配信される産経新聞を始め、宅配の全国紙•地方紙は「サッカー」などまるで行われていないかのような紙面作りになっていた。
笑える。
新聞の武器は速報性だったはずだ。そこにテレビがとってかわり、正確性や掘り下げなどが付加価値と胸を張るようになった。だが、何も書けないジレンマに今、何の価値があるというのだろう。>(P.189-190)
引用ばかりで恐縮だが、これだけ読めばもう充分ではないだろうか。私はかつて、新聞をちゃんと読もうと思った時期がないわけではないが、ついに行動に移すことがなかった。それは私自身の怠惰と思っていたけれど、どうやら違っていたようだ。
やはり、新聞の中身が面白くないから。これに尽きる。
そして日垣さんはその理由を余す事無く伝えている。記者クラブや新聞協定や宅配新聞や「1県1紙」などの悪習、その日その日の報告をするだけでデータベースの価値しかない記事内容、そして速報性においても他メディアから大きく遅れを取っている、などなど•••。こんなメディアだから広告だってどんどん離れていく。
私の周囲で新聞を購読している人はほとんどいない。そして私もそこに加わった。しかし、それは当然の結果であろう。
これに対して、新聞業界はこのような指摘に負けることなく、また20世紀の(笑)黄金時代を取り戻すことができるだろうか。私はそう思わないのでこの世界から身を引いたわけである。
たぶん浮上しないだろう。なぜならば、この業界は人的資源も実に乏しいからだ。新聞社の子会社という現場の片隅の片隅にいたから、それは多少はわかる(笑)。
「せめて自分が退職までは大丈夫だろう•••」
そう願って、あれから10年もこの先10年も、新聞業界にしがみつこうとお考えの方には「頑張ってね!」という言葉しか私はもっていない。こういう人は直下型地震が起きても自分だけは無事だと根拠もなく考える人種だから、もはや救う方法はないのである。
それにしても、この本はもっと色々なことが書いてあるのだが、新聞のことに特化してしまった。著者には少し失礼だったかもしれないが、あまりに指摘がすごかったのでご了承いただきたい。
作家•ジャーナリストの日垣隆さんはこれまでの著書や有料メルマガなどで新聞の不毛さを指摘し続けてきた。そして、今年の4月28日(私が前の会社を出た最後の日)に発売された本書はその極めつけとなっている。これを読んでしまったら、もはや新聞の存在意義など吹っ飛んでしまうこと間違いない。本日は私にとっての「新聞購読最期の日」であるため、これを記念して本書を紹介してみたい。
新聞業界の先行きについて書かれた本で、歌川令三「新聞がなくなる日」(05年、草思社)というものがある。これも日垣さんの「すぐに稼げる文章術」(06年、幻冬舎文庫)で紹介されていたものだが、毎日新聞社に長年勤めていた人が新聞業界の過去•現在•未来について論じている。
この本の冒頭で日本の新聞がたどった歴史が触れられている。それによれば日本最古の「日刊新聞」は1830(明治3)年の「横浜毎日新聞」だという。「グーテンベルクの活版印刷術を用いた最古の日刊紙」(本書P.17)だ。ちなみに横浜が新聞誕生の地ということで「日本新聞博物館」が00年10月に設立されている。
我が国における新聞普及の速度はかなり速かった。江戸時代から民衆の識字率は高かったうえに、売り捌き店(新聞販売店)も全国に広がって行く。そして日本独自の新聞経営は20世紀初頭で早くも確立される。きっかけは1904年から05年に起きた日露戦争だった。当時の新聞は戦況を伝える唯一のメディアだったからである。日清戦争から日露戦争までの10年間で新聞の部数は10倍にふくれあがる。
肝心の新聞経営のことだが、当時ですでに以下のようなシステムができあがっている(以下はP.19-20より)。
•部数増のおかげて、個別配達網が確立した。
•月極め読者獲得のための販売合戦が激化した。拡張のためには付録や増ページなど何でもありの企業文化ができ上がった。1907年、時事新報は創刊25周年記念号でページ数が200を超える新聞を発行。この記録はいまだに破られていない。
•手動の平版印刷機の代わりに、輪転機が導入された。
•多色刷りのカラー印刷が始まった。
•広告集めが軌道に乗った(広告代理店「電通」の前身、「日本広告」が1901年に誕生)。
•新聞販売促進策として、美人コンクール、遠泳大会、四国八十八箇所の巡礼競争、全国テニス大会などの事業部門が開設された。
宅配新聞、新聞広告、輪転機にカラー印刷、文化事業など、現在も新聞社でおこなわれている業務の基礎は全てこの時代にできあがっているといえよう。特に新聞業界の安定的な経営の柱となった宅配新聞制度は重要だ。「まだラジオもなかった頃、すでに、世界一の戸別配達制度ができ上がっていた」(P,20)のである。著者はこうした新聞の経営法を「日露戦争式ビジネスモデル」または「20世紀モデル」と称している。
このビジネスモデルはなかなか強固で完成度の高いもので、1950年代にテレビという新たなメディアが登場したときも、その親会社となったり「◯◯新聞」の冠付きのニュースを流したりして、依然マスコミの王者に君臨していた。その間に新聞社で大きな技術革新といえば1980年にコンピューターによる新聞制作技術が開発され、鉛の活字の存在が消えたことだろうか。新聞制作にも「デジタル化」が押し寄せたわけだが、明治以来のビジネスモデルはそれ以外にほとんど変化することがなかった。新聞の経営モデルはそれくらい「凄かった」のである。あくまで過去形ではあるが。
しかしそれに翳りが見えたのは「インターネット元年」と言われた1996年であろう。かくいう私も「インターネット」なるものを触ったのもこの年であった。これを機会に新聞は、いやテレビをはじめ旧来のメディアは軒並み経営が右肩下がりとなっていく。著者が新聞を「20世紀モデル」と表現したのは実に見事というしかない。つまり、21世紀には通用しないものだからである。テレビもラジオもアナログからデジタルに移行しつつある中、新聞だけが取り残されている。かつては強みであった20世紀モデルのあちこちに綻びが出てきているからだ。では、ここからは日垣さんの指摘を紹介しよう。
<新聞業界は落ちるところまで落ちたかに見えるが、違う。さらに深い奈落の底がある。
かつてなら新聞をとらないと恥ずかしい思いをせざるをえない時代があった。けれども、今はそんなことはない。ネットで充分と考える賢明な人が圧倒的になった。
もともと宅配新聞は、自ら新聞を選ぶ頭脳さえ使わない、単なる「習慣だった」と本当のことを言ったのである。
(中略)
私も宅配新聞を読む習慣を経って久しい。新聞は知恵を研鑽する手段としてはもう役割を終えた。
晩酌と等価の習慣にすぎない。>(P.99-100)
宅配新聞は習慣であると喝破したのはさすがだが、私自身を例にすれば「習慣」のレベルにすら至らなかったといえる。毎日届けられる新聞も広げることは滅多にない。そのまま古紙回収に出すか、近所の居酒屋のキッチンに敷かれて活用されるかのどちらかだった。しかしそれでも仕事をするのにほとんど支障がなかった(新聞業界の片隅で働いていたのにもかかわらず!)。また、毎日読んでるからといって仕事ができるというわけでもない、という事実も付け加えておこう。
日垣さんは続ける。
<そもそも新聞は、必要なのだろうか。
いや、実はもう13年ほど前に私の結論は出ている。
必要など、ない。>(P.103)
文章はさらに続く、しかも徹底的に。
<新聞社の方々にお聞きしたい。
なぜ毎日毎日「同じ量のニュース」があるのか。逆に談合による一斉休刊日には、なぜ一行もないのですかねえ。
私も、よく取材されることがある。一昨日も、昨日も、依頼があった。ここのところ7年ほど、新聞社からの取材は原則断っている。
つまらないからだ。
記事もつまらないし、大切なことを、わかりやすく喋っても、新聞記者の多くは、摩訶不思議な教育機関でもあるのか、コメントをつまらなく縮める技に秀でている。
これは大変な技術かもしれない。すごい伝統だ。
間違って数日前、西日本新聞の取材を受けてしまった。テーマがおもしろそうだったからだ。けれども長大な記事を見て、やっぱりこうなるのかと思った。
見事に、つまらないものに化けていたからである。すべて電話かメールの取材だろう。直接合っていたら、ここまで阿呆な記事にはなりえない。なるのかな(笑)
雑誌で酷い取材者もいるけれど、新聞ほどではない。経験上、それは断言できる。>(P.103-104)
<雑誌だった、本だって、つまらないものが多いではないか、という反論もあろうかと思う。
ならば、買わなければいい。
そういうふうになっている。
新聞だけは、宅配制度と、再販制度による景品物量作戦で、かろうじて延命しているにすぎない。>(P.106)
<なぜ新聞各紙の中身が8割方も酷似したものになるかと言えば、昔から「黒板協定」だの「ぶら下がり」だのという各種談合を各社が繰り返してきたからだ。>(P.113)
<満州事変を機にポツダム宣言受諾まで新聞統制が行われ、いわゆる「1県1紙」となったわけだが、この独禁法違反としか思えぬ状況は、今でも維持されている。
重大な、そして恥ずべき既得権益だ。おおむね各県で一つだけの地方紙が独占を未だ継承しているため、地方紙のほうが全国紙より部数の減少が穏やかなのである。>(P.128)
<テレビの凋落が激しいと言われる。しかし、やはり同時にナマで見るという連帯感にかなうものはない。一方、デンマーク戦(引用者注:サッカーW杯南アフリカ大会のこと)翌日の新聞は、日経新聞電子版が5時35分に第一報をブチこめただけで、5時にiPhoneで配信される産経新聞を始め、宅配の全国紙•地方紙は「サッカー」などまるで行われていないかのような紙面作りになっていた。
笑える。
新聞の武器は速報性だったはずだ。そこにテレビがとってかわり、正確性や掘り下げなどが付加価値と胸を張るようになった。だが、何も書けないジレンマに今、何の価値があるというのだろう。>(P.189-190)
引用ばかりで恐縮だが、これだけ読めばもう充分ではないだろうか。私はかつて、新聞をちゃんと読もうと思った時期がないわけではないが、ついに行動に移すことがなかった。それは私自身の怠惰と思っていたけれど、どうやら違っていたようだ。
やはり、新聞の中身が面白くないから。これに尽きる。
そして日垣さんはその理由を余す事無く伝えている。記者クラブや新聞協定や宅配新聞や「1県1紙」などの悪習、その日その日の報告をするだけでデータベースの価値しかない記事内容、そして速報性においても他メディアから大きく遅れを取っている、などなど•••。こんなメディアだから広告だってどんどん離れていく。
私の周囲で新聞を購読している人はほとんどいない。そして私もそこに加わった。しかし、それは当然の結果であろう。
これに対して、新聞業界はこのような指摘に負けることなく、また20世紀の(笑)黄金時代を取り戻すことができるだろうか。私はそう思わないのでこの世界から身を引いたわけである。
たぶん浮上しないだろう。なぜならば、この業界は人的資源も実に乏しいからだ。新聞社の子会社という現場の片隅の片隅にいたから、それは多少はわかる(笑)。
「せめて自分が退職までは大丈夫だろう•••」
そう願って、あれから10年もこの先10年も、新聞業界にしがみつこうとお考えの方には「頑張ってね!」という言葉しか私はもっていない。こういう人は直下型地震が起きても自分だけは無事だと根拠もなく考える人種だから、もはや救う方法はないのである。
それにしても、この本はもっと色々なことが書いてあるのだが、新聞のことに特化してしまった。著者には少し失礼だったかもしれないが、あまりに指摘がすごかったのでご了承いただきたい。
新作発売も来日公演も来日公演中止も、全く知りませんでした
2011年5月12日 音楽知り合いと飲んでいた時に、最近CDをほとんど買っていないことにふと気づいた。
新作だったら渡辺美里、BONNIE PINK、eastern youthといった自分にとって特別なミュージシャンを必ず買うくらいである。昔のCDにいたっては、ブックオフなどはよく足を運ぶものの買うのはもっぱら書籍だ。
時代をさかのぼってみると、よくCDを買っていたのは高校生から01年くらいまでの時期だったと思う。01年は私が社会を出た年である。そして仕事をするようになってからはライブに行く機会が飛躍的に多くなっていった。それは自由に使えるお金が増えたためだろうが、普通は社会に出ると忙しくなってライブなどには行けなくなるという人のほうが多いだろう。我ながらおかしな人生を送っている気がする。
CDを買わなくなった理由は色々あるけれど、
「たくさん音楽を聴いたからといって必ずしも幸せになれるわけでもないし、人間性が良くなるわけでもないんだな」
と悟ったのがやはり大きかった。たくさんのCDやライブに接しているであろう音楽ライターと言われる人たちの末路を見ていると、そういう気持ちになってしまうのは仕方ない。また、正式に数えてはいないが、私の部屋には600枚くらいはCDがあるので、これをたらい回しに聴いていっても死ぬまで退屈することは無いに違いない。いずれにしても、私にとってCDとか音楽はそれなりに満ち足りている状態になっているのだろう。
ただ、音楽雑誌を読むなど情報を入れるのを怠っていると、好きなミュージシャンが来日しているのを見落とす場合も出てくることがある。今日「ミュージック・マガジン」5月号のライブ情報のページをめくったら「リチャード・トンプソン」という名前を見つけて、
「しまった!全く知らなかった!」
とガックリ肩を落とした。大阪公演は「4月23日」のビルボードライブ大阪となっていた。もう少し早くこの情報を知っていたら絶対に行っていたのに・・・。
さきほどの話に戻るが、CDを買わなくなるのに反比例してライブへ行くようになったのは、やはり、
「これを見逃したらもう二度と観られないだろうな」
という思いが頭をよぎってしまうからだろう。よって、たいして興味もないミュージシャンでも一回くらいは見ておいたほうが良いかなとチケットを買ってライブ会場に足を運んだものだ。私が観た人で鬼籍に入ったのはジェイムス・ブラウンくらいだと思うが、あと20年もすれば多くのミュージシャンは・・・という感じである。
ただ、凄いとか感動したとかいう内容のライブにはなかなか出会えないのが正直な感想だ。ポッと出のミュージシャンなどほとんど観ないので大ハズレのライブというのもほとんど記憶にないが、まあこんなもんかな、というのが大半である。しかし、10年前(01年2月24日、心斎橋クラブクアトロ)に観たリチャード・トンプソンのライブは間違いなく「凄い!」と人に言いふらせるものだった。トンプソンがエレアコ一本を抱えるのみという一見寂しそうな編成だったが、一人で3人は演奏している姿は素人目でも驚異的だった。最前列で観たあのトンプソンの勇姿をもう一度とずっと思っていた、のだったが。
せめて演奏曲目でも知りたいと思った私は、mixiのコミュニティをたどってみた。コミュニティの参加人数は300人足らずである。少ないなあ。しかし来日直後だし盛り上がっていることだろう、と最初は思ったが、ライブ情報らしきものが載っていない。いくつかのトピックを調べみると、驚愕の事実が判明した。
震災の影響で、来日が取りやめになっていたのだ。あららららぁ。
そういえば01年の時、トンプソンはタバコが嫌いなので吸わないでください、というようなアナウンスが流れていたことを思い出した。タバコの煙すら嫌がるほど神経質な人だから、放射能の漏れている国に足を踏み入れるなど論外だったんだろうなあ。
それはともかく、トンプソンの公式サイトでは来年に来日公演を再調整をしているという話も出ているという。私はすぐさま2012年に備えてトンプソンのコミュニティに入ることにした。これで来日情報を見失うこともないだろう。
トンプソンの情報といえば、3年ぶりの新作「ドリーム・アティック」(10年)が出ているのも知らなかった。国内盤も出ているようだし、見つけたら買っておきたい。これを聴きながら、来日公演を待とう。
京都中央卸売第一市場にて
2011年5月7日
今日は京都中央卸売第一市場が一般開放され「京朱雀市場 食彩市」を開催していると聞いて、普段は入れない場所を見れる貴重な機会でもあるし自転車で足を運んでみた。
魚介類の売っているところが面白そうかなと向かってみたが、最初はその臭いが鼻につく。小さい時は市場や海岸もけっこう行っていたため気にならなかったけれど、そういう場所に通わなくなると臭いに免疫がなくなる。そういえば何年か前、小さなカエルを見つけた時にパッと捕まえようとしたら、ヌルヌルした感触が気持ち悪くてすぐ手放したことを思い出す。カエルも小さい時はよく取ったり触ったりしていて平気だったのだが。
それはともかく、市場で売っているものは全く違っているものが多くて興味深い。写真は見ての通りマグロであるが、そのそばには解体した後の骨が置いてある(写真の上部に少し映っている)。いわゆる「中落ち」という部分であるが、その骨の回りには身がビッシリと付いている。それをそぎ落としたのがネギトロになる。マグロ自体があれだけ大きいからネギトロもそれなりの量が取れるのだなあと、実際に見て気づくことがある。
他にも生のホッケ(スーパーなどでは開きしか置いてない)など珍しいものを見かけたが、一番おどろいたのは1メートルほどあるハモだった。あんなに大きかったら煮るのも無理だし、落としハモも無理ではないだろうか。どうやって調理するのか、そもそも買い手がつくのかも疑問である。ちなみに価格は「3500円」だった。これは果たして安いのか、それとも高いのか。
魚介類の売っているところが面白そうかなと向かってみたが、最初はその臭いが鼻につく。小さい時は市場や海岸もけっこう行っていたため気にならなかったけれど、そういう場所に通わなくなると臭いに免疫がなくなる。そういえば何年か前、小さなカエルを見つけた時にパッと捕まえようとしたら、ヌルヌルした感触が気持ち悪くてすぐ手放したことを思い出す。カエルも小さい時はよく取ったり触ったりしていて平気だったのだが。
それはともかく、市場で売っているものは全く違っているものが多くて興味深い。写真は見ての通りマグロであるが、そのそばには解体した後の骨が置いてある(写真の上部に少し映っている)。いわゆる「中落ち」という部分であるが、その骨の回りには身がビッシリと付いている。それをそぎ落としたのがネギトロになる。マグロ自体があれだけ大きいからネギトロもそれなりの量が取れるのだなあと、実際に見て気づくことがある。
他にも生のホッケ(スーパーなどでは開きしか置いてない)など珍しいものを見かけたが、一番おどろいたのは1メートルほどあるハモだった。あんなに大きかったら煮るのも無理だし、落としハモも無理ではないだろうか。どうやって調理するのか、そもそも買い手がつくのかも疑問である。ちなみに価格は「3500円」だった。これは果たして安いのか、それとも高いのか。
このコンサートの案内が届いた時(1月)は行くつもりはなかった。仕事で疲弊してライブに行く余裕がなかったし、コンサートの内容自体にも興味がなかったからである。それから紆余曲折があって、10年ほどいた職場を4月で去ることになった。実は会社を辞める日についても、当初は4月に決めていたわけではない。個人的には6月いっぱいにしたかったのだが、会社とのやり取りの過程で4月までということに落ち着いたのである。今日のチケットを取ったのはそれからのことだった。
図らずもこのような日に渡辺美里が大阪でコンサートをするというのは、自分と何か因縁があるのかなと思ってしまう。私は信心深い人間でないし、日頃も運だの縁だのといったものを意識しているわけではない。しかし、これは俺を送別するために開催してくれるのかなと、勝手に解釈して大阪へ向かう。
会場のザ・シンフォニーホールはJR福島駅から北へ徒歩7分ほどにある。
http://www.asahi.co.jp/symphony/
周囲の飲食店では、シンフォニーホールのチケット提示でサービス、うんぬんの張り紙がしてある。餃子の「みんみん」(漢字が出ない)は杏仁豆腐を無料で食べられるという。杏仁豆腐かあ。月餅か芝麻球(チーマーカオ)だったら入ったかもしれないが。
私の席は2階の右側だったが客席からステージがものすごく近く感じる。席数が1704と後からサイトで知って少し驚いた。実際に観た限りではかなりこじんまりとした会場だったからだ。お客の入りが7割くらいとしても、1000人以上は入ったことになる。思いのほか集まったな、というのが正直な感想だ。
ところで、純粋なオーケストラをバックに彼女が歌うツアーはこれが初めてのことである。最初の「misato ’99 うたの木 春」(99年)の時も、それ以後の「うたの木」シリーズでも、通常のバンドが混ざっているという奇妙な編成だった。そもそも「うたの木」シリーズは、「アコースティック」と冠したライブでエレキギターや打ち込みが出てくるなど理解不能な内容が多い。先日アルバム「BIG WAVE」(93年)に書いた時にも触れたけれど、彼女が新しいチャレンジをしてみてもほとんど成果を挙げていない。「うたの木」と題したライブを私はたぶん全て観たけれど、全体的に中途半端な内容で終始している。ネットで感想を調べても散々なことが書かれていると思う。
当然ながら、この日のチケットも売り切れてはいなかった。8500円という通常より高い設定でしかも内容も中途半端なものとわかっている賢明なファンならば買わないだろう。当の私も、もう「うたの木」でオーケストラは行かなくてもいいかな、と思っていたのだし。
コンサートはほぼ時間通りに始まった。冒頭はいきなり”My Revolution~第2章~”だったが、イントロだけで終わり童謡の”ふるさと”、そして大江千里のバージョンに近い”10 years”という、いかにも「うたの木」シリーズらしい、ガックリくるような始まり方だった。今回も厳しい内容になりそうだな、という思いが頭をよぎる。
演奏曲目は下に記すけれど、「行かなければ損をしていた!」という瞬間はやはりなかった。今回のツアーでしか聴けないような珍しい曲もいっさいない。敢えていてば、ルイ・アームストロングの”What A Wonderful World”は初めて披露したかもしれない。
個人的には”PAJAMA TIME”が歌われたのが唯一嬉しかったことか。しかし”PAJAMA TIME”にしても12年前に「うたの木」で披露しているから、想定内といえば想定内だが、大好きな曲なので私の餞(はなむけ)だと勝手に思ってみた。
身もふたもないことを言わせてもらえば、あえてオーケストラでする必要があるのか?という疑問は拭えない。どの曲も通常のバンド演奏の方がずっと良いのは間違いないだろう。もちろんファンもオーケストラとの共演などを望んでいる人はいないと確信している。いくら熱心なヲタでも信者でも、この一連の「うたの木」シリーズに付き合うのは苦痛だったのでないかと、自分を照らし合わせてつくづく感じる。
かと思いきゃ、アンコール時に、
「みさとぉ、”Life”を歌ってくださぁい」
と言って会場からヒンシュクを買う逞しいヲタがいるのには恐れ入った。確かコイツは去年も大阪で同じようなことを言った気がする。その時もこの日も当の美里は冷たくあしらっていたが。それにしても”Life”(96年のアルバム「Spirits」に入っている曲)なんて、本人に直接リクエストするほど聴きたい曲なのだろうか。実に不思議だ。
そんなこともありながら、2時間半ほどでコンサートは終了した。何か感慨深い気持ちになり涙でも出るかなと間抜けた思いもよぎったが、「うたの木」の内容ではそれは無理だろうとつくづく感じる。ただ、俺のためにこの日に大阪に来てくれてありがとう、と心の中で一方的にお礼を言って会場を去った。
次に彼女と会うのは8月6日の大阪城野外音楽堂だろうか。これも行く気が起きてなかったものの、全てから解放された今となっては「やっぱり行こうかな」という気持ちになりつつある。
【演奏曲目】
(1)My Revolution~第2章~(イントロのみ)/ふるさと(童謡)
(2)10 years
(3)あしたの空
(4)さくらの花の咲くころに
(5)ココロ銀河
(6)シンシアリー
(7)PAJAMA TIME
(8)My Love Your Love(たったひとりしかいない あなたへ)
<15分の休憩>
(9)What A Wonderful World(ルイ・アームストロングのカバー)
(10)My Revolution
(11)すき
(12)パイナップル ロマンス
(13)ジャングルチャイルド
(14)いつかきっと
(15)始まりの詩、あなたへ
<アンコール>
(16)Lovin’ you
(17)サンキュ
図らずもこのような日に渡辺美里が大阪でコンサートをするというのは、自分と何か因縁があるのかなと思ってしまう。私は信心深い人間でないし、日頃も運だの縁だのといったものを意識しているわけではない。しかし、これは俺を送別するために開催してくれるのかなと、勝手に解釈して大阪へ向かう。
会場のザ・シンフォニーホールはJR福島駅から北へ徒歩7分ほどにある。
http://www.asahi.co.jp/symphony/
周囲の飲食店では、シンフォニーホールのチケット提示でサービス、うんぬんの張り紙がしてある。餃子の「みんみん」(漢字が出ない)は杏仁豆腐を無料で食べられるという。杏仁豆腐かあ。月餅か芝麻球(チーマーカオ)だったら入ったかもしれないが。
私の席は2階の右側だったが客席からステージがものすごく近く感じる。席数が1704と後からサイトで知って少し驚いた。実際に観た限りではかなりこじんまりとした会場だったからだ。お客の入りが7割くらいとしても、1000人以上は入ったことになる。思いのほか集まったな、というのが正直な感想だ。
ところで、純粋なオーケストラをバックに彼女が歌うツアーはこれが初めてのことである。最初の「misato ’99 うたの木 春」(99年)の時も、それ以後の「うたの木」シリーズでも、通常のバンドが混ざっているという奇妙な編成だった。そもそも「うたの木」シリーズは、「アコースティック」と冠したライブでエレキギターや打ち込みが出てくるなど理解不能な内容が多い。先日アルバム「BIG WAVE」(93年)に書いた時にも触れたけれど、彼女が新しいチャレンジをしてみてもほとんど成果を挙げていない。「うたの木」と題したライブを私はたぶん全て観たけれど、全体的に中途半端な内容で終始している。ネットで感想を調べても散々なことが書かれていると思う。
当然ながら、この日のチケットも売り切れてはいなかった。8500円という通常より高い設定でしかも内容も中途半端なものとわかっている賢明なファンならば買わないだろう。当の私も、もう「うたの木」でオーケストラは行かなくてもいいかな、と思っていたのだし。
コンサートはほぼ時間通りに始まった。冒頭はいきなり”My Revolution~第2章~”だったが、イントロだけで終わり童謡の”ふるさと”、そして大江千里のバージョンに近い”10 years”という、いかにも「うたの木」シリーズらしい、ガックリくるような始まり方だった。今回も厳しい内容になりそうだな、という思いが頭をよぎる。
演奏曲目は下に記すけれど、「行かなければ損をしていた!」という瞬間はやはりなかった。今回のツアーでしか聴けないような珍しい曲もいっさいない。敢えていてば、ルイ・アームストロングの”What A Wonderful World”は初めて披露したかもしれない。
個人的には”PAJAMA TIME”が歌われたのが唯一嬉しかったことか。しかし”PAJAMA TIME”にしても12年前に「うたの木」で披露しているから、想定内といえば想定内だが、大好きな曲なので私の餞(はなむけ)だと勝手に思ってみた。
身もふたもないことを言わせてもらえば、あえてオーケストラでする必要があるのか?という疑問は拭えない。どの曲も通常のバンド演奏の方がずっと良いのは間違いないだろう。もちろんファンもオーケストラとの共演などを望んでいる人はいないと確信している。いくら熱心なヲタでも信者でも、この一連の「うたの木」シリーズに付き合うのは苦痛だったのでないかと、自分を照らし合わせてつくづく感じる。
かと思いきゃ、アンコール時に、
「みさとぉ、”Life”を歌ってくださぁい」
と言って会場からヒンシュクを買う逞しいヲタがいるのには恐れ入った。確かコイツは去年も大阪で同じようなことを言った気がする。その時もこの日も当の美里は冷たくあしらっていたが。それにしても”Life”(96年のアルバム「Spirits」に入っている曲)なんて、本人に直接リクエストするほど聴きたい曲なのだろうか。実に不思議だ。
そんなこともありながら、2時間半ほどでコンサートは終了した。何か感慨深い気持ちになり涙でも出るかなと間抜けた思いもよぎったが、「うたの木」の内容ではそれは無理だろうとつくづく感じる。ただ、俺のためにこの日に大阪に来てくれてありがとう、と心の中で一方的にお礼を言って会場を去った。
次に彼女と会うのは8月6日の大阪城野外音楽堂だろうか。これも行く気が起きてなかったものの、全てから解放された今となっては「やっぱり行こうかな」という気持ちになりつつある。
【演奏曲目】
(1)My Revolution~第2章~(イントロのみ)/ふるさと(童謡)
(2)10 years
(3)あしたの空
(4)さくらの花の咲くころに
(5)ココロ銀河
(6)シンシアリー
(7)PAJAMA TIME
(8)My Love Your Love(たったひとりしかいない あなたへ)
<15分の休憩>
(9)What A Wonderful World(ルイ・アームストロングのカバー)
(10)My Revolution
(11)すき
(12)パイナップル ロマンス
(13)ジャングルチャイルド
(14)いつかきっと
(15)始まりの詩、あなたへ
<アンコール>
(16)Lovin’ you
(17)サンキュ
日垣隆「折れそうな心の鍛え方」(09年。幻冬舎新書)
2011年4月27日 読書
作家・ジャーナリストの日垣隆さんは、その徹底的な取材と緻密な構成で知られている。その文章は素人目からすれば、どうやったらここまで調べられるのか想像もつかないほどクオリティが高い。またむやみに「批判」をしてきた相手に対してはコッパミジンに叩き潰すことでも有名だ。また、その行動力もずば抜けており、先月はリビア、そして震災後の東北地方など誰も行きたがらない(行けそうにない)場所も取材してきた。
パッと見る限りは相当にタフな精神と体の持ち主に見える日垣さんであるが、いまから5年前(06年)に「ウツ」に襲われる。その25年前にも経験しているというから2度目のウツだ。
しかし通常ならば精神科医に相談するところだが、日垣さんは医者やクスリに頼らず「ウツ」と戦うという選択をする。それはなぜか。
<ウツ病は英語でdepression、不況にも同じ言葉が使われています。
「不況」という概念は、市場経済が成立した近代以降にできあがったものです。「ウツ」も近代の成立に伴って、「ウツ病」という病気になりました。
「病気」は医者によって「発見」され、「ラベリング」されて誕生します。診断して処方することが医療関係者の「フレームワーク」ですから、当然の話です。>(P.18)
<そもそもウツ病かどうかは、医者が一方的に決めつけるにすぎません。>(P.10)
ちなみに、「落ち込みの症状が2週間続けば、ウツ病として判断してよい」ことになっているという。
ここで注意をしなければならないのは、日垣さんが戦ったのは「ウツ病」ではなく「ウツ」ということだ。誰が見ても病気という状態ならば即刻医者と相談しなければならないだろうが、「ウツ」はその病気か病気でないかの境界線上にある状態といえる。
<例えば悲しい出来事に見舞われ、ひどいショックを受け、しばらくの間、ろくに食べられない、眠れない人がいても、それはごく自然な感情の発露だと私は思います。
落ち込みからウツ状態までの微妙なグラデーションは、もしかすると人間の精神の正常なありかたかもしれないのです。>(P.11)
「ウツ病」になったことがない人(私もそうだ)も、上のような前段階を過去に経験した人がほとんどではないだろうか。また、それが人間であろう。
<本書で言うところの「ウツ」は、日常的な「落ち込み」の連続線上にあり、「ウツ病」とは一線を画すものです。
誰もがウツになるのでしょうか?ーそういうわけでは、もちろんありません。
では、誰もがなりうるのか?ーもちろん、そうです。
ウツを確実に避ける方法はあるのでしょうか?ーそんなものは、ないと思います。>(P.13)
<ウツの原因は、言ってみればインフルエンザ・ウイルスのようなもので、いつ何時、誰が罹患するかわからないほど日常に溢れています。インフルエンザに限らず、ウイルスは常に変異しますから、100パーセント完璧な予防ワクチンというものはありません。>(P.14)
本書は、日垣さんが自分がウツから立ち直った経験をもとに、50のノウハウが紹介されている。その中でも「これが肝心」と思った箇所は、たとえばストレスの定義が三者三様(例えばシイタケは私にとってストレスになる)であるように、「ウツ」の原因となるものも人によって違うということだ。
<これはおそらく、人は誰でも、強さと弱さがまだらに存在するとは、人それぞれ「このポイントには強いが、このポイントには弱い」という、ダメージ・パターンがあるということ。
(中略)
心を鍛えるには、どんなことで折れやすいか、自分のダメージ・パターンを知り、そこを補強するトレーニングをしていくのがいいでしょう。>(P.31)
ウツの原因も人それぞれならば、その対処法も人によって個々に違ってくるのは道理である。となれば結局のところ、家族や友人や医者の協力を得るとしても、ウツを克服できるかどうかは自分しだいということになるかもしれない。
「ウツ」の予防については、
<一番良い「予防」とは、栄養をとり、日々、体を鍛えておくことです。>(P.14)
と書いている。月並みな話になるが、日々の生活を大切にし、自分の弱いところなどを把握していくことが最も確実な予防法になるのだろう。
現時点では、自分がウツのなりそうな兆候は全くない。ただ、これから生きてくなかでウツに近い状態になることも出てくる可能性は否定できない。周囲の友人にもそんな人が出てくることだってあるだろう。最悪な状態になった時のことを頭に入れておくことは思いのほか重要なことだ。この本を読みながら、そんなことをつくづく思った。
今回、自分は人生の節目になったこともあり、この日記を読んでいる方すべての人にこの本を捧げたい。もし気持ちが落ち込みそうになった時、必ず役立つ部分が本書にはたくさん詰まっているからだ。
皆さんの今後のご健勝を祈りたい。
パッと見る限りは相当にタフな精神と体の持ち主に見える日垣さんであるが、いまから5年前(06年)に「ウツ」に襲われる。その25年前にも経験しているというから2度目のウツだ。
しかし通常ならば精神科医に相談するところだが、日垣さんは医者やクスリに頼らず「ウツ」と戦うという選択をする。それはなぜか。
<ウツ病は英語でdepression、不況にも同じ言葉が使われています。
「不況」という概念は、市場経済が成立した近代以降にできあがったものです。「ウツ」も近代の成立に伴って、「ウツ病」という病気になりました。
「病気」は医者によって「発見」され、「ラベリング」されて誕生します。診断して処方することが医療関係者の「フレームワーク」ですから、当然の話です。>(P.18)
<そもそもウツ病かどうかは、医者が一方的に決めつけるにすぎません。>(P.10)
ちなみに、「落ち込みの症状が2週間続けば、ウツ病として判断してよい」ことになっているという。
ここで注意をしなければならないのは、日垣さんが戦ったのは「ウツ病」ではなく「ウツ」ということだ。誰が見ても病気という状態ならば即刻医者と相談しなければならないだろうが、「ウツ」はその病気か病気でないかの境界線上にある状態といえる。
<例えば悲しい出来事に見舞われ、ひどいショックを受け、しばらくの間、ろくに食べられない、眠れない人がいても、それはごく自然な感情の発露だと私は思います。
落ち込みからウツ状態までの微妙なグラデーションは、もしかすると人間の精神の正常なありかたかもしれないのです。>(P.11)
「ウツ病」になったことがない人(私もそうだ)も、上のような前段階を過去に経験した人がほとんどではないだろうか。また、それが人間であろう。
<本書で言うところの「ウツ」は、日常的な「落ち込み」の連続線上にあり、「ウツ病」とは一線を画すものです。
誰もがウツになるのでしょうか?ーそういうわけでは、もちろんありません。
では、誰もがなりうるのか?ーもちろん、そうです。
ウツを確実に避ける方法はあるのでしょうか?ーそんなものは、ないと思います。>(P.13)
<ウツの原因は、言ってみればインフルエンザ・ウイルスのようなもので、いつ何時、誰が罹患するかわからないほど日常に溢れています。インフルエンザに限らず、ウイルスは常に変異しますから、100パーセント完璧な予防ワクチンというものはありません。>(P.14)
本書は、日垣さんが自分がウツから立ち直った経験をもとに、50のノウハウが紹介されている。その中でも「これが肝心」と思った箇所は、たとえばストレスの定義が三者三様(例えばシイタケは私にとってストレスになる)であるように、「ウツ」の原因となるものも人によって違うということだ。
<これはおそらく、人は誰でも、強さと弱さがまだらに存在するとは、人それぞれ「このポイントには強いが、このポイントには弱い」という、ダメージ・パターンがあるということ。
(中略)
心を鍛えるには、どんなことで折れやすいか、自分のダメージ・パターンを知り、そこを補強するトレーニングをしていくのがいいでしょう。>(P.31)
ウツの原因も人それぞれならば、その対処法も人によって個々に違ってくるのは道理である。となれば結局のところ、家族や友人や医者の協力を得るとしても、ウツを克服できるかどうかは自分しだいということになるかもしれない。
「ウツ」の予防については、
<一番良い「予防」とは、栄養をとり、日々、体を鍛えておくことです。>(P.14)
と書いている。月並みな話になるが、日々の生活を大切にし、自分の弱いところなどを把握していくことが最も確実な予防法になるのだろう。
現時点では、自分がウツのなりそうな兆候は全くない。ただ、これから生きてくなかでウツに近い状態になることも出てくる可能性は否定できない。周囲の友人にもそんな人が出てくることだってあるだろう。最悪な状態になった時のことを頭に入れておくことは思いのほか重要なことだ。この本を読みながら、そんなことをつくづく思った。
今回、自分は人生の節目になったこともあり、この日記を読んでいる方すべての人にこの本を捧げたい。もし気持ちが落ち込みそうになった時、必ず役立つ部分が本書にはたくさん詰まっているからだ。
皆さんの今後のご健勝を祈りたい。
岩明均「ヒストリエ(1)」 (04年。アフタヌーンKC)
2011年4月24日 読書
日本が誇る文化はマンガとアニメだけ、と外国から揶揄されていると聞いたことがある。日本人から見れば「それはあんまりでは」と思う一方、マンガやアニメについては少なくとも世界水準の評価を受けていると喜んでいいのかもしれない。
そんな日本に住んでいながら、私自身はそれほどマンガを読んできたとはいいがたい。パッと思い浮かぶ作品も数える程度なのでマンガ経験は全く乏しいといえる。ブックオフなどを覗いてみれば置いてあるマンガの数は凄まじい。それを見るだけで、もう圧倒される。そんな感じの人間なのでこれから読むであろうマンガの数もそれほど増えない気がする。
こんな人間が新しいマンガに出会うためには、さまざまな偶然が絡まり合わないと起こらない。この「ヒストリエ」を見つけたのは、京都市中京区にある「京都国際マンガミュージアム」の「マンガの壁」(自由に読めるマンガが並んでいる棚)においてであった。そこにあった1巻と2巻を読んだのが運の尽きである。すっかりその世界にハマってしまい、古本屋で4巻まで集め、手に入らなかった5巻は書店で新刊を購入した。6巻(10年)にいたっては発売日にすぐ買ってしまう。発売されたその日にマンガを買ったのは西原理恵子「ぼくんち」3巻(98年)以来、実に12年ぶりの出来事であった。
「ヒストリエ」は2003年より月刊誌「アフターヌーン」にて連載している作品で、これまで単行本は現在6巻まで出ており、現在も継続中だ。昨年(10年には第14回文化庁メディア芸術祭マンガ部門の大賞を受賞している。
作者の岩明均氏の代表作といえば、第17回講談社漫画賞や第27回星雲賞コミック部門を受賞した「寄生獣」(全10巻。アフタヌーンKC)になるだろうが、これまで出した作品は「七夕の国」(全4巻。ビッグコミックス)や「雪の峠・剣の舞」(KCDX)など数えるほどしかないので、興味があればぜひ他の作品も揃えてもらえたらと思う。
そんな寡作の岩明氏が漫画家としてデビューする前から構想していたのがこの「ヒストリエ」だ。あまり作品の中身について細かく書くのは読んでいない人に対して気が引けるので、支障のない範囲で紹介してみたい。
物語は紀元前343年のペルシア帝国までさかのぼる。哲学者アリストテレスがスパイ容疑で帝国から追われている途中、海岸で一人の蛮人(バルバロイ)と出会う。バルバロイとはギリシア人が他民族に対して付けた蔑称のことだ。ギリシア人は彼らの言語が理解できず「バルバル」と言っているように聞こえたため、バルバロイと名付けたと言われている。
このバルバロイこそ、物語の主人公のエウメネスである。エウメネスは蛮人でありながら歴史家ヘロドトスの書を読んだことがあるなど身分不相応に博識の持ち主だった。そんな二人は紆余曲折あって海峡を渡り、アテネの植民市であるカルディアに辿り着く。そこはエウメネスの故郷だった。そして物語はエウメネスの幼少時代へとさらに時代をさかのぼる。当時のエウメネスは奴隷商ヒエロニュモス家の子どもという非常に裕福な貴族の身分だった。そんな彼が何をきっかけに蛮人の身分へと身を落とすことになるのだろうか。それは単行本の2巻まで読み進めればひとまず明らかにはなる。
歴史を題材にした作品というのはマンガに限らず小説ですら読んだことがないし、そもそも私は歴史自体が苦手である。そんな人間がどうしてこのマンガにハマってしまったのか、非常に不思議な話である。自分なりに色々と分析してみたけれど、やはり作品の読みやすさというか入りやすさが最も大きな要因ではないかと今は結論づけている。なにしろアレキサンダー大王が生きていた時代の人物を、現代の私たちが違和感なく受け入れられる物語の構成には、パッと読んでいる時は実感できないが、よくよく考えてみれば凄いことである。
この作品は自由市民と奴隷の関係という現代の私たちの価値観では理解できない世界も登場する。この時代は奴隷の存在が当たり前であり、ご存知のように家畜並みの扱いをされていた。それゆえに働かなくてよい自由市民が余った時間で学問や芸術を発達させてきたわけだが(アリストテレスもその一人である)、こうした世界を実に平易に表現をしているところに作者の力量を感じさせる。また、物語を読み進めていくほど随所に細かい配慮(言葉の訛りとか、剣を差す位置とか)が見られ、どうしたらこんな描写を思いつくのか?と、私の頭の中で考えても出てくるわけないのに、次々と疑問が湧いてくる。
そもそもの話、エウメネスは実在の人物ではあるものの、その前半生についてほとんど資料らしきものが残されていない。よって、この頃の話(単行本でいえば1巻から5巻)はほとんど作者の想像力で構築された世界ということになる。そんなことまで考えると、人間の頭の中でここまでできるのかと目眩いがする思いだ。
あまりに面白かったので思わず周囲の知人に貸したりしてみたが、今のところおおむね好評であった。よって、この作品の面白さはそれなりに普遍的なものがあると勝手に解釈している。
作中でエウメネスは、
「お前も本当は戦より、『地球』の裏側を見てみたいのであろう?」(5巻のP.104)
と言われる場面がある。喜ばしいことにこの時代を生きる私たちには、エウメネスが果たして「地球の裏側」まで辿り着けるのどうかを同時代で確認できる楽しみが残されている(まだ連載中だから)。いまからでも過去の作品を追いかけても全く遅くはない。未読の人には是非そこのところを強調したい。
そんな日本に住んでいながら、私自身はそれほどマンガを読んできたとはいいがたい。パッと思い浮かぶ作品も数える程度なのでマンガ経験は全く乏しいといえる。ブックオフなどを覗いてみれば置いてあるマンガの数は凄まじい。それを見るだけで、もう圧倒される。そんな感じの人間なのでこれから読むであろうマンガの数もそれほど増えない気がする。
こんな人間が新しいマンガに出会うためには、さまざまな偶然が絡まり合わないと起こらない。この「ヒストリエ」を見つけたのは、京都市中京区にある「京都国際マンガミュージアム」の「マンガの壁」(自由に読めるマンガが並んでいる棚)においてであった。そこにあった1巻と2巻を読んだのが運の尽きである。すっかりその世界にハマってしまい、古本屋で4巻まで集め、手に入らなかった5巻は書店で新刊を購入した。6巻(10年)にいたっては発売日にすぐ買ってしまう。発売されたその日にマンガを買ったのは西原理恵子「ぼくんち」3巻(98年)以来、実に12年ぶりの出来事であった。
「ヒストリエ」は2003年より月刊誌「アフターヌーン」にて連載している作品で、これまで単行本は現在6巻まで出ており、現在も継続中だ。昨年(10年には第14回文化庁メディア芸術祭マンガ部門の大賞を受賞している。
作者の岩明均氏の代表作といえば、第17回講談社漫画賞や第27回星雲賞コミック部門を受賞した「寄生獣」(全10巻。アフタヌーンKC)になるだろうが、これまで出した作品は「七夕の国」(全4巻。ビッグコミックス)や「雪の峠・剣の舞」(KCDX)など数えるほどしかないので、興味があればぜひ他の作品も揃えてもらえたらと思う。
そんな寡作の岩明氏が漫画家としてデビューする前から構想していたのがこの「ヒストリエ」だ。あまり作品の中身について細かく書くのは読んでいない人に対して気が引けるので、支障のない範囲で紹介してみたい。
物語は紀元前343年のペルシア帝国までさかのぼる。哲学者アリストテレスがスパイ容疑で帝国から追われている途中、海岸で一人の蛮人(バルバロイ)と出会う。バルバロイとはギリシア人が他民族に対して付けた蔑称のことだ。ギリシア人は彼らの言語が理解できず「バルバル」と言っているように聞こえたため、バルバロイと名付けたと言われている。
このバルバロイこそ、物語の主人公のエウメネスである。エウメネスは蛮人でありながら歴史家ヘロドトスの書を読んだことがあるなど身分不相応に博識の持ち主だった。そんな二人は紆余曲折あって海峡を渡り、アテネの植民市であるカルディアに辿り着く。そこはエウメネスの故郷だった。そして物語はエウメネスの幼少時代へとさらに時代をさかのぼる。当時のエウメネスは奴隷商ヒエロニュモス家の子どもという非常に裕福な貴族の身分だった。そんな彼が何をきっかけに蛮人の身分へと身を落とすことになるのだろうか。それは単行本の2巻まで読み進めればひとまず明らかにはなる。
歴史を題材にした作品というのはマンガに限らず小説ですら読んだことがないし、そもそも私は歴史自体が苦手である。そんな人間がどうしてこのマンガにハマってしまったのか、非常に不思議な話である。自分なりに色々と分析してみたけれど、やはり作品の読みやすさというか入りやすさが最も大きな要因ではないかと今は結論づけている。なにしろアレキサンダー大王が生きていた時代の人物を、現代の私たちが違和感なく受け入れられる物語の構成には、パッと読んでいる時は実感できないが、よくよく考えてみれば凄いことである。
この作品は自由市民と奴隷の関係という現代の私たちの価値観では理解できない世界も登場する。この時代は奴隷の存在が当たり前であり、ご存知のように家畜並みの扱いをされていた。それゆえに働かなくてよい自由市民が余った時間で学問や芸術を発達させてきたわけだが(アリストテレスもその一人である)、こうした世界を実に平易に表現をしているところに作者の力量を感じさせる。また、物語を読み進めていくほど随所に細かい配慮(言葉の訛りとか、剣を差す位置とか)が見られ、どうしたらこんな描写を思いつくのか?と、私の頭の中で考えても出てくるわけないのに、次々と疑問が湧いてくる。
そもそもの話、エウメネスは実在の人物ではあるものの、その前半生についてほとんど資料らしきものが残されていない。よって、この頃の話(単行本でいえば1巻から5巻)はほとんど作者の想像力で構築された世界ということになる。そんなことまで考えると、人間の頭の中でここまでできるのかと目眩いがする思いだ。
あまりに面白かったので思わず周囲の知人に貸したりしてみたが、今のところおおむね好評であった。よって、この作品の面白さはそれなりに普遍的なものがあると勝手に解釈している。
作中でエウメネスは、
「お前も本当は戦より、『地球』の裏側を見てみたいのであろう?」(5巻のP.104)
と言われる場面がある。喜ばしいことにこの時代を生きる私たちには、エウメネスが果たして「地球の裏側」まで辿り着けるのどうかを同時代で確認できる楽しみが残されている(まだ連載中だから)。いまからでも過去の作品を追いかけても全く遅くはない。未読の人には是非そこのところを強調したい。
渡辺美里「BIG WAVE」(93年)
2011年4月22日 渡辺美里
(1)ブランニューヘブン
(2)Overture
(3)ジャングル チャイルド
(4)BIG WAVEやってきた
(5)Nude
(6)I WILL BE ALRIGHT
(7)いつか きっと
(8)若きモンスターの逆襲
(9)みんないた夏
(10)さえない20代
(11)はじめて
(12)素直に泣ける日笑える日(Re-Mix)
(13)Audrey
ローリング・ストーンズのキース・リチャーズやエリック・クラプトンなど多くのミュージシャンに影響を与えたアメリカ南部のブルース・ミュージシャン、ロバート・ジョンソンはその生涯が多くの謎に包まれている。それゆえ彼に関する伝説も多い。
中でも最も有名なのは、ジョンソンの驚異的なギター・テクニックは悪魔と魂を引き換えに「十字路」で手に入れたというものである。おそらく彼の代表曲”クロスロード・ブルース”から出てきた話であろう。ちなみにミシシッピ州クラークスデールにある国道61号線と国道49号線が交わる十字路がその場所だと言われている。
「人生の分岐点」という言葉がある。ジョンソンのような極端な例はないだろうが、生きていれば様々な場面で私たちも十字路に立たされる。あの時は左に進んでしまったが、もし右に曲がっていたらどうなるだろう、などと後になって振り返ることも数知れない。いや、「十字路」などと表現したけれど、そもそも人生は立ち戻ることが出来ないのだから「逆T字路」とでもいったほうが正確だろうか。
それはともかく、渡辺美里の経歴を振り返ってみた時に最も大きな分岐点はこの「BIG WAVE」を出した時ではないだろうか。いや、彼女だけでなく私自身にとってもこの作品は、好き嫌いの枠を超えて、特別な意味を持つアルバムである。このたび人生の岐路に立っている私なので、これを機会に「BIG WAVE」について書いてみたい。
「BIG WAVE」は渡辺美里の9枚目のオリジナル・アルバムである。と書いてはみたものの、自身の曲を歌い直した前作「HELLO LOVERS」(92年)は純粋なオリジナルと言いがたい部分もあるので、そう考えれば8枚目の作品となるだろう(個人的は「HELLO LOVERS」をオリジナルのアルバムと解釈しているが)
いわゆるセルフ・カバーである「HELLO LOVERS」は彼女にとって自分のキャリア点検作業にもなったと思われるが、「BIG WAVE」を作るにあたり、彼女は色々な挑戦をして新機軸を打ち出そうと相当に意気込んでいたのは間違いない。そして、それはどうも彼女のこの時の年齢(27歳)と関係しているようだ。自身が敬愛するシンガー、ジャニス・ジャプリンを始め、ジム・モリソン(ザ・ドアーズ)やジミ・ヘンドリックスといった伝説的ミュージシャンも軒並み27歳で亡くなっている(ロバート・ジョンソンもそうだ)。
かつて周囲から、
「美里、そんなことしているとジャニスみたいになるよ」
と言われていたらしいが(この時の彼女はジャニス・ジョプリンを知らなかったそうだが)、好きなミュージシャンが27歳で夭折しているというのが彼女に強く意識されていたようだ。当時「月刊カドカワ」93年9月号などの雑誌インタビューでもそんな話を交えていたことをおぼろげながらに記憶している。そういえば彼女と生前交流があった尾崎豊も前年に亡くなっていた(享年26歳)のも彼女の脳裏にはまだ鮮明に残っていただろう。
世間的に見ても27歳といえば大学を出て会社に入って5年ほど経った頃である。それなりに仕事をこなせるようになっていく一方で、自分の人生をこのままいってもいいのかな?とか振り返るのもこのあたりからだろう。
「BIG WAVE」の発売に合わせて、この時期(93年8月3日)に特別番組「渡辺美里スペシャル93 若きモンスターの逆襲」という特別番組が深夜に放送された。私もこの番組は見ていてビデオにも録画していたが、冒頭ではこんな字幕スーパーが出てくる。
「この街にはたくさんの顔がある
それは、いつでも誰でも見ることができるけれど、見ないまま過ごしてしまう時もある。
たくさんの顔とたくさんの人間が交差する街
そんな街で、夢を追い続けて暮らしている27歳の若者達がいます
27歳・・・それは、とても微妙な年齢であると、あなたは知っていますか?
それは、この街と同じようにとても不思議なのです」
番組は彼女の音楽を紹介し、3人のカメラマンとのやり取りを交えながら、さまざま27歳(イルカの調教師や政治家志望など)を取り上げるという内容だった。「you tube」で検索したらその番組が出てきたので紹介したい(1時間ほどの番組なので5分割されている)
http://www.youtube.com/watch?v=I1JeyrBhMzc
http://www.youtube.com/watch?v=7YacMRhUlFo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PZnNmSGgzbA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rjRPkl7jYo4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sf93H4YTLkw&feature=related
残念ながら内容が要約されている部分がある(彼女以外に登場する「27歳の人たち」が削除されている)。それはともかく、こうした番組を作るくらい27歳という年齢を彼女は意識していた。
そんな彼女が新作のプロデューサーに選んだのが小林武史であった。この頃の小林といえばサザン・オールスターズなどのプロデューサーというくらいの知名度だったが、92年のデビューから手掛けていたミスター・チルドレンが”CROSS ROAD”(十字路!)でブレイクするのもこの年であった。たしか「月刊カドカワ」のインタビューによれば、小林の方から「僕と一緒にしましょう」と売り込んできたと美里は話していた。彼にとってはこの時の仕事がかなり大きな経験になったらしい。しかし私としては、この両者の出会いが無かったらどうなっていたのだろう、といつも思ってしまう。
当時も今も桑田圭佑の嫌いな私にとって、関係者の小林武史が美里の新作を手がけると聞いたときは実にイヤーな気持ちになった。それから間もなくして届いたのがシングル”BIG WAVEやってきた”(93年7月1日発売)だった。これを買ったのCD出荷日だったから前日の6月30日である。学校帰りにCDショップでシングルCD(懐かしいねえ)を買って、真っすぐ家に帰って聴いてみた。
しかしパッと聴いた瞬間、「あれ?いつもと印象が違うぞ」とすぐに感じる。これまで(シングル”いつかきっと”まで)は聴いた瞬間にグッと惹き付けられるような力が彼女の音楽には確かにあった。しかし、今回のこのシングルにはそうしたものが見られなかったからだ。それはカップリング曲(この表現も今は使われないだろうな)の”素直に泣ける日笑える日”についても同様だった。この日はシングルを通しで10回聴いた。これほど1枚のシングルを続けて聴いたことは無いが(これが最初で最後かな)、それでも体や頭に曲が入ってくることはなかった。
何度も日記で書いているが、当時の私は渡辺美里の「信者」であった。自分にとって手に届かない、もう神か仏かのような存在とまで彼女を思っていた。しかしこのCDを聴いた時、
「あれ?いままでのようなマジックが無い」
と感じた。この人は必ずしも完璧な存在ではないのでは?と思った最初の瞬間である。
この先行シングルで失望した矢先、さらに酷い事態が起きる。7月12日に北海道奥尻島へ津波が襲い約200人が命を落とす大惨事だ。北海道南西沖地震である。泉谷しげるがゲリラ風な募金活動を始めたのがこの頃だが、あの津波がきっかけで”BIG WAVEやってきた”はラジオやテレビで放送自粛をされてしまう。ファンとしてはなんともやりきれない気持ちだった。そうした流れの中、7月21日にアルバム「BIG WAVE」が発売される。これも出荷日当日に買ったから手に入れたのは7月20日だ。
正直いって、これを最初に聴いたときの印象ははっきりとは覚えていない。ただ、彼女の声や音質がこれまで全く違う印象を受けたのは確かである。そして、それは全く肯定的に受け入れることができないものだった。パッと聴いて良いなと思ったのは”いつかきっと”(小林武史と組む前に作られたシングル曲)だけである。
その他の曲は軒並み「パッとしないなあ」というのが正直なところであった。ファンク色の強い最初の3曲は未だに好きになれない(ライブではほぼ必ず演奏される”ジャングル チャイルド”はもはや「嫌い」の領域である)。”はじめて”という曲の歌詞は、
「盗んだ自転車 二人乗りして」
というフレーズが出てくるが、堅物なほど生真面目な彼女の世界観にはなじまない印象を受ける。”さえない20代”にいたってはタイトルからしてなあ・・・という感じで、実際の楽曲についても「本当にさえないですねえ」と思うような雰囲気に満ちている。
確かに色々な挑戦はしている。アルバム制作に関わる人も一新されており、大江千里や小室哲哉といったいつもの楽曲提供者の名前がない。そのほか曲調や歌詞などにも変化をしようとした痕跡はいたるところで見つけることができる。だが、しかしである。こうしたことがどれほど成功しているかといわれると、私はほとんど否定的な意見しか出てこない。
これまで一番決定的に違うことは、彼女の音楽から出てくる力が大幅に無くなっていたことである。それは”BIG WAVEやってきた”を聴いた時と同じ印象であった。それはサウンドが原因なのか、彼女が歌唱法を変えたのか、そもそも彼女の力が失われたのか、そこのところがどうもわからない。もっと専門的な解説をしてくれる人が出てくることを望んでいるのだが、未だに誰もしてくれない。そこで私が今回いろいと書いてみたものの、このような印象論が限界である。
根本的なことをいうと、渡辺美里という人は器用な表現者ではない。新しいことをいくつもこなせる柔軟さを持っていない。あくまで彼女は歌手やパフォーマーという面で優れていたわけであり、新進気鋭なアーティストというタイプではないのだ。また、肝心の聴き手が彼女に対して大きな変化を望んでいたかという大きな問題もある。少なくとも私はそんなことを願ったことはこれまで一度もない。それはともかく、このアルバムを契機に多くのファンは失望し彼女から離れていった。「BIG WAVE」はオリコン1位を獲得し前作なみのセールスを記録したものの、翌年に出た「BABY FAITH」(94年)は半分ほどの売り上げに落ち込んでいるのがその証拠だ。
露骨にいえば、「BIG WAVE」は渡辺美里が新しい挑戦を無理にして失敗してしまった作品といえる。そして、その軌道修正ができないまま現在に至っているというのが私の見方である。
このアルバムを聴くたびに、
「こういう無意味な方向転換をしなければ、果たして彼女はどうなっていたのだろう・・・」
とやりきれない気持ちになるのが辛い。しかしこういう「たら、れば」の話をしても今ではもう意味がない。このアルバムは彼女自身にとってもファンにとっても十字路となる作品である。
この年も彼女のライブを観ることができたが(93年12月19日、北海道厚生年金会館)、それほど強い印象は残っていない.93年が終わる頃には彼女に対する熱意も相当に薄れていった。私の「信者歴」は2年ほどで終わってしまった。夢中になれる存在がいなくなるというのは悲しいことである一方、自分にとっては実に貴重な経験であったことも間違いない。何かにベッタリと依存するような真似はこれが最初で最後にすることができたからだ。これ以後の私はどんなものに対しても「完璧なものなどはない」という姿勢に接するようになっていく。これは自分にとって大きな変化であろう。
また、もしこの前年(92年8月18日、真駒内アイスアリーナ)に彼女のライブを観ていなかったら、自分にとってこれほどの存在にはなっていなかったことも間違いない。信者どころかファンになっていたどうかかも怪しいところだ。さらにいえば、京都というのは彼女の出身地(厳密には京都市内ではなく精華町だが)ということで頭に入っていたので、彼女との繋がりがなければ大学に京都の地を選んでなかったかもしれない。
そんなことをあれこれ考えてみると、人生にはいたるところに十字路が張り巡らされているのだろう。その時の本人は気づかないとしても。
(2)Overture
(3)ジャングル チャイルド
(4)BIG WAVEやってきた
(5)Nude
(6)I WILL BE ALRIGHT
(7)いつか きっと
(8)若きモンスターの逆襲
(9)みんないた夏
(10)さえない20代
(11)はじめて
(12)素直に泣ける日笑える日(Re-Mix)
(13)Audrey
ローリング・ストーンズのキース・リチャーズやエリック・クラプトンなど多くのミュージシャンに影響を与えたアメリカ南部のブルース・ミュージシャン、ロバート・ジョンソンはその生涯が多くの謎に包まれている。それゆえ彼に関する伝説も多い。
中でも最も有名なのは、ジョンソンの驚異的なギター・テクニックは悪魔と魂を引き換えに「十字路」で手に入れたというものである。おそらく彼の代表曲”クロスロード・ブルース”から出てきた話であろう。ちなみにミシシッピ州クラークスデールにある国道61号線と国道49号線が交わる十字路がその場所だと言われている。
「人生の分岐点」という言葉がある。ジョンソンのような極端な例はないだろうが、生きていれば様々な場面で私たちも十字路に立たされる。あの時は左に進んでしまったが、もし右に曲がっていたらどうなるだろう、などと後になって振り返ることも数知れない。いや、「十字路」などと表現したけれど、そもそも人生は立ち戻ることが出来ないのだから「逆T字路」とでもいったほうが正確だろうか。
それはともかく、渡辺美里の経歴を振り返ってみた時に最も大きな分岐点はこの「BIG WAVE」を出した時ではないだろうか。いや、彼女だけでなく私自身にとってもこの作品は、好き嫌いの枠を超えて、特別な意味を持つアルバムである。このたび人生の岐路に立っている私なので、これを機会に「BIG WAVE」について書いてみたい。
「BIG WAVE」は渡辺美里の9枚目のオリジナル・アルバムである。と書いてはみたものの、自身の曲を歌い直した前作「HELLO LOVERS」(92年)は純粋なオリジナルと言いがたい部分もあるので、そう考えれば8枚目の作品となるだろう(個人的は「HELLO LOVERS」をオリジナルのアルバムと解釈しているが)
いわゆるセルフ・カバーである「HELLO LOVERS」は彼女にとって自分のキャリア点検作業にもなったと思われるが、「BIG WAVE」を作るにあたり、彼女は色々な挑戦をして新機軸を打ち出そうと相当に意気込んでいたのは間違いない。そして、それはどうも彼女のこの時の年齢(27歳)と関係しているようだ。自身が敬愛するシンガー、ジャニス・ジャプリンを始め、ジム・モリソン(ザ・ドアーズ)やジミ・ヘンドリックスといった伝説的ミュージシャンも軒並み27歳で亡くなっている(ロバート・ジョンソンもそうだ)。
かつて周囲から、
「美里、そんなことしているとジャニスみたいになるよ」
と言われていたらしいが(この時の彼女はジャニス・ジョプリンを知らなかったそうだが)、好きなミュージシャンが27歳で夭折しているというのが彼女に強く意識されていたようだ。当時「月刊カドカワ」93年9月号などの雑誌インタビューでもそんな話を交えていたことをおぼろげながらに記憶している。そういえば彼女と生前交流があった尾崎豊も前年に亡くなっていた(享年26歳)のも彼女の脳裏にはまだ鮮明に残っていただろう。
世間的に見ても27歳といえば大学を出て会社に入って5年ほど経った頃である。それなりに仕事をこなせるようになっていく一方で、自分の人生をこのままいってもいいのかな?とか振り返るのもこのあたりからだろう。
「BIG WAVE」の発売に合わせて、この時期(93年8月3日)に特別番組「渡辺美里スペシャル93 若きモンスターの逆襲」という特別番組が深夜に放送された。私もこの番組は見ていてビデオにも録画していたが、冒頭ではこんな字幕スーパーが出てくる。
「この街にはたくさんの顔がある
それは、いつでも誰でも見ることができるけれど、見ないまま過ごしてしまう時もある。
たくさんの顔とたくさんの人間が交差する街
そんな街で、夢を追い続けて暮らしている27歳の若者達がいます
27歳・・・それは、とても微妙な年齢であると、あなたは知っていますか?
それは、この街と同じようにとても不思議なのです」
番組は彼女の音楽を紹介し、3人のカメラマンとのやり取りを交えながら、さまざま27歳(イルカの調教師や政治家志望など)を取り上げるという内容だった。「you tube」で検索したらその番組が出てきたので紹介したい(1時間ほどの番組なので5分割されている)
http://www.youtube.com/watch?v=I1JeyrBhMzc
http://www.youtube.com/watch?v=7YacMRhUlFo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PZnNmSGgzbA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rjRPkl7jYo4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Sf93H4YTLkw&feature=related
残念ながら内容が要約されている部分がある(彼女以外に登場する「27歳の人たち」が削除されている)。それはともかく、こうした番組を作るくらい27歳という年齢を彼女は意識していた。
そんな彼女が新作のプロデューサーに選んだのが小林武史であった。この頃の小林といえばサザン・オールスターズなどのプロデューサーというくらいの知名度だったが、92年のデビューから手掛けていたミスター・チルドレンが”CROSS ROAD”(十字路!)でブレイクするのもこの年であった。たしか「月刊カドカワ」のインタビューによれば、小林の方から「僕と一緒にしましょう」と売り込んできたと美里は話していた。彼にとってはこの時の仕事がかなり大きな経験になったらしい。しかし私としては、この両者の出会いが無かったらどうなっていたのだろう、といつも思ってしまう。
当時も今も桑田圭佑の嫌いな私にとって、関係者の小林武史が美里の新作を手がけると聞いたときは実にイヤーな気持ちになった。それから間もなくして届いたのがシングル”BIG WAVEやってきた”(93年7月1日発売)だった。これを買ったのCD出荷日だったから前日の6月30日である。学校帰りにCDショップでシングルCD(懐かしいねえ)を買って、真っすぐ家に帰って聴いてみた。
しかしパッと聴いた瞬間、「あれ?いつもと印象が違うぞ」とすぐに感じる。これまで(シングル”いつかきっと”まで)は聴いた瞬間にグッと惹き付けられるような力が彼女の音楽には確かにあった。しかし、今回のこのシングルにはそうしたものが見られなかったからだ。それはカップリング曲(この表現も今は使われないだろうな)の”素直に泣ける日笑える日”についても同様だった。この日はシングルを通しで10回聴いた。これほど1枚のシングルを続けて聴いたことは無いが(これが最初で最後かな)、それでも体や頭に曲が入ってくることはなかった。
何度も日記で書いているが、当時の私は渡辺美里の「信者」であった。自分にとって手に届かない、もう神か仏かのような存在とまで彼女を思っていた。しかしこのCDを聴いた時、
「あれ?いままでのようなマジックが無い」
と感じた。この人は必ずしも完璧な存在ではないのでは?と思った最初の瞬間である。
この先行シングルで失望した矢先、さらに酷い事態が起きる。7月12日に北海道奥尻島へ津波が襲い約200人が命を落とす大惨事だ。北海道南西沖地震である。泉谷しげるがゲリラ風な募金活動を始めたのがこの頃だが、あの津波がきっかけで”BIG WAVEやってきた”はラジオやテレビで放送自粛をされてしまう。ファンとしてはなんともやりきれない気持ちだった。そうした流れの中、7月21日にアルバム「BIG WAVE」が発売される。これも出荷日当日に買ったから手に入れたのは7月20日だ。
正直いって、これを最初に聴いたときの印象ははっきりとは覚えていない。ただ、彼女の声や音質がこれまで全く違う印象を受けたのは確かである。そして、それは全く肯定的に受け入れることができないものだった。パッと聴いて良いなと思ったのは”いつかきっと”(小林武史と組む前に作られたシングル曲)だけである。
その他の曲は軒並み「パッとしないなあ」というのが正直なところであった。ファンク色の強い最初の3曲は未だに好きになれない(ライブではほぼ必ず演奏される”ジャングル チャイルド”はもはや「嫌い」の領域である)。”はじめて”という曲の歌詞は、
「盗んだ自転車 二人乗りして」
というフレーズが出てくるが、堅物なほど生真面目な彼女の世界観にはなじまない印象を受ける。”さえない20代”にいたってはタイトルからしてなあ・・・という感じで、実際の楽曲についても「本当にさえないですねえ」と思うような雰囲気に満ちている。
確かに色々な挑戦はしている。アルバム制作に関わる人も一新されており、大江千里や小室哲哉といったいつもの楽曲提供者の名前がない。そのほか曲調や歌詞などにも変化をしようとした痕跡はいたるところで見つけることができる。だが、しかしである。こうしたことがどれほど成功しているかといわれると、私はほとんど否定的な意見しか出てこない。
これまで一番決定的に違うことは、彼女の音楽から出てくる力が大幅に無くなっていたことである。それは”BIG WAVEやってきた”を聴いた時と同じ印象であった。それはサウンドが原因なのか、彼女が歌唱法を変えたのか、そもそも彼女の力が失われたのか、そこのところがどうもわからない。もっと専門的な解説をしてくれる人が出てくることを望んでいるのだが、未だに誰もしてくれない。そこで私が今回いろいと書いてみたものの、このような印象論が限界である。
根本的なことをいうと、渡辺美里という人は器用な表現者ではない。新しいことをいくつもこなせる柔軟さを持っていない。あくまで彼女は歌手やパフォーマーという面で優れていたわけであり、新進気鋭なアーティストというタイプではないのだ。また、肝心の聴き手が彼女に対して大きな変化を望んでいたかという大きな問題もある。少なくとも私はそんなことを願ったことはこれまで一度もない。それはともかく、このアルバムを契機に多くのファンは失望し彼女から離れていった。「BIG WAVE」はオリコン1位を獲得し前作なみのセールスを記録したものの、翌年に出た「BABY FAITH」(94年)は半分ほどの売り上げに落ち込んでいるのがその証拠だ。
露骨にいえば、「BIG WAVE」は渡辺美里が新しい挑戦を無理にして失敗してしまった作品といえる。そして、その軌道修正ができないまま現在に至っているというのが私の見方である。
このアルバムを聴くたびに、
「こういう無意味な方向転換をしなければ、果たして彼女はどうなっていたのだろう・・・」
とやりきれない気持ちになるのが辛い。しかしこういう「たら、れば」の話をしても今ではもう意味がない。このアルバムは彼女自身にとってもファンにとっても十字路となる作品である。
この年も彼女のライブを観ることができたが(93年12月19日、北海道厚生年金会館)、それほど強い印象は残っていない.93年が終わる頃には彼女に対する熱意も相当に薄れていった。私の「信者歴」は2年ほどで終わってしまった。夢中になれる存在がいなくなるというのは悲しいことである一方、自分にとっては実に貴重な経験であったことも間違いない。何かにベッタリと依存するような真似はこれが最初で最後にすることができたからだ。これ以後の私はどんなものに対しても「完璧なものなどはない」という姿勢に接するようになっていく。これは自分にとって大きな変化であろう。
また、もしこの前年(92年8月18日、真駒内アイスアリーナ)に彼女のライブを観ていなかったら、自分にとってこれほどの存在にはなっていなかったことも間違いない。信者どころかファンになっていたどうかかも怪しいところだ。さらにいえば、京都というのは彼女の出身地(厳密には京都市内ではなく精華町だが)ということで頭に入っていたので、彼女との繋がりがなければ大学に京都の地を選んでなかったかもしれない。
そんなことをあれこれ考えてみると、人生にはいたるところに十字路が張り巡らされているのだろう。その時の本人は気づかないとしても。
「ウェブ2.0」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「ウェブ」(Web)はもちろんインターネットのことで、「2.0」はパソコンソフトでよく見かけるバージョン(例えば「iTunes 10.2.1」)の数字のことである。本書でこう説明している。
<とりあえず動くソフトウェアができました、というレベルがバージョン1.0。普通に使ってもいろいろなトラブルが頻出、「インストールするだけでも大変かもしれないし、肝心の機能もないかもしれないが、それを承知の上で使ってみてください」という感じの製品である。そして、この段階で使ってくれた勇気あるユーザーのフィードバックを元にあれこれ手直しする。ちょっと直すごとに、1.1、1.2と小数点以下をバージョンアップ。で、「うむ、かなりまともに動くようになった」というところで、2.0というバージョンに改称する。>(P.10)
一般に、小数点単位のバージョン・アップは細かい進化というレベルで、1.0から2.0へ移行するときはソフトの内容が大幅に変わる局面と言われる。これに習って、ウェブの世界がどんどん発展し新たな次元に突入した、というのがウェブ2.0の概念だと思っていただければ差し支えないだろう。いや、そもそもウェブ2.0という概念を提唱したティム•オライリー(アメリカのメディア企業「オライリー・メディア」の創業者)自身もこの言葉にあまり明確な定義を与えていないので、あまり細かい部分を詮索しても仕方ないかもしれない。
本書のタイトルとなっている「ヒューマン2.0」というのは、この「ウェブ2.0」をもじったものだ。IT技術の進歩にともない、私たちの環境にもパソコンやインターネットが身近になっていた。私が初めて社会に出た時(01年)、会社にはまだパソコンが一人1台に割り振られている状態でなかったけれど、それから1年ほどで社員全員に行き渡っていったのを覚えている。ウェブの進歩によって人間の働き方も劇的に変わってきているわけだが、それが如実に見えてくるのがアメリカ西海岸の「シリコンバレー」と言われる地域だ。インテル、アップル、オラクル、シスコなどの世界に名だたる大企業が集積しており、ヤフーやイーベイ、そしてアドビといった会社も以前はここにあった。
著者の渡辺さんは東京都出身で、東大工学部から三菱商事へ入社、それからスタンフォード大でMBAを取得したりマッキンゼーへ入るなどの経験を積み、現在はアメリカのシリコンバレーに在住しながら技術関連やコンサルティングの仕事をしている人だ。「ON,OFF AND BEYOND」という自身のブログでも彼の地の様子を伝えてくれている。
http://www.chikawatanabe.com/blog/
シリコンバレーが人口240万人で、115万人の就業者のうち30%ほどの人がITやバイオといった技術系の仕事に携わっている。これは日本でいうところの「サラリーマン」のほとんどが何らかの形で技術に関わっているくらいの比率だという。本書は、そんなシリコンバレーで働く人たちや企業の姿を紹介しながら、「働く」という行為がどのように変化していくのか、そういう展望を描いている。
IT技術の進歩における良くも悪くも凄いところは、いままでは人間がやっていたことをコンピューターが替わってしまうことだろう。たとえば、大規模な家具ショップをチェーン展開する「イケア(IKEA)」の米国向けサイトで、閲覧者の質問に答える「アンナ(Anna)」さんという「バーチャル店員」の事例だ。
http://www.ikea.com/jp/en
「あそこの店舗は何時までやってるんですか?」というような簡単な質問なら一瞬にして的確な答えを返してくれるのである。実際にやってみたら、確かにパッと答えてくれた。
しかしながらこれは、スゴいシステムだなあ、と単純に感心できるような話ではない。
<アンナさん一人のために、それまでコールセンターで働いていた数十人、数百人という人が職を失ったことになる。「決まりきった質問に、決まりきった答えをする」といった、機械に置き換えられるような仕事をしている人の仕事はこうしてなくなっていくわけだ。これが「ITによる生産性の向上」の中身。実際のところ、アメリカでは、「生産性が1%向上すると130万人の職がなくなる」と推定されている。>(P.34)
イケアのサイトではアンナさんがにこやかに笑っているが、その向こうでは職を失って泣いている人がたくさんいるわけだ。そして、技術の進歩によって世の中が便利になる一方、そのおかげで旧来の仕事がなくなるという話は別にアメリカに限った話ではない。厳しい話だが、この流れは誰も抗えないだろう。
渡辺さんはこうした事例をふまえた上で、シリコンバレーで誕生する「会社に依存しない新しい生き方」を4つ紹介する。これが「ヒューマン2.0」の本題だ。それらを列挙すると、
・フリーランス:誰かに雇用されるのではなく、何らかの専門性を持って個人で仕事を請ける。
・ライフタイムワーカー:自分好きな場所に住むことを重視する。
・チャンクワーカー:働く期間と休みを取る期間を分割する。
・ポートフォリオワーカー:複数のタイプの仕事を掛け持ちする。
いずれの働き方も、入社から定年までずっと同じ会社にいる終身雇用とは全く異なっている。しかもシリコンバレーでは、全就業人口の15~30%がフリーランスだというのだ。それは必ずしも本人の希望かどうかは難しいところが、こうした生き方をしている人がたくさんいるというのは心強い気もする。
この4つの働き方の中で個人的には、複数の仕事を掛け持ちするポートフォリオワーカーが理想かなという気がする。もはや年功序列や終身雇用を求められない日本の企業において、収入源を一つしかないというのはリスクが高いからだ。
しかしながら、給料を上げることができないくせに社員の副業を禁止している会社が日本ではまだ大多数だ。どうしてなのか理由はわからないけれど(会社の秘密が漏れたりするのを恐れているのだろうか。そういう会社に限って社外で役立つ情報など無いものだが)、一人でも多くの人が兼業などで収入源を増やしてリスク分散のできる働き方をする人が増えていけば、この国の社会も多少は活性化していくと思うのだが。
<とりあえず動くソフトウェアができました、というレベルがバージョン1.0。普通に使ってもいろいろなトラブルが頻出、「インストールするだけでも大変かもしれないし、肝心の機能もないかもしれないが、それを承知の上で使ってみてください」という感じの製品である。そして、この段階で使ってくれた勇気あるユーザーのフィードバックを元にあれこれ手直しする。ちょっと直すごとに、1.1、1.2と小数点以下をバージョンアップ。で、「うむ、かなりまともに動くようになった」というところで、2.0というバージョンに改称する。>(P.10)
一般に、小数点単位のバージョン・アップは細かい進化というレベルで、1.0から2.0へ移行するときはソフトの内容が大幅に変わる局面と言われる。これに習って、ウェブの世界がどんどん発展し新たな次元に突入した、というのがウェブ2.0の概念だと思っていただければ差し支えないだろう。いや、そもそもウェブ2.0という概念を提唱したティム•オライリー(アメリカのメディア企業「オライリー・メディア」の創業者)自身もこの言葉にあまり明確な定義を与えていないので、あまり細かい部分を詮索しても仕方ないかもしれない。
本書のタイトルとなっている「ヒューマン2.0」というのは、この「ウェブ2.0」をもじったものだ。IT技術の進歩にともない、私たちの環境にもパソコンやインターネットが身近になっていた。私が初めて社会に出た時(01年)、会社にはまだパソコンが一人1台に割り振られている状態でなかったけれど、それから1年ほどで社員全員に行き渡っていったのを覚えている。ウェブの進歩によって人間の働き方も劇的に変わってきているわけだが、それが如実に見えてくるのがアメリカ西海岸の「シリコンバレー」と言われる地域だ。インテル、アップル、オラクル、シスコなどの世界に名だたる大企業が集積しており、ヤフーやイーベイ、そしてアドビといった会社も以前はここにあった。
著者の渡辺さんは東京都出身で、東大工学部から三菱商事へ入社、それからスタンフォード大でMBAを取得したりマッキンゼーへ入るなどの経験を積み、現在はアメリカのシリコンバレーに在住しながら技術関連やコンサルティングの仕事をしている人だ。「ON,OFF AND BEYOND」という自身のブログでも彼の地の様子を伝えてくれている。
http://www.chikawatanabe.com/blog/
シリコンバレーが人口240万人で、115万人の就業者のうち30%ほどの人がITやバイオといった技術系の仕事に携わっている。これは日本でいうところの「サラリーマン」のほとんどが何らかの形で技術に関わっているくらいの比率だという。本書は、そんなシリコンバレーで働く人たちや企業の姿を紹介しながら、「働く」という行為がどのように変化していくのか、そういう展望を描いている。
IT技術の進歩における良くも悪くも凄いところは、いままでは人間がやっていたことをコンピューターが替わってしまうことだろう。たとえば、大規模な家具ショップをチェーン展開する「イケア(IKEA)」の米国向けサイトで、閲覧者の質問に答える「アンナ(Anna)」さんという「バーチャル店員」の事例だ。
http://www.ikea.com/jp/en
「あそこの店舗は何時までやってるんですか?」というような簡単な質問なら一瞬にして的確な答えを返してくれるのである。実際にやってみたら、確かにパッと答えてくれた。
しかしながらこれは、スゴいシステムだなあ、と単純に感心できるような話ではない。
<アンナさん一人のために、それまでコールセンターで働いていた数十人、数百人という人が職を失ったことになる。「決まりきった質問に、決まりきった答えをする」といった、機械に置き換えられるような仕事をしている人の仕事はこうしてなくなっていくわけだ。これが「ITによる生産性の向上」の中身。実際のところ、アメリカでは、「生産性が1%向上すると130万人の職がなくなる」と推定されている。>(P.34)
イケアのサイトではアンナさんがにこやかに笑っているが、その向こうでは職を失って泣いている人がたくさんいるわけだ。そして、技術の進歩によって世の中が便利になる一方、そのおかげで旧来の仕事がなくなるという話は別にアメリカに限った話ではない。厳しい話だが、この流れは誰も抗えないだろう。
渡辺さんはこうした事例をふまえた上で、シリコンバレーで誕生する「会社に依存しない新しい生き方」を4つ紹介する。これが「ヒューマン2.0」の本題だ。それらを列挙すると、
・フリーランス:誰かに雇用されるのではなく、何らかの専門性を持って個人で仕事を請ける。
・ライフタイムワーカー:自分好きな場所に住むことを重視する。
・チャンクワーカー:働く期間と休みを取る期間を分割する。
・ポートフォリオワーカー:複数のタイプの仕事を掛け持ちする。
いずれの働き方も、入社から定年までずっと同じ会社にいる終身雇用とは全く異なっている。しかもシリコンバレーでは、全就業人口の15~30%がフリーランスだというのだ。それは必ずしも本人の希望かどうかは難しいところが、こうした生き方をしている人がたくさんいるというのは心強い気もする。
この4つの働き方の中で個人的には、複数の仕事を掛け持ちするポートフォリオワーカーが理想かなという気がする。もはや年功序列や終身雇用を求められない日本の企業において、収入源を一つしかないというのはリスクが高いからだ。
しかしながら、給料を上げることができないくせに社員の副業を禁止している会社が日本ではまだ大多数だ。どうしてなのか理由はわからないけれど(会社の秘密が漏れたりするのを恐れているのだろうか。そういう会社に限って社外で役立つ情報など無いものだが)、一人でも多くの人が兼業などで収入源を増やしてリスク分散のできる働き方をする人が増えていけば、この国の社会も多少は活性化していくと思うのだが。
「ウェブ2.0」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「ウェブ」(Web)はもちろんインターネットのことで、「2.0」はパソコンソフトでよく見かけるバージョン(例えば「iTunes 10.2.1」)の数字のことである。本書でこう説明している。
<とりあえず動くソフトウェアができました、というレベルがバージョン1.0。普通に使ってもいろいろなトラブルが頻出、「インストールするだけでも大変かもしれないし、肝心の機能もないかもしれないが、それを承知の上で使ってみてください」という感じの製品である。そして、この段階で使ってくれた勇気あるユーザーのフィードバックを元にあれこれ手直しする。ちょっと直すごとに、1.1、1.2と小数点以下をバージョンアップ。で、「うむ、かなりまともに動くようになった」というところで、2.0というバージョンに改称する。>(P.10)
一般に、小数点単位のバージョン・アップは細かい進化というレベルで、1.0から2.0へ移行するときはソフトの内容が大幅に変わる局面と言われる。これに習って、ウェブの世界がどんどん発展し新たな次元に突入した、というのがウェブ2.0の概念だと思っていただければ差し支えないだろう。いや、そもそもウェブ2.0という概念を提唱したティム•オライリー(アメリカのメディア企業「オライリー・メディア」の創業者)自身もこの言葉にあまり明確な定義を与えていないので、あまり細かい部分を詮索しても仕方ないかもしれない。
本書のタイトルとなっている「ヒューマン2.0」というのは、この「ウェブ2.0」をもじったものだ。IT技術の進歩にともない、私たちの環境にもパソコンやインターネットが身近になっていた。私が初めて社会に出た時(01年)、会社にはまだパソコンが一人1台に割り振られている状態でなかったけれど、それから1年ほどで社員全員に行き渡っていったのを覚えている。ウェブの進歩によって人間の働き方も劇的に変わってきているわけだが、それが如実に見えてくるのがアメリカ西海岸の「シリコンバレー」と言われる地域だ。インテル、アップル、オラクル、シスコなどの世界に名だたる大企業が集積しており、ヤフーやイーベイ、そしてアドビといった会社も以前はここにあった。
著者の渡辺さんは東京都出身で、東大工学部から三菱商事へ入社、それからスタンフォード大でMBAを取得したりマッキンゼーへ入るなどの経験を積み、現在はアメリカのシリコンバレーに在住しながら技術関連やコンサルティングの仕事をしている人だ。「ON,OFF AND BEYOND」という自身のブログでも彼の地の様子を伝えてくれている。
http://www.chikawatanabe.com/blog/
シリコンバレーが人口240万人で、115万人の就業者のうち30%ほどの人がITやバイオといった技術系の仕事に携わっている。これは日本でいうところの「サラリーマン」のほとんどが何らかの形で技術に関わっているくらいの比率だという。本書は、そんなシリコンバレーで働く人たちや企業の姿を紹介しながら、「働く」という行為がどのように変化していくのか、そういう展望を描いている。
IT技術の進歩における良くも悪くも凄いところは、いままでは人間がやっていたことをコンピューターが替わってしまうことだろう。たとえば、大規模な家具ショップをチェーン展開する「イケア(IKEA)」の米国向けサイトで、閲覧者の質問に答える「アンナ(Anna)」さんという「バーチャル店員」の事例だ。
http://www.ikea.com/jp/en
「あそこの店舗は何時までやってるんですか?」というような簡単な質問なら一瞬にして的確な答えを返してくれるのである。実際にやってみたら、確かにパッと答えてくれた。
しかしながらこれは、スゴいシステムだなあ、と単純に感心できるような話ではない。
<アンナさん一人のために、それまでコールセンターで働いていた数十人、数百人という人が職を失ったことになる。「決まりきった質問に、決まりきった答えをする」といった、機械に置き換えられるような仕事をしている人の仕事はこうしてなくなっていくわけだ。これが「ITによる生産性の向上」の中身。実際のところ、アメリカでは、「生産性が1%向上すると130万人の職がなくなる」と推定されている。>(P.34)
イケアのサイトではアンナさんがにこやかに笑っているが、その向こうでは職を失って泣いている人がたくさんいるわけだ。そして、技術の進歩によって世の中が便利になる一方、そのおかげで旧来の仕事がなくなるという話は別にアメリカに限った話ではない。厳しい話だが、この流れは誰も抗えないだろう。
渡辺さんはこうした事例をふまえた上で、シリコンバレーで誕生する「会社に依存しない新しい生き方」を4つ紹介する。これが「ヒューマン2.0」の本題だ。それらを列挙すると、
・フリーランス:誰かに雇用されるのではなく、何らかの専門性を持って個人で仕事を請ける。
・ライフタイムワーカー:自分好きな場所に住むことを重視する。
・チャンクワーカー:働く期間と休みを取る期間を分割する。
・ポートフォリオワーカー:複数のタイプの仕事を掛け持ちする。
いずれの働き方も、入社から定年までずっと同じ会社にいる終身雇用とは全く異なっている。しかもシリコンバレーでは、全就業人口の15~30%がフリーランスだというのだ。それは必ずしも本人の希望かどうかは難しいところが、こうした生き方をしている人がたくさんいるというのは心強い気もする。
この4つの働き方の中で個人的には、複数の仕事を掛け持ちするポートフォリオワーカーが理想かなという気がする。もはや年功序列や終身雇用を求められない日本の企業において、収入源を一つしかないというのはリスクが高いからだ。
しかしながら、給料を上げることができないくせに社員の副業を禁止している会社が日本ではまだ大多数だ。どうしてなのか理由はわからないけれど(会社の秘密が漏れたりするのを恐れているのだろうか。そういう会社に限って社外で役立つ情報など無いものだが)、一人でも多くの人が兼業などで収入源を増やしてリスク分散のできる働き方をする人が増えていけば、この国の社会も多少は活性化していくと思うのだが。
<とりあえず動くソフトウェアができました、というレベルがバージョン1.0。普通に使ってもいろいろなトラブルが頻出、「インストールするだけでも大変かもしれないし、肝心の機能もないかもしれないが、それを承知の上で使ってみてください」という感じの製品である。そして、この段階で使ってくれた勇気あるユーザーのフィードバックを元にあれこれ手直しする。ちょっと直すごとに、1.1、1.2と小数点以下をバージョンアップ。で、「うむ、かなりまともに動くようになった」というところで、2.0というバージョンに改称する。>(P.10)
一般に、小数点単位のバージョン・アップは細かい進化というレベルで、1.0から2.0へ移行するときはソフトの内容が大幅に変わる局面と言われる。これに習って、ウェブの世界がどんどん発展し新たな次元に突入した、というのがウェブ2.0の概念だと思っていただければ差し支えないだろう。いや、そもそもウェブ2.0という概念を提唱したティム•オライリー(アメリカのメディア企業「オライリー・メディア」の創業者)自身もこの言葉にあまり明確な定義を与えていないので、あまり細かい部分を詮索しても仕方ないかもしれない。
本書のタイトルとなっている「ヒューマン2.0」というのは、この「ウェブ2.0」をもじったものだ。IT技術の進歩にともない、私たちの環境にもパソコンやインターネットが身近になっていた。私が初めて社会に出た時(01年)、会社にはまだパソコンが一人1台に割り振られている状態でなかったけれど、それから1年ほどで社員全員に行き渡っていったのを覚えている。ウェブの進歩によって人間の働き方も劇的に変わってきているわけだが、それが如実に見えてくるのがアメリカ西海岸の「シリコンバレー」と言われる地域だ。インテル、アップル、オラクル、シスコなどの世界に名だたる大企業が集積しており、ヤフーやイーベイ、そしてアドビといった会社も以前はここにあった。
著者の渡辺さんは東京都出身で、東大工学部から三菱商事へ入社、それからスタンフォード大でMBAを取得したりマッキンゼーへ入るなどの経験を積み、現在はアメリカのシリコンバレーに在住しながら技術関連やコンサルティングの仕事をしている人だ。「ON,OFF AND BEYOND」という自身のブログでも彼の地の様子を伝えてくれている。
http://www.chikawatanabe.com/blog/
シリコンバレーが人口240万人で、115万人の就業者のうち30%ほどの人がITやバイオといった技術系の仕事に携わっている。これは日本でいうところの「サラリーマン」のほとんどが何らかの形で技術に関わっているくらいの比率だという。本書は、そんなシリコンバレーで働く人たちや企業の姿を紹介しながら、「働く」という行為がどのように変化していくのか、そういう展望を描いている。
IT技術の進歩における良くも悪くも凄いところは、いままでは人間がやっていたことをコンピューターが替わってしまうことだろう。たとえば、大規模な家具ショップをチェーン展開する「イケア(IKEA)」の米国向けサイトで、閲覧者の質問に答える「アンナ(Anna)」さんという「バーチャル店員」の事例だ。
http://www.ikea.com/jp/en
「あそこの店舗は何時までやってるんですか?」というような簡単な質問なら一瞬にして的確な答えを返してくれるのである。実際にやってみたら、確かにパッと答えてくれた。
しかしながらこれは、スゴいシステムだなあ、と単純に感心できるような話ではない。
<アンナさん一人のために、それまでコールセンターで働いていた数十人、数百人という人が職を失ったことになる。「決まりきった質問に、決まりきった答えをする」といった、機械に置き換えられるような仕事をしている人の仕事はこうしてなくなっていくわけだ。これが「ITによる生産性の向上」の中身。実際のところ、アメリカでは、「生産性が1%向上すると130万人の職がなくなる」と推定されている。>(P.34)
イケアのサイトではアンナさんがにこやかに笑っているが、その向こうでは職を失って泣いている人がたくさんいるわけだ。そして、技術の進歩によって世の中が便利になる一方、そのおかげで旧来の仕事がなくなるという話は別にアメリカに限った話ではない。厳しい話だが、この流れは誰も抗えないだろう。
渡辺さんはこうした事例をふまえた上で、シリコンバレーで誕生する「会社に依存しない新しい生き方」を4つ紹介する。これが「ヒューマン2.0」の本題だ。それらを列挙すると、
・フリーランス:誰かに雇用されるのではなく、何らかの専門性を持って個人で仕事を請ける。
・ライフタイムワーカー:自分好きな場所に住むことを重視する。
・チャンクワーカー:働く期間と休みを取る期間を分割する。
・ポートフォリオワーカー:複数のタイプの仕事を掛け持ちする。
いずれの働き方も、入社から定年までずっと同じ会社にいる終身雇用とは全く異なっている。しかもシリコンバレーでは、全就業人口の15~30%がフリーランスだというのだ。それは必ずしも本人の希望かどうかは難しいところが、こうした生き方をしている人がたくさんいるというのは心強い気もする。
この4つの働き方の中で個人的には、複数の仕事を掛け持ちするポートフォリオワーカーが理想かなという気がする。もはや年功序列や終身雇用を求められない日本の企業において、収入源を一つしかないというのはリスクが高いからだ。
しかしながら、給料を上げることができないくせに社員の副業を禁止している会社が日本ではまだ大多数だ。どうしてなのか理由はわからないけれど(会社の秘密が漏れたりするのを恐れているのだろうか。そういう会社に限って社外で役立つ情報など無いものだが)、一人でも多くの人が兼業などで収入源を増やしてリスク分散のできる働き方をする人が増えていけば、この国の社会も多少は活性化していくと思うのだが。
かつてほぼ全ての大学は、最初の2年間が「教養課程」という段階でさまざまな「教養科目」を勉強し、それから後半の2年が自分の専門の学問をする「専門課程」へ入るという流れになっていた。しかし、私が大学に在籍していたころ(96年4月〜2000年3月)もすでに教養課程というものは無くなっていた。「教養科目」とはいわゆる「パンキョー」(一般教養)のことである。ただ、大学に入ってもすぐには専門領域の科目ではなく、外国語や法学や哲学といった一般教養をまず勉強するという流れ自体はそれほど違いはない。
とわかったような書き方をしているが、私もこのような知識をしったのはこの本を読んだおかげである。大学時代はこういうことについて無頓着だった。いやそれどころか、
「自分は心理学専攻に入学したのに、どうして1回生の時は心理学関係の科目をほとんど取ることができないんだ?」
と疑問に思っていたくらいである。私の大学で1年目に取れた心理学関係の科目は、確か3科目くらいしかなかったと記憶している。
私に限らず多くの人は、なんで自分の学部(法学でも経済学でも)と関係ない科目をとらなければならないんだ?と疑問を抱いたことがあるだろう。そして一般教養を勉強する意味を教えてくれた大学教員も皆無に違いない。当の私もそんな人に出会うこともなく大学時代は終わった。
この本の著者の仲正さんは、
<私の教えている法学部の学生の中には、
「僕たちは専門科目を勉強するために大学に入学したので、最初から専門科目の授業があると期待していた。教養科目のようなものをやるのは、時間と授業料のムダだ」
という調子で、分かったような顔をして大学のカリキュラムを”批判”したがる子がいます。
ふつうに考えれば、「教養科目」というものがあることを知らないまま受験して入学する本人が悪いのだし、大学の教育課程について規則をたしかめもしないで「法学部」に入学する姿勢自体が全然法学部的でありません。しかし、本人は結構本気で「教養」不要論を展開しているつもりになっているのです。
そういう子に、「では君は教養とはどういうものか分かっているのか?」と聴くと、面白いくらい、ちゃんと理解していないのが分かる奇妙な答えしか出てきません。どうも「軽チャー」とか「教養番組」の”教養”のような意味合いで、「教養」を理解しているようなのです。多分、サークルの先輩などから「教養科目というのは意味がない。役に立たない。でもその単位を取らないと卒業できない」というようなことを言われて、そういうイメージをもってしまったのでしょう>(P.146-147)
やや長い引用になってしまったが、一般教養について、いや大学で学問をするということについての問題点がここに凝縮してるような気がしたので紹介させてもらった。
話を戻すが、はたして「一般教養」なるものを学習することにどんな目的があるのだろうか。それは本書の3章でくわしく述べられているけれど、私なりに要約してみたい。
そもそも「大学」の起源は13世紀頃のヨーロッパまでさかのぼる。この頃の大学というのは、専門的な知識をもったキリスト教の僧侶を養成することを目的にしている。その僧侶たちが学習する「専門的知識」とは「神学」、「法学」、「医学」の3つであった。これらの知識を伝承するのが知識人としての僧侶の役割だった。
しかし、これらの3つの専門のいずれかを修めて教会の中で専門職として出世したい人は、まず当時のヨーロッパの貴族・知識人の共通言語であったラテン語の読み書きや算術を学び、大学に入ってからは専門の勉強の前提となる基礎学力と思考能力と理解力を身につけるために「自由七科」(文法、修辞学、弁証法、算術、幾何、天文、音楽)を学ばなければならなかった。
この「自由七科」というのが大学の「教養科目」(一般教養)と呼ばれるものの起源である。そして、基礎的な教養を学習する「教養課程」と、自分の専門の勉強をする「専門課程」が分かれていたのは既にこの頃からであった。ちなみに「教養課程」を勉強するところは「学芸学部」と言われ、それは後に「哲学部」と呼ばれるようになる。
外国語に一般教養に哲学部と、最近の学生には縁も人気もなさそうな分野ばかりであるが、いずれもそれなりの歴史や必然性があって存在していることが多少は理解していただけただろうか。
大学科目に一般教養があり、かつて教養課程が存在していた理由をひとことでいえば、「教養」を身につけるためである。しかし、いきなりこんなこと書いてもピンとくる方はほとんどいないだろう。先に引用した仲正さんの文章の通り、教養というのはいわゆる雑学とは違うレベルのものである。この点は内田樹さん(神戸女学院大学教授)がこのように言っている。
<教養は情報ではない。
教養とはかたちのある情報単位の集積のことではなく、カテゴリーもクラスも重要度もまったく異にする情報単位のあいだの関係性を発見する力である。
雑学は「すでに知っていること」を取り出すことしかできない。教養とは「まだ知らないこと」へフライングする能力のことである。>(内田樹「知に働けば蔵が建つ」P.11。08年。文春文庫)
<「教養」というのは、「生(なま)」の知識や情報のことではない。そうではなくて、知識や情報を整序したり、統御したり、捜査したりする「仕方」のことである。
(中略)
「教養」とは「自分が何を知らないかについて知っている」、すなわち「自分の無知についての知識」のことなのである。>(内田樹「街場の現代思想」
P.11。08年。文春文庫)
そして仲正さん自身は本書の最後で「教養」において最も大事なことを、
<「今の私には分からない問題」に直面してしまった時に、どうすべきか」を心得ていること>(P.193)
と締めくくっている。こうやっていろいろと文章を並べてみて、「教養」というのがどんなものか、だんだんと具体的なイメージが湧いてきたような気がする。例えば、資格を取るとか就職に有利になるかというような短期的な目的を達成することに対して、「教養」はおそらくあまり役に立たないだろう。しかし、自分の頭の中のもっと根本的な影響を与えてくれるものという感じだ。
私がよくその著書を買っている日垣隆(作家・ジャーナリスト)さんや橘玲(作家)さんは、現代社会について鋭く切り込んだ文章を書いているけれど、一般的には難しそうな古典や現代思想や経済書などをよく読んでいるような傾向にあることに気づく。そして、それはどうしてなのだろうかと考えるようになった。やはり、そういう本を読むことにメリットがあるとしか思えない。
正直いって、いままでの私は古典や思想書などを敬遠してきた。昔の書物は読みづらく読破するにはかなりの根気がいる。また、別に苦労してそんなものを読まなくても良いのでは、とも腹の底では思っていた。
しかし、である。ウインドウズ95が登場したあたりから世の中の流れがグッと変わっていくようになり、世界はますます混迷の度合いが深まっていく。そして最近ではこの大震災だ。はっきりいって、過去の情報をもとにこれから先のことを予測するのは困難に違いない。
そんな状況で個人にできることといえば、目の前にある情報を分析して自分なりに行動することしかないだろう。となれば、やはりもっと根本的なところで考えることのできる頭を持っていなければならない。そのために必要なのがいわゆる「教養」というものではないか。
それは学習したところでパッとは役に立たない。しかし仲正さんが言うように、
<今すぐに利益がなくても、長期的な視野から見て、ごく表面的でも学んでおいた方がいいこともある。>(P.186)
と今では考えるようになっている。
本書は上に挙げたような「教養」の本来の意味にとどまらず、大学で学問をするために必要な心構え、また古典や外国語を勉強する意義などをかなり平易に書いて説明してくれている。本当だったらこれから大学に入る人に最適な本であるけれど、すでに大学を出た人にもかなり有益なことが満載だといいたい。特に、大学で何をしたのかわからない、というような人にはぜひ手にとってもらいたいと願う。
締めくくりにこの本の末尾の一文を紹介したい。
<ほとんどの人間は傲慢で横着です。自分が無知で勉強が必要だということをなかなか認められません。そのため、無自覚的に自分にとって都合の悪い情報をシャットアウトしがちです。自分が賢くなったと思い始めたら要注意です。「疑うこと」を回避して、楽になろうとする「私」自身を警戒してください。それが「何も信じられない世界」で生きていくための唯一の方策です。>(P.198)
とわかったような書き方をしているが、私もこのような知識をしったのはこの本を読んだおかげである。大学時代はこういうことについて無頓着だった。いやそれどころか、
「自分は心理学専攻に入学したのに、どうして1回生の時は心理学関係の科目をほとんど取ることができないんだ?」
と疑問に思っていたくらいである。私の大学で1年目に取れた心理学関係の科目は、確か3科目くらいしかなかったと記憶している。
私に限らず多くの人は、なんで自分の学部(法学でも経済学でも)と関係ない科目をとらなければならないんだ?と疑問を抱いたことがあるだろう。そして一般教養を勉強する意味を教えてくれた大学教員も皆無に違いない。当の私もそんな人に出会うこともなく大学時代は終わった。
この本の著者の仲正さんは、
<私の教えている法学部の学生の中には、
「僕たちは専門科目を勉強するために大学に入学したので、最初から専門科目の授業があると期待していた。教養科目のようなものをやるのは、時間と授業料のムダだ」
という調子で、分かったような顔をして大学のカリキュラムを”批判”したがる子がいます。
ふつうに考えれば、「教養科目」というものがあることを知らないまま受験して入学する本人が悪いのだし、大学の教育課程について規則をたしかめもしないで「法学部」に入学する姿勢自体が全然法学部的でありません。しかし、本人は結構本気で「教養」不要論を展開しているつもりになっているのです。
そういう子に、「では君は教養とはどういうものか分かっているのか?」と聴くと、面白いくらい、ちゃんと理解していないのが分かる奇妙な答えしか出てきません。どうも「軽チャー」とか「教養番組」の”教養”のような意味合いで、「教養」を理解しているようなのです。多分、サークルの先輩などから「教養科目というのは意味がない。役に立たない。でもその単位を取らないと卒業できない」というようなことを言われて、そういうイメージをもってしまったのでしょう>(P.146-147)
やや長い引用になってしまったが、一般教養について、いや大学で学問をするということについての問題点がここに凝縮してるような気がしたので紹介させてもらった。
話を戻すが、はたして「一般教養」なるものを学習することにどんな目的があるのだろうか。それは本書の3章でくわしく述べられているけれど、私なりに要約してみたい。
そもそも「大学」の起源は13世紀頃のヨーロッパまでさかのぼる。この頃の大学というのは、専門的な知識をもったキリスト教の僧侶を養成することを目的にしている。その僧侶たちが学習する「専門的知識」とは「神学」、「法学」、「医学」の3つであった。これらの知識を伝承するのが知識人としての僧侶の役割だった。
しかし、これらの3つの専門のいずれかを修めて教会の中で専門職として出世したい人は、まず当時のヨーロッパの貴族・知識人の共通言語であったラテン語の読み書きや算術を学び、大学に入ってからは専門の勉強の前提となる基礎学力と思考能力と理解力を身につけるために「自由七科」(文法、修辞学、弁証法、算術、幾何、天文、音楽)を学ばなければならなかった。
この「自由七科」というのが大学の「教養科目」(一般教養)と呼ばれるものの起源である。そして、基礎的な教養を学習する「教養課程」と、自分の専門の勉強をする「専門課程」が分かれていたのは既にこの頃からであった。ちなみに「教養課程」を勉強するところは「学芸学部」と言われ、それは後に「哲学部」と呼ばれるようになる。
外国語に一般教養に哲学部と、最近の学生には縁も人気もなさそうな分野ばかりであるが、いずれもそれなりの歴史や必然性があって存在していることが多少は理解していただけただろうか。
大学科目に一般教養があり、かつて教養課程が存在していた理由をひとことでいえば、「教養」を身につけるためである。しかし、いきなりこんなこと書いてもピンとくる方はほとんどいないだろう。先に引用した仲正さんの文章の通り、教養というのはいわゆる雑学とは違うレベルのものである。この点は内田樹さん(神戸女学院大学教授)がこのように言っている。
<教養は情報ではない。
教養とはかたちのある情報単位の集積のことではなく、カテゴリーもクラスも重要度もまったく異にする情報単位のあいだの関係性を発見する力である。
雑学は「すでに知っていること」を取り出すことしかできない。教養とは「まだ知らないこと」へフライングする能力のことである。>(内田樹「知に働けば蔵が建つ」P.11。08年。文春文庫)
<「教養」というのは、「生(なま)」の知識や情報のことではない。そうではなくて、知識や情報を整序したり、統御したり、捜査したりする「仕方」のことである。
(中略)
「教養」とは「自分が何を知らないかについて知っている」、すなわち「自分の無知についての知識」のことなのである。>(内田樹「街場の現代思想」
P.11。08年。文春文庫)
そして仲正さん自身は本書の最後で「教養」において最も大事なことを、
<「今の私には分からない問題」に直面してしまった時に、どうすべきか」を心得ていること>(P.193)
と締めくくっている。こうやっていろいろと文章を並べてみて、「教養」というのがどんなものか、だんだんと具体的なイメージが湧いてきたような気がする。例えば、資格を取るとか就職に有利になるかというような短期的な目的を達成することに対して、「教養」はおそらくあまり役に立たないだろう。しかし、自分の頭の中のもっと根本的な影響を与えてくれるものという感じだ。
私がよくその著書を買っている日垣隆(作家・ジャーナリスト)さんや橘玲(作家)さんは、現代社会について鋭く切り込んだ文章を書いているけれど、一般的には難しそうな古典や現代思想や経済書などをよく読んでいるような傾向にあることに気づく。そして、それはどうしてなのだろうかと考えるようになった。やはり、そういう本を読むことにメリットがあるとしか思えない。
正直いって、いままでの私は古典や思想書などを敬遠してきた。昔の書物は読みづらく読破するにはかなりの根気がいる。また、別に苦労してそんなものを読まなくても良いのでは、とも腹の底では思っていた。
しかし、である。ウインドウズ95が登場したあたりから世の中の流れがグッと変わっていくようになり、世界はますます混迷の度合いが深まっていく。そして最近ではこの大震災だ。はっきりいって、過去の情報をもとにこれから先のことを予測するのは困難に違いない。
そんな状況で個人にできることといえば、目の前にある情報を分析して自分なりに行動することしかないだろう。となれば、やはりもっと根本的なところで考えることのできる頭を持っていなければならない。そのために必要なのがいわゆる「教養」というものではないか。
それは学習したところでパッとは役に立たない。しかし仲正さんが言うように、
<今すぐに利益がなくても、長期的な視野から見て、ごく表面的でも学んでおいた方がいいこともある。>(P.186)
と今では考えるようになっている。
本書は上に挙げたような「教養」の本来の意味にとどまらず、大学で学問をするために必要な心構え、また古典や外国語を勉強する意義などをかなり平易に書いて説明してくれている。本当だったらこれから大学に入る人に最適な本であるけれど、すでに大学を出た人にもかなり有益なことが満載だといいたい。特に、大学で何をしたのかわからない、というような人にはぜひ手にとってもらいたいと願う。
締めくくりにこの本の末尾の一文を紹介したい。
<ほとんどの人間は傲慢で横着です。自分が無知で勉強が必要だということをなかなか認められません。そのため、無自覚的に自分にとって都合の悪い情報をシャットアウトしがちです。自分が賢くなったと思い始めたら要注意です。「疑うこと」を回避して、楽になろうとする「私」自身を警戒してください。それが「何も信じられない世界」で生きていくための唯一の方策です。>(P.198)
中山治「『格差突破力』をつける方法 勉強法から人生戦略まで」(07年。洋泉社)
2011年3月21日 読書
せっかくの3連休だったが、いつもの休日と違わずほとんどを寝て過ごしてしまった。ただ、本だけはけっこう読んだとは思う。本書はその中の1冊だ。去年の夏くらいに買ったはずで一度は目を通したが、ちょっと気になる箇所があったのを思い出して再読する。
本書の内容はタイトルを読んで想像がつくように、
<グローバルな厳しい格差社会の中で「格差突破力」をいかに磨いていったらよいのか、について述べたもの>(P.3)
である。格差社会をテーマにした書物は数多いものの、この本を貫く思想はちょっと比較できるものがないかもしれない。
<本書は悲観論の予測に基づいて議論を組み立てています。日本を経済恐慌が襲い、再び軍国主義ファシズムが台頭する、といった極端に悲観的なシナリオが実現する可能性は低いかもしれませんが、日本の衰退は避けられない、との立場に立っています。>(P.22)
政治でも経済でも先が全く見えない昨今だから、悲観論に立った予測をするのは正当なやり方ではあろう。と、ここまでは別に異論もなく読み進んではいた。しかし、日本が衰退する理由として中山さんの挙げる点を見ると、「え?!と思ってしまった。中山さんはそれを「国内的な要因」と「国際的な要因」があるとして、まず国内的な要因を以下の4点だ。
・巨額の財政赤字
・少子高齢化の進行
・日本社会の劣化
・大地震のリスク
上の3点は良いとして、大地震まで勘定にいれるのか?と読んだ当時(もちろん大震災の前の話)はけっこう違和感を持った。以下にその理由が書かれている。
<日本列島は明らかに地震の活動期に入っています。近未来の日本に大地震が来ることがわかっていますが、地震予知は今のところ不可能に近い状況です。
(中略)
運良く生き延びることを前提に話を進めますが、東海地震、東南海地震、南海地震や首都直下型の大地震が起きた場合、日本経済に相当の悪影響が出ることを避けられません。一番恐ろしいのは、原子力発電所の近くで激しい揺れが起きて、稼働中の原子炉が破壊された場合です。
(中略)
だから、地震学者は東海の浜岡原子力発電所は危険だ、と常々警告しているのです。にもかかわらず、政府は無視しています。原子力発電所は絶対壊れない、という立場を取っているからです。実際には、震度6強の地震で原発の破壊が始まる、ということが2007年7月の新潟柏崎原発の地震で明らかになりました。
(中略)
今後予想される東海地震は、関東大震災をしのぐ巨大地震です。その発生確率は毎年上昇しています。直前予想はまず無理です。これが来たら、日本の衰退に拍車がかかることは避けられないでしょう。>(P.30-32)
この大惨事が起こった後となっては・・・まさにその通りで言葉も出てこない。
また日本が衰退する「国際的な要因」については、
・アメリカの力の衰退
・それにともなう中国の台頭
・人口爆発と資源の枯渇
・地球温暖化
・市場原理主義のグローバル化
の5点が出てくる。これらの指摘についても、果たして自分の生活に関係あるのか?と思う方もいるに違いない。本書はパッと見た限りではけっこう面を食らうような箇所が全編にわたって出てくる。ある種のイデオロギーを持った方はおそらく激怒すること間違いない。Amazonのサイトでの書評は散々な言われ方をされている。(ちなみに中山さん自身は、あらゆる政治イデオロギーが不完全なので信じない、という「脱政治イデオロギー」の持ち主だという)。
個人的にも、挑発的な筆致だな、と感じる部分もないわけでないが、その論理は地に足がついているというか、納得している点の方が多い。その中でも自分にとってこれは大事だな、と思ったことを2点挙げておきたい。
一つは、世の中に広まっている情報は都合の悪い部分(中山さんは「不都合な真実」と表現している)を見抜けられる能力をもつことだ。
<どこの国であれ、国家は「情報操作がいっぱい」なのです。情報操作しないと人々を動員できないからです。人々を戦争に動員する。人々の経済活動を貯蓄から投資に動員する。情報操作なしにこれは不可能です。
だから、国家を簡単に信じてはいけない。自分は情報操作で利用されているのではないか、と常に疑いを持たなくてはいけないのです。そのためには、情報分析にあたって「得をするのは誰か」を常に考えることです>(P.130-131)
<私にいわせると、「大国の権力者は金正日」なのです。独裁国家のように強権的に人々を操るのか、民主国家のようにメディアと学校教育と御用文化人を利用して、情報操作とマインドコントロールで巧妙に操るのか、という違いがあるだけです。>(P.141)
なかなか凄い表現だなあと思う一方、国家なんてそんなものかもしれないなあ、と納得している自分も確かに存在している。
そしてもう1点は、モンゴル帝国のチンギス・ハーンのようなノマド(遊牧民)の精神を持つこと、つまり世界的視野を持つことを奨めている。情報操作を見抜くためには外からの視点も持たなければならいないからだ。しかし、そのためには日本語圏の情報だけでは足りない。だから、英語を勉強したり外国に人的ネットワークを作るのが望ましいという。
中山さんのやり方はさらに徹底していて、日本を脱出するような緊急的事態になった場合を備えて、その第一候補をオーストラリアにしているという。そして銀行に口座を作ってお金を預けてもいる。
<滞在先で必要なものはまずお金で、まさに「富は要塞」「お金は安全保障」なのです。私が逃げられないときは、子どもだけでも逃がします。だから、長女のサインだけでお金を引き出せるようにしてあるのです。
「何をバカなことを」と笑う人も多いでしょう。しかし、「一寸先は闇」の法則を私は信じているのです。私と同じ考えの日本人も少なくありません。日本に危機がひたひたと忍び寄っているからです。ただ、それを人にいわないだけです。子どもさえ逃げることができれば、私は安心して死ねます。餓死か核ミサイルかはわかりませんが。(P.180)
絵に描いたような「悲観論の予測」だが、果たして中山さんの備えが笑い話で終わるような未来に日本にはなっているのだろうか。そうあってほしいと願っているのだが、個人的な願望と世の中の流れを混同してはいけない。
中山さんも本音は、おそらく下のような文章にあるのだろう。
<私は中流の生活を保って、その中で充実した幸せな人生を送ることができれば、それで大満足なのです。有名になりたいとも、偉くなりたいとも、大金持ちになりたいとも思わない。生きてゆくうえで、それらはすべて「過剰」だからです。「過剰なもの」はあってもなくてもよい。どうでもよいのです。これが私のモノサシです。>(P.166)
あまり考えたくはないが、現代を「一寸先は闇」と捉えてこれからの人生を組み立てるというのも、一つの選択肢として必要なのかもしれない。
本書の内容はタイトルを読んで想像がつくように、
<グローバルな厳しい格差社会の中で「格差突破力」をいかに磨いていったらよいのか、について述べたもの>(P.3)
である。格差社会をテーマにした書物は数多いものの、この本を貫く思想はちょっと比較できるものがないかもしれない。
<本書は悲観論の予測に基づいて議論を組み立てています。日本を経済恐慌が襲い、再び軍国主義ファシズムが台頭する、といった極端に悲観的なシナリオが実現する可能性は低いかもしれませんが、日本の衰退は避けられない、との立場に立っています。>(P.22)
政治でも経済でも先が全く見えない昨今だから、悲観論に立った予測をするのは正当なやり方ではあろう。と、ここまでは別に異論もなく読み進んではいた。しかし、日本が衰退する理由として中山さんの挙げる点を見ると、「え?!と思ってしまった。中山さんはそれを「国内的な要因」と「国際的な要因」があるとして、まず国内的な要因を以下の4点だ。
・巨額の財政赤字
・少子高齢化の進行
・日本社会の劣化
・大地震のリスク
上の3点は良いとして、大地震まで勘定にいれるのか?と読んだ当時(もちろん大震災の前の話)はけっこう違和感を持った。以下にその理由が書かれている。
<日本列島は明らかに地震の活動期に入っています。近未来の日本に大地震が来ることがわかっていますが、地震予知は今のところ不可能に近い状況です。
(中略)
運良く生き延びることを前提に話を進めますが、東海地震、東南海地震、南海地震や首都直下型の大地震が起きた場合、日本経済に相当の悪影響が出ることを避けられません。一番恐ろしいのは、原子力発電所の近くで激しい揺れが起きて、稼働中の原子炉が破壊された場合です。
(中略)
だから、地震学者は東海の浜岡原子力発電所は危険だ、と常々警告しているのです。にもかかわらず、政府は無視しています。原子力発電所は絶対壊れない、という立場を取っているからです。実際には、震度6強の地震で原発の破壊が始まる、ということが2007年7月の新潟柏崎原発の地震で明らかになりました。
(中略)
今後予想される東海地震は、関東大震災をしのぐ巨大地震です。その発生確率は毎年上昇しています。直前予想はまず無理です。これが来たら、日本の衰退に拍車がかかることは避けられないでしょう。>(P.30-32)
この大惨事が起こった後となっては・・・まさにその通りで言葉も出てこない。
また日本が衰退する「国際的な要因」については、
・アメリカの力の衰退
・それにともなう中国の台頭
・人口爆発と資源の枯渇
・地球温暖化
・市場原理主義のグローバル化
の5点が出てくる。これらの指摘についても、果たして自分の生活に関係あるのか?と思う方もいるに違いない。本書はパッと見た限りではけっこう面を食らうような箇所が全編にわたって出てくる。ある種のイデオロギーを持った方はおそらく激怒すること間違いない。Amazonのサイトでの書評は散々な言われ方をされている。(ちなみに中山さん自身は、あらゆる政治イデオロギーが不完全なので信じない、という「脱政治イデオロギー」の持ち主だという)。
個人的にも、挑発的な筆致だな、と感じる部分もないわけでないが、その論理は地に足がついているというか、納得している点の方が多い。その中でも自分にとってこれは大事だな、と思ったことを2点挙げておきたい。
一つは、世の中に広まっている情報は都合の悪い部分(中山さんは「不都合な真実」と表現している)を見抜けられる能力をもつことだ。
<どこの国であれ、国家は「情報操作がいっぱい」なのです。情報操作しないと人々を動員できないからです。人々を戦争に動員する。人々の経済活動を貯蓄から投資に動員する。情報操作なしにこれは不可能です。
だから、国家を簡単に信じてはいけない。自分は情報操作で利用されているのではないか、と常に疑いを持たなくてはいけないのです。そのためには、情報分析にあたって「得をするのは誰か」を常に考えることです>(P.130-131)
<私にいわせると、「大国の権力者は金正日」なのです。独裁国家のように強権的に人々を操るのか、民主国家のようにメディアと学校教育と御用文化人を利用して、情報操作とマインドコントロールで巧妙に操るのか、という違いがあるだけです。>(P.141)
なかなか凄い表現だなあと思う一方、国家なんてそんなものかもしれないなあ、と納得している自分も確かに存在している。
そしてもう1点は、モンゴル帝国のチンギス・ハーンのようなノマド(遊牧民)の精神を持つこと、つまり世界的視野を持つことを奨めている。情報操作を見抜くためには外からの視点も持たなければならいないからだ。しかし、そのためには日本語圏の情報だけでは足りない。だから、英語を勉強したり外国に人的ネットワークを作るのが望ましいという。
中山さんのやり方はさらに徹底していて、日本を脱出するような緊急的事態になった場合を備えて、その第一候補をオーストラリアにしているという。そして銀行に口座を作ってお金を預けてもいる。
<滞在先で必要なものはまずお金で、まさに「富は要塞」「お金は安全保障」なのです。私が逃げられないときは、子どもだけでも逃がします。だから、長女のサインだけでお金を引き出せるようにしてあるのです。
「何をバカなことを」と笑う人も多いでしょう。しかし、「一寸先は闇」の法則を私は信じているのです。私と同じ考えの日本人も少なくありません。日本に危機がひたひたと忍び寄っているからです。ただ、それを人にいわないだけです。子どもさえ逃げることができれば、私は安心して死ねます。餓死か核ミサイルかはわかりませんが。(P.180)
絵に描いたような「悲観論の予測」だが、果たして中山さんの備えが笑い話で終わるような未来に日本にはなっているのだろうか。そうあってほしいと願っているのだが、個人的な願望と世の中の流れを混同してはいけない。
中山さんも本音は、おそらく下のような文章にあるのだろう。
<私は中流の生活を保って、その中で充実した幸せな人生を送ることができれば、それで大満足なのです。有名になりたいとも、偉くなりたいとも、大金持ちになりたいとも思わない。生きてゆくうえで、それらはすべて「過剰」だからです。「過剰なもの」はあってもなくてもよい。どうでもよいのです。これが私のモノサシです。>(P.166)
あまり考えたくはないが、現代を「一寸先は闇」と捉えてこれからの人生を組み立てるというのも、一つの選択肢として必要なのかもしれない。
的確な指摘だが、もはや手遅れか
2011年3月18日石原慎太郎東京都知事は18日、地域ごとに電気の供給を止める計画停電の影響が大きすぎることを指摘する文書を海江田万里経済産業相に提出した。
石原氏は計画停電の問題点をこうまとめている。
(1)鉄道、病院など社会的に不可欠な機能の維持に影響を及ぼす
(2)経済活動に過大な負荷を与える
(3)地域的な不公平が生じている
そして、大規模施設での計画的な使用制限やネオンサインの禁止、コンビニエンスストアの深夜営業中止などを実施するよう要望している。
計画停電については、当の東京電力が実施に二の足を踏んでいるし、事故などが起きるのを不安に感じている人は多いに違いない。石原氏によるこれらの指摘は計画停電がどれだけ問題が多いかを実に的確に衝いているといえよう。生活に比較的影響の小さな時間帯や施設で使用制限をするようなやり方がやはり安全ではないだろうか。
ただ、いまさら石原氏がどれほど良いことを言ったとしても、あの「天罰」発言の後では誰も相手にしてくれないだろう。上の指摘自体は優れたものだから、誰か他の政治家や首長が賛同の意を表してくれないだろうか。
石原氏は計画停電の問題点をこうまとめている。
(1)鉄道、病院など社会的に不可欠な機能の維持に影響を及ぼす
(2)経済活動に過大な負荷を与える
(3)地域的な不公平が生じている
そして、大規模施設での計画的な使用制限やネオンサインの禁止、コンビニエンスストアの深夜営業中止などを実施するよう要望している。
計画停電については、当の東京電力が実施に二の足を踏んでいるし、事故などが起きるのを不安に感じている人は多いに違いない。石原氏によるこれらの指摘は計画停電がどれだけ問題が多いかを実に的確に衝いているといえよう。生活に比較的影響の小さな時間帯や施設で使用制限をするようなやり方がやはり安全ではないだろうか。
ただ、いまさら石原氏がどれほど良いことを言ったとしても、あの「天罰」発言の後では誰も相手にしてくれないだろう。上の指摘自体は優れたものだから、誰か他の政治家や首長が賛同の意を表してくれないだろうか。
地震を予測した人は凄いのか
2011年3月16日mixiでマイミクの方が、地震を予告した云々の話題を触れていたのを見てパッと思い浮かんだことがある。それについて書いてみたい。
かつて、第三次世界大戦が起きる、というような予測が何度か流れたことがある。そして、それはある程度の根拠や信憑性が伴う予測だった。
しかしご存じのように、そのような戦争はいままで起きてはいない。それは何故だろう。
そうした予測を信じた多くの人たちが、そのような最悪の事態を避けるため必死で動いたからである。逆説的な話だが、予測の精度が高かったゆえに、結果としてその予測が外れてしまったわけだ。
こんな悲惨な事態を予測できたといっても、それを止められなかったということは、その程度のレベルの予測だったということにしかならないのである。
かつて、第三次世界大戦が起きる、というような予測が何度か流れたことがある。そして、それはある程度の根拠や信憑性が伴う予測だった。
しかしご存じのように、そのような戦争はいままで起きてはいない。それは何故だろう。
そうした予測を信じた多くの人たちが、そのような最悪の事態を避けるため必死で動いたからである。逆説的な話だが、予測の精度が高かったゆえに、結果としてその予測が外れてしまったわけだ。
こんな悲惨な事態を予測できたといっても、それを止められなかったということは、その程度のレベルの予測だったということにしかならないのである。
節電などするならば、いっそのこと
2011年3月14日関西に住んでいる身としては、震災の報道はいまでもあまりピンときていないのが正直なところだ。原発事故についても同じような感じだった。
しかし、電気の供給が足りなくなって停電とか節電とかいったことが呼びかけられるようになるにつれ、鈍い自分でもウーンと考えるようになってきた。
今朝の「スーパーモーニング」(テレビ朝日系列)でも指摘されていたが、現代の私たちは想像をはるかに超えるくらい電気に依存している。衣食住はもとより、エレベーターや信号なども電気で動いているわけだ。もしそれらが急に止まったりしたら、二次災害が起きることも大いにありうる。
そんな時、NHKが電力節減に協力するため教育テレビとBS2の深夜の番組放送を停止するというニュースが目に止まった。14〜18日の深夜0時から午前5時まで停止するという。節電などの行為に懐疑的だった私も、これにはピンときた。
これを機会に、民放もコンビニもファーストフードも、みんな深夜営業を止めたらどうだろうか。そうすれば一部の人たちが節電をするよりもずっと効果は大きいに違いない。
東京都知事選に4度目の出馬を決めた石原慎太郎氏が、かつてこんなことを記者会見で言っていた。
《——コンビニエンスストアの深夜営業規制に向けた動きが各地で相次いでい
ます。
石原「一晩中開いているストアが都民にとってコンビニエントだと私は思い
ませんね」
——規制する考えは?
石原「これから庁内の会議を経て意見を出し合って、合議の末に基本的な姿
勢を決めるべき問題だと思いますけれども。ただ、やっぱりネオンとかね、自
動販売機を一晩中つけておくのはおかしい。この時代にね、余り人のいない大
きな店舗が、明かりをこうこうとつけて朝まで開いているというのは、やっぱ
り意味ないと思うね」》(2008年6月20日の都庁内記者会見にて)
「意味ない」というばかりでなく、エネルギーの観点から考えても深夜営業は無駄な面が多すぎる。犯罪者の標的にされてしまうことが多いのも深夜のコンビニだ。
確かに深夜にコンビニが開いていたら便利なのは間違いない。しかし、私が小学生の時でもそんな営業形態の店はまだほとんどなかった。そして、それで生活は普通にできていたのである。
悲しいことに私たちは。いったん便利なものに慣れてしまったらそれを再び捨てて後戻りすることが困難な生き物だ。例えば携帯を手放して生活するのは大半の現代人には不可能だろう。それはそれで仕方ないかもしれない。
しかし、今回のような致命的な出来事を前にすると、多少の生活の不便は耐えられるような気がしないだろうか。そもそも電気がなくなってしまったら、元も子もないわけだし。
今回の原発事故を見てつくづく感じたのは、私たちの使える資源はやはり有限なのだということであった。その限りあるものを少しでも長く使い伸ばすような工夫がこれからの私たちには必要になってくるだろう。
しかし、電気の供給が足りなくなって停電とか節電とかいったことが呼びかけられるようになるにつれ、鈍い自分でもウーンと考えるようになってきた。
今朝の「スーパーモーニング」(テレビ朝日系列)でも指摘されていたが、現代の私たちは想像をはるかに超えるくらい電気に依存している。衣食住はもとより、エレベーターや信号なども電気で動いているわけだ。もしそれらが急に止まったりしたら、二次災害が起きることも大いにありうる。
そんな時、NHKが電力節減に協力するため教育テレビとBS2の深夜の番組放送を停止するというニュースが目に止まった。14〜18日の深夜0時から午前5時まで停止するという。節電などの行為に懐疑的だった私も、これにはピンときた。
これを機会に、民放もコンビニもファーストフードも、みんな深夜営業を止めたらどうだろうか。そうすれば一部の人たちが節電をするよりもずっと効果は大きいに違いない。
東京都知事選に4度目の出馬を決めた石原慎太郎氏が、かつてこんなことを記者会見で言っていた。
《——コンビニエンスストアの深夜営業規制に向けた動きが各地で相次いでい
ます。
石原「一晩中開いているストアが都民にとってコンビニエントだと私は思い
ませんね」
——規制する考えは?
石原「これから庁内の会議を経て意見を出し合って、合議の末に基本的な姿
勢を決めるべき問題だと思いますけれども。ただ、やっぱりネオンとかね、自
動販売機を一晩中つけておくのはおかしい。この時代にね、余り人のいない大
きな店舗が、明かりをこうこうとつけて朝まで開いているというのは、やっぱ
り意味ないと思うね」》(2008年6月20日の都庁内記者会見にて)
「意味ない」というばかりでなく、エネルギーの観点から考えても深夜営業は無駄な面が多すぎる。犯罪者の標的にされてしまうことが多いのも深夜のコンビニだ。
確かに深夜にコンビニが開いていたら便利なのは間違いない。しかし、私が小学生の時でもそんな営業形態の店はまだほとんどなかった。そして、それで生活は普通にできていたのである。
悲しいことに私たちは。いったん便利なものに慣れてしまったらそれを再び捨てて後戻りすることが困難な生き物だ。例えば携帯を手放して生活するのは大半の現代人には不可能だろう。それはそれで仕方ないかもしれない。
しかし、今回のような致命的な出来事を前にすると、多少の生活の不便は耐えられるような気がしないだろうか。そもそも電気がなくなってしまったら、元も子もないわけだし。
今回の原発事故を見てつくづく感じたのは、私たちの使える資源はやはり有限なのだということであった。その限りあるものを少しでも長く使い伸ばすような工夫がこれからの私たちには必要になってくるだろう。
放射能
2011年3月12日津波の被害が徐々に明らかになるにつれ、新たに福島原発の問題が出てきている。原発から半径20キロ圏内の住民に避難勧告が出ているという。
放射能が人体に有害だという話は、広島・長崎の原爆や旧ソ連のチェルノブイリといった事例で私たちの頭の中には強く残っているに違いない。
しかし、放射能が人体にどれほどの影響を与えるのかは、現在でもはっきりとはしていない。人体実験などできるわけはないのだから、それはそれで仕方ない話ではあるが。
手塚治虫のマンガ「火の鳥」にも、核戦争で放射能の犠牲になる人が描かれている場面があるけれど、どうして死に至ってしまうのかは、やはりわからない。
放射能はどこまで浴びたら危険か、またはどこまでは安全なのか。そのあたりがわからない私たちは、決して不安を拭うことができないのが辛い。
放射能が人体に有害だという話は、広島・長崎の原爆や旧ソ連のチェルノブイリといった事例で私たちの頭の中には強く残っているに違いない。
しかし、放射能が人体にどれほどの影響を与えるのかは、現在でもはっきりとはしていない。人体実験などできるわけはないのだから、それはそれで仕方ない話ではあるが。
手塚治虫のマンガ「火の鳥」にも、核戦争で放射能の犠牲になる人が描かれている場面があるけれど、どうして死に至ってしまうのかは、やはりわからない。
放射能はどこまで浴びたら危険か、またはどこまでは安全なのか。そのあたりがわからない私たちは、決して不安を拭うことができないのが辛い。
サラリーマンが唯一の生き方、ではないはずだが
2011年3月5日3月3日(木)の毎日新聞記事に「自殺 就活難航で大学生の自殺者が倍増 10年警察庁統計」という見出しで、自殺に関する深刻な統計結果が紹介されていた。警察庁が3日に公表した昨年(2010年)の自殺統計によると、前年より3.5%減少したものの3万1690人の人が自殺しており、3万人を超えるのは13年連続だという。
その中でも「就職失敗」を原因に含むとされた自殺者は、
07年:180人
08年:253人
09年:354人
10年:424人
と年々増えている。自殺した大学生については、
07年:13人
08年:22人
09年:23人
10年:53人(高校生や専修学校生も含む)
と、確かに多くはなっている。
自殺する年代は20代が最も多い(153人)。こうした数字を見るだけでも、自殺まではいかないとしても、就職がうまくいかずに苦しんでいる人が日本で増えていることが察せられる。
就職ができないのは確かに大変だけど死ぬほどの問題か、と思う方もいるかもしれない。ただ、自殺したくなる人たちの心境はなんとなくわかるような気がする。おそらく自殺した人たち、いや多くの日本人がそうだと思うが、サラリーマンしか人生のモデルが想像できないからではないだろうか。
サラリーマンが唯一の生き方と思っている人が就職に失敗した時に、「自分の人生はもう終わりだ」と絶望して自殺をしたとしても何の不思議でもないだろう。
新卒で大学に入り、会社から安定した給料をもらい、定年したら退職金をもらって老後は年金で悠々と暮らす・・・。しかしこうした「かつての」サラリーマン像は既に崩壊している。長く勤めても給料は上がらないし、年金も払った分が戻ってくる可能性も現時点では、ない。
それならばサラリーマンとは違った選択肢を私たちは探さなければならない、はずなのだが、契約社員を正社員化せよ、というような論調がいまでも強いのを考えると、サラリーマン神話はまだまだ根強く残っているような気がする。
その中でも「就職失敗」を原因に含むとされた自殺者は、
07年:180人
08年:253人
09年:354人
10年:424人
と年々増えている。自殺した大学生については、
07年:13人
08年:22人
09年:23人
10年:53人(高校生や専修学校生も含む)
と、確かに多くはなっている。
自殺する年代は20代が最も多い(153人)。こうした数字を見るだけでも、自殺まではいかないとしても、就職がうまくいかずに苦しんでいる人が日本で増えていることが察せられる。
就職ができないのは確かに大変だけど死ぬほどの問題か、と思う方もいるかもしれない。ただ、自殺したくなる人たちの心境はなんとなくわかるような気がする。おそらく自殺した人たち、いや多くの日本人がそうだと思うが、サラリーマンしか人生のモデルが想像できないからではないだろうか。
サラリーマンが唯一の生き方と思っている人が就職に失敗した時に、「自分の人生はもう終わりだ」と絶望して自殺をしたとしても何の不思議でもないだろう。
新卒で大学に入り、会社から安定した給料をもらい、定年したら退職金をもらって老後は年金で悠々と暮らす・・・。しかしこうした「かつての」サラリーマン像は既に崩壊している。長く勤めても給料は上がらないし、年金も払った分が戻ってくる可能性も現時点では、ない。
それならばサラリーマンとは違った選択肢を私たちは探さなければならない、はずなのだが、契約社員を正社員化せよ、というような論調がいまでも強いのを考えると、サラリーマン神話はまだまだ根強く残っているような気がする。